

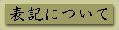
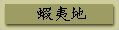
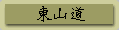
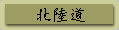
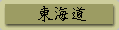
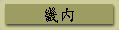
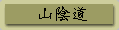
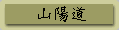
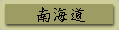
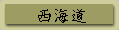
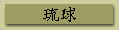
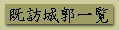

    | ||
|---|---|---|
|
| ||
| ||
  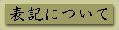 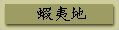 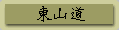 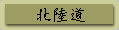 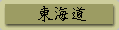 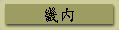 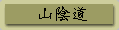 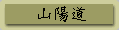 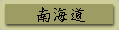 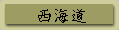 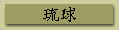 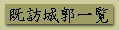 
|
| ||||||||




| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 和歌山城 近世 平山城 |
 〈岡口門〉 〈岡口門〉言うまでもなく徳川御三家紀州家の本城。1585年に秀吉が紀州征伐を行った際、若山と呼ばれる丘陵に弟秀長に築城させ、城代を桑山重晴とした。この時は緑泥片岩の野面積みであった。関ヶ原の合戦後、その戦功により浅野幸長が37万石で入城。石垣の修築を行うが、その時は打ち込み剥石垣で、刻印がある。その後浅野氏は広島に移封、家康の第10子頼宣が55.5万石で入城。1629年より砂の丸石垣、南の丸石垣に着手し、この時に打ち込み、切り込みが混然した壮大な石垣にした。曲輪塁上には大天守・小天守・乾櫓・二の門櫓・二の門があり、多聞櫓で結ばれる連立式天守であった。また、本丸と天守曲輪が双立した珍しい形態を取り、その麓に二の丸・南の丸・砂の丸・西の丸を配した典型的な平山城である。1846年には天守が焼失、五層天守をあげる計画を立てたが、幕府に対して遠慮し、旧来と同じ三層天守に甘んじた。昭和20年の空襲で天守は全焼し、現在見られるのはコンクリート製の再建。岡口門、狭間塀、追廻門が現存。本丸台所、多聞櫓は移築されて現存する。 *管理事務所  近所なのだが、物心ついて初めて行った。天守閣と並んで本丸がある構造が興味深い。天守閣は御三家の城郭にしては三層の貧弱なものともいえるが、虎伏山の頂上にそびえる連郭式城郭はどの角度から見ても勇壮な姿を見せる。近所にこれだけの城があるというのはなかなかうれしいことではある。(H8.3.27) 近所なのだが、物心ついて初めて行った。天守閣と並んで本丸がある構造が興味深い。天守閣は御三家の城郭にしては三層の貧弱なものともいえるが、虎伏山の頂上にそびえる連郭式城郭はどの角度から見ても勇壮な姿を見せる。近所にこれだけの城があるというのはなかなかうれしいことではある。(H8.3.27)
少々辛口に過ぎるかもしれないが、正直「城っぽいものを見せられている」感覚だった。さらに、忍者押しがひどく、いろんなところに忍者が出てくる。売店の自動販売機では、ジュースを買うと、武士や忍者がしゃべる。外国人観光客はそういうのを好むのかもしれないが、もうテンションを上げようがない。 |
| 根来寺 | |
| 広城 | |
| 田辺城(C) 近世 水城 |
 関ヶ原の合戦後、浅野氏定が上野山城から移るために湊城が作られた。1619年に浅野氏が三原に移封となり、和歌山藩城代として家老安藤直次が入城した。直次が湊城を拡張させ、田辺城と改名したものである。現在は本丸東中央にあった埋門型の水門が残るのみであるが、領国統治のために築かれたものであり、往時にも天守閣等の高層櫓はなかった。 関ヶ原の合戦後、浅野氏定が上野山城から移るために湊城が作られた。1619年に浅野氏が三原に移封となり、和歌山藩城代として家老安藤直次が入城した。直次が湊城を拡張させ、田辺城と改名したものである。現在は本丸東中央にあった埋門型の水門が残るのみであるが、領国統治のために築かれたものであり、往時にも天守閣等の高層櫓はなかった。 家族で白浜温泉に旅行に行き、帰りに寄る。海か川かという境目のところに水門がある。その水門の川側に道が走っているため、それがなかった状態での水門というのは想像するしかないのだが、それでも石垣の残存状態は非常によく、十分に当時を偲ぶことができた。特に実際に木の門があったと思われるところには石垣が削れていて趣き深い。石垣の上に「最近作りました」と言わんばかりの白壁があるのは致し方ないところだろうか。総評としては水門以外は全く何も残っていない城跡であるが、ある程度歴史に造詣の深い人であれば十分に見る価値のあるものであると言える。(H12.2.12) 家族で白浜温泉に旅行に行き、帰りに寄る。海か川かという境目のところに水門がある。その水門の川側に道が走っているため、それがなかった状態での水門というのは想像するしかないのだが、それでも石垣の残存状態は非常によく、十分に当時を偲ぶことができた。特に実際に木の門があったと思われるところには石垣が削れていて趣き深い。石垣の上に「最近作りました」と言わんばかりの白壁があるのは致し方ないところだろうか。総評としては水門以外は全く何も残っていない城跡であるが、ある程度歴史に造詣の深い人であれば十分に見る価値のあるものであると言える。(H12.2.12) |
| 湯浅城 | 武士団「湯浅党」が居城として1143年に築いた城。南北朝の頃には楠木氏の残党とともに南朝方として後村上天皇の孫「義有王」を迎え、戦っている。現在は土塁・空掘・井戸などが残る。城跡の前の敷地に天守閣型の国民宿舎が建てられているが、歴史的に何ら関連性はない。 *国民宿舎湯浅城のページ *和歌山watchingのページ  田辺城とともに白浜温泉旅行の帰りに寄ったものであるが、遠くからでも五層の天守がよく見えてとにかく目立つ城である。とはいえ、こんなところに五層の天守があったわけもなく、近くに来てみてびっくり。これは何と「国民宿舎」なんだそうだ。(大人一泊7400円也!!)実際の湯浅城跡はこの国民宿舎の道をはさんだ前の丘で、土塁や堀が残っているらしい。この時は時間がなくて探しに行くことはできず。とにかく、全く関係のない建物を建てるにも、いくらなんでも限度があると思うのは俺だけだろうか?(H12.2.12) 田辺城とともに白浜温泉旅行の帰りに寄ったものであるが、遠くからでも五層の天守がよく見えてとにかく目立つ城である。とはいえ、こんなところに五層の天守があったわけもなく、近くに来てみてびっくり。これは何と「国民宿舎」なんだそうだ。(大人一泊7400円也!!)実際の湯浅城跡はこの国民宿舎の道をはさんだ前の丘で、土塁や堀が残っているらしい。この時は時間がなくて探しに行くことはできず。とにかく、全く関係のない建物を建てるにも、いくらなんでも限度があると思うのは俺だけだろうか?(H12.2.12) |
| 手取城 戦国 山城 |
|
| 田尻城 戦国 山城(810m) |
手取城の支城。和歌山では最も高いところに築かれた。 *和歌山watchingのページ |
| 平須賀城 戦国 山城 |
*松本さんのページ |
| 名杭城 戦国 山城 |
|
| 新宮城(C) 近世 平山城 |
|
| 赤木城 | *紀和町のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 洲本城 近世 平山城(133m) |
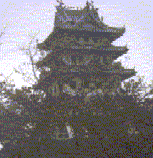 *内橋さんのページ  友人と淡路島にキャンプに行き、その途中で行った。石垣が相当残っていて、情緒たっぷり。その割には模擬天守閣が非常に貧弱。縄張りで感動して天守でガックリするパターン。(H8.10.14) 友人と淡路島にキャンプに行き、その途中で行った。石垣が相当残っていて、情緒たっぷり。その割には模擬天守閣が非常に貧弱。縄張りで感動して天守でガックリするパターン。(H8.10.14) |
| 白巣城 戦国 山城 |
(エピソード)秀吉に攻撃にあい、山の上に城があるため竹の皮をしきつめて攻撃を逃れていたのですがそれが、あだとなり焼けうちにあい城は全焼したそうです。その時、大事な姫を井戸の中にある隠れ部屋に隠していて難を逃れたのですが・・・焼け野原となった後その姫も見つかり、首をはねられたそうです。(s.nakayaさんより) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 高松城 近世 海城 |
 〈旧東之丸艮櫓,北の丸月見櫓,北の丸水手御門,北の丸渡櫓〉 〈旧東之丸艮櫓,北の丸月見櫓,北の丸水手御門,北の丸渡櫓〉1588年、生駒親正が始め、改易の後松平頼重が入城し、引き継がれた。天守は南蛮造りといわれる三重五階で、五階目と一階目が大きく張り出す珍しい構造をしていた。また、月見櫓は元々着見櫓であり、船をそこにつけられるようになっており、城から直接船に乗ったり、船から直接城に入ったりできるようになっている。 *大島さんの旅行のページ  考えていたよりも断然広くてきれいな城跡だった。完全に堀に海水を引き入れているために潮の満ち干きによって堀の水が増減したり、完全に一つの簡単な橋のみでしか行けなくなっている本丸の構造が特徴だろう。天守台には社が建てられていて在りし日の最上階(五層目)が四層目より出っぱっているという特殊な天守は想像するほかはない。が、櫓は2つ残っていて、特に月見櫓とそれに付随する門が興味深い。それらはちょうど外に向かっていて、当時その外側は海であり、その門から直接城内に入れたのである。月見櫓はその名前からは想像できないが入ってくる船の監視をするためのものだったらしい。大正時代の再建らしい御殿もあるが、内部の見学はさせてもらえなかった。全体的には櫓などの中に入ることはできないため単なる散歩という形にならざるを得ないが、城ファンは必見だろう。(H9.3.13) 考えていたよりも断然広くてきれいな城跡だった。完全に堀に海水を引き入れているために潮の満ち干きによって堀の水が増減したり、完全に一つの簡単な橋のみでしか行けなくなっている本丸の構造が特徴だろう。天守台には社が建てられていて在りし日の最上階(五層目)が四層目より出っぱっているという特殊な天守は想像するほかはない。が、櫓は2つ残っていて、特に月見櫓とそれに付随する門が興味深い。それらはちょうど外に向かっていて、当時その外側は海であり、その門から直接城内に入れたのである。月見櫓はその名前からは想像できないが入ってくる船の監視をするためのものだったらしい。大正時代の再建らしい御殿もあるが、内部の見学はさせてもらえなかった。全体的には櫓などの中に入ることはできないため単なる散歩という形にならざるを得ないが、城ファンは必見だろう。(H9.3.13) |
| 丸亀城 近世 平山城(66.6m) |
 〈天守,大手一の門,大手二の門〉 〈天守,大手一の門,大手二の門〉1600年に生駒親正の起工であり、縄張りは麓と亀山からなる階郭・梯郭併用で、石垣の総高は日本一である。天守は1660年の造立、現存天守のうちもっとも小さいものである。 *山ぽんのホームページ *香川ネットのページ *内橋さんのページ *大島さんの旅行のページ  今治側から丸亀の市内に入るとひときわ高い石垣が目に入り、その上にちっちゃな天守が見える。その時点では石垣が非常に高く立派なため天守は貧弱に思えたのだが近くに行ってみるとなかなかどうしてかっこいい城だった。櫓などは大手門を除いてすべて取り払われてしまっているので天守だけ浮いて見えてしまうのはある程度致し方ないことであろう。天守内部には京極家ゆかりの武具などが置かれ、最上階は小藩らしくちっちゃなもので、非常に趣き深かった。そこからは瀬戸内海が見渡せ、当然ながら瀬戸大橋も一望の下である。とはいえ、この城の目玉はやはり石垣。累々と総計60メートルにも及ぶという石垣はそのウェーブも配置も優美そのもの。三の丸裏側から見た石垣と天守は撮影ポイントとしては最高ではなかろうか。高知・松山・宇和島と現存天守の多い四国では霞んでしまいがちな丸亀だが非常に趣きのあるいい城で、大いに行く価値はある。(H9.3.12) 今治側から丸亀の市内に入るとひときわ高い石垣が目に入り、その上にちっちゃな天守が見える。その時点では石垣が非常に高く立派なため天守は貧弱に思えたのだが近くに行ってみるとなかなかどうしてかっこいい城だった。櫓などは大手門を除いてすべて取り払われてしまっているので天守だけ浮いて見えてしまうのはある程度致し方ないことであろう。天守内部には京極家ゆかりの武具などが置かれ、最上階は小藩らしくちっちゃなもので、非常に趣き深かった。そこからは瀬戸内海が見渡せ、当然ながら瀬戸大橋も一望の下である。とはいえ、この城の目玉はやはり石垣。累々と総計60メートルにも及ぶという石垣はそのウェーブも配置も優美そのもの。三の丸裏側から見た石垣と天守は撮影ポイントとしては最高ではなかろうか。高知・松山・宇和島と現存天守の多い四国では霞んでしまいがちな丸亀だが非常に趣きのあるいい城で、大いに行く価値はある。(H9.3.12) |
| 天霧城 戦国 山城(360m) |
南北朝時代に讃岐の守護であった細川氏を補佐した四天王のひとつである「香川氏」が多度津本台山に居館を構え、その詰めの城として築いたのが始まりといわれる。その後200年余りの期間この城を中心に西讃岐一円を領したが、秀吉の四国征伐の後に廃城となった。現在でも郭、土塁、石垣、井戸などが残り、香川県では有数の規模と遺構を留める山城であるが、近年採掘等で保存状態が危ぶまれる城でもある。 |
| 屋島城 古代 山城 |
白村江の戦いで敗れた日本が造った五大城郭の一つ。(大野、基肄、長門、屋島、高安) 屋島に来てみたら城跡があるというので立ち寄った。日本書紀に書かれており、山の中腹には石垣も見つかっているらしいが遊歩道には説明版があるだけ。石垣を見に行こうかとも思ったのだが、時間もないのでやめておいた。屋島は自然が豊かで歩いてて楽しくないこともないが、壇ノ浦はよくわかんないし、歴史が好きな人には特に勧められるところではない。(H9.3.13) 屋島に来てみたら城跡があるというので立ち寄った。日本書紀に書かれており、山の中腹には石垣も見つかっているらしいが遊歩道には説明版があるだけ。石垣を見に行こうかとも思ったのだが、時間もないのでやめておいた。屋島は自然が豊かで歩いてて楽しくないこともないが、壇ノ浦はよくわかんないし、歴史が好きな人には特に勧められるところではない。(H9.3.13) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 徳島城(C) 近世 平山城(61.9m) |
1586年に蜂須賀家政が築城。山部分を本丸・二の丸とし、麓を居館とする当城は山頂より一段低い東二の丸に三層天守をあげる特殊な構造であった。今日、現存建築物は特にないが、石垣や三之丸庭園は非常に美しい。 *徳島県のページ(博物館) *徳島大学のページ *吉野川のページ  徳島市内にある平山城。徳島中央公園の中にあり、本丸はここらしいというものしかなく、実際に碑すら立っていない。遺構は石垣と堀、そして庭園のみ。庭園は往時を偲ばせるもの大いにあり、一見の価値があるが、庭園のとなりにある徳島城博物館には大名が用いた船としては日本で現存する唯一の鯨船である千山丸を保存し、その他の展示物も徳島城と阿波水軍についてよく解説されていて見ごたえがある。(H8.10.15) 徳島市内にある平山城。徳島中央公園の中にあり、本丸はここらしいというものしかなく、実際に碑すら立っていない。遺構は石垣と堀、そして庭園のみ。庭園は往時を偲ばせるもの大いにあり、一見の価値があるが、庭園のとなりにある徳島城博物館には大名が用いた船としては日本で現存する唯一の鯨船である千山丸を保存し、その他の展示物も徳島城と阿波水軍についてよく解説されていて見ごたえがある。(H8.10.15) |
| 一宮城 南北朝 山城(144m) |
山頂一帯に石垣が整然と残り、四国を代表する山城である。南北朝時代に築城されたと言われ、小笠原氏の本拠地であった。秀吉の四国征伐の際には長宗我部元親の宿老谷忠澄がおり、秀長4万の軍勢と20日に渡って交戦したと伝えられる。残存石垣は蜂須賀氏入封の折の修復によるものである。 |
| 日和佐城 戦国 山城 |
*Telefax Networkのページ |
| 岡崎城 戦国 山城 |
*徳島県のページ(鳥居博物館) 淡路島から鳴門大橋を渡り、四国徳島県に入ってすぐの鳴門市にある。妙見山山頂には模擬天守閣があり、鳥居龍蔵記念博物館になっている。その前にある妙見神社の裏手には石垣がわずかに残っており、在りし日の姿を偲ばせる。阿波九城の一つ。(H8.10.15) 淡路島から鳴門大橋を渡り、四国徳島県に入ってすぐの鳴門市にある。妙見山山頂には模擬天守閣があり、鳥居龍蔵記念博物館になっている。その前にある妙見神社の裏手には石垣がわずかに残っており、在りし日の姿を偲ばせる。阿波九城の一つ。(H8.10.15) |
| 宍喰城(ししくい) 戦国 山城 |
|
| 川島城 近世 平城 |
*徳島中央広域連合のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 松山城 近世 平山城(132m) 日本百名城:81 |
 〈天守,乾櫓,野原櫓,一の門,一の門南櫓,二の門,二の門南櫓,三の門,三の門南櫓,仕切門,紫竹門,隠門,隠門続櫓,戸無門,その他塀7〉 〈天守,乾櫓,野原櫓,一の門,一の門南櫓,二の門,二の門南櫓,三の門,三の門南櫓,仕切門,紫竹門,隠門,隠門続櫓,戸無門,その他塀7〉当城は1602年に築城の名手加藤嘉明によって築城された。嘉明はこの地の中心であった湯築城・松前城といった城郭を破却し、石材や建物を移築したと伝えられる。ここには五層の大天守が上がったが、1642年に三層に改められ、それも1784年に落雷により焼失してしまった。現在残る天守は幕末に瀬戸内への外国船監視という名目で幕府の許可を得て1852年に再築されたもので、現存する天守の中では最も新しいものである。しかしそれだけに櫓19基、門20棟が現存し、高い現存率を誇る。 *公式 *松山市 *松山市公式観光WEBサイト
|
| 湯築城 戦国 丘城 日本百名城:80 |
戦国大名河野氏の居城。 道後温泉の隣にある道後公園がそれであるが、石垣は松山城築城の際にその礎石として持ち出され、明治になるまでは荒れ放題だったという。今はきちんと整備された公園になっており、頂上には展望台もできて東に温泉街、西に松山の町並みと城が見渡せるようになっている。ただ遺構はまったくなく、入り口のところに碑が立つのみである。道後温泉に来たついでに散歩でもしようかという感じで寄るにはいいところかもしれない。(H9.3.11) 道後温泉の隣にある道後公園がそれであるが、石垣は松山城築城の際にその礎石として持ち出され、明治になるまでは荒れ放題だったという。今はきちんと整備された公園になっており、頂上には展望台もできて東に温泉街、西に松山の町並みと城が見渡せるようになっている。ただ遺構はまったくなく、入り口のところに碑が立つのみである。道後温泉に来たついでに散歩でもしようかという感じで寄るにはいいところかもしれない。(H9.3.11)
|
| 今治城 近世 海城 |
 1604年に藤堂高虎によって築城された。櫓は19基あげられたが、天守は1608年に丹波亀山城に移築されたと伝えられる。
1604年に藤堂高虎によって築城された。櫓は19基あげられたが、天守は1608年に丹波亀山城に移築されたと伝えられる。*今治市  思っていたよりはずいぶん大きな城という印象を持った。が、やはりコンクリート城の悲しさで史跡という感じは非常に薄い。隅櫓も5つのうち2つを復元しているのだが多聞が途中で切られていてなんか変。また山里櫓の入り口から入ったのだがこんなところに入り口があったのかどうかはなはだ疑問。また、三の丸はどこに行ったのだろう?小藩になった時点でなくしてしまったのだろうか?とまあ、いろんな疑問の残る城だったが、高虎らしい縄張りが印象的な城だった。それから駅からの往復を入れて1時間半もあれば大丈夫だろうと思っていたら結構離れていて帰りは走ることになってしまった。わざわざ降りてまで見に行く城ではないと思う。(H9.3.12) 思っていたよりはずいぶん大きな城という印象を持った。が、やはりコンクリート城の悲しさで史跡という感じは非常に薄い。隅櫓も5つのうち2つを復元しているのだが多聞が途中で切られていてなんか変。また山里櫓の入り口から入ったのだがこんなところに入り口があったのかどうかはなはだ疑問。また、三の丸はどこに行ったのだろう?小藩になった時点でなくしてしまったのだろうか?とまあ、いろんな疑問の残る城だったが、高虎らしい縄張りが印象的な城だった。それから駅からの往復を入れて1時間半もあれば大丈夫だろうと思っていたら結構離れていて帰りは走ることになってしまった。わざわざ降りてまで見に行く城ではないと思う。(H9.3.12) |
| 大洲城 近世 平山城 |
 〈三の丸南隅櫓,高欄櫓,台所櫓,苧綿櫓〉 〈三の丸南隅櫓,高欄櫓,台所櫓,苧綿櫓〉鎌倉時代末期、宇都宮氏によって築城され、大野氏・戸田氏などが入城。藤堂高虎・脇坂安治の時代に近世城郭として完成し、四重天守があげられた。それに現存する高欄櫓、台所櫓を多聞櫓で結んだ複合連結式天守であった。1617年、加藤氏が入封、明治まで在城した。 *大洲市  伊予大洲駅について地図を見たら結構離れていたので、時間の都合でタクシーで城に向かった。すると、橋を渡りながら見える城。一瞬ここは木曽川か?というような風景。期待に胸膨らませながら城に向かったのだが、天守の真下くらいまでタクシーが入っていく。タクシーを降りて、本丸に上がってみても何だか重みが薄い。周りを見て感じたのは、道路だと思う。城の中の道路が整備され過ぎていて、完全に自動車道になっているのだ。本丸のギリギリまで車道が続いていて、車が入れるようになっている。これは完全に出鼻をくじかれた感じになった。やはり城は全体として歴史を感じられるものであってほしいのである。 伊予大洲駅について地図を見たら結構離れていたので、時間の都合でタクシーで城に向かった。すると、橋を渡りながら見える城。一瞬ここは木曽川か?というような風景。期待に胸膨らませながら城に向かったのだが、天守の真下くらいまでタクシーが入っていく。タクシーを降りて、本丸に上がってみても何だか重みが薄い。周りを見て感じたのは、道路だと思う。城の中の道路が整備され過ぎていて、完全に自動車道になっているのだ。本丸のギリギリまで車道が続いていて、車が入れるようになっている。これは完全に出鼻をくじかれた感じになった。やはり城は全体として歴史を感じられるものであってほしいのである。若干残念な気持ちを持ちつつも、完全再現したという天守に入ってみた。最初に入ったところが歴史の重みを感じたので、あれ?と思ったのだが、どうも隣接する櫓は現存していて、そこに復元天守を繋げた形になっているようだった。天守の両側に現存櫓があり、その両方に入れるのである。これは逆に感動した。もちろん天守も感動しなかったわけではない。復元するのであれば、絶対に木で作ってもらいたいし、よくこれを木で作れたものだと思う。ただ、それでもやはり軽さを感じてしまう。我ながら無理を言っている。歴史を重ねれば重みが出るはずである。それでも全体的に言うと感動までは至らなかった。それは車道も影響しているのか。期待し過ぎていたせいもあるかもしれない。非常に良い城跡であるとは思うが、最上位レベルではない、そんな感覚だった。(H28.4.6) |
| 宇和島城 近世 平山城 |
 〈天守〉 〈天守〉築城は藤堂高虎、現存天守は伊達宗利が城主の時代、1662年からの修築工事で再建されたもので、装飾性が重んじられる層塔式天守である。 *宇和島市観光協会 *宇和島市  現存12城で唯一行けていなかった城だったので、すごいワクワクして行った。とは言っても、小さな天守がぽつんと残っていて、というレベルかと想定していたところ…いい意味で裏切られた。 現存12城で唯一行けていなかった城だったので、すごいワクワクして行った。とは言っても、小さな天守がぽつんと残っていて、というレベルかと想定していたところ…いい意味で裏切られた。駅から城に向かって歩いていくと途中で山の上に城が見え始め、入口の武家長屋門を入ると急な石段が続き、大規模な石垣が出現して、その間を登っていって、本丸に至り、本丸の一角に天守があって、というこのストーリー性が何とも言えない。石段をセメントで固めていることが若干残念ではあったが、雰囲気を壊すほどではない。 本丸では桜が満開で、一部花見客もいる中、天守の外観を観察した。行く前から感じていたのだが、この天守、人が笑っているように見えないだろうか。非常にユーモラスで、実際に見てもなお親しみを持てる城であった。 もちろん、天守の中も全く期待を裏切らない。現存天守ならではの歴史に裏付けられた重みと安定感。末永く保存していってもらいたいと心から思える城跡であった。(H28.4.6) |
| 大森城 戦国 山城(319m) |
|
| 川之江城 室町 山城 |
|
| 能島城 室町 水城 続日本百名城:178 |
 室町から戦国時代にかけて芸予諸島で活躍した村上水軍。村上義顕の代の時、3人の子が分家独立した。1419年に長男雅房が築城したのがこの城で、周囲700メートルの島全体を城塞化した。 室町から戦国時代にかけて芸予諸島で活躍した村上水軍。村上義顕の代の時、3人の子が分家独立した。1419年に長男雅房が築城したのがこの城で、周囲700メートルの島全体を城塞化した。*今治地方観光協会
|
| 因島城 室町 水城 |
因島には次男の村上吉豊が築城。 昭和58年に模擬天守閣が建てられたが、歴史的には何の関連性も無い。水軍ゆかりの資料が展示される。 |
| 来島城 室町 水城 |
来島には三男村上吉房が築城。この城も周囲850メートルの島全体を城塞化している。 *内橋さんのページ |
| 岩城亀山城 室町 水城 |
村上水軍の海城の一つ。岩城島に築かれた。 *山ぽんのホームページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 高知城 近世 平山城(42m) |
 〈天守,懐徳館,黒鉄門,詰門,東多聞,廊下門,納戸蔵,西多聞,追手門,その他矢狭間塀6〉 〈天守,懐徳館,黒鉄門,詰門,東多聞,廊下門,納戸蔵,西多聞,追手門,その他矢狭間塀6〉高知山内家の本城である。前身は長宗我部氏の浦戸城で、黒鉄門はそのまま移築されたと伝えられる。1601年に高知に入国してきた山内一豊によって構築される。1727年に焼失するが20年後に望楼型天守として再建される。現在残るのはその時のもので、本丸が建築群ごと残る城郭としては全国で唯一高知城だけである。(姫路城は備前曲輪が明治に焼失している)天守は三重六階で、大壁づくりである。 *公式ページ  ほんとに言葉が出ない。まず追手門に来た時にそこから見える景色に圧倒されてしまった。これぞお城!!という構えなのだ。もう大きさ、縄張り、御殿建築、何をとっても文句のつけようがない。登っていくと三の丸・二の丸があるが、こちらは明治になる時に破壊されてしまったとの事でただの広場になっている。そちらを横目に見ながら本丸の入り口へ。本丸の入り口?そう、まさに入り口があるのである。本丸は完全に独立した曲輪で、周りを石垣に囲まれているためにそちらに渡るには橋のようなものが必要なのだ。高知城では廊下門という門をそこに挟み込み、橋ではなく櫓として一階と二階が交差するような構造になっている。つまり二階部分を通って本丸に移動できるのである。そういうものを現実に見るのは初めてで、かつその中にある家老などの控えの間の存在が非常に珍しく感じた。そして本丸に出るとやはり日本唯一と言われる完全に残存した本丸は威厳が違う。天守閣だけではなく本丸御殿が、本丸を囲む多聞が、相乗的に迫ってくるものがある。中に入ると天守内部には余計な展示物はなく本物の木の匂いが心地よく、上では縄張りが一望できて気分は最高。その他にも完存する貴重な本丸御殿も見学でき、多聞櫓も陳列室として内部を見学できる。実際ほとんど呆然と見学してしまったので展示物などはほとんど見ていないのだが、それでも二時間以上時間がかかってしまった。とにかくお城にきてこんなに感動したのは初めての経験だった。(H9.3.11)(H25.1.11)(H28.8.25)(H30.3.1)(H30.3.26) ほんとに言葉が出ない。まず追手門に来た時にそこから見える景色に圧倒されてしまった。これぞお城!!という構えなのだ。もう大きさ、縄張り、御殿建築、何をとっても文句のつけようがない。登っていくと三の丸・二の丸があるが、こちらは明治になる時に破壊されてしまったとの事でただの広場になっている。そちらを横目に見ながら本丸の入り口へ。本丸の入り口?そう、まさに入り口があるのである。本丸は完全に独立した曲輪で、周りを石垣に囲まれているためにそちらに渡るには橋のようなものが必要なのだ。高知城では廊下門という門をそこに挟み込み、橋ではなく櫓として一階と二階が交差するような構造になっている。つまり二階部分を通って本丸に移動できるのである。そういうものを現実に見るのは初めてで、かつその中にある家老などの控えの間の存在が非常に珍しく感じた。そして本丸に出るとやはり日本唯一と言われる完全に残存した本丸は威厳が違う。天守閣だけではなく本丸御殿が、本丸を囲む多聞が、相乗的に迫ってくるものがある。中に入ると天守内部には余計な展示物はなく本物の木の匂いが心地よく、上では縄張りが一望できて気分は最高。その他にも完存する貴重な本丸御殿も見学でき、多聞櫓も陳列室として内部を見学できる。実際ほとんど呆然と見学してしまったので展示物などはほとんど見ていないのだが、それでも二時間以上時間がかかってしまった。とにかくお城にきてこんなに感動したのは初めての経験だった。(H9.3.11)(H25.1.11)(H28.8.25)(H30.3.1)(H30.3.26)
|
| 岡豊城 戦国 平山城 |
 築城年代は不明だが、長宗我部氏によって築城したと伝わる。1500年代、長宗我部国親・元親親子が土佐・四国全土を統一する間、居城としていた。秀吉の四国征伐の後、土佐一国を安堵され、浦戸城に移った。 築城年代は不明だが、長宗我部氏によって築城したと伝わる。1500年代、長宗我部国親・元親親子が土佐・四国全土を統一する間、居城としていた。秀吉の四国征伐の後、土佐一国を安堵され、浦戸城に移った。*高知県立歴史民俗資料館 *お城の旅日記 *城郭放浪記  高知市中心部から車で30分あまりの小高い丘の中腹に歴史民俗資料館があり、そのさらに上が城跡だった。公園というか、散策コースとしての整備が進んではいるが、過去の遺構がよく残っており、十分に楽しむことができた。特に空堀は昔の状態をよく残しており、また詰・二ノ段・三ノ段・四ノ段等の曲輪も非常によく残っている。遺構のメインは土塁の中から出てきたという「三ノ段にある石垣」と思われるが、修復された上に苗木が植えられており、正直興醒めだった。ただ、その狭い三ノ段のほぼ目一杯を使って建物の礎石跡があり、在りし日を偲ぶにはもってこいだった。 高知市中心部から車で30分あまりの小高い丘の中腹に歴史民俗資料館があり、そのさらに上が城跡だった。公園というか、散策コースとしての整備が進んではいるが、過去の遺構がよく残っており、十分に楽しむことができた。特に空堀は昔の状態をよく残しており、また詰・二ノ段・三ノ段・四ノ段等の曲輪も非常によく残っている。遺構のメインは土塁の中から出てきたという「三ノ段にある石垣」と思われるが、修復された上に苗木が植えられており、正直興醒めだった。ただ、その狭い三ノ段のほぼ目一杯を使って建物の礎石跡があり、在りし日を偲ぶにはもってこいだった。いずれにしても、1時間以上ゆっくりと散策してもし足りないくらい。これほどよく遺構を残している戦国時代の城跡はあまりないと思われる。結論としては非常に良い。是非行くべき城の一つである。(H25.1.11) |
| 浦戸城 戦国 平山城 |
 秀吉の四国征伐の後、長宗我部元親が岡豊城から居城を移した。関ヶ原の合戦後、山内一豊が入城したが、長宗我部氏の家臣が非常に反発したと言われる。一豊は間もなく高知城に居城を移し、廃城となった。 秀吉の四国征伐の後、長宗我部元親が岡豊城から居城を移した。関ヶ原の合戦後、山内一豊が入城したが、長宗我部氏の家臣が非常に反発したと言われる。一豊は間もなく高知城に居城を移し、廃城となった。*高知県立坂本龍馬記念館 *高知市  桂浜にある坂本龍馬記念館と国民宿舎周辺が本丸跡ということらしいが、ある程度石垣が移築されている。とはいえ全体像を想像できなくなっている点は残念ではある。それでも天守曲輪が残り、面白い。ただの丘といってしまえばそれまでだが過渡期にできた城だけにそう思って見ると興味深いものがある。(H9.3.11) 桂浜にある坂本龍馬記念館と国民宿舎周辺が本丸跡ということらしいが、ある程度石垣が移築されている。とはいえ全体像を想像できなくなっている点は残念ではある。それでも天守曲輪が残り、面白い。ただの丘といってしまえばそれまでだが過渡期にできた城だけにそう思って見ると興味深いものがある。(H9.3.11) 28年ぶりに再訪。ほとんど記憶が無くなっていたが、桂浜から水族館の裏手の山道を15分ほど登ると、坂本龍馬記念館があり、その裏手にある天守曲輪が良く残っている。そして、天守曲輪の記念館側に、少し石垣が移築されている。ただ、若干石垣がきれいすぎて、本当に?と言いそうになってしまった。とはいえ、前回来たときは城巡りを始めたてのタイミングのため、何もない印象だったが、改めて来てみると十分に城跡。興味深い城跡だった。(R7.10.30) 28年ぶりに再訪。ほとんど記憶が無くなっていたが、桂浜から水族館の裏手の山道を15分ほど登ると、坂本龍馬記念館があり、その裏手にある天守曲輪が良く残っている。そして、天守曲輪の記念館側に、少し石垣が移築されている。ただ、若干石垣がきれいすぎて、本当に?と言いそうになってしまった。とはいえ、前回来たときは城巡りを始めたてのタイミングのため、何もない印象だったが、改めて来てみると十分に城跡。興味深い城跡だった。(R7.10.30) |
| 中村城 戦国 平山城 |
|
| 安芸城 近世 平山城 |
お城トップページ |
トピックス |
データベースの歩き方 |
読み替え |
既訪城郭一覧 |
掲示板
蝦夷地 |
東山道 |
北陸道 |
東海道 |
畿内 |
山陰道 |
山陽道 |
南海道 |
西海道 |
琉球