

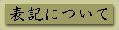
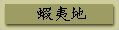
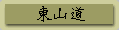
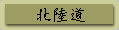
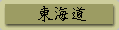
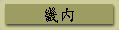
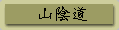
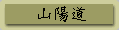
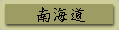
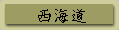
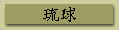
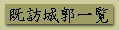

    | ||
|---|---|---|
|
| ||
| ||
  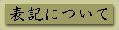 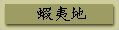 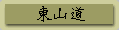 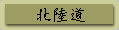 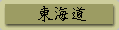 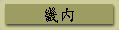 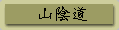 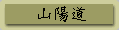 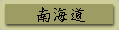 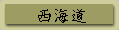 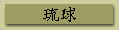 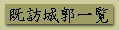 
|
| ||||||||
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 村上城(C) 近世 平山城(135m) |
揚北衆として名高い本庄氏の居城である。1598年に村上頼勝が改修、1618年には堀直寄が総石垣で麓に居館を営む近世城郭に改修した。戊辰戦争の折に兵火にかかり、全焼した。 *越後の歴史探訪観光案内所 |
| 新発田城 戦国 平城 |
 〈表門,旧二の丸隅櫓〉 〈表門,旧二の丸隅櫓〉1598年に蒲原郡六万石を領した溝口秀勝によって築城されたが1684年失火により全焼し、再築された。現存する櫓・櫓門などはその時のもの。加えて、三階櫓、辰巳櫓が16年6月完成を目指して復元工事中。
|
| 春日山城(C) 戦国 山城(180m) |
  15〜16世紀初、守護代長尾為景の居城として築かれる。守護上杉顕定を破り、戦国大名の居城となり、整備が進む。その後上杉謙信・景勝の居城として栄えるが、景勝会津移封に伴い、堀秀治が入城。福島城築城によって廃城となる。 15〜16世紀初、守護代長尾為景の居城として築かれる。守護上杉顕定を破り、戦国大名の居城となり、整備が進む。その後上杉謙信・景勝の居城として栄えるが、景勝会津移封に伴い、堀秀治が入城。福島城築城によって廃城となる。遺構としては、縄張りが広範囲に残り、空掘・土塁を広く見ることができる。林泉寺惣門は春日山城より移築されたと伝えられる。 *上越市のホームページ  僕を山城ファンにさせた張本人。あいにくの雨だったが、今考えてみるとそれがこの城を引き立てたような気すらする。石垣もほとんど残っていなかったが、これまで城というと天守閣というイメージだったのを、城の縄張り等に目を向けるきっかけになった。これ以来城跡のある山を訪れることが趣味になりつつある。(H3.8.6) 僕を山城ファンにさせた張本人。あいにくの雨だったが、今考えてみるとそれがこの城を引き立てたような気すらする。石垣もほとんど残っていなかったが、これまで城というと天守閣というイメージだったのを、城の縄張り等に目を向けるきっかけになった。これ以来城跡のある山を訪れることが趣味になりつつある。(H3.8.6)  城跡の中にあるという春日山旅館に宿泊し、起床後、朝から念願の再訪を果たした。夜中それも朝方に物凄い大雨になり、どうなることやらと思ったが、起きる頃には何とか雨も上がり、天候も味方してくれた。 城跡の中にあるという春日山旅館に宿泊し、起床後、朝から念願の再訪を果たした。夜中それも朝方に物凄い大雨になり、どうなることやらと思ったが、起きる頃には何とか雨も上がり、天候も味方してくれた。感想としては、やはり素晴らしい城跡だった。写真は本丸から見た二の丸と頚城平野。この景色を謙信も見ていたのかと思うと、やはり興奮するものがある。それから直江屋敷跡周辺、3段に渡る曲輪があるのだが、側道を歩いていると、そこに屋敷があった時が思い浮かぶようである。その下にある千貫門跡。土塁が切れていて、そこに門があったというだけのものなのだが、奥には二本の道がある。その道はどちらも土塁に挟まれていて、奥に進むと、なんと急峻な崖に通じている。不審者はそこに通して土塁上から攻撃し、崖に突き落としたということらしい。何というリアリティだろうか。 さて、その後林泉寺まで足を伸ばす。惣門は春日山城から移築したものと伝えられる。(写真参照)しかし入場料500円は高くないか。見るべきものは山門と惣門だけ、本堂は入口がサッシの扉になっていて、歴史の「れ」も感じられない。宝物館にはいろいろとあるようだったが、時間の関係で寄ることはできなかった。参拝するのにすら金を取るとは・・・どう考えても宝物館の入場料とすべき。つまらないところで興醒めだった。(H16.9.25) |
| 高田城 近世 平城 |
 1613年徳川家康が信越・北陸の押えとして築城。石垣を一切使わない土塁と濠による城郭で、本丸南西隅土塁上に三重櫓が構築された。天守に代わって「御三階櫓」と呼ばれ、城の象徴となったが、明治19年頃取り壊されてしまった。 1613年徳川家康が信越・北陸の押えとして築城。石垣を一切使わない土塁と濠による城郭で、本丸南西隅土塁上に三重櫓が構築された。天守に代わって「御三階櫓」と呼ばれ、城の象徴となったが、明治19年頃取り壊されてしまった。平成五年に御三階櫓が外観復元され、高田公園として整備されている。広大な外堀と内堀、土塁が残る。 *上越市のホームページ *越後の歴史探訪観光案内所   堀が非常に多く残っていることに驚いた。特に外堀はすごい。川を堀の代わりにした城であれば、残っていてもおかしくないのだが、高田城はそうではない。その証拠に広大な外堀が蓮の葉で埋め尽くされているのである。幅30mくらいはあるのではないだろうか。時代の流れの中で内堀が残っていても外堀は埋められてしまうケースが多いが、ここはすごい。これだけの外堀を見たのは初めてかもしれない。 堀が非常に多く残っていることに驚いた。特に外堀はすごい。川を堀の代わりにした城であれば、残っていてもおかしくないのだが、高田城はそうではない。その証拠に広大な外堀が蓮の葉で埋め尽くされているのである。幅30mくらいはあるのではないだろうか。時代の流れの中で内堀が残っていても外堀は埋められてしまうケースが多いが、ここはすごい。これだけの外堀を見たのは初めてかもしれない。本丸は上越教育大学付属中学が大半を占めており、外観復元された御三階櫓が控えめに建っているが、それでも内堀に映える御三階櫓は見ていて飽きない。また、二の丸跡には陸上競技場や野球場ができているものの、それが曲輪に忠実に建っていて、大枠は崩れていない。明治末期に軍の駐屯地となったことから本丸土塁が大きく崩されていることは残念ではあるが、それでもこれだけ広範囲に曲輪が残っているのは驚嘆に値する。是非一度訪れるべき城跡だと思う。(H16.9.24) |
| 長岡城(E) 近世 平城 |
 南北朝時代、蔵王に城が築かれ、古志長尾氏が居城してこの地方を治めたが、江戸時代に堀直寄が長岡に城を移し、1618年に牧野忠成が封された。 南北朝時代、蔵王に城が築かれ、古志長尾氏が居城してこの地方を治めたが、江戸時代に堀直寄が長岡に城を移し、1618年に牧野忠成が封された。現在のJR長岡駅周辺を中心とした平城で、本丸の隅櫓の一つに御三階が築かれ、天守代わりをしていた。しかし、1868年、戊辰戦争で跡形もなく焼失し、当時を偲ばせるものは何も残っていない。 *越後の歴史探訪観光案内所
|
| 栃尾城(C) 戦国 山城 |
*越後の歴史探訪観光案内所 |
| 坂戸城(C) 戦国 山城 |
 南北朝時代以降、上田長尾の本拠となり、戦国時代には長尾政景が春日山の長尾景虎と対立したのは有名である。景虎が政景の子(景勝)を自分の養子とし、この城を手中とする。以来坂戸城は春日山城の支城として、関東と越後を結ぶ交通路を押さえてきた。江戸時代には堀氏の居城となったが、堀直寄の飯山転封に伴い、廃城となった。 南北朝時代以降、上田長尾の本拠となり、戦国時代には長尾政景が春日山の長尾景虎と対立したのは有名である。景虎が政景の子(景勝)を自分の養子とし、この城を手中とする。以来坂戸城は春日山城の支城として、関東と越後を結ぶ交通路を押さえてきた。江戸時代には堀氏の居城となったが、堀直寄の飯山転封に伴い、廃城となった。現在は杉林の中に城主の館や家臣屋敷跡が残り、またその背後の坂戸山(634m)には大規模な山城遺構が残っている。
|
| 与板城 | *越後の歴史探訪観光案内所 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 波多城(E) 鎌倉 平城 |
|
| 久知城 戦国 平山城 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 富山城 近世 平城 |
 越中守護の畠山氏が来任しないため、実際は守護代神保氏が越中西部を、もう一人の守護代椎名氏が東部を治めていた。1543年神保長職が家臣水越勝重に命じその境界にあたる神通川と鼬川に囲まれた川洲に砦を築いたのが始まりとされる。1579年織田軍の部将佐々成政が越中に入り、拡張・改築を重ねる。その後前田氏の領有となるが三代利常が富山藩を分封し、以後230年間歴代藩主の居城となった。 越中守護の畠山氏が来任しないため、実際は守護代神保氏が越中西部を、もう一人の守護代椎名氏が東部を治めていた。1543年神保長職が家臣水越勝重に命じその境界にあたる神通川と鼬川に囲まれた川洲に砦を築いたのが始まりとされる。1579年織田軍の部将佐々成政が越中に入り、拡張・改築を重ねる。その後前田氏の領有となるが三代利常が富山藩を分封し、以後230年間歴代藩主の居城となった。現在城跡は公園となり、石垣や土塁、内堀の一部が残されている。現在本丸虎口石垣には模擬天守が建てられている。  夕方になっていたのだが、雪の中を這うようにやってきた。ところが、本丸跡内には入れたのだが、天守閣的建物(郷土博物館)には入れなかった。17:00までで、入場は16:30までだという。ついたのが17:00過ぎだったからなんともタイミングの悪い。ただ、その天守閣的建物たるや、鉄門石垣の上に建てられているというからばかばかしくなってくる。また、その逆側(市役所側)にも天守閣的な建物(隅櫓のつもりか?)があるが、これまた美術館のようなものと連結していて、意味不明。外から見ると普通の城なのだが、本丸内から見るとその美術館のガラス張りとくっついてて誠に奇怪。どちらも入れなかったが、入っても大した事は無かっただろうと思われる。(H11.2.20) 夕方になっていたのだが、雪の中を這うようにやってきた。ところが、本丸跡内には入れたのだが、天守閣的建物(郷土博物館)には入れなかった。17:00までで、入場は16:30までだという。ついたのが17:00過ぎだったからなんともタイミングの悪い。ただ、その天守閣的建物たるや、鉄門石垣の上に建てられているというからばかばかしくなってくる。また、その逆側(市役所側)にも天守閣的な建物(隅櫓のつもりか?)があるが、これまた美術館のようなものと連結していて、意味不明。外から見ると普通の城なのだが、本丸内から見るとその美術館のガラス張りとくっついてて誠に奇怪。どちらも入れなかったが、入っても大した事は無かっただろうと思われる。(H11.2.20) |
| 高岡城(C) 近世 平城 |
富山城焼失に伴い、前田利長が隠居城として築いたもの。利長病没後、一国一城令により廃城。 *高岡市のページ  これまた雪の中をてこてこやってきた。途中大仏さんがドンと座っていてびっくりした。そのすぐ近くが城跡なのだが、高岡古城公園として市の公共施設が入っている。本丸跡は射水神社と芸術公園となり、二の丸三の丸をはじめ、各曲輪には図書館、体育館、博物館等が曲輪毎に建っている。近代平城でしかできない使い方であろう。公共施設が入ってしまっている関係で、城跡らしいところはほとんど見られなかったものの、ある意味曲輪はきちんと残っていて面白かった。(H11.2.20) これまた雪の中をてこてこやってきた。途中大仏さんがドンと座っていてびっくりした。そのすぐ近くが城跡なのだが、高岡古城公園として市の公共施設が入っている。本丸跡は射水神社と芸術公園となり、二の丸三の丸をはじめ、各曲輪には図書館、体育館、博物館等が曲輪毎に建っている。近代平城でしかできない使い方であろう。公共施設が入ってしまっている関係で、城跡らしいところはほとんど見られなかったものの、ある意味曲輪はきちんと残っていて面白かった。(H11.2.20) |
| 魚津城(E) 戦国 平城 |
1335年、南朝方の権名孫八が松倉城の支城として築いたのが始まりといわれる。戦国の頃、上杉謙信・景勝が前線の城として守らせたが、柴田・佐々・前田の大軍の前に落城した。元和一国一城令で廃城となったものと思われるが、三方を川に囲まれた堅固な城であった。 |
| 木舟城 | 1184年に石黒氏が築城、以後周辺の勢力を持つが、1574年に上杉謙信に攻められ、落城。その後、佐々氏の領有するところとなったが、1585年に秀吉に攻められて陥落、前田秀継が入ったものの同年11月に大地震で崩壊、秀継は圧死した。これにより廃城。 |
| 今石動城(D) 戦国 山城 |
四万石の前田利秀の居城であった。今は城山公園となり、4000本のソメイヨシノが咲き誇る。 *城山公園のページ |
| 道坪野城(D) 室町 山城(166.2m) |
|
| 安楽寺砦(D) 室町 山城(176.9m) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 七尾城(C) 戦国 山城(300m) |
 能登守護畠山義元によって築城された典型的な山城。1574年の城主暗殺事件以後、内乱状態となった中で上杉謙信が能登へ侵攻してきたため、畠山勢は当城に依って守りを固めた。謙信は支城を攻略して七尾城を孤立化させた上で、越後に戻る。畠山軍は織田軍に助けを求めるべく南加賀に軍を進めるも一向一揆軍に阻まれ、さらに五歳の城主が流行性疾病により急死。最後は重臣遊佐継光の裏切りによってついに落城を見ることになった。1578年には織田軍がこれを攻略、能登を与えられた前田利家はあまりに実戦的にすぎるとして小丸山城を築き、そこに入った。遺構としては曲輪跡や石垣、土塁などが残る。 能登守護畠山義元によって築城された典型的な山城。1574年の城主暗殺事件以後、内乱状態となった中で上杉謙信が能登へ侵攻してきたため、畠山勢は当城に依って守りを固めた。謙信は支城を攻略して七尾城を孤立化させた上で、越後に戻る。畠山軍は織田軍に助けを求めるべく南加賀に軍を進めるも一向一揆軍に阻まれ、さらに五歳の城主が流行性疾病により急死。最後は重臣遊佐継光の裏切りによってついに落城を見ることになった。1578年には織田軍がこれを攻略、能登を与えられた前田利家はあまりに実戦的にすぎるとして小丸山城を築き、そこに入った。遺構としては曲輪跡や石垣、土塁などが残る。*益田市のページ *内橋さんのページ  和倉温泉で一泊して、朝からお城に向かう。和倉温泉駅で駅員さんに行き方を聞くと、「え?そんなとこに行くの?」と言われ、バス停でおじさんとしゃべっててこれから行くと言うと「え?城跡って言っても何もないよ」と言われ、散々だったが、とにかくバスで七尾の駅まで行って、そこからタクシーで行くこととする。ただ、「往復すると4〜5千円かかる」と言われ、「じゃあ往復で4千円ぽっきりで」ということで交渉をまとめ、いざ出発。タクシーの運転手さんが本部と無線でいろいろ聞いてくれるのだが、それが、「雪でそんなとこまで行けない」だの「長靴は持ってるか?」だの、冷や汗ものの会話。実際山に登り始めると徐々に雪深くなっていって、途中あと一キロというところで車が徐行し始めたときはあせった。ここまでか。。。という感じだったのだが、何とか到着。車を降りてから本丸跡までは少し歩かないと行けないのだが、それがきれいに雪が積もっていて、そこには狐の足跡だけ。きれいに残る石垣には適度に雪が積もっていて、さらに感動。本丸跡では吹雪がすごく、きれいであろう景色もほとんど見られなかったが、それでも相当すばらしい城だった。山城フリークには、見逃せない城の一つだろう。(H11.2.20) 和倉温泉で一泊して、朝からお城に向かう。和倉温泉駅で駅員さんに行き方を聞くと、「え?そんなとこに行くの?」と言われ、バス停でおじさんとしゃべっててこれから行くと言うと「え?城跡って言っても何もないよ」と言われ、散々だったが、とにかくバスで七尾の駅まで行って、そこからタクシーで行くこととする。ただ、「往復すると4〜5千円かかる」と言われ、「じゃあ往復で4千円ぽっきりで」ということで交渉をまとめ、いざ出発。タクシーの運転手さんが本部と無線でいろいろ聞いてくれるのだが、それが、「雪でそんなとこまで行けない」だの「長靴は持ってるか?」だの、冷や汗ものの会話。実際山に登り始めると徐々に雪深くなっていって、途中あと一キロというところで車が徐行し始めたときはあせった。ここまでか。。。という感じだったのだが、何とか到着。車を降りてから本丸跡までは少し歩かないと行けないのだが、それがきれいに雪が積もっていて、そこには狐の足跡だけ。きれいに残る石垣には適度に雪が積もっていて、さらに感動。本丸跡では吹雪がすごく、きれいであろう景色もほとんど見られなかったが、それでも相当すばらしい城だった。山城フリークには、見逃せない城の一つだろう。(H11.2.20) |
| 穴水城(D) 室町 平山城 |
勇名をはせた畠山氏の重臣長氏の居城。一度は上杉謙信によって落城し、長一族も滅んでしまうが、当時僧となっていた長連龍が謙信の死の知らせを受けると5ヶ月後には当城を奪回、さらに各地で上杉軍を迎え撃ち、織田軍とも協力して上杉勢力を払拭するめざましい活躍を見せた。こうして信長から所領を安堵され、前田利家の能登入部後も前田家重臣の列に加わり、幕末までの安泰を築いた。 |
| 小丸山城 近世 山城 |
1581年に信長から能登を与えられた前田利家が金沢に居城を移すまで本拠とした城。畠山氏の七尾城よりも城下町経営のしやすく、港に近くて交通の便もよい小丸山に新しく築城した。 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 金沢城 近世 平山城 |
 〈石川門,三十間長屋〉 〈石川門,三十間長屋〉1546年一向一揆が富樫氏を滅ぼし、尾山御坊を本拠としたのが始まり。堅固な寺院城郭の寺内町だったと言われる。1580年、信長は柴田勝家を総大将にこれを攻略、勝家の甥の佐久間盛政が13万石で入城、御坊を改修、尾山城とした。1583年、賤ヶ岳の合戦の後、秀吉は前田利家に加賀2郡と能登を与え、利家は七尾城から尾山城に入城、以後加賀百万石の本拠となる。利家は高山右近に縄張を依頼したと言われ、1592年には5層の天守が上がった。 今日残るのは石川門・菱櫓・長塀・水手門・三十三間長屋。また、平成13年7月に菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓が復元された。明治以降に建てられた木造城郭建築物としては全国最大規模で、大径木の事前調達や土台石垣の解体、修築を含め、平成10年3月から3年4ヶ月をかけて造られた。 *金沢城・兼六園管理事務所 *再現金沢城 *金沢観光協会 *「お城の旅日記」のページ *「きまっし金沢」のページ  スキーの予定を取りやめ(膝痛のため)、急遽北陸旅行に変更し、特急雷鳥でやってきた。やはり主役は石川門とそれに併設されている櫓と中門なのだが、ただの門と思っていたので結構感動してしまった。裏門とはいえ、しっかりと残っているではないか。それどころかこれだけの門がきちんとした姿で現存している城は少ないだろう。感動しながら城内に入ると、三の丸で工事が行われている。菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓の復元工事中のようだ。完成が楽しみである。 スキーの予定を取りやめ(膝痛のため)、急遽北陸旅行に変更し、特急雷鳥でやってきた。やはり主役は石川門とそれに併設されている櫓と中門なのだが、ただの門と思っていたので結構感動してしまった。裏門とはいえ、しっかりと残っているではないか。それどころかこれだけの門がきちんとした姿で現存している城は少ないだろう。感動しながら城内に入ると、三の丸で工事が行われている。菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓の復元工事中のようだ。完成が楽しみである。さて、奥の本丸跡に入っていくと、うっそうとした森になっていて何も残っていない。また、一部がきれいに切り取られていて、戦中に何かに使われたのかと思わせた。で、その工事とともに特に印象に残ったのは人の少なさ。兼六園の人の多さに比して異常とも言える。城内で見た人というと工事関係者と韓国人と思われる観光客のみ。「おーい、何をやってる日本人?」と言いたい。(H11.2.19) |
| 小松城(C) 戦国 平城 |
1576年加賀一向一揆の部将若林長門が築城。1579年に柴田勝家によって攻略され、村上義明を置いた。その後丹羽長秀、長重の領土となるが関ヶ原合戦後は加賀前田藩領の支城として機能し、御三階櫓などが上がった。1639年から三代利常が隠居所として入城、一国一城制の下で二城の併存は異例のことであった。現在曲輪跡と櫓台の石垣が残る。 |
| 大聖寺城(D) 鎌倉 平山城 |
柴田勝家の越前攻めの際、拠点とするために城郭として整備したのが始まり。のち、加賀藩3代利常の3男利治が分封された。*鳥越村のページ |
| 鳥越城(D) | |
| 二曲城 | *鳥越村のページ |
| 松任城 | 一向一揆の際、一揆衆の一拠点として鏑木頼信が在城。1587年には丹羽長秀が入った。 *松任市のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 丸岡城 戦国 平山城 |
 〈天守〉 〈天守〉1576年柴田勝家の甥にあたる勝豊の造営と伝えられる。江戸時代に入ってからは福井城の支城として今村氏、本多氏が城代となった。本多成重の代に大名になったが、1695年丸岡騒動が起こり断絶、有馬清純が城主となり明治に及んだ。最盛期には櫓七基、城門七棟などがあったが天守以外には不明門(あかずのもん)の下層の一部が残るだけである。昭和21年の福井大地震で天守は崩壊し、現在見られる天守はその復旧であるが、完存する天守としては最古の遺構である。 *坂井市丸岡観光協会 *日本最古の丸岡城と日本の城郭めぐり  高橋(中学からの友達)とキャンプに行こうということになり、強引に押しとおして福井に行き、まず行った城。イメージとしては丘か山の上に林に囲まれてひっそりと天守閣が立っているという感じであったのだが、行ってみると結構ちゃんとした市街地にあってちょっと意外だった。一目見た時、高橋が最初に言った言葉が「ちょっとした金持ちの家みたいやな」。確かにあまり城という感じがしない。ところが中に入ってみればそこはやはり日本最古の天守閣建造物、その重みたるや並大抵のものではない。一層目には入り口を除く三方に石落しのでっぱりがあり、二層目には四方に小部屋があり、最上部の三層目は外に出れるようになっている。どれもこれも洗練されているとは思えないものであり、それが逆に古さを物語っていて非常に趣き深い。また、瓦がすべて石で出来ていて非常に珍しく感じた。おそらく相当の重さがあるであろうと推定されるため、それを支えるためには当時では相当な技術が必要だったろうし、ずいぶん丈夫な木を使って作られているのだろう。異常なほどに暑い中ではあったが、行った価値は充分にあった。(H9.8.2) 高橋(中学からの友達)とキャンプに行こうということになり、強引に押しとおして福井に行き、まず行った城。イメージとしては丘か山の上に林に囲まれてひっそりと天守閣が立っているという感じであったのだが、行ってみると結構ちゃんとした市街地にあってちょっと意外だった。一目見た時、高橋が最初に言った言葉が「ちょっとした金持ちの家みたいやな」。確かにあまり城という感じがしない。ところが中に入ってみればそこはやはり日本最古の天守閣建造物、その重みたるや並大抵のものではない。一層目には入り口を除く三方に石落しのでっぱりがあり、二層目には四方に小部屋があり、最上部の三層目は外に出れるようになっている。どれもこれも洗練されているとは思えないものであり、それが逆に古さを物語っていて非常に趣き深い。また、瓦がすべて石で出来ていて非常に珍しく感じた。おそらく相当の重さがあるであろうと推定されるため、それを支えるためには当時では相当な技術が必要だったろうし、ずいぶん丈夫な木を使って作られているのだろう。異常なほどに暑い中ではあったが、行った価値は充分にあった。(H9.8.2) |
| 福井城(C) 近世 平城 |
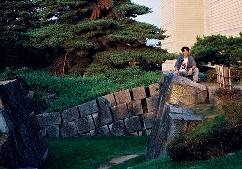 1601年、越前に入国してきた家康の次男結城秀康の居城として柴田勝家の居城のあった北庄に築城を開始。徳川政権北陸最大の拠点として重要視されたこの城は本丸や二の丸は家康自身が縄張りをするという力の入れようであった。しかし大城郭を一から築城するとなると経費がかさむというので北庄城を大改修することになったのである。その後松平忠昌の代に「北の庄」というのは敗北に通じ縁起がよくないと「福居」と改称したと言われている。現在では本丸跡に福井県庁舎が建っており、その他の遺構は何ら残っていない。 1601年、越前に入国してきた家康の次男結城秀康の居城として柴田勝家の居城のあった北庄に築城を開始。徳川政権北陸最大の拠点として重要視されたこの城は本丸や二の丸は家康自身が縄張りをするという力の入れようであった。しかし大城郭を一から築城するとなると経費がかさむというので北庄城を大改修することになったのである。その後松平忠昌の代に「北の庄」というのは敗北に通じ縁起がよくないと「福居」と改称したと言われている。現在では本丸跡に福井県庁舎が建っており、その他の遺構は何ら残っていない。*福井市のページ  ちょっと申し訳ないが、結構笑えるお城である。堀と石垣は堂々としたものでさすがと思えるものなのだが、それとその中にある県庁舎と県警の建物があまりにもミスマッチなのだ。ちょっと呆気に取られたというのが本音だろうか。確かに市の中心街で土地を有効利用したかったのは分かるのだが・・・もうちょっと他に利用方法を考えられなかったものか少々残念ではある。その県庁舎と県警の建物の影に隠れて天守台跡が残っている。これが思ったよりもお城らしさが残っていて趣き深かった。天守台と控天守台という二つがあるのだが、その控天守台は一方が地にのめり込んだ状態になっている。それには説明があって、福井大震災で陥没した跡なんだそうだ。さて逆側の城外が何やら騒がしいなと思って見てみると夜店が並んでお祭りという感じである。早速行ってみるとフェニックス祭りとか言うものらしかった。うちわをもらってフランクフルトを買って帰ってきた。(H9.8.2) ちょっと申し訳ないが、結構笑えるお城である。堀と石垣は堂々としたものでさすがと思えるものなのだが、それとその中にある県庁舎と県警の建物があまりにもミスマッチなのだ。ちょっと呆気に取られたというのが本音だろうか。確かに市の中心街で土地を有効利用したかったのは分かるのだが・・・もうちょっと他に利用方法を考えられなかったものか少々残念ではある。その県庁舎と県警の建物の影に隠れて天守台跡が残っている。これが思ったよりもお城らしさが残っていて趣き深かった。天守台と控天守台という二つがあるのだが、その控天守台は一方が地にのめり込んだ状態になっている。それには説明があって、福井大震災で陥没した跡なんだそうだ。さて逆側の城外が何やら騒がしいなと思って見てみると夜店が並んでお祭りという感じである。早速行ってみるとフェニックス祭りとか言うものらしかった。うちわをもらってフランクフルトを買って帰ってきた。(H9.8.2) |
| 北庄城(E) 近世 平城 |
1575年織田信長から越前49万石を与えられた柴田勝家は当城を本拠とし、九重の天守をもつと伝わる大城郭を築いた。のちに結城秀康が改築した北庄城(今の福井城)よりも少し南に位置し、現在の柴田神社境内に天守があったと言われている。 *日本の城のページ *内橋さんのページ  福井城を見た後、どうせなら北庄も見て行こうということになり、探すのだが延延見つからない。いろんな人に聞きつつようやく柴田神社を見付け、喜び勇んで見に行ったのだが。。。これはどう表現すればいいのだろう。とにかくすごかった。入るところに鳥居があり、その近くに説明板が立っていて、どうも平成十何年かには神社と城跡を合体させて一大公園にするということだった。「ほう、じゃあ今は工事中かもしれんな」とか思いつつ中に入っていくと、そこには城跡、神社どころか木材が積まれ、動かないブルドーザーがぽつんと・・・。周りをよく見てみると「勝家公、お市の方、茶々姫、はつ姫、江与姫居城の地」と書かれた立て札が倒れていた。元々遺構なんてなかったんだろうし、別にいいといえばいいんだろうが、やはりちょっと悲しいと思うのは僕だけではなかろう。(H9.8.2) 福井城を見た後、どうせなら北庄も見て行こうということになり、探すのだが延延見つからない。いろんな人に聞きつつようやく柴田神社を見付け、喜び勇んで見に行ったのだが。。。これはどう表現すればいいのだろう。とにかくすごかった。入るところに鳥居があり、その近くに説明板が立っていて、どうも平成十何年かには神社と城跡を合体させて一大公園にするということだった。「ほう、じゃあ今は工事中かもしれんな」とか思いつつ中に入っていくと、そこには城跡、神社どころか木材が積まれ、動かないブルドーザーがぽつんと・・・。周りをよく見てみると「勝家公、お市の方、茶々姫、はつ姫、江与姫居城の地」と書かれた立て札が倒れていた。元々遺構なんてなかったんだろうし、別にいいといえばいいんだろうが、やはりちょっと悲しいと思うのは僕だけではなかろう。(H9.8.2) |
| 一乗谷城(C) 戦国 山城(473m) |
朝倉氏の居城として栄えた戦国山城。一乗山を中心に南に砥石・城山、西に八地山、その外側に槇山があり、それぞれ城郭を形成していた。1573年に落城。昭和43年から発掘調査中である。 *福井県のページ *福井市のページ  素晴らしい。一乗谷に入った瞬間からまさに山が迫ってくる谷に入ったという状態で始まり、その後すぐに建物の遺構らしき礎石群が左右に現れる。わくわくしながら駐車場に車を止め、朝倉氏居館後へ。唐門があるだけであとは礎石があるだけなのだが、十分に当時の栄華を想像できるレベルの遺構であり、中庭などはいまだに緑が多く何とも言えない。そのすぐ上には庭園跡があり、岩組で作られた人工池はその岩のほとんどがそのまま残り、今水を張ったらすぐにでも庭になりそうな感じすらさせるもので、こちらも見逃せない遺構であろう。で、ここまで来たら山城にも登っとく?てな事になってサンダルで来ていた高橋には申し訳なかったのだが登ることに。登り口にはあと1.1キロという看板が立っており、それくらいなら大丈夫だろうということだったのだ。ところがである、登るごとに坂はきつくなり、途中岩だらけの道だとかもう全くすごい道のオンパレードである。そろそろ着かないかなとか思っていると、お、次の看板が見えてきた「あと0.8キロ」。一瞬帰ろうかと思ったのだが一応思いなおして登ることに。何とか千畳敷までたどり着いたもののTシャツは既に普段の五倍くらいの重さになっているし、あとの一の丸、二の丸、三の丸と見ていった時はもう上半身にTシャツは着れなかった。ここまで苦労したというのに千畳敷以外は一の丸二の丸三の丸ともに曲輪らしきものもなく、もちろん石垣などはかけらもない。苦労に報いてくれない城ではあったが、山登りという意味では達成感は非常にあった。これまでに行った城の中では間違いなく険しさNO.1である。この城に来ることはお勧めするが、山に登るのは間違ってもお勧めしない。(H9.8.3) 素晴らしい。一乗谷に入った瞬間からまさに山が迫ってくる谷に入ったという状態で始まり、その後すぐに建物の遺構らしき礎石群が左右に現れる。わくわくしながら駐車場に車を止め、朝倉氏居館後へ。唐門があるだけであとは礎石があるだけなのだが、十分に当時の栄華を想像できるレベルの遺構であり、中庭などはいまだに緑が多く何とも言えない。そのすぐ上には庭園跡があり、岩組で作られた人工池はその岩のほとんどがそのまま残り、今水を張ったらすぐにでも庭になりそうな感じすらさせるもので、こちらも見逃せない遺構であろう。で、ここまで来たら山城にも登っとく?てな事になってサンダルで来ていた高橋には申し訳なかったのだが登ることに。登り口にはあと1.1キロという看板が立っており、それくらいなら大丈夫だろうということだったのだ。ところがである、登るごとに坂はきつくなり、途中岩だらけの道だとかもう全くすごい道のオンパレードである。そろそろ着かないかなとか思っていると、お、次の看板が見えてきた「あと0.8キロ」。一瞬帰ろうかと思ったのだが一応思いなおして登ることに。何とか千畳敷までたどり着いたもののTシャツは既に普段の五倍くらいの重さになっているし、あとの一の丸、二の丸、三の丸と見ていった時はもう上半身にTシャツは着れなかった。ここまで苦労したというのに千畳敷以外は一の丸二の丸三の丸ともに曲輪らしきものもなく、もちろん石垣などはかけらもない。苦労に報いてくれない城ではあったが、山登りという意味では達成感は非常にあった。これまでに行った城の中では間違いなく険しさNO.1である。この城に来ることはお勧めするが、山に登るのは間違ってもお勧めしない。(H9.8.3) |
| 勝山城(E) 戦国 平城 |
もともと村岡山城の呼称であったものであるが、一向一揆が勝利して占拠した際、これを勝山と改めたのが始まりといわれる。1691年に小笠原氏が入城、明治まで続く。加賀百万石に対する隠し目付けとも言われる。 |
| 三峯城(E) 中世 山城(400m) |
*鯖江市のページ |
| 大野城 戦国 平山城 |
一向一揆を平定した信長が金森長近に三万石を与え、1576年に亀山に築城したのが始まり。1682年より土井氏が入封。 |
| 杣山城 室町 山城 |
|
| 金ヶ崎城(D) 室町 山城 |
1336年に新田義貞が二人の親王を奉じて北陸に下り、この城に立てこもった。後醍醐天皇の管理下にあった気比神宮は南朝に味方し、宮司自ら700騎を率いて新田義貞と合流したのである。親王の勅旨もそれほどの効果を上げないままに足利軍の包囲は厳しくなり、高師泰の援軍にあって落城の他は無かった。新田義貞は落ち延びるが、城はそれ以後本格的に再建されることは無かった。 現在城は金崎神社となり、月見御殿跡と呼ばれるところが手筒山の頂上であり、ここに本丸があったといわれる。非常に見晴らしがよく、戦国時代にもここで月見をしたことが記録に残っている。  神社まではすぐなのだが、そこから月見御殿跡までが結構階段を上らねばならず、またそれ以上に蚊が異常に多くて閉口した。遺構としては何も残っていなかったが、1,2,3の木戸の位置がはっきりしており、月見御殿跡なども、在りし日を偲ぶのに十分である。ただ、月見御殿跡からは月どころか眼下に敦賀火力発電所が大きく場所を占めている。それは致し方ないことだろうが。(H11.9.8) 神社まではすぐなのだが、そこから月見御殿跡までが結構階段を上らねばならず、またそれ以上に蚊が異常に多くて閉口した。遺構としては何も残っていなかったが、1,2,3の木戸の位置がはっきりしており、月見御殿跡なども、在りし日を偲ぶのに十分である。ただ、月見御殿跡からは月どころか眼下に敦賀火力発電所が大きく場所を占めている。それは致し方ないことだろうが。(H11.9.8) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 小浜城(C) 近世 海城 |
関が原の合戦の功により若狭に封じられた京極高次は港としての小浜の繁盛のために1601年海辺に臨む城の築城に着工する。海に面した城であり、基礎固めに難航し、延々六年を費やして一応の完成を見るが、天守完成前に松江に移封となった。その後川越城から入封してきた酒井忠勝が天守の造営を続行し、1637年に三層の天守が完成、港と城を一体化した大城郭が完成した。 |
| 後瀬山城(E) 戦国 山城 |
戦国大名武田氏の居城。 |
お城トップページ |
トピックス |
データベースの歩き方 |
読み替え |
既訪城郭一覧 |
掲示板
蝦夷地 |
東山道 |
北陸道 |
東海道 |
畿内 |
山陰道 |
山陽道 |
南海道 |
西海道 |
琉球