

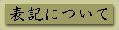
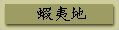
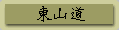
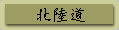
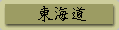
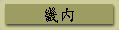
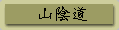
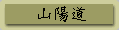
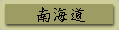
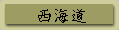
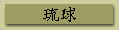
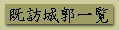

    | |
|---|---|
|
| |
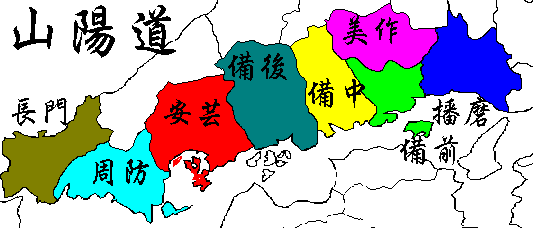
播磨(兵庫南西部) 美作(岡山北東部) 備前(岡山南東部) 備中(岡山西部) 備後(広島東部) 安芸(広島西部) 周防(山口東部) 長門(山口西部) | |
  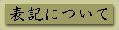 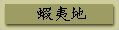 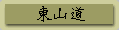 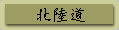 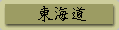 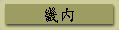 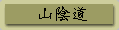 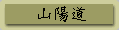 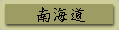 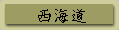 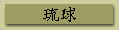 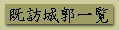 
|
| ||||||
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 姫路城 近世 平山城(50m) 日本百名城:59 |
 《大天守,東小天守,乾小天守,西小天守,イの渡櫓,ロの渡櫓,ロの櫓,ハの渡櫓,二の渡櫓》 《大天守,東小天守,乾小天守,西小天守,イの渡櫓,ロの渡櫓,ロの櫓,ハの渡櫓,二の渡櫓》〈ニの櫓,ホの櫓,ヘの渡櫓,トの櫓,チの櫓,リの一渡櫓,リの二渡櫓,ヌの渡櫓,ルの櫓,ヲの櫓,ワの櫓,カの櫓,カの渡櫓,ヨの渡櫓,タの渡櫓,レの渡櫓,折廻り櫓,化粧櫓,菱の門,帯の櫓,井郭櫓,帯郭櫓,太鼓櫓,水の一門,水の二門,備前門,いの門,ろの門,はの門,にの門,への門,との一門,との二門,ちの門,りの門,ぬの門,その他土塀31,築地塀1〉 [姫路藩] 1346年赤松貞範によって姫山に「姫山城」を築城したのが最初である。その後小寺、黒田と城主が変わり、中国攻めの先鋒羽柴秀吉の部将となった黒田官兵衛は秀吉に城を譲り渡し、その時に姫山と隣の鷺山を取り込んで城を拡張し、姫路城と改称した。関が原の合戦の後、家康により娘婿の池田輝政が入城し、秀吉時代の建物をすべて取り除き、縄張りも新たに築城した。1601年から9年かけて作られた大城郭が現在見られるものである。1993年12月、法隆寺と共に日本で初めての世界文化遺産に指定される。 *国宝 姫路城(公式ページ)  ただひたすらすごい城だった。どうもこの城を甘く見過ぎていたようだ。もう文句のつけようがない。みんなすごいというし、文献でもそのすごさは理解しているつもりだったのだが、そんな物ではぜんぜんキャパが足りなかった感じだ。特に西の丸の櫓の中はもう圧巻。高知城でも似たような感覚に襲われたが、本当に感動で涙が出そうだった。また当たり前のことなのだがあれだけの大天守を本当に木だけで作っているのはただただ驚くばかり。その一番の支えである二本の大柱のうちの一本は一本木を使っているというからもう二重の驚異であった。他にも現存する遺構の多さにはただただ目をみはるばかりで、写真を撮るのも忘れてただ呆然と時を過ごしてしまった。これこそが日本が世界に誇れる最大の文化遺産であると確信できる、そんな唯一のお城ではないだろうか。(H9.3.14) ただひたすらすごい城だった。どうもこの城を甘く見過ぎていたようだ。もう文句のつけようがない。みんなすごいというし、文献でもそのすごさは理解しているつもりだったのだが、そんな物ではぜんぜんキャパが足りなかった感じだ。特に西の丸の櫓の中はもう圧巻。高知城でも似たような感覚に襲われたが、本当に感動で涙が出そうだった。また当たり前のことなのだがあれだけの大天守を本当に木だけで作っているのはただただ驚くばかり。その一番の支えである二本の大柱のうちの一本は一本木を使っているというからもう二重の驚異であった。他にも現存する遺構の多さにはただただ目をみはるばかりで、写真を撮るのも忘れてただ呆然と時を過ごしてしまった。これこそが日本が世界に誇れる最大の文化遺産であると確信できる、そんな唯一のお城ではないだろうか。(H9.3.14) 平成27年3月27日に平成の大天守保存修理が終了してグランドオープンしたというので、早速行ってみた。何度来ても飽きることがない。特に今回はとにかく白い。まさに出来立てといった感じである。これまでは白鷺城と言われても何となくピンと来なかったが、今回はしっくり来た。まさに白鷺が飛び立とうとしている感じである。たまたま平日に来ることが出来たので、さほどの混雑はなかったが、入口には行列のための紐が張られていた。聞く話によると休日は入るだけで大変だという話である。入場で待たされることはなかったが、中は完全に通路が固定されていて、順番に歩いてください、ということになっている。昔の雰囲気に浸りながら自分の行きたいところをウロウロするのが好きな人間としては、若干辛かったが、それだけ注目されている証拠である。これに文句は言えない。そんなこんなを差し引いても、やっぱりすごい城である。何というか、格の違いを見せつけられる感じ。本当によくここまで残ってくれたものである。(H27.4.21) 平成27年3月27日に平成の大天守保存修理が終了してグランドオープンしたというので、早速行ってみた。何度来ても飽きることがない。特に今回はとにかく白い。まさに出来立てといった感じである。これまでは白鷺城と言われても何となくピンと来なかったが、今回はしっくり来た。まさに白鷺が飛び立とうとしている感じである。たまたま平日に来ることが出来たので、さほどの混雑はなかったが、入口には行列のための紐が張られていた。聞く話によると休日は入るだけで大変だという話である。入場で待たされることはなかったが、中は完全に通路が固定されていて、順番に歩いてください、ということになっている。昔の雰囲気に浸りながら自分の行きたいところをウロウロするのが好きな人間としては、若干辛かったが、それだけ注目されている証拠である。これに文句は言えない。そんなこんなを差し引いても、やっぱりすごい城である。何というか、格の違いを見せつけられる感じ。本当によくここまで残ってくれたものである。(H27.4.21) 今回、初めて姫路に泊まって、じっくり姫路城を堪能した。何度目か分からないが、他の城に訪問した経験は今が一番多いはずで、それでも仮に順位をつけるとしたら圧勝だろう。別格という言葉がこれほどしっくりくる城は他にはない。 今回、初めて姫路に泊まって、じっくり姫路城を堪能した。何度目か分からないが、他の城に訪問した経験は今が一番多いはずで、それでも仮に順位をつけるとしたら圧勝だろう。別格という言葉がこれほどしっくりくる城は他にはない。駅前から真正面に天守が見え、そこに向けて大手道があり、途中、外堀の石垣を抜けて大手門に至る。大手門に至るまでの道のりがこれほど城下なのもなかなかない。彦根も若干そういう感覚があったが、姫路は街全体がその状態に誇りを持っているような感覚がある。どうせなら外堀を復活してくれるとそれがさらに一段進むような気がするが、さすがにそれは贅沢か。 そして観光客の数がものすごい。特に外国人の数がすごい。半分以上が海外の人だろう。中国からのツアー客、欧米からの個人旅行、一括りにはできないが、多くはそういう感じだろうか。大手門の橋はそういう人たちでごった返していた。大手門を抜けると広大な三の丸。三の丸広場の奥には昭和大修理の際に取り替えられた昔の心柱(旧西大柱)が展示されている。これが350年もの期間、あの大天守を支えてきた心柱かと思うと、頭が下がる思いがする。管理事務所で百名城スタンプを押して、入城料を払って入城。しかしこれだけの城で入城料が1,000円は安すぎる。需要が多いから単価が安くても成り立つのか…。 まずは菱の門、三国堀、いの門、ろの門、はの門、にの門、ほの門、水の一門、水の二門、水の三門、水の四門、水の五門と怒涛のように続く。見るべきところが多すぎて混乱する。どれか一つだけでもわざわざ見に行く価値があるようなものばかり。まさに宝の山である。そしてそこから大天守が始まる。水の五門は石垣にぴったりくっついた門で、全面に鉄板が張られた重厚なもの。さらに水の六門を潜って大天守地階へ。石垣に囲まれたような地階は、薄暗く、雰囲気抜群。こうした地階はいくつかの城で行った経験があるが、ここまで広い地階はここだけだろう。大柱二本は非常に太い。当たり前だが。。 そして、1階・2階・3階・4階・5階・6階、見どころ満載だが、特に階高が高くなっている3階、四方に千鳥破風の内側がある4階、南北に千鳥破風の内側がある5階、少しずつ細くなっていく東西の大柱。そして、最上階は混雑がピークに達していた。こんなに人がいて大丈夫なのだろうかと要らぬ心配をしてしまいそうなほど。そして1階まで下りたら小天守と渡櫓をいくつか通って、出口へ。いやー素晴らしい。何もかもが素晴らしく、何とも言いようがない。興奮してここまで来たが、木の床が想定以上に冷たく、足の裏が痛くなった。  天守の次は西の丸である。百閒廊下と言われる西の丸の外周を巡る櫓群を見学することができる。こうした櫓に入城させてもらえるのは高知城で記憶にあるくらいで、あまりないうえに、百閒廊下と言われるだけあって、長い。実際には約121間、約240mということらしいが、これだけの一繋ぎの櫓を見学できるのは間違いなくここだけである。唯一不思議に思ったのが、この百閒廊下の最後、化粧櫓でやっていた「千姫・忠刻の復元着物展示」。ここだけ、観覧料200円を取られて、復元着物が置いてあるだけ・・・これだけすごいものを1,000円で見せておいて、着物だけで200円。あまりにバランスが悪いような気はした。しかし、西の丸に来たら、観光客が激減したが、どうせならここまで見ていってほしいものである。(R6.3.21) 天守の次は西の丸である。百閒廊下と言われる西の丸の外周を巡る櫓群を見学することができる。こうした櫓に入城させてもらえるのは高知城で記憶にあるくらいで、あまりないうえに、百閒廊下と言われるだけあって、長い。実際には約121間、約240mということらしいが、これだけの一繋ぎの櫓を見学できるのは間違いなくここだけである。唯一不思議に思ったのが、この百閒廊下の最後、化粧櫓でやっていた「千姫・忠刻の復元着物展示」。ここだけ、観覧料200円を取られて、復元着物が置いてあるだけ・・・これだけすごいものを1,000円で見せておいて、着物だけで200円。あまりにバランスが悪いような気はした。しかし、西の丸に来たら、観光客が激減したが、どうせならここまで見ていってほしいものである。(R6.3.21) |
| 感状山城 近世 山城(275m) |
1336年に赤松則祐が当城に篭城し、その戦功により尊氏から感状を与えられ、感状山城と称されることになった。その後赤松政村・晴政・義祐・則房と続き、1577年に羽柴秀吉の播磨攻略で落城したと伝えられる。 昭和56年以降遺構確認・実測調査が実施されているが、全城域の累壁を石垣で固め、いずれも4メートル以内、それ以上の高さは数段に構築されており、さらに累壁の角では緩やかにカーブしていることから隅石垣の技術が確立していなかったとみられており、戦国山城の石垣技術を解明する有力な資料である。 |
| 赤穂城 近世 平城 日本百名城:60 |
[赤穂藩] *兵庫県のページ *全国温泉案内『Oh!YU』のページ  大手門や隅櫓などが復元されていたがなぜか本丸の中には入れなかった。中でクレーンなどが見えていたから工事中だったのか、もしくは単に時間切れだったのか、定かではない。現存する建造物としては大石邸長屋門くらいなもので、敷地内に普通の民家などがあり、縄張りもわかりづらかった。大石神社が大きなスペースを取っているなど、忠臣蔵ファンのための観光地になっている感じだった。(H9.3.14) 大手門や隅櫓などが復元されていたがなぜか本丸の中には入れなかった。中でクレーンなどが見えていたから工事中だったのか、もしくは単に時間切れだったのか、定かではない。現存する建造物としては大石邸長屋門くらいなもので、敷地内に普通の民家などがあり、縄張りもわかりづらかった。大石神社が大きなスペースを取っているなど、忠臣蔵ファンのための観光地になっている感じだった。(H9.3.14) |
| 明石城 近世 平山城 日本百名城:58 |
 〈辰巳門,坤櫓〉 〈辰巳門,坤櫓〉[明石藩]  姫路に向かう途中、強風か何かの影響でJRのダイヤが乱れ、乗っていた姫路行の新快速が急に行き先が変更になり、明石駅で乗り換えが必要になり、ホームに降りたところ、明石城の櫓がライトアップされているのが見え、ちょっと寄っていくことに。 姫路に向かう途中、強風か何かの影響でJRのダイヤが乱れ、乗っていた姫路行の新快速が急に行き先が変更になり、明石駅で乗り換えが必要になり、ホームに降りたところ、明石城の櫓がライトアップされているのが見え、ちょっと寄っていくことに。もう18時を過ぎていたので薄暗がりの中だったが、堀を渡ったところの桝形状の石垣、そこを抜けたところにある広大な広場(西の丸?)、そしてその向こうにある坤櫓と巽櫓と周辺の石垣。この時間なので観光客は誰一人いなかったが、櫓に向かって階段を登っていくと、櫓の見え方がちょっとずつ変わり、どんどんテンションが上がっていった。櫓まで来ると、そこは展望台になっていて、明石大橋とのコラボレーションも楽しむことができる。地図を見ると奥の階段を下りたら二ノ丸に抜けられるようになっているようだったので、下りてみたら通行止めになっていたので引き返すことに。 この時間なのでサービスセンターは閉館となっていて百名城スタンプを押すことは叶わず、翌日に再訪してスタンプだけ押させてもらった。来てみて気づいたのだが、3~5月の土日祝は櫓の特別公開をやっているらしい。ツイテなかったが、これだけ広範囲に石垣が残っていて、その周りも公園として残してくれているので、お城の雰囲気は十分に味わうことができた。公園と一体化させて城を残していく、素晴らしい事例だと思う。そして晩御飯は明石焼を堪能したのは言うまでもない・・・(R6.3.20) *明石城公式 *明石公園 |
| 尼崎城 近世 平城 |
|
| 龍野城 室町 山城 |
[龍野藩] *兵庫県のページ  立派な大手門があり、その奥に三之丸御殿と隅櫓があった。管理人さんの話だとすべて復元らしかった。脇坂氏が藩主となってからは三之丸しか使われていなかったらしいが、それ以前は山の上に天守閣を持った城郭を構えていたらしい。そちらの跡も見に行きたかったのだが赤穂にも行きたかったので急いで帰らねばならず断念。(H9.3.14) 立派な大手門があり、その奥に三之丸御殿と隅櫓があった。管理人さんの話だとすべて復元らしかった。脇坂氏が藩主となってからは三之丸しか使われていなかったらしいが、それ以前は山の上に天守閣を持った城郭を構えていたらしい。そちらの跡も見に行きたかったのだが赤穂にも行きたかったので急いで帰らねばならず断念。(H9.3.14) |
| 三木城 戦国 丘城 |
[三木藩] *山ぽんのホームページ |
| 平福城(利神城) | [平福藩]赤松氏の家臣別所氏によって築城。 *山ぽんのホームページ |
| 鹿澤城 | [山崎藩] |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 津山城(C) 近世 平山城 日本百名城:69 |
 [津山藩] [津山藩]1616年、森忠政が13年の歳月をかけて築いた輪郭式の近世平山城。五層の天守と60もの櫓があった。明治6年に廃城、翌年建物はすべて取り壊されたが、石垣はほぼ当時のものをとどめる。現在、備中櫓が復元工事中であり、平成17年3月完成予定。 *津山観光センターのページ  広大な土地にほとんど手が加えられていない立派な石垣が残り、非常に素晴らしい城跡だった。特に本丸周辺は、石垣の合間合間に細い通路があり、その趣深さといったらない。それこそ一日中城の中をうろうろしていたいくらいだった。 広大な土地にほとんど手が加えられていない立派な石垣が残り、非常に素晴らしい城跡だった。特に本丸周辺は、石垣の合間合間に細い通路があり、その趣深さといったらない。それこそ一日中城の中をうろうろしていたいくらいだった。ちょうど備中櫓が復元工事中で、青いビニールシートがかぶされていたが、柵の外から中を覗いてみると、もちろん総木造りで、もう半分以上できているようなイメージで、完成が非常に楽しみである。(H15.9.7)  |
| 勝山城(E) 近世 |
[勝山藩] |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 岡山城 近世 平山城 日本百名城:72 |
 〈月見櫓〉 〈月見櫓〉[岡山藩] 1597年に宇喜多秀家が完成させたと伝えられ、六階の天守を持つ壮大な城郭であった。天守の初重平面は五角形の特殊なものであり、天守前面を殿主曲輪といい、本丸内に本段ともいう区画を持った古式手法によるものであった。その後小早川秀秋が入城し、領内の支城である亀山城・富山城などを廃して建物を岡山城へと移したと伝えられる。次いで入城した池田忠継が西の丸を整備、今に残る高石垣を構築した。1687年には池田綱政によって天守背後に後楽園が造園されたが、これは山里曲輪を兼ねた隠し城であった。今日では、月見櫓と西手櫓が残るのみである。 *岡山城天守閣 *岡山観光WEB
|
| 下津井城(C) 近世 山城 |
戦国大名宇喜多氏が築城、四国との航路の要港であったために小早川秀秋、岡山藩主池田氏も整備を重ねた。一国一城令で廃城。 *山ぽんのホームページ |
| 撫川城(C) | *山ぽんのホームページ *しげもりけいたさんのページ |
| 常山城(C) | 戦国大名三村氏の有力武将上野氏の居城。 *山ぽんのホームページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 高梁城(備中松山城) 近世 山城 日本百名城:70 |
 〈天守,二重櫓,三の平櫓東土塀〉 [松山藩] 1240年、備中の地頭秋庭重信が現在の城地の東北にある大松山に城を築いたのが始め。その後南北朝時代に、高橋氏が城域を大松山から小松山に広げ、壮大な山城とする。現在残る城跡は1680年台に五万石で入封した水谷勝宗が大改修したものである。その後板倉氏が7代125年在城。 (注)もともと備中松山城と言われてきたが、近年城郭研究家の申し合わせにより、近世城郭の呼称を可能な限り現市町村名で行うとのことにより、高梁城と呼ばれるものである。 *高梁市 *高梁市観光協会  ほんとに素晴らしい山城だった。ただ、いろいろと驚かされるお城でもあった。 ほんとに素晴らしい山城だった。ただ、いろいろと驚かされるお城でもあった。まず、17:30頃に駐車場に着いたのだが、それより上に行くのは18:00以降、それまではバスが運行しているので車では行けないというのだ。では歩いていくとどれくらいかかるか聞くと50分くらい。しかも公開は16:30で終了しているときた。これはGWの特例で、いつもは15:30には終了するらしい。これは全く唖然としたという表現しかない。せっかく来たのだからと無理に頼んでバスの後を車で行かせてもらい、外見だけは見ることができた。といっても車で行けるのは途中までで、そこからは山道を歩かないといけない。10分くらい歩いたろうか、上でがさがさと木がゆれる音がする。何だろうと凝視してみるとなんと野猿である。で、もう少し歩いてみると出てくるは出てくるは。特に三の丸跡では20匹くらいの猿が食事をしている。本丸跡でも10匹くらいいただろうか、みんな草とか花とかをむしゃむしゃと。。。 城はというと、本当に素晴らしく、その連格式の天守と山城特有の山を削って造る曲輪の配置がなんとも言えなかった。生きているうちにもう一度来て、今度は天守に登ってみたいものである。ただ、今回の印象としてはやはり猿の印象が強すぎる。しかしまぁいろんな意味ですごい城だ。(H10.5.3)
|
| 高松城(D) 戦国 平城 続日本百名城:171 |
秀吉の水攻めで有名な城 来てみてびっくりした。単なる湿地公園。資料館のようなものとそこかしこに旗が建っているが、城を見せるつもりは一切なさそう。(R6.7.13) 来てみてびっくりした。単なる湿地公園。資料館のようなものとそこかしこに旗が建っているが、城を見せるつもりは一切なさそう。(R6.7.13) |
| 鬼ノ城 古代 山城 日本百名城:71 |
 標高約400mの鬼城山に築かれた古代山城。白村江の戦いで敗れた大和朝廷が唐・新羅連合軍の日本侵攻を恐れて築いたのではないかと言われる。城内はおよそ30haという広大な面積があり、城壁は前週2.8㎞にも及ぶ。 標高約400mの鬼城山に築かれた古代山城。白村江の戦いで敗れた大和朝廷が唐・新羅連合軍の日本侵攻を恐れて築いたのではないかと言われる。城内はおよそ30haという広大な面積があり、城壁は前週2.8㎞にも及ぶ。*総社市
|
| 足守陣屋 | [足守藩] *城郭放浪記 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 福山城 近世 平山城 日本百名城:73 |
 〈伏見櫓,筋鉄御門〉 〈伏見櫓,筋鉄御門〉[福山藩] 1619年、備後10万石の領主として大和郡山より転封してきた水野勝成が構築した近世城郭。1622年8月15日に入城、城下を福山と命名した。現在の天守閣は昭和41年に外観復元されたもので、中は博物館。2022年には築城400年記念事業として、天守北側鉄板張りが復元された。 *福山城博物館 *えっと福山  新幹線で福山駅を通ると天守がちらっと見えるので、いつか来てみたかった城だったが、正直少し幻滅した。立派な石垣が広範囲に残り、伏見櫓や筋鉄御門など現存遺構もあるのだが、何か物足りない。考えられるのは、まずお堀が全くないこと。かなりの市街地になっているため、埋められてしまったのだろう。それから、城内にかなりの電線が張られていること。やはりお城は俗世間のものとは隔離されていて欲しいものである。そしてやはりあの天守。建てられたのが割と古いからだろう、こもる熱気の中を汗をかきかき階段を登っていかないといけない。誤解を恐れずに言うと、どうせ木で作らないならエレベーターくらいつけて欲しいものである。(H15.9.7) 新幹線で福山駅を通ると天守がちらっと見えるので、いつか来てみたかった城だったが、正直少し幻滅した。立派な石垣が広範囲に残り、伏見櫓や筋鉄御門など現存遺構もあるのだが、何か物足りない。考えられるのは、まずお堀が全くないこと。かなりの市街地になっているため、埋められてしまったのだろう。それから、城内にかなりの電線が張られていること。やはりお城は俗世間のものとは隔離されていて欲しいものである。そしてやはりあの天守。建てられたのが割と古いからだろう、こもる熱気の中を汗をかきかき階段を登っていかないといけない。誤解を恐れずに言うと、どうせ木で作らないならエレベーターくらいつけて欲しいものである。(H15.9.7) 以前の感想を見るとちょっと辛口に過ぎると思う。少し時間ができたので何度目か、立ち寄ったが、現存している伏見櫓や筋鉄御門などの周辺は本当に素晴らしい。実際に伏見城の建物を移築してきたということでもあるし、その石垣、周りの景観も含めて何度行っても飽きない良さがある。15年前の感想は撤回したい。天守が城ではないと公言してきたが、その自分が天守にこだわり過ぎていたということではないか。反省して訂正したい。(H30.9.25) 以前の感想を見るとちょっと辛口に過ぎると思う。少し時間ができたので何度目か、立ち寄ったが、現存している伏見櫓や筋鉄御門などの周辺は本当に素晴らしい。実際に伏見城の建物を移築してきたということでもあるし、その石垣、周りの景観も含めて何度行っても飽きない良さがある。15年前の感想は撤回したい。天守が城ではないと公言してきたが、その自分が天守にこだわり過ぎていたということではないか。反省して訂正したい。(H30.9.25) 築城400年記念事業で天守北面の鉄板張りを復元したと聞いていたので、一度行ってみたいと思っていた。福山駅北口を出て、石段を登り、伏見櫓、筋金御門方面へ進む。この辺は若干綺麗になったかな、というくらいで、以前と大きな変化はない。ところが、門を入ったところの天守前広場が活気に溢れている!以前は活気がなかったような言い方で申し訳ないが、結構な変化。そして、その向こうの天守がかなりきれいになった。以前は、正直さびれた感じの天守だったのが、生まれ変わった感じに見える。 築城400年記念事業で天守北面の鉄板張りを復元したと聞いていたので、一度行ってみたいと思っていた。福山駅北口を出て、石段を登り、伏見櫓、筋金御門方面へ進む。この辺は若干綺麗になったかな、というくらいで、以前と大きな変化はない。ところが、門を入ったところの天守前広場が活気に溢れている!以前は活気がなかったような言い方で申し訳ないが、結構な変化。そして、その向こうの天守がかなりきれいになった。以前は、正直さびれた感じの天守だったのが、生まれ変わった感じに見える。 そして、裏側に廻ってみると・・・確かに黒い!鉄板が張られている。これまで城、特に天守というと、「白漆喰を基調として、いくつかの破風で装飾されたもの」というイメージで、元の天守を無視して模擬天守が建てられたり、天守が建っていなかった天守台に無理やり天守を建てたり、ということが日本中で繰り返されてきたが、建物はコンクリートとはいいながら、歴史的背景を踏まえて、北面を鉄板張りにするという動き。元々が珍しい城なので、それをもって観光資源にしようとしたきらいはあるものの、それでも歓迎すべきだと思う。 そして、裏側に廻ってみると・・・確かに黒い!鉄板が張られている。これまで城、特に天守というと、「白漆喰を基調として、いくつかの破風で装飾されたもの」というイメージで、元の天守を無視して模擬天守が建てられたり、天守が建っていなかった天守台に無理やり天守を建てたり、ということが日本中で繰り返されてきたが、建物はコンクリートとはいいながら、歴史的背景を踏まえて、北面を鉄板張りにするという動き。元々が珍しい城なので、それをもって観光資源にしようとしたきらいはあるものの、それでも歓迎すべきだと思う。せっかく来たので、天守の中にも入ってみた。以前の印象は、古い市役所のようなにおいのする古びた博物館だったが、一気に近代的な博物館になっていた。映像を多用し、初めての人にもわかりやすく、それでいて壁は木目を基調としたものにして木を感じられるようになっている。もちろん、城郭建築とは言い難いものの、博物館としてはよくできていると感じた。(R6.3.27) |
| 三原城(C) 戦国 海城 続日本百名城:172 |
 瀬戸内海の水軍を掌握していた小早川隆景が1567年に沼田川河口にあった大島と小島を繋いで築かれたと伝わる。満潮時には海に浮かんだように見えたことから浮城とも呼ばれた。現在は山陽本線が本丸中心部を貫いていて、本丸の半分以上は三原駅が占めている。 瀬戸内海の水軍を掌握していた小早川隆景が1567年に沼田川河口にあった大島と小島を繋いで築かれたと伝わる。満潮時には海に浮かんだように見えたことから浮城とも呼ばれた。現在は山陽本線が本丸中心部を貫いていて、本丸の半分以上は三原駅が占めている。 三原駅に到着すると、駅のコンコースに「三原城天守台→」の看板があり、そちら方向に行くと、扉の向こうにまさに天守台にたどり着いた。天守台に登るには駅から行くしかないようだ。天守台は木が植えられたちょっとした庭のような状態になっており、周りには堀を見下ろせる。本来は駅があったところも本丸であったはずで、そう考えると何ともやるせない。 三原駅に到着すると、駅のコンコースに「三原城天守台→」の看板があり、そちら方向に行くと、扉の向こうにまさに天守台にたどり着いた。天守台に登るには駅から行くしかないようだ。天守台は木が植えられたちょっとした庭のような状態になっており、周りには堀を見下ろせる。本来は駅があったところも本丸であったはずで、そう考えると何ともやるせない。駅に戻り、「隆景公園」という看板に向かって歩くと、堀の部分に出てこれた。天守台の石垣は思った以上に高石垣で、下から見上げるとかなり立派。堀もかなり広く、これだけの城が海に浮かんでいたというのはすごいことである。そう考えると、やはり線路というか駅というか、ここでないとダメだったのだろうか。これでも天守台の部分は避けたということなのか。特に近代の城は市街地にあるので、全てを残そうとすると、経済活動に支障が出るレベルで広かったりするから難しいのだろうが。 駅の逆側に行くと、この駅が城跡の上に立っているとは到底思えないきれいな駅前広場になっている。近くでは、広島城や福山城は観光地として残そうとしているのに対し、この城は城跡があることを隠そうとしているかのよう。そこから5分ほど歩くと、中門跡の石垣が保存されているが、それも商業施設の裏手の影にひっそりと隠れるようにある。 なんというか、城跡の活用方法について考えさせられる城跡だった。私は全国の城跡を巡っているので、観光客が全くいない城跡でも違和感ないし、全く構わない。逆に往時の状態を崩して模擬天守を建てたり石垣を改変したりすることの方がよっぽど問題だと思う。でも今回の城は、新幹線の駅でもある三原駅の周りが城跡という状態で、それを観光地としてどう使うか、という観点である。経済的には城跡の存在そのものが邪魔なのだろうから、つぶしてしまいたい人もいただろうが、学術的にすべてをつぶせないのなら、できる範囲で駅を作ってしまえ、ということだったのだろう。残さざるを得ない部分については、駅前の一等地なのだから、何かを復元して観光地化する、というのが定石な気がするが、もともと天守が建っていない城だったこともあり、そういうわけにもいかず、今の状況に落ち着いたということなのか。(R7.2.11) |
| 新高山城 戦国 山城(190m) 続日本百名城:173 |
毛利元就の三男、小早川隆景が小早川家を継いで本拠として築いた山城。本丸、北の丸、太鼓の丸、千畳敷などが残る。 |
| 今高野山城 戦国 山城 |
 三の丸跡に中世の山城風の展望台が建つ。 三の丸跡に中世の山城風の展望台が建つ。 親戚の家に遊びに来た帰りに少し寄ったもの。結構な山を延々登るのだが、久々の山城攻略で、大汗をかいてしまった。遺構としてはほとんど残っていないが、少なくとも山道の散策としては楽しかった。しかし天守などなかった時代の城跡に、天守的建造物を建ててしまうというのは、やはり何と言うか・・・(H15.9.6) 親戚の家に遊びに来た帰りに少し寄ったもの。結構な山を延々登るのだが、久々の山城攻略で、大汗をかいてしまった。遺構としてはほとんど残っていないが、少なくとも山道の散策としては楽しかった。しかし天守などなかった時代の城跡に、天守的建造物を建ててしまうというのは、やはり何と言うか・・・(H15.9.6) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 広島城 近世 平城 日本百名城:75 |
 [広島藩] [広島藩]1589年、時の戦国大名毛利輝元が山間の吉田郡山城が領国支配には不適であると判断し、築いたのが広島城である。最終的に城が整ったのは1599年で、豊臣大名らしく聚楽第を参考にした作りであった。しかし、輝元が西軍の総大将となった関ヶ原の合戦に敗れて完成の翌年の1600年に毛利氏は萩に移ることになる。その後、福島正則が五十万石の太守として入城し、更に整備した。しかしその整備が無断城郭修理に当たるとして1619年に突然改易され、代わって紀州浅野氏が入り明治維新を迎える。戦略上非常に重要な位置を占めていたらしく、明治維新では広島鎮台となり、日清戦争では大本営が置かれている。そして太平洋戦争においてはまさにここが原爆の標的になった。 最盛時の広島城は天守二基に二重櫓三十三基、単層櫓三十二基長櫓四基、多聞櫓四基、櫓門十二棟を数える大城郭であったという。現在見られる天守閣はもちろん復興天守であり、その他の建物も復興計画が進められている。 *広島城アソシエイツ
|
| 吉田郡山城(D) 戦国 山城 日本百名城:74 |
 1336年毛利時親が旧本城を築城したと伝わるが、後に元就が郡山全山を城郭化し、更に輝元が改修を加えた大規模な山城。この城を中心にして、幾多の合戦を経て、中国地方の統一を成し遂げた。1540年9月、尼子晴久が3万の大軍を率いて攻め寄せたが、翌年1月撤退に追い込んだことでも知られる。1591年輝元の広島城移転後、廃城になり、江戸時代に入って、建物・石垣は壊され、堀も埋められた。 可愛川と多治比川との合流点の北側にあり、標高390m、比高190m、範囲は約1キロ四方に広がっていた。山頂に本丸、二ノ丸、三の丸を置き、その他大小約270の曲輪が配され、中世山城の特徴を良く今に伝えている。 *安芸高田市観光ナビ *安芸高田市歴史民俗資料館  何とか時間を作って、念願の登城を果たした。広島まで新幹線3時間半、広島バスセンターから1時間半、1日がかりなのだ。そして着く頃に雨がパラパラと・・・それでも来るだけの価値がある城跡だと思う。 何とか時間を作って、念願の登城を果たした。広島まで新幹線3時間半、広島バスセンターから1時間半、1日がかりなのだ。そして着く頃に雨がパラパラと・・・それでも来るだけの価値がある城跡だと思う。バス停から歴史民俗博物館を横目に見ながら山を登っていくと、毛利隆元の墓、毛利元就の墓所と続き、その裏手に登山道入り口がある。そこからはいよいよ山道ではあるのだが、1キロ足らずなのでそんなに大変ではない。まず御蔵屋敷跡に着くと、広めの曲輪跡に石が散乱している。恐らくは崩れた石垣の跡と思われる。さらに進むと二の丸跡。二の丸跡の入口に、少しだけ石垣の跡らしきものが残っている。(上記写真)二ノ丸自体は少し広い曲輪という感じで、その奥に一段高くなって本丸、その奥に櫓台があり、この地点が一番高いところらしい。来る時に飛ばしてしまったので、二ノ丸の奥にある三の丸に行くと、そこには二の丸との境の坂の下に、大小の石が散乱している。その坂は恐らく石垣があったところで、石垣が崩れた状態のまま、保存されているということと思われた。 この光景、本当に驚いた。まず、その保存方法。観光地としては、石垣は石垣の状態である方がいいに決まっている。熊本城でも地震で倒壊してしまった石垣をどう復旧するか、という話になっている。普通はそうだと思う。でもこの城は違う。崩れた状態の石垣が歴史の事実だということなのだろう。その状態のままで保存されているのだ。しかも、歴史的に非常に貴重な遺構であるはずの石垣が、誰でも入れるところに放置されている。そうした城は私の知る限り、この城だけではないだろうか。 石を持ち帰られたりすることはないのだろうか。誰かが石を入れ替えてしまったりしないだろうか。非常に画期的だし、この保存方法は私は賛成だが、とは言っても、今後のことを考えると、何か対策を取るべきなのではないかと感じた。この山奥の遺構を誰かが常駐して監視することは非現実的でもあろうし、不可能だと思う。といって、これだけの遺構を観覧者の良心にのみ頼っていて大丈夫なのだろうか。難しい課題だと思う。私の立場では、とにかく来る人は良心に従って行動してくれることを切に祈るだけである。 帰りは来た道とは別の道を下りた。途中尾崎丸跡などがあって、展望台、郡山公園、清神社を経て、バス停に戻った。見るべきところはじっくり見ながら、とはいえバスの時間も気にしながら、約1時間半。非常に興味深い散策であった。私の城めぐりの原点は春日山城に行ったことだと思っている。上杉謙信の姿を思い浮かべながら山城を散策したその記憶が、その後の城巡りに繋がっているような気がする。この城はその原点を思い起こさせる城と言える。毛利元就の姿を思い浮かべながら、中世山城を散策する。こんな贅沢な観光はないと思う。当日は雨がパラパラ降っていたこともあってか、すれ違ったのは数人しかいなかった。もっと多くの人に行ってもらいたい、最高の城跡だと思う。(H30.9.24) |
| 桜尾城 | 厳島神領地を支配するための本拠地 *「いにしえのロマンの郷はつかいち」のページ |
| 亀居城 | 関が原の戦後処理で対毛利外交を担当していた福島正則が、芸備ニ国という毛利氏の旧領で、かつ毛利領に隣接した国の太守となったのは、毛利封じ込め政策の主役をまかされた意味合いが強い。吉川による岩国築城に対抗するため、慶長8年(1603)福島正則は領域西端の小方(おがた)の地に支城としてこの城を築城した。 慶長16年(1611)に家康の意向により破却。 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 岩国城 近世 平山城(200m) 日本百名城:76 |
 [岩国藩] [岩国藩]関が原の合戦後、六万石の領地を与えられた吉川広家(元春の子)が築城したもので、1608年に完成するが、1615年の一国一城令によって破却される。以後吉川家は麓の館『土居』で生活をし、政治を行った。これは今の吉香公園であり、城山を背に三面に堀をめぐらした堅固なものであった。現在の天守閣は昭和37年に復興されたもので、麓からの景観上、旧本丸南隅に建てられている。 *岩国市  土日で広島に来たので、宮島観光ついでにふらっと寄る。JR岩国駅を降りてからさらにバスで、錦帯橋まで来て、そこからロープウェーで山に上れるようになっている。ともかくその錦帯橋がいい。アーチが5つあって、それが非常に優雅。そしてそれと、山上に見える岩国城が妙にマッチしている。ロープウェーは午後5時が最終で、ぎりぎりに行ったために下りは使えず、足で下りることとなったものの、それ以上にその時間だと天守にも入れなかった。まぁ感想としては中の下。まず、天守に全く歴史的関連性がないこと、さらに建っている位置が全く違う。なんと構内の地図には、「天守閣」「天守閣跡」という意味不明な書き方が。別にその書き方はいいが、ちゃんと説明すべきだなぁ。さらに、大手門。とにかくちゃちい。簡単な木で作ったものを堂々と大手門と書いている。うーん、書き出すとどんどん苦言が、、、とにかく、どうも整備されすぎていて昔の面影をしのびにくい。公園として整備するのはいいことだが、ちょっとやりすぎか。あ、それと、ロープウェーの降り口から天守までの道が二通りあり、一つは山道、一つはアスファルトで、看板ではアスファルトを勧めている。が、なんと山道の方を歩かないと最も趣のある石垣を見ることはできない。安全性を考慮するのもいいが、やはりどうも説明不足の感が否めない。(H12.2.26) 土日で広島に来たので、宮島観光ついでにふらっと寄る。JR岩国駅を降りてからさらにバスで、錦帯橋まで来て、そこからロープウェーで山に上れるようになっている。ともかくその錦帯橋がいい。アーチが5つあって、それが非常に優雅。そしてそれと、山上に見える岩国城が妙にマッチしている。ロープウェーは午後5時が最終で、ぎりぎりに行ったために下りは使えず、足で下りることとなったものの、それ以上にその時間だと天守にも入れなかった。まぁ感想としては中の下。まず、天守に全く歴史的関連性がないこと、さらに建っている位置が全く違う。なんと構内の地図には、「天守閣」「天守閣跡」という意味不明な書き方が。別にその書き方はいいが、ちゃんと説明すべきだなぁ。さらに、大手門。とにかくちゃちい。簡単な木で作ったものを堂々と大手門と書いている。うーん、書き出すとどんどん苦言が、、、とにかく、どうも整備されすぎていて昔の面影をしのびにくい。公園として整備するのはいいことだが、ちょっとやりすぎか。あ、それと、ロープウェーの降り口から天守までの道が二通りあり、一つは山道、一つはアスファルトで、看板ではアスファルトを勧めている。が、なんと山道の方を歩かないと最も趣のある石垣を見ることはできない。安全性を考慮するのもいいが、やはりどうも説明不足の感が否めない。(H12.2.26) |
| 山口城(C) 近代 平城 |
 [山口藩] [山口藩]関が原で西軍の大将となった毛利家が領地を没収され、輝元の嫡子「秀就」に防長二国を与えるという厳しい処置となったことは有名であるが、その時にここへの築城願いを幕府に提出するも認められず、萩を本拠とした。ところが、幕末を迎え、二州の中心に藩庁を移すことが必要となり、幕府の意向を聞かずに築城を敢行した。1864年に完成、明治維新後は山口藩議事館と改称され、さらに山口県庁となった。1911年に県庁舎が改築されたときにすべての建物を解体、表門が新庁舎横に移築保存されるだけになった。
|
| 沼城(D) 戦国 山城 |
*「毛利元就・防長最大の激戦地」 |
| 若山城(C) 戦国 山城 |
陶氏の居城。あの陶晴賢が大内義隆を倒し、防長の主権を握ったときに、兵を上げたのもこの城である。1555年に元就と戦って厳島に敗死、翌年には息子の長房が城を逃れて自刃、毛利家の攻撃で落城。 *「毛利元就・防長最大の激戦地」 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 萩城 近世 平山城 日本百名城:77 |
 [萩藩] [萩藩]関が原の合戦で敗れて防長二カ国三十六万石に減封された毛利輝元に許可された新居城の地は山口ではなく、片田舎の萩であった。そしてそこでは毛利家の威信をかけた大普請が行われることになる。萩の指月山を詰めの城として実戦用の城とすると共に、麓にはその城とは別個に政庁・藩邸を備えた平城を構えたのである。詰めの城とした山城は海抜143mの山頂に五基の二重櫓と櫓門を上げ、中腹には山中櫓を上げた。そして麓の城には五層の複合式天守と壮大な殿舎を営み、二の丸には十基の櫓を設け、三の丸には武家屋敷を置いた。 萩城の天守は明治新政府の廃城令によって破却されたが、五重五層の大壁づくりで最上階を古式望楼としていた。現在は曲輪跡が残るだけであるが、九州の中津城の模擬天守閣は萩城の復元とされている。 *萩市観光協会 *戦国探究  来てみて初めて分かることがある。そもそも萩は三角州になっていて、三角州全体が城下町を形成している。その三角州の最も海側に指月山があり、それを詰めの城にして、麓に平城がある。つまり、海を背後に城が建ち、川を広い意味での堀にして堅固な城郭を形成している。毛利家の威信をかけた城というのも頷けるというものである。 来てみて初めて分かることがある。そもそも萩は三角州になっていて、三角州全体が城下町を形成している。その三角州の最も海側に指月山があり、それを詰めの城にして、麓に平城がある。つまり、海を背後に城が建ち、川を広い意味での堀にして堅固な城郭を形成している。毛利家の威信をかけた城というのも頷けるというものである。城跡としては、整備されているとはいいがたいが、それゆえにしなびたというか、古い雰囲気が色濃く残る風情ある城跡となっている。時間の都合で指月山に登ることはできなかったが、山頂からの眺めはまた格別ではないかと思われた。さらに、日本海に面していて、「潮入門」という門があり、それを抜けると海岸になっている。なかなかに見どころの多い城であることは間違いない。ただ、ちょうど大河ドラマをやっている最中だからということなのか、入場料を取られたのは少し不可解ではあった。(H27.7.2)
|
| 勝山城(C) 戦国 平山城 |
勝山城とは厳密には2つあり、一つ目は大内義長が拠って落城した中世山城であり、二つ目は幕末の下関攘夷戦のために急造された近世城郭で、勝山御殿と呼ばれる。現在勝山御殿跡には広大な石垣が残る。 |
| 串崎城 | [長府藩] |
お城トップページ |
トピックス |
データベースの歩き方 |
読み替え |
既訪城郭一覧 |
掲示板
蝦夷地 |
東山道 |
北陸道 |
東海道 |
畿内 |
山陰道 |
山陽道 |
南海道 |
西海道 |
琉球