

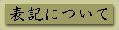
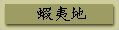
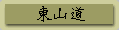
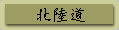
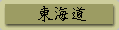
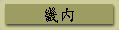
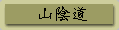
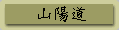
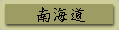
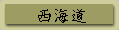
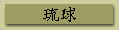
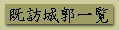

    | ||
|---|---|---|
|
| ||
| ||
  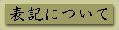 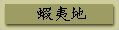 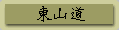 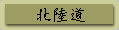 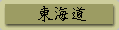 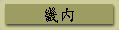 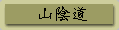 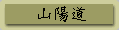 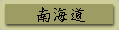 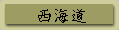 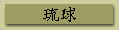 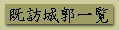 
|
| ||||||||
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 水戸城(C・・・移築門あり) 日本百名城:14 |
 水戸城は鎌倉時代、馬場氏によって築城されたと言われる。その後江戸氏、佐竹氏の居城となり、その改修は関ヶ原合戦まで続いた。その後家康の七男武田信吉、十男頼宣、十一男頼房が入城。頼房の子孫が御三家水戸徳川家となった。連郭式で二重櫓三基を上げ、三重天守は明和気に再築された。 水戸城は鎌倉時代、馬場氏によって築城されたと言われる。その後江戸氏、佐竹氏の居城となり、その改修は関ヶ原合戦まで続いた。その後家康の七男武田信吉、十男頼宣、十一男頼房が入城。頼房の子孫が御三家水戸徳川家となった。連郭式で二重櫓三基を上げ、三重天守は明和気に再築された。現在、遺構としては水戸第一高校に「薬医門」が復元されて現存、三の丸に「弘道館」の一部が残るほか、2020年に大手門、2021年に二の丸角櫓が復元されている。 *水戸観光コンベンション協会 *城址うぉっち頁
|
| 笠間城(C・・・移築櫓あり) 近世 山城(182m) 続日本百名城:112 |
 宇都宮一族の笠間家が鎌倉期に築城、戦国期には北条方につき共に滅亡。関ヶ原の合戦後、永井・浅野家らが入城、近世城郭とした。その時、この佐白山が石材地であったため、関東では異例の石垣を用いた天守曲輪となった。遺構としては関東で唯一の石垣の天守曲輪に合わせ、城下の真浄寺には八幡櫓が移築現存している。 宇都宮一族の笠間家が鎌倉期に築城、戦国期には北条方につき共に滅亡。関ヶ原の合戦後、永井・浅野家らが入城、近世城郭とした。その時、この佐白山が石材地であったため、関東では異例の石垣を用いた天守曲輪となった。遺構としては関東で唯一の石垣の天守曲輪に合わせ、城下の真浄寺には八幡櫓が移築現存している。*笠間市(公式)  日帰りで来るには少々遠かったが、来た価値は充分にあった。関東でこれだけの石垣を持つ山城に出会えるとは思わなかった。高梁・高取と並ぶ近代山城ではないかと思う。大手門の石垣から古道を登っていくと石段と石垣が続き、二の丸・本丸・天守曲輪が続く。全体像として城を見る事ができるという点で、近代山城はやはり最もワクワクする。 日帰りで来るには少々遠かったが、来た価値は充分にあった。関東でこれだけの石垣を持つ山城に出会えるとは思わなかった。高梁・高取と並ぶ近代山城ではないかと思う。大手門の石垣から古道を登っていくと石段と石垣が続き、二の丸・本丸・天守曲輪が続く。全体像として城を見る事ができるという点で、近代山城はやはり最もワクワクする。 惜しむらくは道路が縦横に走っていること。大手門から本丸までの古道を何度かアスファルトの道路が交差しているのである。それでもできる限り石垣や石段には影響が無いように存在しているのでまだマシではあった。 惜しむらくは道路が縦横に走っていること。大手門から本丸までの古道を何度かアスファルトの道路が交差しているのである。それでもできる限り石垣や石段には影響が無いように存在しているのでまだマシではあった。帰りに、櫓が現存すると言う真浄寺に寄ってみた。七面堂と呼ばれる建物だったが、入口正面に建っていて、不思議な感じがした。県内唯一の現存櫓だと言う。全国を見てもとにかく現存する城郭建造物は少ない。どんな形であれ、少しでも長く、こうした遺構が残っていて欲しい、切に願うばかりである。(H16.11.6)
|
| 逆井城 戦国 水城 |
 1557年、後北条氏が佐竹・結城・多賀谷氏と境を接するこの地に築城。玉縄城主であった北条氏繁が飯沼を臨む高台に築城し、北進を続けるも翌年本城で没、その後氏舜が城代となった。秀吉の小田原攻め後、廃城。 1557年、後北条氏が佐竹・結城・多賀谷氏と境を接するこの地に築城。玉縄城主であった北条氏繁が飯沼を臨む高台に築城し、北進を続けるも翌年本城で没、その後氏舜が城代となった。秀吉の小田原攻め後、廃城。昭和58年度より始まった城址整備計画として、日本では初めての戦国城郭建築の模擬天守が作られ、その他、礎石を基に復元された櫓門・橋や、土塁・空掘りなど、中世城郭の遺構が良く残っている。別名:飯沼城  駐車場からまず目に入るのは凝った模擬天守と櫓。 駐車場からまず目に入るのは凝った模擬天守と櫓。 その向こうにはわずかに残る飯沼がある。天守には入れるようになっていて、入ってみると模擬天守とは言いながら、総木作りの本格的なもの。余計な展示もなく、非常に好感を持ちながら奥へ進む。屋敷跡を囲む空掘、井戸、その向こうには櫓門と橋、さらに奥には大きな郭があって虎口まで分かる。広大な敷地に非常によく遺構が残っていて、大変満足した。ちなみに、観光客はゼロ。世間にはなかなか受け入れてもらえないなぁ・・・(H15.2.23) その向こうにはわずかに残る飯沼がある。天守には入れるようになっていて、入ってみると模擬天守とは言いながら、総木作りの本格的なもの。余計な展示もなく、非常に好感を持ちながら奥へ進む。屋敷跡を囲む空掘、井戸、その向こうには櫓門と橋、さらに奥には大きな郭があって虎口まで分かる。広大な敷地に非常によく遺構が残っていて、大変満足した。ちなみに、観光客はゼロ。世間にはなかなか受け入れてもらえないなぁ・・・(H15.2.23) |
| 土浦城 続日本百名城:113 |
 永享の頃、若泉氏の築城と伝えられ、後に菅谷氏、結城氏が入城。関ヶ原の合戦後、松平信一・西尾忠長・朽木稙綱らによって拡張され、土屋氏が城主で明治を迎えた。現在、関東唯一の櫓門建築「太鼓門」薬医門の霞門、高麗門が残り、本丸の東櫓・西櫓が復元されている。 永享の頃、若泉氏の築城と伝えられ、後に菅谷氏、結城氏が入城。関ヶ原の合戦後、松平信一・西尾忠長・朽木稙綱らによって拡張され、土屋氏が城主で明治を迎えた。現在、関東唯一の櫓門建築「太鼓門」薬医門の霞門、高麗門が残り、本丸の東櫓・西櫓が復元されている。 久しぶりに城らしい城に行った、というのが本音。少し語弊があるが、やはり城と言うと「櫓」「門」「石垣」「堀」があって欲しいというのが正直なところなのだ。(天守があれば、なお良いが・・・)この城は二の丸と本丸がほぼそのまま残り、本丸の周囲の堀もほぼ残っている。さらに櫓門とさらに2つの門が現存し、2つの櫓が復元されている。土浦と言うとやはり櫓門が有名なのだが、周りの石垣の修復か何かをやっていて、肝心の櫓門が半分隠された状態で、かなり残念だった。復元された東櫓には入場することが出来るのだが、総木作りで工法も江戸時代のもので復元されているため、非常に好感が持てた。 久しぶりに城らしい城に行った、というのが本音。少し語弊があるが、やはり城と言うと「櫓」「門」「石垣」「堀」があって欲しいというのが正直なところなのだ。(天守があれば、なお良いが・・・)この城は二の丸と本丸がほぼそのまま残り、本丸の周囲の堀もほぼ残っている。さらに櫓門とさらに2つの門が現存し、2つの櫓が復元されている。土浦と言うとやはり櫓門が有名なのだが、周りの石垣の修復か何かをやっていて、肝心の櫓門が半分隠された状態で、かなり残念だった。復元された東櫓には入場することが出来るのだが、総木作りで工法も江戸時代のもので復元されているため、非常に好感が持てた。ちなみに、堀の周りをうろうろしながら写真を撮っていたら、何とデジカメの電池が切れてしまった!情けない。まぁそれほどいい城だったという事である。(H16.11.6)
|
| 小田城 南北朝 平城 |
 鎌倉初期より小田氏の居城。南北朝の動乱期には、北畠親房が滞在、南朝方の関東勢力として、ここを拠点に活躍。有名な「神皇正統記」はここで書かれた。 鎌倉初期より小田氏の居城。南北朝の動乱期には、北畠親房が滞在、南朝方の関東勢力として、ここを拠点に活躍。有名な「神皇正統記」はここで書かれた。戦国期には、北条氏の勢力拡大のもと、小田氏は去就が定まらず、上杉謙信や佐竹義重、太田三楽斎らに攻められ、三度落城、最終的には佐竹氏に完全降伏することとなった。関ケ原の合戦後、佐竹氏は秋田に移封となり、廃城となった。  普通の広い農地のど真ん中に方形の丘があって、これが本丸跡だという。周りを見回してみると、農地なのだが、明らかに堀だったであろう部分が浮かび上がってくる。農地が段々になっていて、低い農地が堀跡、高い農地は土塁跡、それが丘の周りに沿うように続いているのである。道も通っているし、失われている部分も多いと思うが、それでも農地であることが幸いしてかなり広大に遺構が残っているように思われる。史跡公園化の計画もあるらしいので、その暁にはまた是非来たいと思う。(H16.11.6) 普通の広い農地のど真ん中に方形の丘があって、これが本丸跡だという。周りを見回してみると、農地なのだが、明らかに堀だったであろう部分が浮かび上がってくる。農地が段々になっていて、低い農地が堀跡、高い農地は土塁跡、それが丘の周りに沿うように続いているのである。道も通っているし、失われている部分も多いと思うが、それでも農地であることが幸いしてかなり広大に遺構が残っているように思われる。史跡公園化の計画もあるらしいので、その暁にはまた是非来たいと思う。(H16.11.6) |
| 豊田城 南北朝 水城 |
 築城は14世紀中旬、豊田12代善基が川べりに築いたと言われる。戦国時代には姻戚関係を結んでいた小田氏と共に佐竹・多賀谷氏の南進を防いだ。現在は石下町地域交流センターとして模擬天守が建てられている。 築城は14世紀中旬、豊田12代善基が川べりに築いたと言われる。戦国時代には姻戚関係を結んでいた小田氏と共に佐竹・多賀谷氏の南進を防いだ。現在は石下町地域交流センターとして模擬天守が建てられている。 石下に向かって車を走らせ、橋を渡ろうとした時、ドドーンとバカでっかい建物が目に飛び込んできた。正直笑えた(すみません)回りは田んぼや小さな建物しかないところに五層天守はどうしても違和感がありすぎる。名古屋城辺りをモチーフにしたんだろうか、緑瓦の五層天守。中はいろんな展示がされているのだが、そこに外国人と思しき数人を見かけた。「これが日本のお城とは思いませんように・・・」(祈)(H15.2.23) 石下に向かって車を走らせ、橋を渡ろうとした時、ドドーンとバカでっかい建物が目に飛び込んできた。正直笑えた(すみません)回りは田んぼや小さな建物しかないところに五層天守はどうしても違和感がありすぎる。名古屋城辺りをモチーフにしたんだろうか、緑瓦の五層天守。中はいろんな展示がされているのだが、そこに外国人と思しき数人を見かけた。「これが日本のお城とは思いませんように・・・」(祈)(H15.2.23) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 千葉城 中世 平山城(30m) |
 古代から中世にかけて下総国を中心に活躍した千葉氏の居城。この城が建てられた平安時代末期(1126)以後、千葉氏は鎌倉幕府創設に尽力し、下総守護職に任ぜられた。鎌倉、室町を通してこの地方に権勢を誇った千葉氏も、次第に衰え、戦国時代には里見氏の進出に苦しみ、後北条氏と結んだが、秀吉の小田原征伐時に滅亡した。いまは千葉市立郷土博物館として小田原城を模した天守閣的建造物が建てられている。また、天守閣的建造物前には実際の城跡と思われる土塁が残っている。 古代から中世にかけて下総国を中心に活躍した千葉氏の居城。この城が建てられた平安時代末期(1126)以後、千葉氏は鎌倉幕府創設に尽力し、下総守護職に任ぜられた。鎌倉、室町を通してこの地方に権勢を誇った千葉氏も、次第に衰え、戦国時代には里見氏の進出に苦しみ、後北条氏と結んだが、秀吉の小田原征伐時に滅亡した。いまは千葉市立郷土博物館として小田原城を模した天守閣的建造物が建てられている。また、天守閣的建造物前には実際の城跡と思われる土塁が残っている。*千葉市のページ *はたぼうさんの日本名城案内  会社の先輩の家に泊めていただき、翌朝車で連れて行ってもらう。城らしい縄張りも何もなく、ただ丘の上に天守閣のようなものが建っているにすぎず、天守閣内部も通り一辺倒の武具や書状の類であった。ただ、市が運営しているからか、入場料が一人60円!!安い。なぜかわからないがエレベーターにはエレベーターガールならぬ「エレベーターおばさん」がいて、しかも何の案内もしてくれない。あれは何の為にあそこにいるんだろうなぁ。実に不思議。(H11.12.19) 会社の先輩の家に泊めていただき、翌朝車で連れて行ってもらう。城らしい縄張りも何もなく、ただ丘の上に天守閣のようなものが建っているにすぎず、天守閣内部も通り一辺倒の武具や書状の類であった。ただ、市が運営しているからか、入場料が一人60円!!安い。なぜかわからないがエレベーターにはエレベーターガールならぬ「エレベーターおばさん」がいて、しかも何の案内もしてくれない。あれは何の為にあそこにいるんだろうなぁ。実に不思議。(H11.12.19) |
| 古河城(E・・・移築城門あり) | 室町時代、中央政府としての幕府が京都に置かれたため、鎌倉を初め戦略上重要な地域である関東地域を統括するため、鎌倉府が置かれた。室町幕府の将軍は公方と呼ばれたが、第二の幕府としての鎌倉府のトップは鎌倉公方と呼ばれた。初代鎌倉公方足利基氏は鎌倉府を鎌倉に置いたが、1455年足利成氏は御在所を当地に移し、以来古河公方と呼ばれる。その後後北条氏が下野、常陸進攻の前線基地とし、その後も重要な戦略上の拠点として整備が繰り返された。その堅固さは秀吉による小田原攻めで破却を命じられる程であった。近世になってからは小笠原秀政・松平康長・奥平信之・永井直勝・土井利勝が入城、この代に御三階が上がり、関東では江戸城に次ぐ規模の大城郭となった。現在、城跡は明治末から昭和初期にかけての渡良瀬川大改修により川の底に沈められてしまい、往時を偲ぶものは市内の福法寺に移築されたと伝えられる城門だけである。 *募巣豚私立博物館 |
| 結城城(D) | 結城合戦において室町幕府と管領上杉氏に対抗した北関東の豪族が立てこもった城であり、主戦場となった。戦国期になって有名な法度を定めた結城氏が入り、小田原平定の後に家康の次男を迎え、結城秀康を城主とした。関ヶ原の合戦後に福井に転封、幕府の直轄地となった。遺構は特にないが、城下を巡る御朱印堀がよく保存される。 *栃木の城+α |
| 佐倉城(C) 日本百名城:20 |
 1610年、土井利勝が江戸城搦手防備の控城的な目的で築城。石垣は一切なく、土塁と空掘を巧みに用いた実践的な城。1617年に三重天守閣と五基の櫓を上げ、虎口には壮大な櫓門が構えられ、さらに馬出・内枡形が駆使されており、兵法上極めて注目される存在であった。 1610年、土井利勝が江戸城搦手防備の控城的な目的で築城。石垣は一切なく、土塁と空掘を巧みに用いた実践的な城。1617年に三重天守閣と五基の櫓を上げ、虎口には壮大な櫓門が構えられ、さらに馬出・内枡形が駆使されており、兵法上極めて注目される存在であった。*佐倉市のページ  JR成田線「佐倉駅」から徒歩20分、佐倉城址公園となっている。晴れていて、また気候も良く、桜も結構残っていたので、たくさんの人が敷物を持って花見に来ていた。という位であるから芝生がたくさんあって、雰囲気のすごいいいところ。今度来るときには是非とものんびりしに来たいものだ。 JR成田線「佐倉駅」から徒歩20分、佐倉城址公園となっている。晴れていて、また気候も良く、桜も結構残っていたので、たくさんの人が敷物を持って花見に来ていた。という位であるから芝生がたくさんあって、雰囲気のすごいいいところ。今度来るときには是非とものんびりしに来たいものだ。さて、城跡であるが、建物は何も残ってはいないが、空掘が非常に良く残り、十分に昔を偲ぶことが出来る。感じたのは、石垣が城ではないということ。「天守閣=城」という人は周りに多く、常に「そうではない!」と主張してきた私だが、生まれも育ちも西日本ということがあったのかもしれない「石垣=城」という認識は思った以上に深かったようだ。最初はあまり遺構が残ってないのかなぁ?と思ってたら、土塁、石垣、さらに馬出しまで、それだけでも縄張りが想像できそうなくらいである。こういう城跡こそ、将来に残していきたい。是非とも訪れていただきたい城である。 城と駅の間には、武者屋敷があり、ちょっと寄ってみた。土塁の上に生垣があるのが佐倉地方独特のものだそう。防御目的もさりながら、登城時の馬に乗った武将から家の中を見えなくする役割もあったのだとか。房総では最大の城下町、今回は思ったようにブラブラできなかったが、一日ブラブラするのもいいだろうと思う。(H13.4.15)
|
| 臼井城(D) |  千葉氏の一族臼井氏の居城。1590年の小田原落城の際に千葉氏と共に滅亡。江戸期には酒井家次3万石の居城となり、1604年の転封まで使用された。 千葉氏の一族臼井氏の居城。1590年の小田原落城の際に千葉氏と共に滅亡。江戸期には酒井家次3万石の居城となり、1604年の転封まで使用された。現在、本丸、二の丸を中心として、空掘・土塁等がよく残る城址公園となっている。  佐倉城の西近くにある。期待していたよりも断然規模が大きく、縄張りもよく分かる。印旛沼を望める要衝にあり、上杉謙信・太田道灌の攻城戦はどんなだっただろうか、と考えていると時の経つのを忘れそうである。こういうところを公園にしているのは素晴らしいと思う。ちなみに、娘は必死にどんぐりを拾っていた・・・(H16.2.14) 佐倉城の西近くにある。期待していたよりも断然規模が大きく、縄張りもよく分かる。印旛沼を望める要衝にあり、上杉謙信・太田道灌の攻城戦はどんなだっただろうか、と考えていると時の経つのを忘れそうである。こういうところを公園にしているのは素晴らしいと思う。ちなみに、娘は必死にどんぐりを拾っていた・・・(H16.2.14) |
| 高岡陣屋(E) |  1640年、島原の乱鎮圧に功を上げた井上政重が一万石に加増されて高岡藩が誕生。但しこの陣屋が建てられるのは曾孫の正蔽の時であるが、周りには芸者屋と居酒屋が数件あった程度とも伝えられる。 1640年、島原の乱鎮圧に功を上げた井上政重が一万石に加増されて高岡藩が誕生。但しこの陣屋が建てられるのは曾孫の正蔽の時であるが、周りには芸者屋と居酒屋が数件あった程度とも伝えられる。*成田市のページ  JR成田線「滑川駅」から徒歩15分、今はJAと神社になってしまっているが、その前に木と石の碑が立っている。本当にそれだけ。(H13.4.15) JR成田線「滑川駅」から徒歩15分、今はJAと神社になってしまっているが、その前に木と石の碑が立っている。本当にそれだけ。(H13.4.15) |
| 関宿城 中世 平山城 |
 1457年、古河公方「足利成氏」の家臣梁田成助の築城と伝えられる。1590年、家康が江戸に入ったときに、江戸の防衛の要であるこの城に異父弟である松平康元を配置、その後藩主は老中、京都所司代など幕府の中心となって活躍した人物が多く、さらにこの城を出る藩主のほとんどは位・石高が上がり、出世城とも呼ばれた。現在は千葉県立関宿城博物館として模擬天守が立つのみであり、遺構は特に残っていない。 1457年、古河公方「足利成氏」の家臣梁田成助の築城と伝えられる。1590年、家康が江戸に入ったときに、江戸の防衛の要であるこの城に異父弟である松平康元を配置、その後藩主は老中、京都所司代など幕府の中心となって活躍した人物が多く、さらにこの城を出る藩主のほとんどは位・石高が上がり、出世城とも呼ばれた。現在は千葉県立関宿城博物館として模擬天守が立つのみであり、遺構は特に残っていない。*千葉県  江戸川と利根川が分岐する千葉県の北端に位置し、見るからに重要な位置に建っていた。博物館は入口を入ったところに顔のところだけ穴があいてある侍とお姫様があったりして、恐ろしく観光地だった。ということもあって、中には結構な観光客らしき人がいた。一応最上階には上がってみると、川の分岐がよくわかり、要衝の地であったことが良く理解できる。 江戸川と利根川が分岐する千葉県の北端に位置し、見るからに重要な位置に建っていた。博物館は入口を入ったところに顔のところだけ穴があいてある侍とお姫様があったりして、恐ろしく観光地だった。ということもあって、中には結構な観光客らしき人がいた。一応最上階には上がってみると、川の分岐がよくわかり、要衝の地であったことが良く理解できる。少し離れたところに実際に本丸があったところであろう、石碑が建っている。一応木で囲まれた郭のようになっているが、特に遺構はなさそうであった。残念。(H15.2.23) |
| 小金城(C) 戦国 平山城 |
 戦国期に下総西部を支配した高城氏の本拠で、起伏のある丘陵地に築いた南北600m、東西800mの大城郭だったという。現在は外曲輪の虎口であった金杉口、達磨口付近のみであり、金杉口が現在、市の歴史公園となっている。障子堀、畝堀などの遺構が残る。 戦国期に下総西部を支配した高城氏の本拠で、起伏のある丘陵地に築いた南北600m、東西800mの大城郭だったという。現在は外曲輪の虎口であった金杉口、達磨口付近のみであり、金杉口が現在、市の歴史公園となっている。障子堀、畝堀などの遺構が残る。  公園としてよく整備されていて、城跡を残していくためにはこうする以外にはないんだろうなぁ、と妙に納得する城跡だった。一部とはいえ、こういう本当の意味での遺構が残っていくのはいいことだと思う。周辺が宅地化されているため、どうしても全体像はつかめないが、特殊な空堀の実物を見ることができるなど、非常に興味深かった。(H15.2.23) 公園としてよく整備されていて、城跡を残していくためにはこうする以外にはないんだろうなぁ、と妙に納得する城跡だった。一部とはいえ、こういう本当の意味での遺構が残っていくのはいいことだと思う。周辺が宅地化されているため、どうしても全体像はつかめないが、特殊な空堀の実物を見ることができるなど、非常に興味深かった。(H15.2.23) |
| 前ヶ崎城(C) 戦国 平山城 |
 戦国期に下総西部を支配した高城氏の本拠である小金城の支城と考えられる。現在、前ヶ崎城址公園として整備され、高さ3~4メートルの土塁と空堀が残る。 戦国期に下総西部を支配した高城氏の本拠である小金城の支城と考えられる。現在、前ヶ崎城址公園として整備され、高さ3~4メートルの土塁と空堀が残る。 公園として整備されているのだが、一方で高い土塁が良く残っているため、周りから隔離されていて、公園感は少ない。逆に言うと、城跡感が強く、身近にこのような遺構が保存されているのは本当に素晴らしい。裏手には相当深い空堀も良く残っており、中世の城の要素を凝縮して味わえる城跡と感じた。しかしこの近辺、城跡公園が多い。自治体に意識の高い方が多いのだろうか。今後とも維持保存をお願いしたいものだ。(R1.11.9) 公園として整備されているのだが、一方で高い土塁が良く残っているため、周りから隔離されていて、公園感は少ない。逆に言うと、城跡感が強く、身近にこのような遺構が保存されているのは本当に素晴らしい。裏手には相当深い空堀も良く残っており、中世の城の要素を凝縮して味わえる城跡と感じた。しかしこの近辺、城跡公園が多い。自治体に意識の高い方が多いのだろうか。今後とも維持保存をお願いしたいものだ。(R1.11.9) |
| 国府台城(C) 戦国 平山城(30m) |
 1479年、太田道灌が千葉自胤を助け、千葉孝胤討伐のために築いたのが始まりと言われる。1538年、小弓公方足利義明は里見義尭をはじめとする房総の軍1万余を率い、北条軍2万余と対陣、江戸川を渡って進出した北条軍を迎え、義明は激闘の末戦死し、房総勢は敗退。1564年、里見軍8千が再び北条軍と対戦、北条軍の奇襲により5千の戦死者を出す大敗北を喫し、義弘は安房に敗走、以後館山城を本拠とする。この後北条氏の支配下となり、江戸時代に廃城とされた。現在は城址一帯が里見公園となっている。 1479年、太田道灌が千葉自胤を助け、千葉孝胤討伐のために築いたのが始まりと言われる。1538年、小弓公方足利義明は里見義尭をはじめとする房総の軍1万余を率い、北条軍2万余と対陣、江戸川を渡って進出した北条軍を迎え、義明は激闘の末戦死し、房総勢は敗退。1564年、里見軍8千が再び北条軍と対戦、北条軍の奇襲により5千の戦死者を出す大敗北を喫し、義弘は安房に敗走、以後館山城を本拠とする。この後北条氏の支配下となり、江戸時代に廃城とされた。現在は城址一帯が里見公園となっている。 *千葉市の遺跡を歩く会  かなり大きな公園で、城跡を丸ごと公園にしたようなイメージだった。市民の憩いの場として、ベンチで話をしている人、広場でバドミントンをしている人、芝生で寝ている人、城跡がこういう風に保存されているのは好感が持てた。ただ、途中あたかも現存しているかのように見える石垣があるのはどうかと思う。時代背景から明らかにおかしいのだ。それでも土塁・空堀がかなり残り、何より全体として残っていること、江戸川沿いにあって城内から対岸の東京都が見えることなど、国府台合戦と呼ばれる二度の合戦の舞台を堪能することが出来た。(H16.11.3) かなり大きな公園で、城跡を丸ごと公園にしたようなイメージだった。市民の憩いの場として、ベンチで話をしている人、広場でバドミントンをしている人、芝生で寝ている人、城跡がこういう風に保存されているのは好感が持てた。ただ、途中あたかも現存しているかのように見える石垣があるのはどうかと思う。時代背景から明らかにおかしいのだ。それでも土塁・空堀がかなり残り、何より全体として残っていること、江戸川沿いにあって城内から対岸の東京都が見えることなど、国府台合戦と呼ばれる二度の合戦の舞台を堪能することが出来た。(H16.11.3) |
| 大野城(E) 戦国 平山城 |
 平将門が天慶の乱の時に築いたという伝説があるが、昭和54年に行われた発掘調査では戦国期のものと推定されている。歴史的な詳細は不明であるが、空掘・土塁の一部が残る。 平将門が天慶の乱の時に築いたという伝説があるが、昭和54年に行われた発掘調査では戦国期のものと推定されている。歴史的な詳細は不明であるが、空掘・土塁の一部が残る。  市川法務局に行く途中で見つける。第五中学校の敷地が中心であったようだ。何か遺構があるかどうか、じっくり調べることは出来なかったが、小高い丘の上であり、雰囲気は楽しむことが出来た。(H16.2.10) 市川法務局に行く途中で見つける。第五中学校の敷地が中心であったようだ。何か遺構があるかどうか、じっくり調べることは出来なかったが、小高い丘の上であり、雰囲気は楽しむことが出来た。(H16.2.10) |
| 松戸城(E) 戦国 平山城 |
 1400年代には千葉氏族である原氏によって築かれたと考えられる。第一次国府台合戦では北条氏綱・氏康軍がこの城に入ったとされる。その後は小金城の支城となり、1590年に後北条氏が滅ぶと共に廃城となった。1884年には徳川慶喜の弟である昭武がここに屋敷を建てた。現在、戸定邸として、一般公開されている。近代徳川家の住まいと庭園が一般公開されている唯一の場所である。 1400年代には千葉氏族である原氏によって築かれたと考えられる。第一次国府台合戦では北条氏綱・氏康軍がこの城に入ったとされる。その後は小金城の支城となり、1590年に後北条氏が滅ぶと共に廃城となった。1884年には徳川慶喜の弟である昭武がここに屋敷を建てた。現在、戸定邸として、一般公開されている。近代徳川家の住まいと庭園が一般公開されている唯一の場所である。  暇つぶしに松戸近辺を散策していて立ち寄った。小高い丘になっており、全体が城だったのだろう。一角に戸定邸があったのでせっかくなので見学することにした。一応、くらいの気持ちで立ち寄ったのだが、想定以上に広く、良く残っていて、非常に楽しむことが出来た。江戸期のものでいえば御殿建築になろうが、それよりも一般家庭寄りだが、普通の家庭の家にしては立派過ぎる。その中間点辺りの感じというか、明治時代のお金持ちの家がそのまま残っていて、感じることができる。見るべきものは多いが、何といっても木造建築の中に石でできた蔵があるのは驚いた。非常に満足できるスポットである。(H28.10.16) 暇つぶしに松戸近辺を散策していて立ち寄った。小高い丘になっており、全体が城だったのだろう。一角に戸定邸があったのでせっかくなので見学することにした。一応、くらいの気持ちで立ち寄ったのだが、想定以上に広く、良く残っていて、非常に楽しむことが出来た。江戸期のものでいえば御殿建築になろうが、それよりも一般家庭寄りだが、普通の家庭の家にしては立派過ぎる。その中間点辺りの感じというか、明治時代のお金持ちの家がそのまま残っていて、感じることができる。見るべきものは多いが、何といっても木造建築の中に石でできた蔵があるのは驚いた。非常に満足できるスポットである。(H28.10.16) |
| 相模台城(E) 戦国 平山城 |
 1241年、第六代執権となった北条長時が館を構えたことに始まる。1538年の第一次国府台合戦では、小弓公方軍が国府台城、北条軍が松戸城に入り、この城には小弓公方軍の先鋒が入っていたとされ、この城付近で最も激戦になったと言われる。 1241年、第六代執権となった北条長時が館を構えたことに始まる。1538年の第一次国府台合戦では、小弓公方軍が国府台城、北条軍が松戸城に入り、この城には小弓公方軍の先鋒が入っていたとされ、この城付近で最も激戦になったと言われる。 暇つぶしに松戸近辺を散策していて立ち寄った。聖徳大学や松戸中央公園があるが、城らしい遺構はほぼない。大正8年に陸軍工兵学校が開設され、松戸中央公園の一角にその門柱と門衛が残る。(H28.10.16) 暇つぶしに松戸近辺を散策していて立ち寄った。聖徳大学や松戸中央公園があるが、城らしい遺構はほぼない。大正8年に陸軍工兵学校が開設され、松戸中央公園の一角にその門柱と門衛が残る。(H28.10.16) |
| 根木内城(C) 戦国 平山城 |
 15世紀中ごろに下総国守護千葉市に関わる武家であった原氏または高城氏が築城したと言われる。小金城の東側を守る拠点、街道の監視の役割を担っていたと考えられる。現在、国道6号線によって跡地は分断され、西側は宅地化されているが、西側は空堀、土塁、土橋と共に、曲輪の一部が芝生公園として残っている。 15世紀中ごろに下総国守護千葉市に関わる武家であった原氏または高城氏が築城したと言われる。小金城の東側を守る拠点、街道の監視の役割を担っていたと考えられる。現在、国道6号線によって跡地は分断され、西側は宅地化されているが、西側は空堀、土塁、土橋と共に、曲輪の一部が芝生公園として残っている。 道路を走っていると、「根木内歴史公園(根木内城址)」という看板を見つけ、ふらっと立ち寄る。恥ずかしながら根木内城のことは全く知らなかったので、全く期待せずに行ったのだが、非常に驚いた。 道路を走っていると、「根木内歴史公園(根木内城址)」という看板を見つけ、ふらっと立ち寄る。恥ずかしながら根木内城のことは全く知らなかったので、全く期待せずに行ったのだが、非常に驚いた。駐車場から跡地に入っていくと、まず湿地帯があるのだが、それを越えていくと、結構大規模な土塁が出現、そのまま歩いていくと綺麗な堀切があって、その奥には何と土橋!中の看板を見てみると、国道6号線によって分断されていて、本丸と思われる曲輪は6号線の向こう側で、既に宅地化されているようだった。それでも土橋の奥には曲輪の一部と思われる広場がある。戦国時代の城の特徴が良く残る素晴らしい城跡。間違いなく、わざわざ出かけていく価値のある城跡だと思う。 ちなみに、季節外れの暑さで、腕と足を蚊に刺されまくった・・・(R1.10.5) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 久留里城 戦国 丘城 |
 1541年真里谷氏の居城であった当城を里見氏が攻略、北条氏との攻防拠点とした。家康の江戸入城後は大須賀氏・土屋氏・酒井氏・黒田氏らが入城した。山頂には二重天守閣、麓の居館にも櫓を配し、根小屋式山城の形態を取った。現在山頂にある二層三重の天守閣は浜松城を模した模擬天守であるが、天守台は当時のものを用いている。戦国山城の形態をよく伝える関東では貴重な遺構である。 1541年真里谷氏の居城であった当城を里見氏が攻略、北条氏との攻防拠点とした。家康の江戸入城後は大須賀氏・土屋氏・酒井氏・黒田氏らが入城した。山頂には二重天守閣、麓の居館にも櫓を配し、根小屋式山城の形態を取った。現在山頂にある二層三重の天守閣は浜松城を模した模擬天守であるが、天守台は当時のものを用いている。戦国山城の形態をよく伝える関東では貴重な遺構である。 異動になって千葉に引っ越してきて初の「お城めぐり」レンタカーを借りてふらっと訪れる。久留里の町のはずれにあり、車で来ると町の真ん中を一回通るのだが、中心部らしきところに、天守閣の絵が乗った門がある。この町にはお城があるんですよ!と言っているのか。 異動になって千葉に引っ越してきて初の「お城めぐり」レンタカーを借りてふらっと訪れる。久留里の町のはずれにあり、車で来ると町の真ん中を一回通るのだが、中心部らしきところに、天守閣の絵が乗った門がある。この町にはお城があるんですよ!と言っているのか。麓の駐車場に車を停め、天守までの道はどうも二つあるらしく、コンクリートの道と、ハイキングコースのような山道。当然山道を登ることにしたのだが、やはり暑くて暑くて。とはいえよく整備された山道で、歩きやすいし、さわやか系の森だったのもあって、気持ちよく山頂に。約一キロくらいか。天守はというと、ありがちなというか、天守台は古そうでいい感じなのに、その上に綺麗な模擬天守が乗っている。中に入ると、現存12城の写真があって、特にその他の展示はなし。てっぺんからみると、綺麗な山の景色。 帰りはコンクリートの道を降りる事にしたのだが、途中で展示館がある。無料というので入り、一通り見るものの、大したものはない。とはいえ、ハイキング的感覚で来れる良いお城ではなかろうかと思う。(H12.7.22)  キャンプに来たら、近所に久留里城があったので帰りに寄ってみた。初夏ということもあって花がたくさん咲いていて、非常に爽やかで、ちょっとしたいい運動になった。天守はコンクリートで、外観復元でもなく、そういう意味では見るべきものはないが、ちょっとしたハイキングコースとしては非常に貴重だと思う。 キャンプに来たら、近所に久留里城があったので帰りに寄ってみた。初夏ということもあって花がたくさん咲いていて、非常に爽やかで、ちょっとしたいい運動になった。天守はコンクリートで、外観復元でもなく、そういう意味では見るべきものはないが、ちょっとしたハイキングコースとしては非常に貴重だと思う。ちなみに、模擬天守のある横に本来の天守台があるのだが、そちらは入ることも見ることもできないのはどうも納得いかない。貴重な遺構なので破損を防ぐ意味なのだとは思うが、誰にも見られず、誰の記憶にも残らない。今後何とかしてほしいものである。(H23.4.30) |
| 大多喜城 近世 山城 続日本百名城:122 |
 1590年、上総夷隅郡十万石に移封となった本多忠勝が築城。夷隅川の作る複雑な山地に自然石と大きな堀切で近世城郭を構築した。三重天守を山頂に、九基の櫓を並べ、麓には壮大な殿舎を構えた。今日、三重天守が復元され、内部は房総地方城郭資料館となる以外にも、麓には御殿薬医門が現存する。 1590年、上総夷隅郡十万石に移封となった本多忠勝が築城。夷隅川の作る複雑な山地に自然石と大きな堀切で近世城郭を構築した。三重天守を山頂に、九基の櫓を並べ、麓には壮大な殿舎を構えた。今日、三重天守が復元され、内部は房総地方城郭資料館となる以外にも、麓には御殿薬医門が現存する。*大多喜城(県立中央博物館大多喜城分館)  大多喜の町からは少し離れたところに位置し、ちょっと迷いながらも、お土産やさんの駐車場に車を停め、100メートルほどで復元天守。これがまたやたら綺麗で、なんとも言えず興醒め。内部は完全に歴史資料館となっていて、資料としては結構な品揃えであったのではないかと思う。そこで麓の高校にある二の丸御殿薬医門が現存していることを発見し、とりあえず見に行くことに。 大多喜の町からは少し離れたところに位置し、ちょっと迷いながらも、お土産やさんの駐車場に車を停め、100メートルほどで復元天守。これがまたやたら綺麗で、なんとも言えず興醒め。内部は完全に歴史資料館となっていて、資料としては結構な品揃えであったのではないかと思う。そこで麓の高校にある二の丸御殿薬医門が現存していることを発見し、とりあえず見に行くことに。夏休みで部活の練習なんかをしている中、堂々と校門から車を乗り付ける。小さい門だったが、これは何ともいい感じで、そこからちらりと見える天守もまたいい感じだった。 帰りには、十万石最中(有名らしい。老舗的な小さい店で買った。)を親にお土産に買って帰る。一つだけ二人で食べてみたのだが、これが美味い。すごい大量のあんこで、これがまた何とも言えない。行かれたら是非とも食べていただきたい(H12.7.22)  続日本100名城スタンプ押印を目的に、再訪。コロナ禍もあって人が少ないかと思いきや、思った以上の人出。駐車場にあった蕎麦屋さんは緊急事態宣言を受けて休業中だったが。 続日本100名城スタンプ押印を目的に、再訪。コロナ禍もあって人が少ないかと思いきや、思った以上の人出。駐車場にあった蕎麦屋さんは緊急事態宣言を受けて休業中だったが。時間は経ったが、感想はほぼ同じ。やはりコンクリートの復元天守ではテンションが上がらない。復元と言っても推定復元である。天守非実在説もあるくらいだから、難しいところである。ただ、天守台の石垣はかなり本物っぽく仕上げている。打ち込みハギの石垣で、矢穴の跡がついているのだ。石はそうやって切り出したのかもしれない。 中は…言うまでもないという感じか。千葉県立博物館の分館の一つなのだそうだから、やむを得ないのかもしれない。それでも続日本100名城のスタンプが入場料を払ってからしか押せないのはいかがなものか。200円をケチっているわけではもちろんないのだが…(R3.9.19) |
| 一宮城(E) 中世 平山城 |
 築城時期は不明だが、戦国時代には里見氏に属した正木氏が支配。小田原合戦で本田忠勝により落城。一旦廃城となるが、江戸後期に陣屋として再整備されるが、廃藩置県により再度廃城となる。 築城時期は不明だが、戦国時代には里見氏に属した正木氏が支配。小田原合戦で本田忠勝により落城。一旦廃城となるが、江戸後期に陣屋として再整備されるが、廃藩置県により再度廃城となる。 久留里にキャンプに来た帰りに足を延ばす。 久留里にキャンプに来た帰りに足を延ばす。一応、城山公園となっているが、見るべきものはほとんどなかった。入り口に大手門らしきものが建てられているが、恐らくは模擬。中に入ると武道場(「振武館」というらしい)があり、その奥に少し開けた場所があって、そこからは一宮の街並みが一望できる。 城のすぐ近くには一ノ宮の地名の由来となった「玉前神社」、3キロほど行けば海岸があり、海鮮料理がおいしい店もたくさんある。町としては非常に楽しい町であった。(H23.10.9) |
| 鷺沼城 中世 平山城 |
平安時代に築かれたとされるが、不明点が多い。 住宅地の中にある普通の公園に見えるが、名前は鷺沼城址公園。犬の散歩に来ている人がいる普通の公園で、中には埴輪のレプリカが置かれている。看板を見ると「鷺沼古墳B号墳箱式石棺」とある。6世紀に造られた古墳でもあったようである。遺構は特に無さそうだが、公園としてであれ、何かしらの痕跡は残していってもらいたいものである。(R1.10.6) 住宅地の中にある普通の公園に見えるが、名前は鷺沼城址公園。犬の散歩に来ている人がいる普通の公園で、中には埴輪のレプリカが置かれている。看板を見ると「鷺沼古墳B号墳箱式石棺」とある。6世紀に造られた古墳でもあったようである。遺構は特に無さそうだが、公園としてであれ、何かしらの痕跡は残していってもらいたいものである。(R1.10.6) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 館山城 近世 丘城 |
 戦国大名里見氏の最後の本拠となった城であり、稲村・久留里・佐貫城を構え、里見義堯の代には北条氏と激しい攻防を繰り返した。近世大名となった里見忠義は近世城郭に改修するが、大久保事件に連座し、改易されてしまう。遺構としては虎口と堀切を伴って本丸跡にわずかに石垣が残る。天守閣は模擬であり、旧館山城の景観とは異なるものである。 戦国大名里見氏の最後の本拠となった城であり、稲村・久留里・佐貫城を構え、里見義堯の代には北条氏と激しい攻防を繰り返した。近世大名となった里見忠義は近世城郭に改修するが、大久保事件に連座し、改易されてしまう。遺構としては虎口と堀切を伴って本丸跡にわずかに石垣が残る。天守閣は模擬であり、旧館山城の景観とは異なるものである。 亀山湖にキャンプに行って、あくる日に鴨川シーワールドに行き、さらに帰りにちらっと寄ってみた。わずかに遺構と思われる堀があったように思うが、下のほうに公園があったり、本丸に至る途中に孔雀のオリがあったりして、基本的に普通の丘。小高い丘の上になぜか天守閣的建物が建っている、という感じ。とてもいいとは言いがたい城だったが、城というものを残していくためには仕方ないんだろうか。妙に考え込んでしまった・・・(H15.6.15) 亀山湖にキャンプに行って、あくる日に鴨川シーワールドに行き、さらに帰りにちらっと寄ってみた。わずかに遺構と思われる堀があったように思うが、下のほうに公園があったり、本丸に至る途中に孔雀のオリがあったりして、基本的に普通の丘。小高い丘の上になぜか天守閣的建物が建っている、という感じ。とてもいいとは言いがたい城だったが、城というものを残していくためには仕方ないんだろうか。妙に考え込んでしまった・・・(H15.6.15)*千葉県のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 忍城(おしじょう) 続日本百名城:118 |
 1490年、中世武士団の頭領であった成田親泰が築城。成田氏は当城を本拠に北武蔵に強大な武士団として成長し、戦国期には関東管領山内上杉憲政や古河公方足利晴氏と結び、北条氏の北進をくいとめ、上杉氏の南進に対しても落城しなかった。後に北条氏に属し、秀吉の小田原合戦に際しては石田三成や長束正家らの大軍による水攻めにも全く動じなかった。ついに小田原落城後に北条氏長が開城勧告を出すまで開城しなかったという天下の堅城である。近世になって川越、岩槻と共に江戸背後の要として松平忠吉・酒井忠次・松平忠堯ら大老・老中といった幕閣の要人が入城した。天守としては二の丸に御三階櫓を上げ、5つの島を曲輪とする行田市街を囲む広大な城域を持っていた。 1490年、中世武士団の頭領であった成田親泰が築城。成田氏は当城を本拠に北武蔵に強大な武士団として成長し、戦国期には関東管領山内上杉憲政や古河公方足利晴氏と結び、北条氏の北進をくいとめ、上杉氏の南進に対しても落城しなかった。後に北条氏に属し、秀吉の小田原合戦に際しては石田三成や長束正家らの大軍による水攻めにも全く動じなかった。ついに小田原落城後に北条氏長が開城勧告を出すまで開城しなかったという天下の堅城である。近世になって川越、岩槻と共に江戸背後の要として松平忠吉・酒井忠次・松平忠堯ら大老・老中といった幕閣の要人が入城した。天守としては二の丸に御三階櫓を上げ、5つの島を曲輪とする行田市街を囲む広大な城域を持っていた。現在、遺構としては石垣・土塁・水堀といったものが残り、昭和63年には天守が復元された。 *埋もれた古城  水城公園の駐車場にとめて、復元されたという天守を探すと・・・無い。少し歩くと・・・彼方に見えてきました。何でこんなに離れてんのかな?と思ったら、天守、というよりも御三階櫓を復元したらしいのだが、これは本丸に復元していて、公園は城の末端に位置するらしい。御三階櫓は行田市郷土博物館になっていて、城の全体模型等も置かれているが、それを見ると御三階櫓は三の丸よりさらに外れに建っていたらしい。つまり、この建物は何も無かったところに勝手に建てたということになる。石垣などはよく作られていて、本物かと思ってしまった。中はご多分に漏れず大したものは無いが、それでも木目調に色を統一しているだけでも少々は好感が持てた。 水城公園の駐車場にとめて、復元されたという天守を探すと・・・無い。少し歩くと・・・彼方に見えてきました。何でこんなに離れてんのかな?と思ったら、天守、というよりも御三階櫓を復元したらしいのだが、これは本丸に復元していて、公園は城の末端に位置するらしい。御三階櫓は行田市郷土博物館になっていて、城の全体模型等も置かれているが、それを見ると御三階櫓は三の丸よりさらに外れに建っていたらしい。つまり、この建物は何も無かったところに勝手に建てたということになる。石垣などはよく作られていて、本物かと思ってしまった。中はご多分に漏れず大したものは無いが、それでも木目調に色を統一しているだけでも少々は好感が持てた。その後水城公園をブラブラしていたのだが、広大な沼に各曲輪を島のように配置していた当時を想像すると、光秀ではないが、水攻めにでもしないと落ちないような気がしてくるのは気のせいだろうか・・・(H15.10.5)  再訪したが、前回の記憶はほとんどなく、郷土博物館の駐車場に車を停めて本丸をうろうろした。感想としては、すべてが嘘っぽい。外見は復元しているのだとは思うが、やはり御三階櫓の位置が異なる以上はどうしてもそういう目で見てしまう。御三階櫓の周りは本丸部分を石垣と塀が囲んでいるのだが、これも城の構造物には見えない。残念ながら郷土博物館に入る気にもなれず、郷土博物館とつながっている御三階櫓にも入らなかった。本丸西側に土塁が残っているらしく、それだけ見たかったのだが、あまりの暑さに探索を断念。帰りに水城公園に立ち寄ったが、こちらは普通の公園。本丸からはそれなりに離れており、そこに外堀があったということなので、相当な規模だったことが想像できる。有名な城であるだけに、正直残念な城と言わざるを得ない。(R3.8.11) 再訪したが、前回の記憶はほとんどなく、郷土博物館の駐車場に車を停めて本丸をうろうろした。感想としては、すべてが嘘っぽい。外見は復元しているのだとは思うが、やはり御三階櫓の位置が異なる以上はどうしてもそういう目で見てしまう。御三階櫓の周りは本丸部分を石垣と塀が囲んでいるのだが、これも城の構造物には見えない。残念ながら郷土博物館に入る気にもなれず、郷土博物館とつながっている御三階櫓にも入らなかった。本丸西側に土塁が残っているらしく、それだけ見たかったのだが、あまりの暑さに探索を断念。帰りに水城公園に立ち寄ったが、こちらは普通の公園。本丸からはそれなりに離れており、そこに外堀があったということなので、相当な規模だったことが想像できる。有名な城であるだけに、正直残念な城と言わざるを得ない。(R3.8.11) |
| 松山城(D) 室町 平山城 |
 武蔵七党の一つ上田氏が1399年に築かれたのが起こりと伝わる。上田氏が城主のまま上杉氏の支配下にあったが、1546年川越城主北条綱成に攻略され、以後後北条氏の支配化に入る。川中島で上杉武田両軍の激突が続いていた1561年、北条の武田加勢を牽制する意味合いで謙信は太田資正に命じて松山城を急襲させ、奪ってしまう。翌1562年には武田北条5万に攻め立てられ、謙信の応援を待ったが、応援到着直前に謀略により落城する。世に言う「松山合戦」がこれである。武田氏滅亡後、一旦は滝川一益の支配下となるが、また北条の支配下に入り、秀吉の小田原攻めで落城。1601年に廃城となる。 武蔵七党の一つ上田氏が1399年に築かれたのが起こりと伝わる。上田氏が城主のまま上杉氏の支配下にあったが、1546年川越城主北条綱成に攻略され、以後後北条氏の支配化に入る。川中島で上杉武田両軍の激突が続いていた1561年、北条の武田加勢を牽制する意味合いで謙信は太田資正に命じて松山城を急襲させ、奪ってしまう。翌1562年には武田北条5万に攻め立てられ、謙信の応援を待ったが、応援到着直前に謀略により落城する。世に言う「松山合戦」がこれである。武田氏滅亡後、一旦は滝川一益の支配下となるが、また北条の支配下に入り、秀吉の小田原攻めで落城。1601年に廃城となる。これだけ攻防の激しい城も珍しく、それだけ重要な位置にあったということであろう。遺構はほとんど残っておらず、ごく一部土塁跡らしきものが見られるのみ。  曲輪跡がよく残る山城だった。 曲輪跡がよく残る山城だった。 裏から道なき道を登ったのだが、割とすぐに本丸跡に到着。すぐに本丸に行けるこんな道、当時はなかっただろうと思うが、今となるとありがたい。上から見ると二の丸、三の丸、その他曲輪がよくわかり、非常に面白かった。ちなみに、本丸跡には神社が建っていたらしいのだが、本尊は土台しか残っておらず、左側にあったと思われる建物は倒壊していた。このままほっといていいのかなぁ?(H15.10.5) 裏から道なき道を登ったのだが、割とすぐに本丸跡に到着。すぐに本丸に行けるこんな道、当時はなかっただろうと思うが、今となるとありがたい。上から見ると二の丸、三の丸、その他曲輪がよくわかり、非常に面白かった。ちなみに、本丸跡には神社が建っていたらしいのだが、本尊は土台しか残っておらず、左側にあったと思われる建物は倒壊していた。このままほっといていいのかなぁ?(H15.10.5) 吉見百穴に来たので、寄ろうと思ったのだが、もう帰る時間で、ゆっくり見れなさそうだったので、退散することにした。今度またゆっくり来よう。(R3.8.11) 吉見百穴に来たので、寄ろうと思ったのだが、もう帰る時間で、ゆっくり見れなさそうだったので、退散することにした。今度またゆっくり来よう。(R3.8.11) |
| 杉山城(C) 室町 平山城 続日本百名城:119 |
 「長享の乱」と呼ばれる山内上杉氏と扇谷上杉氏との一連の戦いのなかで、山内上杉氏が扇谷上杉氏に対抗して築城したものと考えられる。 「長享の乱」と呼ばれる山内上杉氏と扇谷上杉氏との一連の戦いのなかで、山内上杉氏が扇谷上杉氏に対抗して築城したものと考えられる。城跡は中世城郭としてはこれ以上ないレベルで遺構が残存している。本郭を中心として北・東・南の三方向にそれぞれ二の郭、三の郭を梯段状に連ね、さらに外郭、馬出郭、井戸郭が配置されており、複雑に入り組んだ帯郭や空堀が非常に良好に保存されている。 *杉山城公式  非常に来たかった城跡にようやく来ることができた。「関東戦国山城の最高傑作」「築城の教科書」と言われる城跡で、その讃辞に相応しい城跡だった。 非常に来たかった城跡にようやく来ることができた。「関東戦国山城の最高傑作」「築城の教科書」と言われる城跡で、その讃辞に相応しい城跡だった。駐車場に車を停め、中学校の敷地の中を城跡に向かって歩くと、大手口に到着する。ここからの眺めがまず素晴らしい。段違いになっている各郭を背に、ここしかない位置に大手口が配置されている。大手口を入ると外郭があるのだが、そこから南三の郭には一旦空堀に下りないと行くことができない。かつては木橋がかかっていたようなのだが、もちろん今はないからである。南三の郭から南二の郭に行く道は食い違い虎口になっていることが良く分かる。さらに南二の郭から、井戸郭に寄り道して、井戸を見る。廃城になったときに石で蓋をされたということだが、その石の周りに水溜りができている。南二の郭に戻り、本郭に向かうのだが、直接は行けず、一旦帯郭に下りてからでないと行けないようになっている。そして本郭、段々の一番上にあるので、眺めも素晴らしいのだが、それ以上に下に見える郭の数々、土塁と空堀、が芸術的で何とも言えない。 歴史の中でほぼ登場することのない城なのに、ここまでの高いレベルで遺構が残存しているのは奇跡に近い。また、この真夏に草がボウボウになることなく、よく整えられているのは役所の方々、中学校の生徒たちが維持活動をしていただいているお陰だと思う。数々の関東の土の城を訪問したが、感動に近い感情を覚えたのはこの城くらいではないか。多少無理をしても訪問していただきたい城である。(R3.8.11) |
| 菅谷館(C) 室町 平山城 続日本百名城:120 |
鎌倉時代に武蔵武士の畠山重忠が居住した所と伝えられる。戦国時代には須賀谷原の合戦の後、山内上杉氏によって再興された「須賀谷旧城」と考えられている。 *埼玉県立嵐山史跡の博物館  博物館に車を停め、裏手から三の郭に入ることができた。そこから二の郭、本郭、と進むのだが、とにかく一つの郭が広い。郭毎に周囲が土塁と空堀で囲われており、入口は1~2ヶ所で、それぞれ狭く、容易には侵入できないようになっている。元々都幾川の断崖上に築かれており、各郭の高低差はさほどなく、ほぼ平城ではないかと思われるほど。中世の城で平城はあまりなく、ある意味興味深かった。この城に来る前には杉山城に行っており、車で30分ほどの距離なのだが、中世の山城と平城の両方を近隣で堪能できる数少ない城跡ではないかと思う。杉山城・菅谷城・松山城・小倉城が「比企城館跡群」として国史跡に指定されたというのも頷ける。(R3.8.11) 博物館に車を停め、裏手から三の郭に入ることができた。そこから二の郭、本郭、と進むのだが、とにかく一つの郭が広い。郭毎に周囲が土塁と空堀で囲われており、入口は1~2ヶ所で、それぞれ狭く、容易には侵入できないようになっている。元々都幾川の断崖上に築かれており、各郭の高低差はさほどなく、ほぼ平城ではないかと思われるほど。中世の城で平城はあまりなく、ある意味興味深かった。この城に来る前には杉山城に行っており、車で30分ほどの距離なのだが、中世の山城と平城の両方を近隣で堪能できる数少ない城跡ではないかと思う。杉山城・菅谷城・松山城・小倉城が「比企城館跡群」として国史跡に指定されたというのも頷ける。(R3.8.11) |
| 鉢形城(C) 日本百名城:18 |
 1476年、関東管領山内上杉の家臣長尾景春が築城、北条氏邦が整備拡張した。後北条氏による北関東支配の拠点として重要な役割を担い、1569年には武田信玄の、1574年には上杉謙信の攻撃を受け、それぞれ撃退している。1590年の秀吉による小田原攻めの際には、前田上杉等の北国軍に包囲され、1ヶ月余りの籠城の後、開城した。 1476年、関東管領山内上杉の家臣長尾景春が築城、北条氏邦が整備拡張した。後北条氏による北関東支配の拠点として重要な役割を担い、1569年には武田信玄の、1574年には上杉謙信の攻撃を受け、それぞれ撃退している。1590年の秀吉による小田原攻めの際には、前田上杉等の北国軍に包囲され、1ヶ月余りの籠城の後、開城した。荒川と深沢川に挟まれた断崖絶壁に築かれていて、天然の要害となっており、その遺構が広範囲に残っている。鉢形城公園として整備され、鉢形城歴史館が建てられ、二の曲輪・三の曲輪には発掘調査の成果を元に戦国時代の石積みの土塁・門・池などを復元している。 *鉢形城歴史館  最初全体像を把握せずに本曲輪の一角に車を停め、本曲輪へ。入口に若干の石垣があり、奥にはかなり広いスペースが。眼下には荒川が流れ、堅固さがよく分かる。ただ、あまりにも広いために何か整備をするのが難しいのか、荒れ放題に見えた。 最初全体像を把握せずに本曲輪の一角に車を停め、本曲輪へ。入口に若干の石垣があり、奥にはかなり広いスペースが。眼下には荒川が流れ、堅固さがよく分かる。ただ、あまりにも広いために何か整備をするのが難しいのか、荒れ放題に見えた。続いて二の曲輪・三の曲輪に。こちらはやり過ぎなほど整備されている。どうもこちらは発掘調査が終わったため、その調査結果を元に整備したようだ。戦国時代の城郭は雰囲気が掴みづらいところがあって、石積みの土塁など、江戸時代の城では見ることのないものも見れてありがたい半面、綺麗過ぎてどうもピンとこない。時間が経てば、味も出てくるのだとは思うが…。 二の曲輪・三の曲輪の向かいには伝逸見曲輪などの曲輪がいくつも広がっており、本当に広範囲に城跡がある。もちろん、その向こう側には深沢川があって、川と川に挟まれた三角州のようなところを丸ごと城にしてしまっている。その手の城は何度か行ったことはあるのだが、これだけ大規模な城で、ここまで保存されているのは非常に珍しいのではないかと思う。惜しむらくはあまりにも広大なためにそれが全体として俯瞰して見ることができないこと。これだけの跡地を全体として整備するのは莫大な費用がかかることが容易に想像できるので、無理な注文であることは間違いない。今はただ、都市開発の波に飲み込まれることの無いよう、切に祈りたい。(R1.8.21) |
| 川越城 日本百名城:19 |
 1457年扇谷上杉の部将太田道灌によって江戸・岩槻と共に築かれた。城の完成と共に扇谷上杉持朝が入城、以後80年間本拠となった。扇谷上杉氏は太田道灌の機略によって勢力を増したが、山内上杉氏によって道灌が暗殺されてからは一進一退を繰り返した。その漁夫の利を得たのが後北条氏で、1537年には事実上扇谷上杉氏を滅亡に追い込んでしまう。同じ年、両上杉氏は手を組んで川越城奪回に八万余騎もの兵を動員し、川越城を取り囲んだ。ところが城を守る北条綱成と北条氏康の機略により簡単に崩壊させられてしまう。いわゆる「川越の夜戦」である。江戸時代になって家康は江戸城の前衛として重要視し、酒井忠重を城主として本格的に改修させ、三層の天守のほか、七基の櫓が上がった。現存する本丸御殿は1848年に松平斉典によって作られたもので全国的にも貴重な遺構である。 1457年扇谷上杉の部将太田道灌によって江戸・岩槻と共に築かれた。城の完成と共に扇谷上杉持朝が入城、以後80年間本拠となった。扇谷上杉氏は太田道灌の機略によって勢力を増したが、山内上杉氏によって道灌が暗殺されてからは一進一退を繰り返した。その漁夫の利を得たのが後北条氏で、1537年には事実上扇谷上杉氏を滅亡に追い込んでしまう。同じ年、両上杉氏は手を組んで川越城奪回に八万余騎もの兵を動員し、川越城を取り囲んだ。ところが城を守る北条綱成と北条氏康の機略により簡単に崩壊させられてしまう。いわゆる「川越の夜戦」である。江戸時代になって家康は江戸城の前衛として重要視し、酒井忠重を城主として本格的に改修させ、三層の天守のほか、七基の櫓が上がった。現存する本丸御殿は1848年に松平斉典によって作られたもので全国的にも貴重な遺構である。*川越市教育委員会 *kみむさんのページ  本丸御殿が残っているというから非常に期待して行ったのだが、なーんと休館日だった。なーんとついてない。駅から結構な距離を歩いて行ったというのに・・・まあ立派な外観を見れたから良しとしておこうか。それと、川越城は天守がなかったため、その代わりをしていた富士見櫓跡があった。ただこれも単なる丘がぽつんとあるだけで、縄張りなどが想像できるレベルのものではなくてちょっと残念だった。(H9.3.21) 本丸御殿が残っているというから非常に期待して行ったのだが、なーんと休館日だった。なーんとついてない。駅から結構な距離を歩いて行ったというのに・・・まあ立派な外観を見れたから良しとしておこうか。それと、川越城は天守がなかったため、その代わりをしていた富士見櫓跡があった。ただこれも単なる丘がぽつんとあるだけで、縄張りなどが想像できるレベルのものではなくてちょっと残念だった。(H9.3.21) 本丸御殿が開いてました!やった!でも車がやたら混んでいるなーと思ったら本丸御殿の向かいで何やら錦鯉祭りなるものをやっている。混んでるわけだ。 本丸御殿が開いてました!やった!でも車がやたら混んでいるなーと思ったら本丸御殿の向かいで何やら錦鯉祭りなるものをやっている。混んでるわけだ。それはそうと、本丸御殿、素晴らしかった。見ようによっては普通の広くて古い家なんだけど、そこは城郭建築、大広間の襖絵とか、廊下に沿った細長い控の間とか、お城たるべき要素が多くて感動。1990年に上福岡市に移築されていたという家老詰め所が戻されたとかで、そちらも合わせて素晴らしかった。やっぱり現存しているものは重みが違うなー。かつては今残っているものの5~10倍あったというから、想像するだけで楽しくなってくる。是非行っていただきたい遺構である。(H15.10.5)  日本百名城のスタンプを押すために、何度目か訪問した。しかし、何度行ってもいいものはいい。現存しているものは重みが全く違う。本丸御殿以外では、以前富士見櫓を見に行ったのだが、今回は中ノ門堀跡に行った。富士見櫓跡も中野門堀跡もそうなのだが、住宅街の中に突然遺構が現れる。川越くらい都会に、これだけの規模の城ということになると、どうしてもこれくらいが限界なのだろう。全体感を掴めないのは残念ではあるが、それでもよく残してくれている方なのだと思う。(R1.8.21) 日本百名城のスタンプを押すために、何度目か訪問した。しかし、何度行ってもいいものはいい。現存しているものは重みが全く違う。本丸御殿以外では、以前富士見櫓を見に行ったのだが、今回は中ノ門堀跡に行った。富士見櫓跡も中野門堀跡もそうなのだが、住宅街の中に突然遺構が現れる。川越くらい都会に、これだけの規模の城ということになると、どうしてもこれくらいが限界なのだろう。全体感を掴めないのは残念ではあるが、それでもよく残してくれている方なのだと思う。(R1.8.21) |
| 江戸城 近世 平山城 日本百名城:14 |
 〈田安門,清水門,外桜田門〉 〈田安門,清水門,外桜田門〉江戸時代の政治・経済の中心となった名城。1605年から30年以上かけて築かれた世界最大の木造建築。当時五層六階で、38×34㍍、高さ61㍍であったが、1657年の明暦大火で全焼し、以後再建されることはなかった。その他にも三重櫓が七基、二重櫓が十二基、単層櫓が五十五基、城門は127基あったという。現在残っている櫓は関東大震災で大破したものをコンクリートで復興したものである。城門はいくつか現存し、3つは国の重要文化財に指定されている。 *宮内庁 *小島さんのページ  就職活動で東京に行った帰りに時間が余ったので立ち寄る。江戸城とは皇居のことであるが、見学できない訳ではない。西の丸とその他2/3ほどは入れないが、本丸跡や二の丸・三の丸のある東御苑には無料で入る事が出来る。中は広大で、周りの官庁社とのコントラストが不思議な感じがする。また、二の丸庭園は花が咲き誇っていて奇麗だった。その後、とりあえず歩いて皇居を一周して大抵の橋を見たのだが、猛烈に疲れた。これだけはお勧めできるものではない。(H8.6.26) 就職活動で東京に行った帰りに時間が余ったので立ち寄る。江戸城とは皇居のことであるが、見学できない訳ではない。西の丸とその他2/3ほどは入れないが、本丸跡や二の丸・三の丸のある東御苑には無料で入る事が出来る。中は広大で、周りの官庁社とのコントラストが不思議な感じがする。また、二の丸庭園は花が咲き誇っていて奇麗だった。その後、とりあえず歩いて皇居を一周して大抵の橋を見たのだが、猛烈に疲れた。これだけはお勧めできるものではない。(H8.6.26) |
| 八王子城(C) 戦国 山城(460m) 日本百名城:22 |
 1584年から1587年にかけて築城され、後北条氏の宿老氏照の居城となった。東国では最も優れた技術を駆使したものだったが、1590年の小田原合戦では上杉・前田らの大軍に攻められ、わずか1日で落城した。現在要所要所に石垣が残り、御主殿・御天守の跡も残っている。 1584年から1587年にかけて築城され、後北条氏の宿老氏照の居城となった。東国では最も優れた技術を駆使したものだったが、1590年の小田原合戦では上杉・前田らの大軍に攻められ、わずか1日で落城した。現在要所要所に石垣が残り、御主殿・御天守の跡も残っている。*中央電子(株) *高尾通信
石段、土の坂、木の根っこ、いろんな種類の山道が行く手を阻む。すれ違う人たちは結構登山用の格好をしていたりして、なかなか本格的である。しかしこの暑い日に、山城を攻めようなんてもの好きが我々以外にも結構いるとは。登っていると、とにかく排水路によく出くわす。山城にはよく出会う排水路だが、おそらくは10個以上あっただろうか。さすがは大規模な山城である。 |
| 滝山城 戦国 山城(80m) 続日本百名城:123 |
1521年に武蔵国守護代の大石定重が築城、北条氏照が落城させ、北関東運営の居点とした。多摩川と秋川の合流点の自然を巧みに利用した城は、難攻不落であり、1569年武田信玄の軍勢2万人を2千の兵で守り抜いたと言われる。しかしこの戦闘の後、氏照はより堅牢な八王子に築城を開始、居を移した。 *八王子市 *中央電子(株) *高尾通信  八王子城の後で行ったのだが、八王子城に時間を取られすぎて、着いたのは5時頃。もう既に日が暮れかけ、ぼやーっとしか見えない状態になっていた。何とか本丸への橋を見つけ、本丸に来てみたものの、何となくしか分からない。それでも規模の大きさと本丸が独立した構造など、概略は見る事が出来た。橋を落とすと本丸が独立する構造は、八王子城の御主殿に通じるところがある。非常に興味深い城跡だった。(H16.10.31) 八王子城の後で行ったのだが、八王子城に時間を取られすぎて、着いたのは5時頃。もう既に日が暮れかけ、ぼやーっとしか見えない状態になっていた。何とか本丸への橋を見つけ、本丸に来てみたものの、何となくしか分からない。それでも規模の大きさと本丸が独立した構造など、概略は見る事が出来た。橋を落とすと本丸が独立する構造は、八王子城の御主殿に通じるところがある。非常に興味深い城跡だった。(H16.10.31) 今回も八王子城の後で行ったが、今回はちゃんと朝から出てきたので、十分明るい状態で見ることができた。土塁と空堀がよく残り、よくというか大規模にクッキリ残っており、入口に置いてある城攻めマップを片手に歩くと、在りし日の名城が目の前によみがえるようである。各曲輪は木々で鬱蒼としていてなかなか全体像は掴みにくいが、曲輪の間にある大規模な堀切は一見の価値ありである。 今回も八王子城の後で行ったが、今回はちゃんと朝から出てきたので、十分明るい状態で見ることができた。土塁と空堀がよく残り、よくというか大規模にクッキリ残っており、入口に置いてある城攻めマップを片手に歩くと、在りし日の名城が目の前によみがえるようである。各曲輪は木々で鬱蒼としていてなかなか全体像は掴みにくいが、曲輪の間にある大規模な堀切は一見の価値ありである。いやぁ、この辺、八王子城もそうだし、素晴らしい城が多く残っている。とはいうものの、八王子城で疲れきった身体には少々きつかった。(R2.8.9) |
| 片倉城 |  大江広元を祖にもつ長井氏によって、室町時代に築城されたと言われる。空堀・土塁等の名残があり、15世紀後半の中世城郭の形態を示す。 大江広元を祖にもつ長井氏によって、室町時代に築城されたと言われる。空堀・土塁等の名残があり、15世紀後半の中世城郭の形態を示す。*八王子市 *高尾通信  完全に公園化されている。二の丸跡では親子連れがボールやフリスビーで遊んでいた。本丸も同様に芝生で広場になっているのだが、どうも城という雰囲気が希薄である。各所に土塁や空堀があり、それなりの規模の城であるとは思うのだが、さすがに時間が経ちすぎて原形を留められていないということだろうか・・・(H16.10.31) 完全に公園化されている。二の丸跡では親子連れがボールやフリスビーで遊んでいた。本丸も同様に芝生で広場になっているのだが、どうも城という雰囲気が希薄である。各所に土塁や空堀があり、それなりの規模の城であるとは思うのだが、さすがに時間が経ちすぎて原形を留められていないということだろうか・・・(H16.10.31) |
| 岩槻城 室町 平城 |
 1457年、太田道真・道灌が築城。扇谷上杉氏が、吉河公方に対する拠点とした。元荒川と綾瀬川にはさまれた地形を利用して築かれ、別名を「浮き城」という。江戸時代は江戸城の衛星的支城として幕府の重臣が配された。 1457年、太田道真・道灌が築城。扇谷上杉氏が、吉河公方に対する拠点とした。元荒川と綾瀬川にはさまれた地形を利用して築かれ、別名を「浮き城」という。江戸時代は江戸城の衛星的支城として幕府の重臣が配された。現在の城跡は、城跡の中心部分を県道が横切り、遺構はかなり限定される。それでも城址公園には大手門が移築され、土塁上には時の鐘が残る。 *川口さんのページ  元荒川沿いに岩槻公園があり、ウロウロしてみる。市民のための公園となっていて、大きな芝生があって、アスレチックのようなものがあったり、池があって鯉が泳いでいたり、なかなかいい雰囲気。その横には野球場があり、向かいに移築された門が二つ。看板にはどこの門か分からないと書かれてあるが、確かに岩槻城の物らしい。あとは土塁と空掘がかなり大きく残っている。 元荒川沿いに岩槻公園があり、ウロウロしてみる。市民のための公園となっていて、大きな芝生があって、アスレチックのようなものがあったり、池があって鯉が泳いでいたり、なかなかいい雰囲気。その横には野球場があり、向かいに移築された門が二つ。看板にはどこの門か分からないと書かれてあるが、確かに岩槻城の物らしい。あとは土塁と空掘がかなり大きく残っている。 ここではなんと空掘をそのまま「散策の路」としてしまっており、非常に興味深かった。結構犬の散歩とかをしている人を見かけた。 ここではなんと空掘をそのまま「散策の路」としてしまっており、非常に興味深かった。結構犬の散歩とかをしている人を見かけた。ただこちらは本丸ではなく、本丸は県道の下に消えてしまったという。残念。本丸のあったところから県道を大手口のほうに戻り、すこし横道を入ると時の鐘が民家の隙間に現存している。かなり注意深く探さないと見つからないかもしれない。ここまでが城跡、ここからは城下町、という区切りらしく、想像力を働かせると少しは往時を偲ぶことができるのではないだろうか。(H15.10.5) |
| 小机城 中世 丘城 続日本百名城:125 |
 長尾景春に味方をした矢野兵庫助は上杉方の武将太田道灌に攻められ、落城。上杉氏が凋落後は北条氏の支配下に入り、氏綱が大修築を行う。その後、秀吉の関東征伐により北条氏は滅亡し、本城も廃城となる。 長尾景春に味方をした矢野兵庫助は上杉方の武将太田道灌に攻められ、落城。上杉氏が凋落後は北条氏の支配下に入り、氏綱が大修築を行う。その後、秀吉の関東征伐により北条氏は滅亡し、本城も廃城となる。 横浜中華街に行った帰りにちょこっと寄る。横浜国際競技場のすぐ近くだった。細い道に、小さな看板で、「←小机城址市民の森」というのがあって、入っていくと民家のゴミ捨て場の間の山道を上がっていくことに。途中で竹が倒れていてやたら通りにくかったが、急な階段を登ると、とりあえずという感じで碑がたっていた。(写真)その横には普通の畑が。ひまわりが咲いていたりして、城跡という感じは全くない。その畑が曲輪跡だったりするのかもしれない。蚊が多かった。(H15.6.21) 横浜中華街に行った帰りにちょこっと寄る。横浜国際競技場のすぐ近くだった。細い道に、小さな看板で、「←小机城址市民の森」というのがあって、入っていくと民家のゴミ捨て場の間の山道を上がっていくことに。途中で竹が倒れていてやたら通りにくかったが、急な階段を登ると、とりあえずという感じで碑がたっていた。(写真)その横には普通の畑が。ひまわりが咲いていたりして、城跡という感じは全くない。その畑が曲輪跡だったりするのかもしれない。蚊が多かった。(H15.6.21) なかなか立派な城跡だった。以前行った時の感想は何なのだろうか?ごく一部だけ見ていたのか、16年の間に整備が進んだのか。。。恐らくは両方なのだろう。 なかなか立派な城跡だった。以前行った時の感想は何なのだろうか?ごく一部だけ見ていたのか、16年の間に整備が進んだのか。。。恐らくは両方なのだろう。階段を登ってまず正面に現れるのが巨大な空堀。その空堀を右手に行くと二ノ丸広場、左手に行くと本丸広場がある。それぞれの曲輪が本丸と二の丸として使われていたかどうかは定かではないらしいが、二つの曲輪を繋ぐ構造になっている。その二つの曲輪の周りにある土塁と空堀が本当によく残っている。市民の森と言っても、完全に城跡であり、公園らしい何かは特に無い。城巡りをしている人間からしたら素晴らしいことだが、一般市民が公園としては使えるかはかなり疑問。ただ、二ノ丸の奥で管楽器を練習している人がいた。あまり人が来ないからじっくり練習できるのだろうか。結論としては中世の城の雰囲気が良く残る素晴らしい城跡であり、この雰囲気を構成にまで伝えていけるよう、是非とも保存していってもらいたいものだ。(R1.10.27) |
| 茅ヶ崎城 中世 丘城 |
14世紀末から15世紀前半に築城され、上杉・後北条氏が関与していたと思われるが、不明点が多い。 全般的に整備され過ぎている印象。階段や通路が9割方コンクリートで固められている。4つの郭がきれいに残り、それぞれかなり大きいので、見ごたえがあるのだが、とにかくコンクリートが・・・。贅沢なのかもしれないが、ワクワクしてこない。小机城とは異なり、この城は城跡と公園を両立させようとしているようにも感じられる。(R1.10.27) 全般的に整備され過ぎている印象。階段や通路が9割方コンクリートで固められている。4つの郭がきれいに残り、それぞれかなり大きいので、見ごたえがあるのだが、とにかくコンクリートが・・・。贅沢なのかもしれないが、ワクワクしてこない。小机城とは異なり、この城は城跡と公園を両立させようとしているようにも感じられる。(R1.10.27) |
| 石神井城 戦国 平山城 |
 あの(矢鴨で)有名な石神井公園内にある城跡。公園駅側から公園に入ると城跡は完全に逆側にあるため、最初どこにあるのかわからず随分うろうろしてしまった。結局この公園、相当規模の大きな公園で、だーいぶ奥に行かねばならなかったのである。遺構としては三宝寺池の南岸に堀切が、少し上に土塁と空掘が残っている程度だった。その土塁・空掘もそう見れば見れなくもないくらいのものだが、フェンスで保護されていたからそれでもよく保存されているもののようだった。中世の、それも平城ではこれくらいが限界なのかもしれないが・・・。(H9.3.21) あの(矢鴨で)有名な石神井公園内にある城跡。公園駅側から公園に入ると城跡は完全に逆側にあるため、最初どこにあるのかわからず随分うろうろしてしまった。結局この公園、相当規模の大きな公園で、だーいぶ奥に行かねばならなかったのである。遺構としては三宝寺池の南岸に堀切が、少し上に土塁と空掘が残っている程度だった。その土塁・空掘もそう見れば見れなくもないくらいのものだが、フェンスで保護されていたからそれでもよく保存されているもののようだった。中世の、それも平城ではこれくらいが限界なのかもしれないが・・・。(H9.3.21) |
| 世田谷城 戦国 平山城 |
 14世紀後半に吉良治家が居住したのが始まりと言われる。始め鎌倉公方に、その後関東管領上杉氏、後北条氏と仕えた。小田原合戦で本城も廃城となった。今は豪徳寺境内とその隣に城址公園として土塁・空堀がわずかに残る。 14世紀後半に吉良治家が居住したのが始まりと言われる。始め鎌倉公方に、その後関東管領上杉氏、後北条氏と仕えた。小田原合戦で本城も廃城となった。今は豪徳寺境内とその隣に城址公園として土塁・空堀がわずかに残る。 城址公園は土塁と空堀らしきものが残っているが、土塁の周りがコンクリートで固められている。公園の奥の方には少し保存状態の良いものもありそうだったが、立ち入り禁止になっていた。豪徳寺は規模の大きな寺だが、城跡らしきものは何も無い。彦根井伊家の飛び地として世田谷領があったらしく、井伊家代々の墓があった。あの井伊直弼の墓もあった。都心での城跡ではこれくらいが仕方ないレベルなのだろうか。(H16.11.2) 城址公園は土塁と空堀らしきものが残っているが、土塁の周りがコンクリートで固められている。公園の奥の方には少し保存状態の良いものもありそうだったが、立ち入り禁止になっていた。豪徳寺は規模の大きな寺だが、城跡らしきものは何も無い。彦根井伊家の飛び地として世田谷領があったらしく、井伊家代々の墓があった。あの井伊直弼の墓もあった。都心での城跡ではこれくらいが仕方ないレベルなのだろうか。(H16.11.2) |
| 渋谷城 平安 平山城 |
 平安時代末期から渋谷氏一族の居館跡で、東に鎌倉道、西に渋谷川、北東には黒鍬谷、と天然の要害であった。しかし1524年の北条軍と上杉軍との合戦で焼き払われてしまったと言う。現在遺構は特に残っていないが、金王八幡宮の敷地が跡地。 平安時代末期から渋谷氏一族の居館跡で、東に鎌倉道、西に渋谷川、北東には黒鍬谷、と天然の要害であった。しかし1524年の北条軍と上杉軍との合戦で焼き払われてしまったと言う。現在遺構は特に残っていないが、金王八幡宮の敷地が跡地。 渋谷駅から歩いて10分ほどの神社。さすがにこの場所では遺構は無い。だが、金王八幡宮社殿・門は江戸初期から現存しているものだというからすごい。この都心でこれだけの建物が見れるのは希少価値大だと思う。(H16.11.4) 渋谷駅から歩いて10分ほどの神社。さすがにこの場所では遺構は無い。だが、金王八幡宮社殿・門は江戸初期から現存しているものだというからすごい。この都心でこれだけの建物が見れるのは希少価値大だと思う。(H16.11.4) |
| 葛西城 戦国 平城 |
 葛西氏が鎌倉時代に築いたとされる。中川を天然の堀とした平城で、後北条氏側の東の最前線における非常に重要な城で、遠山綱景が城主となった。秀吉の小田原征伐で落城し、廃城となった。 葛西氏が鎌倉時代に築いたとされる。中川を天然の堀とした平城で、後北条氏側の東の最前線における非常に重要な城で、遠山綱景が城主となった。秀吉の小田原征伐で落城し、廃城となった。 環七通りの両側に御殿山公園、葛西城址公園があり、城跡の上を環七が横切っていることがよく分かる。恐らく遺構は何もない。これだけの都会であり、しかも平城ではやむを得ないと思う。それでも公園の名前として残っているだけでも良かったということだと思う。公衆トイレが異様に臭かった。(R1.10.14) 環七通りの両側に御殿山公園、葛西城址公園があり、城跡の上を環七が横切っていることがよく分かる。恐らく遺構は何もない。これだけの都会であり、しかも平城ではやむを得ないと思う。それでも公園の名前として残っているだけでも良かったということだと思う。公衆トイレが異様に臭かった。(R1.10.14) |
| 品川台場 近世 台場 続日本百名城:124 |
 幕末、ペリー艦隊来訪などを受け、江戸幕府が外国船に対する大砲を設置する要塞として、品川沖に11基の台場建設を計画した。第一・第三・第五・第六台場が完成、第四・第七台場は開国に伴って、途中で建設が中止された。現在、お台場地区と陸続きにされて、見学できるのは第三台場。第六台場も残っているが、渡ることはできない。 幕末、ペリー艦隊来訪などを受け、江戸幕府が外国船に対する大砲を設置する要塞として、品川沖に11基の台場建設を計画した。第一・第三・第五・第六台場が完成、第四・第七台場は開国に伴って、途中で建設が中止された。現在、お台場地区と陸続きにされて、見学できるのは第三台場。第六台場も残っているが、渡ることはできない。 お台場には数限りなく行っていて、いつか行きたいと思っていたが、ようやく来れた。近いところにはなかなか行かないもので…。実際に行ってみるといろんなものがきれいに残っていて驚いた。しかも、東京湾に来た船を打ち払うための要塞なのだから当たり前なのだが、そこから見える対岸の景色やレインボーブリッジは絶景。 お台場には数限りなく行っていて、いつか行きたいと思っていたが、ようやく来れた。近いところにはなかなか行かないもので…。実際に行ってみるといろんなものがきれいに残っていて驚いた。しかも、東京湾に来た船を打ち払うための要塞なのだから当たり前なのだが、そこから見える対岸の景色やレインボーブリッジは絶景。看板を見て驚いたのは、これを計画・設計したのが江川英龍だということ。去年のGW、韮山に行った時に反射炉を見学したのだが、それを作ったのが江川英龍であったのを覚えていたのだ。こういう繋がりは興味を倍増させる。 ちなみに、続日本百名城のスタンプはマリンハウス1階に設置されているのだが、これが恐ろしく乾かない。インクのせいなのか、紙質のせいなのか、私が強く押しすぎたせいなのか、原因は不明だし、もしかしたらすべて原因なのかもしれないが、いずれにしても半日触らないでようやく乾いた。(R1.11.2) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 小田原城 戦国 平山城 日本百名城:23 |
 後北条氏の居城であり、戦国時代最大の城郭である。最初に築かれたのがいつなのかははっきりしないが、西相模国人領主大森氏が領主の時に北条早雲が乗っ取ってしまう。それ以後北条氏の居城として拡張が続けられ、1590年には惣構えの12キロに及ぶ囲郭が完成した。開城後の1591年には、その堅固さにより惣構えは破却された。現在天守閣と常盤木門が復元され、本丸跡は動物園になっている。 後北条氏の居城であり、戦国時代最大の城郭である。最初に築かれたのがいつなのかははっきりしないが、西相模国人領主大森氏が領主の時に北条早雲が乗っ取ってしまう。それ以後北条氏の居城として拡張が続けられ、1590年には惣構えの12キロに及ぶ囲郭が完成した。開城後の1591年には、その堅固さにより惣構えは破却された。現在天守閣と常盤木門が復元され、本丸跡は動物園になっている。*公式  復元天守閣が建っているが、説明で見るのと階段のついてる場所が反対。さらに本丸跡一帯がなんと動物園になっている。なかなか良い復元をしている常盤木門の前ではゾウが飼われている。天下の名城小田原城を愚弄していると思うのは僕だけだろうか?駿府城とは逆に最悪の利用法ではないかと感じた。(H8.9.29) 復元天守閣が建っているが、説明で見るのと階段のついてる場所が反対。さらに本丸跡一帯がなんと動物園になっている。なかなか良い復元をしている常盤木門の前ではゾウが飼われている。天下の名城小田原城を愚弄していると思うのは僕だけだろうか?駿府城とは逆に最悪の利用法ではないかと感じた。(H8.9.29) 前に一度来たが、きちんと見れなかったので、100名城スタンプを目的に、再訪。車を停めて、近くの入り口から入ったのだが、それが学橋だった。たもとに集成館という藩校があったためにその名前がついているらしいが、本来の入り口ではない。戻って馬出門から入り直そうかと思ったが、帰りそちらに出ればいいかと思って、そのまま二ノ丸から本丸に向かう。 前に一度来たが、きちんと見れなかったので、100名城スタンプを目的に、再訪。車を停めて、近くの入り口から入ったのだが、それが学橋だった。たもとに集成館という藩校があったためにその名前がついているらしいが、本来の入り口ではない。戻って馬出門から入り直そうかと思ったが、帰りそちらに出ればいいかと思って、そのまま二ノ丸から本丸に向かう。常盤木門に向かう途中、植栽や舗装の仕方がどうにもしっくりこない。明らかに城郭としての整備ではない。常盤木門は重厚ないい雰囲気を保っているが、門をくぐると本丸が。一角に猿の檻があるものの、20数年前に来た時と比べると、随分動物園感は少なくなっている。そして天守へ。非常にきれいな博物館的な雰囲気になっている。どうも「平成の大改修」として、平成27~28年にかけて整備がなされたらしい。小田原城の成り立ちや歴史を詳しく紹介しており、好感が持てる内容ではあった。ただもちろん博物館として、の話であり、当たり前だが、城郭建築ではない。御多分に漏れず、さっさと出てきてしまった。 そして、帰りは予定通り銅門から馬出門に至るルートへ。銅門に来たら、特別公開中と書かれている。勇んで入ろうと思ったら、15:10…15時までの公開時間が終わったところだった。内部を見れなかったのは残念だったが、この銅門から住吉橋、馬出門に至るルート、本当に素晴らしい。平成9年に復元されたということで、前回来た時には復元されていなかったということらしい。城郭を城郭として整備しているので、その他のエリアとは全く違う。この城で最も来るべきエリアだと思う。が・・・天守にあれほどいた観光客がここには全然いない。小田原市さん、次は二ノ丸の整備、お願いします。(R1.8.25) |
| 石垣山城(C) 近世 山城(261m) |
1590年の小田原合戦に際し、秀吉は水陸二十万の大軍で小田原城を包囲、当初は湯本早雲寺に本陣を置いた。四月に入り小田原城西方にそびえる笠懸山に築城を開始。突貫工事により築城は100日足らずで終了し、その日の夜それまで城の前面を覆っていた樹木をいっせいに取り除いた。小田原城では一夜のうちに現れた巨城に恐れおののき、落城を早めたと言われている。それで「一夜城」の別名を持つ。今日もところどころに石垣の跡が見られ、特に井戸の曲輪は圧巻。 *小田原市  小田原城を出たのはもう夕方だったが、そこから石垣山に向かう。途中で道を聞きながら向かうも、これもまたすごい山。前日の観音寺城がこたえていて、足ががくがくしていた。本丸跡はなんとか城であったことが分かるという感じでフーンという感じだったのだが、その後行った井戸の郭跡が良かった。これはほぼ完全な形で残っているのではないだろうか。あまり見に来ている人はいなかったが、見ずに帰った人は不幸である。そして帰る頃には暗くなりかけていた。(H8.9.29) 小田原城を出たのはもう夕方だったが、そこから石垣山に向かう。途中で道を聞きながら向かうも、これもまたすごい山。前日の観音寺城がこたえていて、足ががくがくしていた。本丸跡はなんとか城であったことが分かるという感じでフーンという感じだったのだが、その後行った井戸の郭跡が良かった。これはほぼ完全な形で残っているのではないだろうか。あまり見に来ている人はいなかったが、見ずに帰った人は不幸である。そして帰る頃には暗くなりかけていた。(H8.9.29) 小田原城から車で向かう。思った以上に険しい山でびっくりした。20数年前はこれを歩いたのか。若いって素晴らしいな…。さて、駐車場に到着したら、思った以上に車が停まっている。城跡の向かいに、「一夜城 Yoroizuka Farm」というレストランと直売所があって、大半の人はそこに来ているようだった。 小田原城から車で向かう。思った以上に険しい山でびっくりした。20数年前はこれを歩いたのか。若いって素晴らしいな…。さて、駐車場に到着したら、思った以上に車が停まっている。城跡の向かいに、「一夜城 Yoroizuka Farm」というレストランと直売所があって、大半の人はそこに来ているようだった。さて、城跡に向かうと、いきなり大規模な石垣が目に入ってくる。ただ、下には大型の石が転がっている。よく見ると通路を半分以上塞ぐような形になっている。石垣がここまでに規模で崩れているのに、修復しようとする意思が全く見えない。崩れた状態こそが自然な状態だから、そのままにしておこうということなのだろうか。その考え方も理解はできるが、正確に復旧できるものは復旧してほしい。かつての姿はできる限り想像できる方が望ましいと思う。さらに奥に歩いていくと、二ノ丸・本丸と続くのだが、本当に陣城かと思うほど、しっかりした石垣が続いている。そして本丸の展望台からは、小田原城天守がきれいに見える。ここで秀吉と家康が関東経営の話をしていたのかも、とか、ここで秀吉は正宗と会ったのだろうか、とか、想像は膨らむばかり。すべての歴史ファンに是非訪問してもらいたい城である。(R1.8.25) |
| 玉縄城(C) | *埋もれた古城 |
| 大庭城 | *藤沢市 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 韮山城(C) |  1491年、今川氏の客将であった北条早雲が、堀越公方の内紛に乗じて伊豆に進出。伊豆を平定した早雲は、韮山城を築城し、自らの本城とした。早雲死後、2代目氏綱が小田原城に拠点を移したことにより、韮山城は伊豆地域を治める支城になったが、今川氏や武田氏などの戦国大名による進出に対する防御地点として、重要な意味を持ち続けた。1590年3月、秀吉の小田原攻めでは、約4万の軍勢に囲まれたが、6月に開城するまで、3ヵ月にわたる籠城戦に耐え抜いた。北条氏滅亡後は、徳川家康の家臣、内藤信成が韮山城に入城するが、1601年に廃城。 1491年、今川氏の客将であった北条早雲が、堀越公方の内紛に乗じて伊豆に進出。伊豆を平定した早雲は、韮山城を築城し、自らの本城とした。早雲死後、2代目氏綱が小田原城に拠点を移したことにより、韮山城は伊豆地域を治める支城になったが、今川氏や武田氏などの戦国大名による進出に対する防御地点として、重要な意味を持ち続けた。1590年3月、秀吉の小田原攻めでは、約4万の軍勢に囲まれたが、6月に開城するまで、3ヵ月にわたる籠城戦に耐え抜いた。北条氏滅亡後は、徳川家康の家臣、内藤信成が韮山城に入城するが、1601年に廃城。*伊豆の国市  看板が少なくて少し迷いながらだったが、何とか辿り着いた。本丸・二の丸・三の丸と、曲輪が良く残っており、堀や土塁なども確認できた。本丸の奥には畝堀のようになっている箇所もあり、非常に興味深かった。近所の家族だろうか、ピクニックのように弁当を食べていて微笑ましかった。(R1.5.3) 看板が少なくて少し迷いながらだったが、何とか辿り着いた。本丸・二の丸・三の丸と、曲輪が良く残っており、堀や土塁なども確認できた。本丸の奥には畝堀のようになっている箇所もあり、非常に興味深かった。近所の家族だろうか、ピクニックのように弁当を食べていて微笑ましかった。(R1.5.3) |
| 長浜城(C) |  北条氏は三崎や浦賀を根拠地とする三浦水軍を組織し、江戸湾から里見氏の勢力を駆逐する一方、今川義元亡き後の駿河に侵入してきた武田氏の脅威に備える水軍根拠城として整備された。1579年には北条水軍を統括する梶原備前守が長浜城におかれ、1580年、武田・北条両氏水軍による駿河湾海戦が行われた。 北条氏は三崎や浦賀を根拠地とする三浦水軍を組織し、江戸湾から里見氏の勢力を駆逐する一方、今川義元亡き後の駿河に侵入してきた武田氏の脅威に備える水軍根拠城として整備された。1579年には北条水軍を統括する梶原備前守が長浜城におかれ、1580年、武田・北条両氏水軍による駿河湾海戦が行われた。*沼津市  水軍の城ということで、とても楽しみにして行った。曲輪の跡が良く残り、第一曲輪からは富士山を含む駿河湾を一望でき、1580年に行われたという武田水軍との海戦の舞台を目の当たりにできる。また、海に面した曲輪からは海岸にまで下りることが出来た。この城も訪問すべき城の一つだと思う。 水軍の城ということで、とても楽しみにして行った。曲輪の跡が良く残り、第一曲輪からは富士山を含む駿河湾を一望でき、1580年に行われたという武田水軍との海戦の舞台を目の当たりにできる。また、海に面した曲輪からは海岸にまで下りることが出来た。この城も訪問すべき城の一つだと思う。ちなみに、周辺はラブライブの聖地なんだそうで、各お店がラブライブの装飾をしていて、ラブライブのイラストが描かれた車が停まっていて、ファンの人と思しき人がたくさんいた。そのせいか、周辺の道路が混雑していて、なかなか辿り着けなかった。(R1.5.3) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 甲府城(C) 日本百名城:25 |
 武田氏を滅ぼし、その領地を支配していた家康は1590年に関八州に移封され、羽柴秀勝、浅野長政・幸長父子らが相次ぎ入城し、城を整備。関ヶ原合戦後平岩氏などが入り、拡張整備、後には柳沢吉保の居城となった。本丸以下七つの曲輪は、階郭式平山城の典型である。 武田氏を滅ぼし、その領地を支配していた家康は1590年に関八州に移封され、羽柴秀勝、浅野長政・幸長父子らが相次ぎ入城し、城を整備。関ヶ原合戦後平岩氏などが入り、拡張整備、後には柳沢吉保の居城となった。本丸以下七つの曲輪は、階郭式平山城の典型である。*山梨放送 *kみむさんのページ  本格的なお城に行くのは約2年ぶり。着いてみると何やら「甲府大好き祭り」なるものが開催されていて、出店がたくさん出ていて、地元の人でごった返している。 本格的なお城に行くのは約2年ぶり。着いてみると何やら「甲府大好き祭り」なるものが開催されていて、出店がたくさん出ていて、地元の人でごった返している。その中をかき分けかき分け、階段を登り、本丸天守台跡へ。想像していたよりかなり広く、本格的な城であった。天守台前の芝生では、娘がはしゃぎまわって遊んでいた。やはり城跡は憩いの場としての在り方が最もいいと思う。その意味ではとても好感の持てる城跡であった。 あと、いろいろと議論はあるのだと思うが、天守台跡に、ある程度歴史検証のできた天守を復元して欲しいものだ。建っていたかどうか分からないものに歴史検証もあったものではないのかもしれないが。難しいなぁ。(H14.10.13)  要害山城のおかげで足がヘロヘロになっていたが、ここは外せない。まずは天守台を見学し、鉄門、稲荷櫓は中を見学することができた。前に来た時にはどちらも復元される前だったと思う。どちらも木造で、非常に好感が持てる復元をしていて素晴らしいと感じた。そしてこの城の最大の見どころは石垣だろう。広範囲にわたって状態よく保存されていて、相当長時間周りをうろうろしてしまった。一つ難点を言うと、復元された鉄門のすぐ近くに、慰霊塔が建っている。慰霊塔を否定するわけではないのだが、城の景観としては邪魔だと思う。これ、何とかならないものなのだろうか…(R3.11.3) 要害山城のおかげで足がヘロヘロになっていたが、ここは外せない。まずは天守台を見学し、鉄門、稲荷櫓は中を見学することができた。前に来た時にはどちらも復元される前だったと思う。どちらも木造で、非常に好感が持てる復元をしていて素晴らしいと感じた。そしてこの城の最大の見どころは石垣だろう。広範囲にわたって状態よく保存されていて、相当長時間周りをうろうろしてしまった。一つ難点を言うと、復元された鉄門のすぐ近くに、慰霊塔が建っている。慰霊塔を否定するわけではないのだが、城の景観としては邪魔だと思う。これ、何とかならないものなのだろうか…(R3.11.3) |
| 躑躅ケ崎館(C) 日本百名城:24 |
 言わずと知れた武田信虎・信玄・勝頼三代の居館。詰めの城として要害山城を設ける。 言わずと知れた武田信虎・信玄・勝頼三代の居館。詰めの城として要害山城を設ける。 武田神社として完全に観光地化している。入口のところの石垣の綺麗なこと。戦国時代の城跡で、あの石垣はひどいなぁ。やはり綺麗な石垣がないと、観光客は城とは思えないのかなぁ?でも西の丸には馬出しの一方が割と残っていて、見ごたえがあった。もちろん我々以外誰も見に来ていなかったが・・・(H14.10.13) 武田神社として完全に観光地化している。入口のところの石垣の綺麗なこと。戦国時代の城跡で、あの石垣はひどいなぁ。やはり綺麗な石垣がないと、観光客は城とは思えないのかなぁ?でも西の丸には馬出しの一方が割と残っていて、見ごたえがあった。もちろん我々以外誰も見に来ていなかったが・・・(H14.10.13) 朝一でやってきたら、結構人がいっぱいいて、出店まで出ている。どうしたんだろうなぁ?と思いながら、とりあえず武田神社に参拝。そして西曲輪へ。北に進むと、きれいな桝形虎口があって、その先に土橋がある。戻って南に進むと、北ほどではないが、やはり桝形虎口があって、先には広い水堀。中世の城跡でここまでの遺構が見学できるのは貴重だと思う。ちなみに、帰り道で気づいたのだが、武田信玄は1521年11月3日生まれらしい。そう、今日が500回目の誕生日。それで何かイベントがあって人が多かったのだろうか・・・(R3.11.3) 朝一でやってきたら、結構人がいっぱいいて、出店まで出ている。どうしたんだろうなぁ?と思いながら、とりあえず武田神社に参拝。そして西曲輪へ。北に進むと、きれいな桝形虎口があって、その先に土橋がある。戻って南に進むと、北ほどではないが、やはり桝形虎口があって、先には広い水堀。中世の城跡でここまでの遺構が見学できるのは貴重だと思う。ちなみに、帰り道で気づいたのだが、武田信玄は1521年11月3日生まれらしい。そう、今日が500回目の誕生日。それで何かイベントがあって人が多かったのだろうか・・・(R3.11.3) |
| 要害山城(C) 続日本100名城:128 |
  せっかく躑躅ケ崎に来たのだからととりあえず向かう。途中まで車で行き、そこから山道を登るも、かなり遠そうなので途中で引き返すことに。車の所に嫁さんと娘を待たせていたのだ。少し残念ではあったが、やはり子供ができると山城攻めは辛い。(H14.10.13) せっかく躑躅ケ崎に来たのだからととりあえず向かう。途中まで車で行き、そこから山道を登るも、かなり遠そうなので途中で引き返すことに。車の所に嫁さんと娘を待たせていたのだ。少し残念ではあったが、やはり子供ができると山城攻めは辛い。(H14.10.13) ついにリベンジ。途中まで車で行けるので、さほどではないかと高を括って行ったのだが、とんでもなかった。ここ最近では八王子城が近いが、5割増しできつかった印象。延々山を登っていくと、途中から石垣、門の跡、曲輪跡が現れてくる。そこからはテーマパークのようで、門を通るたびに大きな曲輪が現れ、が繰り返されて足の疲れは忘れられる。結局、本丸に行きつくまでに門の跡を4回通ることになる。中世の山城でここまでしっかりと縄張りを感じられる城は珍しいと思う。結論、非常に楽しかったが、かなりの登山になるので、覚悟を持っていくべき城だと思う。(R3.11.3) ついにリベンジ。途中まで車で行けるので、さほどではないかと高を括って行ったのだが、とんでもなかった。ここ最近では八王子城が近いが、5割増しできつかった印象。延々山を登っていくと、途中から石垣、門の跡、曲輪跡が現れてくる。そこからはテーマパークのようで、門を通るたびに大きな曲輪が現れ、が繰り返されて足の疲れは忘れられる。結局、本丸に行きつくまでに門の跡を4回通ることになる。中世の山城でここまでしっかりと縄張りを感じられる城は珍しいと思う。結論、非常に楽しかったが、かなりの登山になるので、覚悟を持っていくべき城だと思う。(R3.11.3) |
| 新府城(C) 続日本100名城:127 |
1581年、武田勝頼が領国防衛のため、新たに本拠地として築いた城。1582年には信長の侵攻を受けて落城した。 要害山城で足がヘロヘロになっていたところでやってきた。駐車場に車を停めて向かったところ、新府藤武神社の長ーい石段が・・・。心が折れそうになりながら、登り切ったら、そこが本丸跡だった。お参りを済ませたら、奥の道を下りながら城見物。途中、二の丸には入ることができたが、三の丸は木と草がボウボウで良く分からない。これで終わりかなぁ?と思いながら歩いていると、右手にきれいに整備された大手の虎口と馬出しが。躑躅ケ崎館にあった虎口の二倍くらいあって、見応えがあった。これだけでも来る価値があると思う。しかしこれだけの城が数か月しか使われなかったとは・・・(R3.11.3) 要害山城で足がヘロヘロになっていたところでやってきた。駐車場に車を停めて向かったところ、新府藤武神社の長ーい石段が・・・。心が折れそうになりながら、登り切ったら、そこが本丸跡だった。お参りを済ませたら、奥の道を下りながら城見物。途中、二の丸には入ることができたが、三の丸は木と草がボウボウで良く分からない。これで終わりかなぁ?と思いながら歩いていると、右手にきれいに整備された大手の虎口と馬出しが。躑躅ケ崎館にあった虎口の二倍くらいあって、見応えがあった。これだけでも来る価値があると思う。しかしこれだけの城が数か月しか使われなかったとは・・・(R3.11.3) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 駿府城 日本百名城:41 |
 1585年、家康は浜松に次ぐ居城として築城に着手、4年後に完成するも翌年関東へ移った。その後中村一氏、内藤信成が入城、1607年からは家康の隠居城として諸大名の助役普請により改修に着手、名古屋城と共に東海道における最大規模の拠点となり、五重の天守があがった。1616年、家康は城内にて没し、城主頼宣は和歌山城に移り、以後は城代がおかれた。 1585年、家康は浜松に次ぐ居城として築城に着手、4年後に完成するも翌年関東へ移った。その後中村一氏、内藤信成が入城、1607年からは家康の隠居城として諸大名の助役普請により改修に着手、名古屋城と共に東海道における最大規模の拠点となり、五重の天守があがった。1616年、家康は城内にて没し、城主頼宣は和歌山城に移り、以後は城代がおかれた。*駿府城公園  ちょっと時間が出来たので静岡駅で降りてちょこっと見てきた。なんと電車を降りてから再び乗るまでにほぼ1時間。それくらいで見てこれる城。どうも第二次世界大戦中に陸軍の基地になったらしく、内堀はほとんど埋められてしまって、その一部が掘り返されていた。それ以外は櫓が一つ復元されているだけで、あとは広場になっている。野球場もあり、歴史公園としてはなかなかいい利用法ではないかと思う。本丸跡には家康の像が立っている。(H8.9.29) ちょっと時間が出来たので静岡駅で降りてちょこっと見てきた。なんと電車を降りてから再び乗るまでにほぼ1時間。それくらいで見てこれる城。どうも第二次世界大戦中に陸軍の基地になったらしく、内堀はほとんど埋められてしまって、その一部が掘り返されていた。それ以外は櫓が一つ復元されているだけで、あとは広場になっている。野球場もあり、歴史公園としてはなかなかいい利用法ではないかと思う。本丸跡には家康の像が立っている。(H8.9.29) 静岡駅から歩いて城に向かうが、駿府城は静岡県の県庁と静岡市の市役所のすぐそばに位置していて、城下町の雰囲気はほぼない。あまりにも都会。橋を渡って、東御門を入ると、桝形で何やら急に劇が始まった。どうもストリートシアターフェスというのを駿府城を含む静岡市内でやっているらしく、それを見に来ている人も多くいたようだ。中に入ると入場券売り場があり、どうも東御門の多聞櫓と巽櫓に入れるらしい。つい先日姫路城に行って百閒廊下を見てきたため、若干物足りなく感じてしまったが、それは比較する方が無理というもの。伝統的な木造工法で復元した、ということを評価すべきだろう。 静岡駅から歩いて城に向かうが、駿府城は静岡県の県庁と静岡市の市役所のすぐそばに位置していて、城下町の雰囲気はほぼない。あまりにも都会。橋を渡って、東御門を入ると、桝形で何やら急に劇が始まった。どうもストリートシアターフェスというのを駿府城を含む静岡市内でやっているらしく、それを見に来ている人も多くいたようだ。中に入ると入場券売り場があり、どうも東御門の多聞櫓と巽櫓に入れるらしい。つい先日姫路城に行って百閒廊下を見てきたため、若干物足りなく感じてしまったが、それは比較する方が無理というもの。伝統的な木造工法で復元した、ということを評価すべきだろう。さて、二の丸から本丸へ向かう。といっても内堀はほとんど埋められているためどこから本丸かは良く分からないのだが、とにかく奥に向かう。すると、天守台があったところが発掘調査現場を見学することができる。とにかく広大な敷地に今川家屋敷跡の遺構、天正期の石垣、慶長期の石垣と時代の異なる遺構を見ることができ、家康が天下普請で造ったという慶長期の天守台は日本最大規模なのだという。そこに見えている石垣はほんの一部であり、その上にその何倍もの石垣があったはずで、その上に巨大な天守が建っていたはずである。発掘調査現場を観光地にしているのはほとんどないと思う。私は初めてだったが、スゴイいいと思う。過去の姿を妄想できる人にはたまらないのではないかと思う。(R6.5.4) |
| 山中城(C) 日本百名城:40 |
 1560年台に、小田原に本拠を置いた北条氏が築城。秀吉との合戦が避けられなくなった北条氏は、1589年、急遽堀や出丸を整備し、城全体の強化を開始。しかし、1590年3月29日、増築が未完成のまま豊臣軍4万の総攻撃を受け、北条軍4千はなす術なく、わずか半日で落城したと伝わる。 1560年台に、小田原に本拠を置いた北条氏が築城。秀吉との合戦が避けられなくなった北条氏は、1589年、急遽堀や出丸を整備し、城全体の強化を開始。しかし、1590年3月29日、増築が未完成のまま豊臣軍4万の総攻撃を受け、北条軍4千はなす術なく、わずか半日で落城したと伝わる。昭和48年から行った発掘調査と復元整備は、戦国時代の山城としては先駆的な整備事例で、現在は400年前の遺構がそのまま復元されて公園として整備されている。堀や土塁が良く残っており、尾根を区切る曲輪の造成法、土橋・木橋の配置、など箱根山の自然の地形を巧みに取り入れた山城の様子がよく分かる。1934年に国の史跡に指定。 *三島市  令和元年の3日目、GW真っ只中に訪れた。到着した時には駐車場が一杯で停めるところがなく、出る車を待ったくらいで、なかなかの混み具合だった。それもそのはず、登り始めてまず思ったのは非常にきれいに整備されていること。言葉を飾らずに言うと「きれい過ぎる」印象。歩道が歩きやすく整備されているのはいいとして、土塁空堀との間の仕切りとして植物が植えられ、その向こうにある堀はまっすぐ平坦に整備されている。二ノ丸、西ノ丸の堀切にはつつじなどが植えられている。 令和元年の3日目、GW真っ只中に訪れた。到着した時には駐車場が一杯で停めるところがなく、出る車を待ったくらいで、なかなかの混み具合だった。それもそのはず、登り始めてまず思ったのは非常にきれいに整備されていること。言葉を飾らずに言うと「きれい過ぎる」印象。歩道が歩きやすく整備されているのはいいとして、土塁空堀との間の仕切りとして植物が植えられ、その向こうにある堀はまっすぐ平坦に整備されている。二ノ丸、西ノ丸の堀切にはつつじなどが植えられている。「堀がまっすぐ平坦に整備されている」のは、在りし日の状態を再現したという意味では望ましいのかもしれないが、何が残っていて何が手を加えたのか分からない。これは我ながら高望みし過ぎだと思う。想像で作ったりしていないことは信じるしかない。 「歩道と堀の間に植物が植えられている」のは、不要だと思う。もちろん鉄製の柵などを作られるよりはよっぽどいいが、実際にはあるはずのないものであり、動物園じゃないのだから、柵を作る必要はないのではないか。 「堀切につつじなどが植えられている」のも、不要だと思う。攻められた時に登りづらくするためものなのに、その斜面に植物が植えられていたら、登る時の助けになってしまう。当たり前だが実際にあったわけではない。 とは書いてきたが、まとめると「非常にいい城跡公園」だと思う。堀が整備され過ぎているのは、一方、放置されたら保存されないリスクがあるものであり、整備されるに越したことはない。歩道や堀に植物が植えられているのも、公園として必要なものに絞られていて、むしろ好感が持てるレベルになっている。とても歩きやすい城跡だったし、堀に花が咲き乱れていて非常にきれいであり、富士山がその向こうに見えて、その景色は感動的なほどだった。我ながら真逆のことを言っているが、両方とも本心である。 さて、城跡としてだが、戦国時代の山城が、ここまで大規模に、また十分に在りし日を想像できる状態で残っているのは非常に素晴らしいと思う。北条氏の城の特徴である「障子堀・畝堀」が非常によく分かり、また途中まで土橋で途中から木橋になっているところなど、見所は限りなくある。さらにこの日は非常に良く晴れていて、富士山がきれいに見えた。これが借景になってさらにこの城を引き立てていた。まとまらなくなってきたが、とにかく是非とも訪問してほしい城であることは間違いない。(R1.5.3) |
| 興国寺城(C) 続日本百名城:145 |
1487年、今川氏の客将であった北条早雲が、今川家の家督争いを収めた功績により与えられた城。その後、韮山の堀越公方を攻めて伊豆に進出した。北条氏の勢力が確定した後は、今川・武田・北条による争奪戦が繰り返され、武田氏滅亡後は徳川の城となったが、1607年に廃城となった。 本丸と北曲輪の間には幅20メートル以上もある尾根を分断する大空堀が残る。天守台からは原の市街と駿河湾の景色を楽しむことができる。 *沼津市  400年以上前に廃城になった城が、また住宅地の中にある城で、ここまで遺構が保存されているのは素晴らしい。特に大空堀、ここが住宅地の中だということを忘れるくらいである。沼津市では将来的に史跡公園としての活用を検討しているそうだが、この良く残る遺構を活かした整備を期待したい。(R1.5.3) 400年以上前に廃城になった城が、また住宅地の中にある城で、ここまで遺構が保存されているのは素晴らしい。特に大空堀、ここが住宅地の中だということを忘れるくらいである。沼津市では将来的に史跡公園としての活用を検討しているそうだが、この良く残る遺構を活かした整備を期待したい。(R1.5.3) |
| 足柄城(C) | 小田原合戦の際に北条氏忠が入り、惨敗した城。山中城と共に関八州の出入り口を固めた重要な城。 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 掛川城 日本百名城:42 |
 〈油山寺山門,御殿〉 〈油山寺山門,御殿〉戦国期には朝比奈氏があり、1590年に山内一豊が入城、改修に着手した。三層の天守をあげ、三重の塁濠を巡らしたが、関ヶ原合戦後に松井氏が入り、定綱の代に天守が再築された。現在全国でも珍しい二の丸御殿と太鼓櫓が現存する。 *掛川城公式  見た瞬間「高知城に似ている」というのが感想だった。やはり縄張りをした人の好みというのはきっちり出るらしい。かつ、山内一豊という人の感性は俺の感性と非常に近いらしい。本丸、二の丸、三の丸という配置も、天守の作りも、何とも俺好みなのである。さらに本丸後には三の丸から移築されたらしい太鼓櫓が現存し、御殿建築まで存在するのである。まずは天守閣だが、復元とはかくあるべきと思えるもので、完全に木での復元であった。展示物はほとんどなく、従業員も気さくな人たちで、彼らの掃除のおかげでいつも奇麗な状態らしかった。城自体を展示しているという意識の現われではないだろうか。本当にかくあるべきである。屋上では従業員のおじさんが古城の場所や大手門の場所などを教えてくれた。さて、天守台の階段を降りると多聞櫓があるのだが、そこには入れてもらえない。ちょっと残念ではあるが、櫓を後方に眺めつつ二の丸御殿へ。明治になりかけの頃に出来たとはいえ、造りは本当に重厚で城主の部屋をはじめ、政務を執った部屋、奥向きの部屋、さらに城主とは直接関係のない財務や警備、目付の部屋などもあり、まさに役所として機能していた事をうかがわせた。全体としては全く素晴らしいというしかない。是非行って頂きたい。(H9.9.1) 見た瞬間「高知城に似ている」というのが感想だった。やはり縄張りをした人の好みというのはきっちり出るらしい。かつ、山内一豊という人の感性は俺の感性と非常に近いらしい。本丸、二の丸、三の丸という配置も、天守の作りも、何とも俺好みなのである。さらに本丸後には三の丸から移築されたらしい太鼓櫓が現存し、御殿建築まで存在するのである。まずは天守閣だが、復元とはかくあるべきと思えるもので、完全に木での復元であった。展示物はほとんどなく、従業員も気さくな人たちで、彼らの掃除のおかげでいつも奇麗な状態らしかった。城自体を展示しているという意識の現われではないだろうか。本当にかくあるべきである。屋上では従業員のおじさんが古城の場所や大手門の場所などを教えてくれた。さて、天守台の階段を降りると多聞櫓があるのだが、そこには入れてもらえない。ちょっと残念ではあるが、櫓を後方に眺めつつ二の丸御殿へ。明治になりかけの頃に出来たとはいえ、造りは本当に重厚で城主の部屋をはじめ、政務を執った部屋、奥向きの部屋、さらに城主とは直接関係のない財務や警備、目付の部屋などもあり、まさに役所として機能していた事をうかがわせた。全体としては全く素晴らしいというしかない。是非行って頂きたい。(H9.9.1) 掛川駅を降りて、城に向かって歩いていると、城下町っぽい雰囲気があって、いい街だなぁと思っていたが、なかなか城が見えてこない。橋を渡ると、左手に寺のような門があって、「←掛川城」と書いてある。門を入ると丘の上に天守が見える。とりあえずチケットを買って天守に向かう。明らかに手が入った階段と塀が続く。塀には狭間があるのだが、覗くとすぐ向こうの塀が見える。どこを狙うための狭間?天守は木で復元されていて好感が持てるのは事実だが、恐らく重みに耐えられなかったのであろう、屋根の柱の一部にヒビが入っていて、それを補強するために鉄で固めている。本当に当時の設計図と工法で建てたのであろうか・・・。最上階の壁は襖になっていて、窓は襖を開けた状態・・・これホント?27年前に行った感想とはほとんど真逆だが、あまりいい印象は受けなかった。もちろん、コンクリートで作った天守よりは明らかにこちらの方がいいし、否定するものでは全くないのだが、正直もやもやした気持ちになった。それに対し、二の丸御殿は素晴らしかった。現存している遺構はやはり重みが違う。こちらの感想は27年前と全く同じなのだが、なんだろう、全体として正直いまいちだったと言わざるを得ない。曲輪が十分に残っていないというのもあるのかもしれない。やはり大手門から入って、三の丸、二の丸、本丸とあって、天守があるとテンションが上がってくるのだが・・・ないものねだりか。(R6.5.4) 掛川駅を降りて、城に向かって歩いていると、城下町っぽい雰囲気があって、いい街だなぁと思っていたが、なかなか城が見えてこない。橋を渡ると、左手に寺のような門があって、「←掛川城」と書いてある。門を入ると丘の上に天守が見える。とりあえずチケットを買って天守に向かう。明らかに手が入った階段と塀が続く。塀には狭間があるのだが、覗くとすぐ向こうの塀が見える。どこを狙うための狭間?天守は木で復元されていて好感が持てるのは事実だが、恐らく重みに耐えられなかったのであろう、屋根の柱の一部にヒビが入っていて、それを補強するために鉄で固めている。本当に当時の設計図と工法で建てたのであろうか・・・。最上階の壁は襖になっていて、窓は襖を開けた状態・・・これホント?27年前に行った感想とはほとんど真逆だが、あまりいい印象は受けなかった。もちろん、コンクリートで作った天守よりは明らかにこちらの方がいいし、否定するものでは全くないのだが、正直もやもやした気持ちになった。それに対し、二の丸御殿は素晴らしかった。現存している遺構はやはり重みが違う。こちらの感想は27年前と全く同じなのだが、なんだろう、全体として正直いまいちだったと言わざるを得ない。曲輪が十分に残っていないというのもあるのかもしれない。やはり大手門から入って、三の丸、二の丸、本丸とあって、天守があるとテンションが上がってくるのだが・・・ないものねだりか。(R6.5.4) |
| 浜松城 | 1570年に徳川家康が新居として建築に着手、1581年頃に一応の完成を見た。家康は1586年頃まで在城し、駿府に移った。城主は西尾氏を経て、譜代大名が入った。 *浜松市 *浜松城公園  思ったよりも小さな城だった。石垣が見えたと思ったらその石垣で出来た小さな本丸があって、その上にはもう天守閣があるというそれだけの城だった。非常にメジャーな城なのでもう少し大きなものを期待していたので余計に小さく思えたのだろうが、天守閣も石垣も立派だったのは間違いない。天守閣内部には家康ファンにはたまらないであろうものでいっぱいだった。屋上はやはりいまいちではあったが。(H9.8.1) 思ったよりも小さな城だった。石垣が見えたと思ったらその石垣で出来た小さな本丸があって、その上にはもう天守閣があるというそれだけの城だった。非常にメジャーな城なのでもう少し大きなものを期待していたので余計に小さく思えたのだろうが、天守閣も石垣も立派だったのは間違いない。天守閣内部には家康ファンにはたまらないであろうものでいっぱいだった。屋上はやはりいまいちではあったが。(H9.8.1) |
| 二俣城(C) | *日本の城(中部地方)のページ |
| 高天神城(C) | *大東市のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 岡崎城 日本百名城:45 |
 1455年に守護代西郷氏によって築城され、1524年松平清康が入城し、1542年の誕生以来28年間家康が居城とした城である。田中吉政と本多氏の時代に近世城郭として整備されたと考えられ、1617年に複合連結式で完成している。昭和34年には復興天守が建てられた。
1455年に守護代西郷氏によって築城され、1524年松平清康が入城し、1542年の誕生以来28年間家康が居城とした城である。田中吉政と本多氏の時代に近世城郭として整備されたと考えられ、1617年に複合連結式で完成している。昭和34年には復興天守が建てられた。*畑さんのページ *岡崎City情報のページ *IBMホームタウン・ホームページ  従兄弟や両親の両親と一緒に行った旅行で訪れる。広大な敷地は岡崎公園となり、藤棚には花があふれていた。桜もたくさんあり、花見シーズンには人があふれていることだろう。天守などはあまり印象に無いが、石垣が多く残り、在りし日を偲ばせる。この旅行では関ヶ原合戦場跡にも行ったが、別に大した物ではなかった。(H5.5.4) 従兄弟や両親の両親と一緒に行った旅行で訪れる。広大な敷地は岡崎公園となり、藤棚には花があふれていた。桜もたくさんあり、花見シーズンには人があふれていることだろう。天守などはあまり印象に無いが、石垣が多く残り、在りし日を偲ばせる。この旅行では関ヶ原合戦場跡にも行ったが、別に大した物ではなかった。(H5.5.4)岡崎公園自体は非常に広く、その周りを川が流れていてそれが外堀なのは間違いなく、城郭自体も相当な規模だったのは容易に想像できるのだが、いかんせん曲輪が全く分からなくなってしまっているのが辛い。天守閣のある曲輪も神社やら何やら城と関係あるのかないのかわからないような建物に囲まれているため、本丸すらどこまでなのか判断しづらい。天守閣自体も確かに旧観に復元しているのだろうが、どちらかというと資料館としての位置づけの方が強そうな感じであった。で、肝心の展示物であるが、これは徳川三河武士の館というのが別にあり、それと合わせてそれなりに興味深い資料がそろっている。特に三河武士の館の方は周辺の小さな古城を紹介するコーナーがあったり、ビジュアル的に関ヶ原合戦を再現するコーナーがあったり、十分に楽しめるものになっていた。(H9.8.1) |
| 吉田城 |  1505年に牧野古白により築かれ、桶狭間合戦後は家康の持ち城となった。1590年に入城した池田輝政が15万石の太守にふさわしい改修をということで石垣を用いた近世城郭となった。関ヶ原合戦後城主はめまぐるしく変わり、松平忠利の代に名古屋城築城の残石をもってさらに改修が加えられた。だが天守は築かれず、三重の鉄櫓が代用された。
1505年に牧野古白により築かれ、桶狭間合戦後は家康の持ち城となった。1590年に入城した池田輝政が15万石の太守にふさわしい改修をということで石垣を用いた近世城郭となった。関ヶ原合戦後城主はめまぐるしく変わり、松平忠利の代に名古屋城築城の残石をもってさらに改修が加えられた。だが天守は築かれず、三重の鉄櫓が代用された。*どんどんタウンのページ *日本の城(中部地方)のページ  立派な石垣で囲まれた本丸があり、一角に櫓が現存している。ただ、その櫓には入れるわけでもなく、ちょっと物足りない印象を受けた。櫓のすぐ下には川が流れており、そちらの対岸から見るとまた違った風に見えるのかもしれない。城跡は広大な公園になっており、芝生が敷き詰められていて公園としては申し分ないものであろう。(H9.8.1) 立派な石垣で囲まれた本丸があり、一角に櫓が現存している。ただ、その櫓には入れるわけでもなく、ちょっと物足りない印象を受けた。櫓のすぐ下には川が流れており、そちらの対岸から見るとまた違った風に見えるのかもしれない。城跡は広大な公園になっており、芝生が敷き詰められていて公園としては申し分ないものであろう。(H9.8.1) |
| 長篠城(D) 日本百名城:46 |
 おそらく誰もが知っている長篠合戦で有名な城。1575年5月、武田勝頼軍15,000に包囲され、徳川方奥平貞昌軍500は10日間を持ちこたえた。信長・家康連合軍約40,000が到着して、かの有名な長篠合戦が行われる。 おそらく誰もが知っている長篠合戦で有名な城。1575年5月、武田勝頼軍15,000に包囲され、徳川方奥平貞昌軍500は10日間を持ちこたえた。信長・家康連合軍約40,000が到着して、かの有名な長篠合戦が行われる。城は1508年に菅沼氏が今川の武将として築いたのが始まりとされる。今川義元死後、菅沼氏は徳川に属したが、武田氏に攻められて一旦降参するが、信玄死後、家康が城を奪回し、奥平氏を城主に任命、その年に長篠合戦が行われた。翌年には新城城に本拠を移した。 *日本の城(中部地方)のページ  1時間に一本しかないJR飯田線で、豊橋駅から約1時間、田園風景を眺めながら電車に揺られ、長篠城駅に到着。電車の中で運賃を支払うバスのような仕組みに面くらいつつ、無人駅に降り立つ。駅の眼の前には武田勝頼が敗走中に立ち寄った農家でのエピソードが書かれた看板があり、期待に胸を膨らませながら城跡に向かう。同じ電車を降りた数人はやはり同じ方向に向かっている。同じような趣味趣向の方たちなのだろうか。 1時間に一本しかないJR飯田線で、豊橋駅から約1時間、田園風景を眺めながら電車に揺られ、長篠城駅に到着。電車の中で運賃を支払うバスのような仕組みに面くらいつつ、無人駅に降り立つ。駅の眼の前には武田勝頼が敗走中に立ち寄った農家でのエピソードが書かれた看板があり、期待に胸を膨らませながら城跡に向かう。同じ電車を降りた数人はやはり同じ方向に向かっている。同じような趣味趣向の方たちなのだろうか。10分ほどすると史跡保存館の建物と小高い丘が見えてきた。まずは城跡に向かう。長篠城は豊川と宇連川が合流する地点にあり、まさに南側を天然の川を堀とした作りになっている。長篠合戦時には、長篠城は徳川方で、武田方は北側にいる訳で、堀とは逆側を強化しないといけなかったはず。もちろん一部ではあるが、土塁と空堀が良く残っており、その強化策の一端を見ることができる。本丸も非常に広くよく整備されていて、南の端には、長篠合戦時、向こう側のどの山に誰が陣取っていたかの解説が書かれている。武田の大軍に囲まれて、どんなに大変だったろうと思うが、その感覚を僅かでも追想することができる、いい城跡であった。一点、残念なのは、本丸と川の間に野牛郭跡があるのだが、本丸と野牛郭の境をJR飯田線の線路に横切られていること。ないものねだりをしても仕方ないし、雰囲気は十分に味わえるのだが、残念は残念である。 帰りに長篠城址史跡保存館に立ち寄った。江戸期の櫓のような建物に長篠合戦関連の資料展示がなされているが、正直さほどの見るべきものは見当たらなかった。また、戦国期の城跡に、江戸期風の建物を建てるのはやめてほしいものではある。 もし叶うものなら、今度はゆっくりと周りの山々を陣跡巡りハイキングなど、してみたいと本気で思った、そんな城跡であった。(H29.12.2) |
| 新城城 | 長篠の合戦後、奥平氏が長篠城から本拠を移した城。現在は新城中学校になっている。 *新城市 |
| 設楽城 鎌倉 山城 |
*愛知県 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 名古屋城 近世 平城 日本百名城:44 |
 〈東南隅櫓,西北隅櫓,西南隅櫓,表二の門,二の丸大手二の門,旧二の丸東二の門〉 〈東南隅櫓,西北隅櫓,西南隅櫓,表二の門,二の丸大手二の門,旧二の丸東二の門〉1610年に、家康の四子松平忠吉の跡を継ぎ、清洲城主となった九子義直の居城という名目で家康が着工。実は豊臣方の拠点である大阪の押えとして急造された城である。大坂の陣ではその役割を果たし、工事中であった外郭・惣構えは戦後中止され、未完成のままである。現存する西北隅櫓は清洲城小天守を移築したもので清洲櫓とも呼ばれる。 *公式ページ *愛知県の城と今月の名古屋城  完全復元というだけあって本丸と二の丸はほぼ旧態を見ているような気分にさせてくれる。多聞櫓と本丸御殿、大手門があればもう完璧。本丸御殿は天守閣内部の展示で20分の1の模型があったがまさに圧巻。実物を非常に見たくなった。天守閣内部といえば、これまで行った城の中で名古屋城がもっとも充実していたと思われる。先述した本丸御殿の模型のほか、井戸、金の鯱の模型、空襲の直前に乃木将軍が避難させたために残ったという本丸御殿の天井絵や襖絵、などなど、どれも一見の価値あるものばかり。2、3、4階は改装中で見ることができなかったにもかかわらず非常に満足できるものだった。ただ唯一の問題は屋上展望台。単なるたくさん窓のついた部屋。あんなのは城ではない。 完全復元というだけあって本丸と二の丸はほぼ旧態を見ているような気分にさせてくれる。多聞櫓と本丸御殿、大手門があればもう完璧。本丸御殿は天守閣内部の展示で20分の1の模型があったがまさに圧巻。実物を非常に見たくなった。天守閣内部といえば、これまで行った城の中で名古屋城がもっとも充実していたと思われる。先述した本丸御殿の模型のほか、井戸、金の鯱の模型、空襲の直前に乃木将軍が避難させたために残ったという本丸御殿の天井絵や襖絵、などなど、どれも一見の価値あるものばかり。2、3、4階は改装中で見ることができなかったにもかかわらず非常に満足できるものだった。ただ唯一の問題は屋上展望台。単なるたくさん窓のついた部屋。あんなのは城ではない。あと、有名な清正石や家紋の入った石垣も確かにすごい。当時の徳川家がいかに強い勢力を誇っていたかということがよく分かる。あれだけ多くの大名が一も二もなく普請を手伝うのでは豊臣も勝てないわけだ。それから、現存する3つの櫓はどれも中に入れてもらえない。一度見てみたいものである。(H9.1.31)   友達と名古屋方面に城巡りに来て、再度訪れた。前回来た時には入れなかった2,3,4階は改装工事が終わっていたため見る事が出来たが、全く大した物ではない。唯一すごいと思ったのは本丸御殿内部をCGで再現していたところであろうか。しかし本当に規模のでかい城である。それだけは再認識させられてしまった。(H9.9.2) 友達と名古屋方面に城巡りに来て、再度訪れた。前回来た時には入れなかった2,3,4階は改装工事が終わっていたため見る事が出来たが、全く大した物ではない。唯一すごいと思ったのは本丸御殿内部をCGで再現していたところであろうか。しかし本当に規模のでかい城である。それだけは再認識させられてしまった。(H9.9.2)
 本丸御殿が復元されたと聞いていたのだがなかなか来れていなかったので、やってきた。何度来てみてもいい城である。これだけの城跡が広範囲に良く保存されているのは本当に素晴らしい。 本丸御殿が復元されたと聞いていたのだがなかなか来れていなかったので、やってきた。何度来てみてもいい城である。これだけの城跡が広範囲に良く保存されているのは本当に素晴らしい。まずは今回の趣旨である本丸御殿に向かう。表二之門を抜けると、手前に御殿、その向こうに天守、という景色が現れる。感動である。本丸御殿建築は現存しているのは高知城、二条城、川越城あたりだが、高知城は規模が小さく、二条城は二ノ丸だし、川越城はその他の遺構がほとんどない。政令指定都市中心部にある大規模な城で本丸御殿建築を城郭の一部として見れるのはここだけだと思う。中に入ると、総檜造りの書院造の建物が精巧に復元されていて、部屋ごとに異なるテーマで描かれた床の間絵や襖絵は正確に復元されているそうで、まさに圧巻。引手金具や釘隠、天井も部屋ごとに正確に復元されているそうで、見るところは限りなくある。何といっても檜のいい匂いが充満し、1615年に建てられた当初はまさにこのような状態だったのではないかと思いながら、鑑賞できた。今のところ第二期工事まで終わっていて、来年には第三期工事が終わって、完成するそうなので、また是非再訪したいと思った。 折角来たのだからと天守にも登ってみたが、正直来なきゃよかったという感じだった。展示物はそれなりに充実してはいたが、やっぱりコンクリート天守の悲しさで、単なる展示館。さっきの御殿に比べて人の数が多かったが、やはり城といえば天守という意識が強いのだろう。天守を見たいなら少し足を延ばして犬山に行ってもらいたい。本当に。ただ、感動したのは、木造復元計画があること。5年後の完成を目指しているということだったので、大いに期待したいところである。(H29.12.2) |
| 犬山城 戦国 平山城 日本百名城:43 |
 《天守》 《天守》幻の現存最古の天守建築遺構であり、日本で唯一の個人所有の城である。天守建築時期は諸説あるが、下部は1537年に築城された金山城の天守閣を移築したもので、上部は江戸時代になってから増築されたというのが通説となっているが、まだはっきりとしてはいない。本丸を最北におき、眼下に木曽川が流れる典型的な「後堅固の城」である。 *犬山市のページ *犬山市観光情報のページ *日本の城(中部地方)のページ *犬山市マルチメディア協議会のページ *イサイズ「じゃらん」  全く期待通りの城であった。木曽川縁からみる犬山城は格別のものがある。内部はまさに理想的で、心地よい木の匂いと必要最小限の展示物。唐破風や千鳥破風の部分の小部屋や、急な階段、頭を打ちそうな柱など、現代的でない部分が時代を感じさせ、本当に興味深かった。他にも、第二層目だったかにある武具庫は素晴らしかった。周りに武者走があって真ん中が武具庫になっているのだが、武具を置く棚などもあり、昔の様子を偲ぶにはもってこいであった。屋上からは優美な木曽川の流れが一望でき、まさに殿様気分。ただ一つだけ気になったのは屋上だけどうして赤い絨毯を敷いているのかという事である。これは意味がなく、やめるべきではないかと感じだ。ただ、全体として本当に素晴らしく、日本が誇ることのできる数少ない城郭の一つであるのは間違いない。(H9.8.31) 全く期待通りの城であった。木曽川縁からみる犬山城は格別のものがある。内部はまさに理想的で、心地よい木の匂いと必要最小限の展示物。唐破風や千鳥破風の部分の小部屋や、急な階段、頭を打ちそうな柱など、現代的でない部分が時代を感じさせ、本当に興味深かった。他にも、第二層目だったかにある武具庫は素晴らしかった。周りに武者走があって真ん中が武具庫になっているのだが、武具を置く棚などもあり、昔の様子を偲ぶにはもってこいであった。屋上からは優美な木曽川の流れが一望でき、まさに殿様気分。ただ一つだけ気になったのは屋上だけどうして赤い絨毯を敷いているのかという事である。これは意味がなく、やめるべきではないかと感じだ。ただ、全体として本当に素晴らしく、日本が誇ることのできる数少ない城郭の一つであるのは間違いない。(H9.8.31) |
| 清洲城 戦国 平城 |
 守護代・守護織田家の本拠地。1582年に信長が本能寺に倒れて後、織田信雄が城主となり、大小天守を持つ近世城郭に改修された。しかし名古屋城の築城が始まると石垣は転用され、天守を初め主要な建物は名古屋に移された。 守護代・守護織田家の本拠地。1582年に信長が本能寺に倒れて後、織田信雄が城主となり、大小天守を持つ近世城郭に改修された。しかし名古屋城の築城が始まると石垣は転用され、天守を初め主要な建物は名古屋に移された。*日本の城(中部地方)のページ *はたぼうさんの日本名城案内  行ったのが5時過ぎだったため天守閣には入れなかったが、門の中には入れた。今回この城に来た一番の目的はあの天守閣は復元(正確には復興か?)なのか、模擬なのかが知りたかったからなのだが、係の人には一人も会わなかったため、知る術はなかった。名古屋城に移築されたということになってるけど、名古屋城では清洲櫓の説明に「清洲城の木材を多く使って作られた」と書かれているだけなので、はっきりとしたことはわからない。ともかく外観は犬山や安土を彷彿とさせるかっこいい城。また、実際に清洲城があったというところにも行ってみる。清洲公園(城周辺がそういう公園になってる)内にあって、ちょうど駐車場の横になるんだが、それもどうも納得できかねるものがある。その曲輪が天守閣を建てるにはちょっと小さすぎることと、石がコンクリートか何かで固められていることである。倒壊してしまったから固め直しただけなのかもしれないが・・・。(H9.1.31) 行ったのが5時過ぎだったため天守閣には入れなかったが、門の中には入れた。今回この城に来た一番の目的はあの天守閣は復元(正確には復興か?)なのか、模擬なのかが知りたかったからなのだが、係の人には一人も会わなかったため、知る術はなかった。名古屋城に移築されたということになってるけど、名古屋城では清洲櫓の説明に「清洲城の木材を多く使って作られた」と書かれているだけなので、はっきりとしたことはわからない。ともかく外観は犬山や安土を彷彿とさせるかっこいい城。また、実際に清洲城があったというところにも行ってみる。清洲公園(城周辺がそういう公園になってる)内にあって、ちょうど駐車場の横になるんだが、それもどうも納得できかねるものがある。その曲輪が天守閣を建てるにはちょっと小さすぎることと、石がコンクリートか何かで固められていることである。倒壊してしまったから固め直しただけなのかもしれないが・・・。(H9.1.31) |
| 刈谷城(E) 戦国 平城 |
|
| 大高城(D) | |
| 小牧山城 戦国 山城(85m) |
|
| 田原城 戦国 丘城 |
|
| 岩崎城 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 桑名城(C) 近世 平城 |
鎌倉初期に桑名行綱がこの地に城塞を築いたのが初めだと言う。本格的に城郭を築いたのは1601年に10万石の大名として入封してきた本多忠勝だった。約十年をかけて櫓51,多聞46という巨大城郭を完成させた。その後松平氏が入り、最後の城主松平定貞(松平容保の弟)は戊辰戦争に際し新政府軍に反対し、函館に走ったため激しい砲撃を浴び、全焼の憂き目を見た。現在城跡は九華公園となり、堀や石垣が残っている。 *桑名市のページ *日本の城(中部地方)のページ  川に面した九華公園というのが城跡に当たるらしい。何と言ったらいいのか、ちょうど扇形をした中洲があって、その弧に平行に2本堀を掘ったような形をしていて、運河みたい。その堀がきれいで、公園としては申し分ないと思う。ただ、石垣は四日市の港を作る時に使われたらしく全く残っておらず、50基以上もあったと言う櫓も一つも残っておらず、跡地も一つだけそれらしいものが認められるだけであとはただの丘になってしまっている。ああいう城の復元も見てみたいものだ。(H9.2.1) 川に面した九華公園というのが城跡に当たるらしい。何と言ったらいいのか、ちょうど扇形をした中洲があって、その弧に平行に2本堀を掘ったような形をしていて、運河みたい。その堀がきれいで、公園としては申し分ないと思う。ただ、石垣は四日市の港を作る時に使われたらしく全く残っておらず、50基以上もあったと言う櫓も一つも残っておらず、跡地も一つだけそれらしいものが認められるだけであとはただの丘になってしまっている。ああいう城の復元も見てみたいものだ。(H9.2.1) |
| 神戸城(C・・・移築櫓・大手門あり) 近世 平城 |
 1367年亀山城主関盛政の長男盛澄が神戸を分け与えられて神戸氏を称したのが始まりとされる。1567年に信長は滝川一益に伊勢を攻略させるが思うに任せず、信長の三男信孝を神戸氏の養子にすることを条件に和解した。信孝は1580年に拡張・整備を行い、本丸・二の丸などの郭と共に、小天守を伴う五層の天守閣を建てた。関が原の合戦後、神戸は天領となり、破却。のち1732年に本田忠統が再築城するも明治維新の際に破却された。 1367年亀山城主関盛政の長男盛澄が神戸を分け与えられて神戸氏を称したのが始まりとされる。1567年に信長は滝川一益に伊勢を攻略させるが思うに任せず、信長の三男信孝を神戸氏の養子にすることを条件に和解した。信孝は1580年に拡張・整備を行い、本丸・二の丸などの郭と共に、小天守を伴う五層の天守閣を建てた。関が原の合戦後、神戸は天領となり、破却。のち1732年に本田忠統が再築城するも明治維新の際に破却された。*鈴鹿サーキットのページ  現在城跡は神戸公園となり、天守台や堀などが残る。ちなみに太鼓櫓は市内蓮花寺の鐘楼に、大手門は四日市市顕正寺の山門になっている。 現在城跡は神戸公園となり、天守台や堀などが残る。ちなみに太鼓櫓は市内蓮花寺の鐘楼に、大手門は四日市市顕正寺の山門になっている。ちょうど神戸高校が建っているところが神戸城跡地らしく、今は本丸の跡だけが学校の横にぽつんと残っている。野面積みの豪快な天守台がきれいに残っていてなかなか楽しめた。高校の逆側には神戸公園としてきれいに整備されていてそちらには少し内堀も保存され、公園側から見た天守台もなかなかのものだった。(H9.2.1) |
| 亀山城 近世 平山城 |
 多聞櫓が現存しているというので相当期待して行ったのだが、その櫓のある石垣以外は縄張りも全くと言っていいほど分からず、ちょっと拍子抜けであった。だがその石垣の高さは相当なもので、その上に現存する櫓も黒塗りの渋いもので、亀山中学校から見た景観はなかなか通好みといえるのではなかろうか。問題はその櫓の窓にアルミサッシの窓がはめ込まれている事。現存する建築物にそんな事をするのは実際許されるのか?少々疑問の残る城であった。櫓の下側には古城時代に城守として招聘された人物の家の門が残っており、また天守台もごく一部だが残っていた。正確には天守の代わりをした三重櫓の台であったらしいが、完全に公園の一部になってしまっており、面影は何ら見られなかった。ただ、その下には豊かに水を湛えた池があり、堀として機能していた事は明らか。こうした部分から在りし日の全体像を偲ぶのも古城巡りの楽しみ方の一つなのである。(H9.9.2) 多聞櫓が現存しているというので相当期待して行ったのだが、その櫓のある石垣以外は縄張りも全くと言っていいほど分からず、ちょっと拍子抜けであった。だがその石垣の高さは相当なもので、その上に現存する櫓も黒塗りの渋いもので、亀山中学校から見た景観はなかなか通好みといえるのではなかろうか。問題はその櫓の窓にアルミサッシの窓がはめ込まれている事。現存する建築物にそんな事をするのは実際許されるのか?少々疑問の残る城であった。櫓の下側には古城時代に城守として招聘された人物の家の門が残っており、また天守台もごく一部だが残っていた。正確には天守の代わりをした三重櫓の台であったらしいが、完全に公園の一部になってしまっており、面影は何ら見られなかった。ただ、その下には豊かに水を湛えた池があり、堀として機能していた事は明らか。こうした部分から在りし日の全体像を偲ぶのも古城巡りの楽しみ方の一つなのである。(H9.9.2) |
| 津城 近世 平城 |
古くは長野氏の一族が築城したとも言われるが不明。 1568年に伊勢攻略を行っていた信長は長野氏の攻略にてこずり、弟の信包を長野氏の養子にすることを条件に和睦し、信包は1580年にこの地に五層の天守閣を持つ城郭を完成させた。1608年には伊予今治から藤堂高虎が入り、11年に東海道を押さえる政治色強い城として大改修を行った。本丸の北側を広げて三層櫓を3つ建てたほか、伊予からついてきた商人を城下町に住まわせて無税としたり伊勢神宮に向かう参宮街道を城下町に引き入れるなどして五百戸ほどに過ぎなかった城下町を生まれ変わらせた。明治に入り、櫓などは売られてしまったが昭和33年に三層の櫓が復興された。 *日本の城(中部地方)のページ *三重県のページ *津市のページ *IBMホームタウン・ホームページ  大手門(があったとこ)をくぐると何と日本庭園が???。それを抜けると今度は洋風の公園に???その奥には復興櫓が。というなんとも不思議な城跡。解説を見てみると日本庭園があった所は西の丸で、公園が本丸跡。とはいえ藤堂高虎らしい立派な石垣ときっちりした曲輪割りがきれいに残っていてみていてわくわくしてくる。特に天守台とは逆側の櫓跡は多聞櫓部分を通って移動できるようになっていて、そこから見える堀はたまんない。ちなみに三層櫓が一つ復興されているがそれは完全に門があったところに建ってて意味不明。そういう城って結構あるけど、どうしてそんなことするんだろう。その後そこで写真を撮ってもらった人が大阪の人で、なかなか面白かった。そういえば天守台の上にはどうしても登れなかった。どうしてだろう?危ないからだろうか。それと、日本庭園の入り口には有造館(江戸時代後期に立てられた学習院らしい)の門が移築されて残ってあった。市指定史跡って書いてたけど、修理しすぎ。すごいきれいで全然重みが無かった。大した事無い。(H9.2.1) 大手門(があったとこ)をくぐると何と日本庭園が???。それを抜けると今度は洋風の公園に???その奥には復興櫓が。というなんとも不思議な城跡。解説を見てみると日本庭園があった所は西の丸で、公園が本丸跡。とはいえ藤堂高虎らしい立派な石垣ときっちりした曲輪割りがきれいに残っていてみていてわくわくしてくる。特に天守台とは逆側の櫓跡は多聞櫓部分を通って移動できるようになっていて、そこから見える堀はたまんない。ちなみに三層櫓が一つ復興されているがそれは完全に門があったところに建ってて意味不明。そういう城って結構あるけど、どうしてそんなことするんだろう。その後そこで写真を撮ってもらった人が大阪の人で、なかなか面白かった。そういえば天守台の上にはどうしても登れなかった。どうしてだろう?危ないからだろうか。それと、日本庭園の入り口には有造館(江戸時代後期に立てられた学習院らしい)の門が移築されて残ってあった。市指定史跡って書いてたけど、修理しすぎ。すごいきれいで全然重みが無かった。大した事無い。(H9.2.1) |
| 松阪城(C) 近世 平山城 日本百名城:48 |
*日本の城(中部地方)のページ 思っていたよりも断然規模が大きく、圧倒された。建築物としては遺構は全く残っていないのだが、とにかく石垣が奇麗に残り、曲輪がはっきりと確認できる。北の大手口から入るのだが、そこから本丸にいたるまで二重三重に立派な石垣があり、特に直接本丸へと続く右に進む道は石垣を抜けては新たな石垣が現れるという感じで、実戦を考慮に入れた非常に重厚な作りになっているように感じた。なぜか二の丸で猿が飼われていたのが不可解ではあったが、それを抜けると連郭式の正方形の本丸が現れる。天守台はあまり高くなく、それも実践を重視している事の現われなのだろうか。結論としてはこの城は行く価値十分にあり。天守閣から一つ一つの櫓・門まで在りし日の姿を思い描けば、城郭とはいかなるものかが分かるのではないだろうか。ついでにというと失礼だが、ここは国学者本居宣長で有名な地であり、彼に関する建物も城内には多いのでそちらも見てみると面白いだろう。(H8.9.2) 思っていたよりも断然規模が大きく、圧倒された。建築物としては遺構は全く残っていないのだが、とにかく石垣が奇麗に残り、曲輪がはっきりと確認できる。北の大手口から入るのだが、そこから本丸にいたるまで二重三重に立派な石垣があり、特に直接本丸へと続く右に進む道は石垣を抜けては新たな石垣が現れるという感じで、実戦を考慮に入れた非常に重厚な作りになっているように感じた。なぜか二の丸で猿が飼われていたのが不可解ではあったが、それを抜けると連郭式の正方形の本丸が現れる。天守台はあまり高くなく、それも実践を重視している事の現われなのだろうか。結論としてはこの城は行く価値十分にあり。天守閣から一つ一つの櫓・門まで在りし日の姿を思い描けば、城郭とはいかなるものかが分かるのではないだろうか。ついでにというと失礼だが、ここは国学者本居宣長で有名な地であり、彼に関する建物も城内には多いのでそちらも見てみると面白いだろう。(H8.9.2) |
| 大河内城(D) 戦国 山城 |
*三重県のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 鳥羽城(D) 戦国 水城 |
*鳥羽市のページ *日本の城(中部地方)のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 伊賀上野城 近世 平山城(184m) 日本百名城:47 |
 伊賀の国は律令制度崩壊後京都や奈良に近いために荘園が多くの土地を占め、国内を統一するような土豪は生まれなかった。逆に小さな土豪同士の闘争のおかげで生まれたのが忍者であった。1581年に信長が伊賀に侵攻した時も小さな土豪が連合してゲリラ戦を挑み、散々てこずっている。 伊賀の国は律令制度崩壊後京都や奈良に近いために荘園が多くの土地を占め、国内を統一するような土豪は生まれなかった。逆に小さな土豪同士の闘争のおかげで生まれたのが忍者であった。1581年に信長が伊賀に侵攻した時も小さな土豪が連合してゲリラ戦を挑み、散々てこずっている。この城は1585年筒井順慶の養子である定次が大和郡山からこの地に移って築城したもので、定次は土豪の掃討に躍起になった。1608年豊臣氏との決戦を控えた家康は定次では頼りないと伊予今治から藤堂高虎を呼び寄せ、伊賀と伊勢の一部を与えた。高虎は津城を平和時の本拠、上野城を大阪城に備える戦闘時の本拠とし、特に西側の城郭を拡張・整備した。また高虎は伊賀の土豪を手なずけ、忍者を無足人として採用したと言われる。 高虎は五層の天守閣を建てたが完成間近の1612年に暴風雨で倒壊、15年に豊臣家が滅びてからは再建されなかったが、昭和十年には復興天守が建てられ、日本一高い石垣と共に大きな見所となっている。 *NINJAのページ *三重県のページ  とりあえず天守閣に登ってみるが、その展示物は鎧兜の類ばかりで見るべき価値のあるものはほとんどない。ただ、内部をすべて木で復元してあり、それはすばらしいと思う。どうせ復元するんならああいう形にすべきだろう。で、この城のすごいのはやはり高石垣。日本一高い石垣で、下から見たらそうでもないかと思うんだけど、上から見下ろすとその高さに足がすくむ。いくら大阪への押さえとはいえそこまでしなくても・・・という感じだ。(H9.2.1) とりあえず天守閣に登ってみるが、その展示物は鎧兜の類ばかりで見るべき価値のあるものはほとんどない。ただ、内部をすべて木で復元してあり、それはすばらしいと思う。どうせ復元するんならああいう形にすべきだろう。で、この城のすごいのはやはり高石垣。日本一高い石垣で、下から見たらそうでもないかと思うんだけど、上から見下ろすとその高さに足がすくむ。いくら大阪への押さえとはいえそこまでしなくても・・・という感じだ。(H9.2.1) |
お城トップページ |
トピックス |
データベースの歩き方 |
読み替え |
既訪城郭一覧 |
掲示板
蝦夷地 |
東山道 |
北陸道 |
東海道 |
畿内 |
山陰道 |
山陽道 |
南海道 |
西海道 |
琉球