

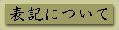
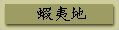
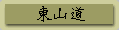
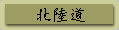
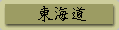
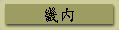
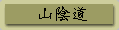
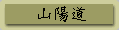
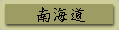
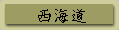
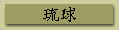
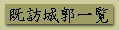

    | |
|---|---|
|
| |
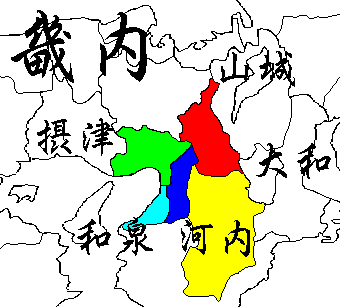 |
山城(京都南東部) 摂津(兵庫南東部・大阪北西部) 河内(大阪東部) 和泉(大阪南部) 大和(奈良)
|
  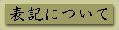 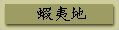 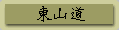 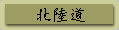 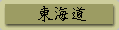 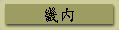 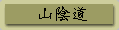 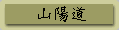 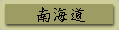 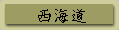 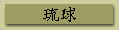 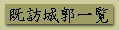 
|
| |||||||
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 平安京 | 言わずとしれた「鳴くようぐいす」平安京である。先般遷都1200年を迎え、日本が誇る古都京都を作り出した日本史最大の都である。都を城郭と考えるのかどうかには議論の余地があるが、都市全体を塀で囲んだ形態は中国では普通の形態であり、それを真似て作っている以上城郭と考えるのが妥当ではないかと思われる。 |
| 二条城 戦国 平城 日本百名城:53 |
 《御殿遠侍及び車寄,御殿式台,御殿大広間,御殿黒書院,御殿白書院,御殿蘇鉄の間》 《御殿遠侍及び車寄,御殿式台,御殿大広間,御殿黒書院,御殿白書院,御殿蘇鉄の間》〈御殿唐門,御殿御常御殿,東大手門,東南隅櫓,南土蔵,北土蔵,櫓門,御殿玄関,御殿御清所,北大手門,西門,御殿御書院,御殿台所及び雁の間,御殿築地,御殿台所,西南隅櫓,鳴子門,桃山門,北中仕切門,南中仕切門〉 信長が1569年に足利義昭の居所として築城したのが最初で、この時の石垣が昭和51年の地下鉄工事中に見つかっている。さらに1575年には自らの在京屋敷として二条御新造を築城。完成後、誠仁親王に献じ、二条御所と呼ばれるようになった。その後、秀吉が在京用の政治向きの城として隣に「聚楽第」を構築。その後家康が聚楽第南に二条城を築城し、伏見城から移り、家光が京都を監視する目的で拡大していった。最大の特徴は本格的城郭殿舎が残ることで、この二の丸殿舎の他には高知城の本丸殿舎があるくらいである。他にも多くの門や米蔵がよく残っており、姫路、高知、彦根と共に近世城郭の保存状態が最良のものの一つである。 *京都府のページ *京都観光協会の世界文化遺産ページ  思っていたものとは相当イメージが異なっていた。何というか、城という感じがすごい希薄な気がした。敷地面積の割には櫓は小さいし、何よりあのちっぽけな天守台。作られた時代と京という場所がそうさせたのだろうが、実践をほとんど考えていない生活の場という印象が強い。で、この城の目玉といえばもちろん二の丸御殿。現存する御殿でこれだけ大規模なものを見れるのは間違いなくここだけである。造りは書院造りなのだが、内部は華麗な装飾が施され、幕府の力を反映したものになっているようだった。僕の好みとしては高知のような無骨な感じのものの方が好きではあるが、大政奉還を宣言した場所が見れたりして非常に興味深かった。 思っていたものとは相当イメージが異なっていた。何というか、城という感じがすごい希薄な気がした。敷地面積の割には櫓は小さいし、何よりあのちっぽけな天守台。作られた時代と京という場所がそうさせたのだろうが、実践をほとんど考えていない生活の場という印象が強い。で、この城の目玉といえばもちろん二の丸御殿。現存する御殿でこれだけ大規模なものを見れるのは間違いなくここだけである。造りは書院造りなのだが、内部は華麗な装飾が施され、幕府の力を反映したものになっているようだった。僕の好みとしては高知のような無骨な感じのものの方が好きではあるが、大政奉還を宣言した場所が見れたりして非常に興味深かった。行った時、たまたま玄関部分を修復工事していて見れなかったのは少し残念ではある。でもたまたまという意味ではこちらの方がそうなのだが、たまたま本丸御殿の特別公開の日に当たっていたため、内部を見学することができた。こちらは御殿と言っても桂離宮から移築してきた建物で、二条城とは直接の関係はないが、朝廷の建物を見る機会はなかなかないし、二の丸御殿と比べて見れた点でも、なかなか興味深いものがあった。ただ全体を通して言えるのは観光客が多すぎるということ。あまりに周りに人が多いと急に冷めてしまったりする人間なんで、ちょっと辛かった。特別公開の日だったからあんなに混んでたのだろうか?いつもあんなに混んでるとするとまさに驚異的だが・・・。それと、二条城の近くに旧本能寺跡があるというので行ってきたが、本能小学校前に碑が立っている、まさにそれだけだった。(H9.3.20)
さて、少し話を戻して、二の丸御殿である。この二の丸御殿、5回目くらいなのだが、何度来ても感動する。江戸城の本丸御殿の雰囲気を実地で味わえるのはここだけだと思う。最初の虎や鷹の襖絵、大広間の将軍の着座構造、黒書院・白書院、それがこれだけの規模で現存している。もう素晴らしいの一言である。日本が誇るべき歴史以降の一つであることは間違いない。(R5.12.1) |
| 聚楽第(E) 近世 平城 |
|
| 嵐山城(D) 室町 平山城 |
|
| 伏見城 近世 平山城 |
 [伏見藩] [伏見藩]1594年に豊臣秀吉が自らの住居として建築したのが最初。地震で崩壊して、一度廃城とし、山の上に再度築城したものの、これも関が原の戦いで焼失する。そして1602年に家康の手によって再建され、近畿における徳川家の本拠となるが、やはり元和一国一城令により取り壊される運命。現在の復興天守はこの徳川時代の天守を、屏風絵などを参考にして昭和39年に再建されたものである。 *長谷川さんのページ *ショッピングモール京都のページ *納屋町商店街のページ  隣にキャッスルランドが併設されていることからも、とにかく全く期待をせずに行ったのだが、それが思ったよりも良かった。というのも、もちろんなかはコンクリート作りなのだが、展示物が重要文化財指定を受けている屏風絵がズラリ。さらに伏見城の変遷、模型などが詳しく、面白かった。本丸跡は明治天皇陵になっていることから、建っているところはお花畑山荘ではあるが、これが本当に立派な建物で、なかなかなものなのである。また、ちょうど入城したのが15:30過ぎだったこともあって、入場料が300円得したのもラッキーだった。(大人800円のところを500円で入れたのである。)とはいえ、やはりこんなところに遊園地を作ってはいけない。この遊園地がまた中途半端で、何の集客力もなさそうだった。これならお城だけにしておいたほうが客は来たのではないか?そんな気がした。 隣にキャッスルランドが併設されていることからも、とにかく全く期待をせずに行ったのだが、それが思ったよりも良かった。というのも、もちろんなかはコンクリート作りなのだが、展示物が重要文化財指定を受けている屏風絵がズラリ。さらに伏見城の変遷、模型などが詳しく、面白かった。本丸跡は明治天皇陵になっていることから、建っているところはお花畑山荘ではあるが、これが本当に立派な建物で、なかなかなものなのである。また、ちょうど入城したのが15:30過ぎだったこともあって、入場料が300円得したのもラッキーだった。(大人800円のところを500円で入れたのである。)とはいえ、やはりこんなところに遊園地を作ってはいけない。この遊園地がまた中途半端で、何の集客力もなさそうだった。これならお城だけにしておいたほうが客は来たのではないか?そんな気がした。また、すぐ近くにある御香宮神社の表門は、在りし日の伏見城の大手門を移築したものということで、重要文化財に指定されていた。唯一の伏見城の遺構ではなかろうか。一見の価値ありである。(H11.2.28) |
| 勝竜寺城(E) 近世 平山城 |
[長岡藩] 暦応二年、細川頼春が築城。信長が上洛の時、柴田勝家が攻略、細川藤孝がこの城を与えられ、丹後に移るまで居城した。山崎の合戦では明智光秀が本陣とした。 *長岡京市のページ |
| 淀城(C) 近世 平城 |
 [淀藩] [淀藩]細川政元が築城、細川藤孝に攻略され、落城。山崎の合戦では陣を張り、対抗したが敗退。秀吉は淀君の出産のため城を修復、鶴丸が病死すると、城を破却。(淀古城)二代将軍徳川秀忠は松平定綱に淀の新規築城を命じ、長井尚政が築城。その後、石川氏、松平氏、稲葉氏が在城。現在本丸跡は城内公園になり、石垣・堀の一部が現存。  京阪淀駅を降りると、京都競馬場の逆方向にいきなり石垣が見える。それも自転車置き場のすぐ裏。それが本丸跡で、公園になっている。おそろしいことに何の整備もされていない様子で、裏の堀はごみの溜まり場になっていた。なぜかわからないが、天守台の中には入れないように柵が設置されていて、少し残念だったが、思った以上に石垣が広範囲に残っていて満足だった。(H11.2.28) 京阪淀駅を降りると、京都競馬場の逆方向にいきなり石垣が見える。それも自転車置き場のすぐ裏。それが本丸跡で、公園になっている。おそろしいことに何の整備もされていない様子で、裏の堀はごみの溜まり場になっていた。なぜかわからないが、天守台の中には入れないように柵が設置されていて、少し残念だったが、思った以上に石垣が広範囲に残っていて満足だった。(H11.2.28) |
| 長岡京 | |
| 長岡城(F) | [長岡藩] |
| 笠置山城 | 後醍醐天皇が立てこもった城。城郭史上初めて山岳寺院が山城となった。鎌倉幕府討伐計画が漏れたために、僧兵、武士、農民ら五千の兵と共に立てこもり、築城した。七万余りの幕府軍が押し寄せ、善戦したが、奇襲により落城した。現在は山頂の笠置寺がそうであり、曲輪跡などが残る。 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 大阪城 近世 平城 日本百名城:54 |
 〈千貫櫓,乾櫓,六番櫓,金蔵,焔硝蔵,多聞櫓,大手門,塀,一番櫓,金明水井戸屋形,桜門〉 〈千貫櫓,乾櫓,六番櫓,金蔵,焔硝蔵,多聞櫓,大手門,塀,一番櫓,金明水井戸屋形,桜門〉[大坂藩] 大阪城は1496年本願寺八世法主蓮如が景観に惹かれて隠居所の別院をこの地に選んだのが初めとされる。その後、十世証如が本山を山科からこの地に移し、以後戦国時代の代表的な大城郭となっていった。信長との石山合戦は11年も続いたが、もう一つの拠点であった雑賀党を攻め落とした信長は十一世顕如と和議を結び、顕如を紀州へ追いやり、この地を手中にした。その後、1583年に秀吉が石山本願寺の曲輪をそのまま用いて数年後には日本一の大城郭が完成した。江戸時代には大坂の陣で全壊した大阪城を再建したが、豊臣大阪城に見劣りしてはならないという理由で本丸を埋め立て、その上に徳川大阪城を造らせた。曲輪の配置も替え、石垣は豊臣時代の2倍にした。その大阪城も戊辰戦争で炎上、昭和6年に徳川大阪城天守台の上に豊臣大阪城を模した天守閣が再建された。コンクリート製の天守閣が作られたのはこれが最初で、内部にエレベーターを設置するなど、近代的なものとして注目された。また平成の大改修も終わり、平成9年3月からリニューアルした天守閣の一般公開が始まっている。現在は徳川時代の多聞櫓・千貫櫓・六番櫓・一番櫓・乾櫓・煙硝蔵・御金蔵などが残る。 *大阪城天守閣 *特別史跡大阪城公園
|
| 真田丸出城 | 1614年真田幸村が大阪城惣構南面の丘に築き、大阪冬の陣では3千余人が防戦したと言われる。現在、真田山公園一帯がその場所であると考えられているが、碑などは全くない。その代わり、少し北寄りにある宰相山公園に大阪城に抜けていたという抜道の跡が残っている。 大阪城の一部として作られた真田丸だからすぐ近くにあるはずだということで探すことになる。雨の中を真田山公園をうろうろするがどうしてもそれらしいものは見つからない。そこで公園事務所にいって聞いてみると城跡のようなものは残っていないが、大阪城に抜ける抜道の跡が残っているということで、少し北寄りにある宰相山公園というところに向かう。そこには真田幸村の銅像と実際に抜道があり、(もちろん入り口には柵がしてあったが)なかなか興味深かった。その後、幸村ゆかりのところを訪ねようと力尽きて切腹した一心寺へと向かう。しかしまたどうしても見つからず、事務所の人に聞いてみるとこれまた一心寺ではなく隣の安居神社だと言われ、そちらに行ってみると確かに立派な碑があり、なかなか閑静でいい所だった。どちらも幸村ファンには一見の価値ありではなかろうか。(H9.3.29) 大阪城の一部として作られた真田丸だからすぐ近くにあるはずだということで探すことになる。雨の中を真田山公園をうろうろするがどうしてもそれらしいものは見つからない。そこで公園事務所にいって聞いてみると城跡のようなものは残っていないが、大阪城に抜ける抜道の跡が残っているということで、少し北寄りにある宰相山公園というところに向かう。そこには真田幸村の銅像と実際に抜道があり、(もちろん入り口には柵がしてあったが)なかなか興味深かった。その後、幸村ゆかりのところを訪ねようと力尽きて切腹した一心寺へと向かう。しかしまたどうしても見つからず、事務所の人に聞いてみるとこれまた一心寺ではなく隣の安居神社だと言われ、そちらに行ってみると確かに立派な碑があり、なかなか閑静でいい所だった。どちらも幸村ファンには一見の価値ありではなかろうか。(H9.3.29) |
| 三田城(D) 近世 平城 |
[三田藩] |
| 伊丹城(D) 近世 平城 |
|
| 池田城 |  取引先がすぐ近くにあり、帰りに寄ったもの。とはいえ、全く何も無い。碑すらない。地図には城跡の表記があるものの、実際には何も無いということか。(H9.9.30) 取引先がすぐ近くにあり、帰りに寄ったもの。とはいえ、全く何も無い。碑すらない。地図には城跡の表記があるものの、実際には何も無いということか。(H9.9.30) |
| 芥川城(D) 近世 平城 |
|
| 芥川山城(C) 戦国 山城(182m) 日本百名城:159 |
芥川山城は1520年頃に細川高国が築かせたものと思われ、昼夜兼行で約千人もの人員を動員して大規模な普請を行った一大城郭であり、現在でも石垣や曲輪跡など相当の遺構が残るものであるが、それが本当にこの城の遺構であるのかという部分を含め今後の調査が待たれる。 細川高国は重臣の能勢氏を城主とするも、細川家の内乱に巻き込まれ、結局は細川晴元側の軍勢に攻め落とされてしまう。1530年代には晴元は京都管領職についたが、たびたびこの城を拠点として指揮をとっており、近畿地方でこの城が重要な意味合いを持っていたことをうかがわせる。その後細川晴元は三好長慶の反乱で京都を追われ、同時にこの城も三好家のものとなる。1568年に信長が上洛するにあたって、この城を攻め落とし、和田惟政を城主とし、その後惟政に高槻城も任すこととなるに至り、廃城することとなったものと思われる。いずれにしても近畿地方で実権を握ったものがこの城を所有することになったことは、非常に重要な意味合いを持って捉えられていたことの何よりの証であろう。  正月休みを用いて気合を入れて向かってみたものの、まず入り口がわからない。三好山というのが城跡らしいということは調べていたのでそのすぐ近くにある料理旅館「山水館」に行ってみると、何と三好山との間に芥川が流れていて到底行けない。しかたないのでぐるっと東に迂回して妙力寺方面から車を走らせると道がどんどん細くなる。もう行き止まりというところで近所の家に聞いてみると、とにかくこの道をまっすぐ行くのだと言う。近くに車を停めて登ること30分、どんどん道は細くなり、そのうち道かどうかすら定かではなくなり、果ては道なき道を進む状態に。3つくらい曲輪らしきものを発見し、石垣らしきものを発見したものの、これ以上不可能と判断し、引き返すことに。恐らくあまりにも人が来ないので小さな土砂崩れやら、落ち葉やらで道がなくなりつつあるようだ。 正月休みを用いて気合を入れて向かってみたものの、まず入り口がわからない。三好山というのが城跡らしいということは調べていたのでそのすぐ近くにある料理旅館「山水館」に行ってみると、何と三好山との間に芥川が流れていて到底行けない。しかたないのでぐるっと東に迂回して妙力寺方面から車を走らせると道がどんどん細くなる。もう行き止まりというところで近所の家に聞いてみると、とにかくこの道をまっすぐ行くのだと言う。近くに車を停めて登ること30分、どんどん道は細くなり、そのうち道かどうかすら定かではなくなり、果ては道なき道を進む状態に。3つくらい曲輪らしきものを発見し、石垣らしきものを発見したものの、これ以上不可能と判断し、引き返すことに。恐らくあまりにも人が来ないので小さな土砂崩れやら、落ち葉やらで道がなくなりつつあるようだ。できれば日を改めてもう一度挑戦したいが、まずここに城があった事実をもう少し認知させ、ハイキングでもできるような設備を整備し、少なくとも説明札なり碑なりを設置するくらいのことはしてもいいのではないかと思う。もしそこまでの調査がなされていないのであれば、早急に行わないと遺構の風化は取り返しのつかない状態になるような気がしてならない。(H12.1.3) |
| 高槻城(E) 近世 平城 |
[高槻藩] キリシタン大名高山右近が入った城。慶安2年からは永井氏が在城。明治7年に城跡の石垣石が鉄道建設の資材に用いられたこともあり、遺構はほぼ残っていない。 キリシタン大名高山右近が入った城。慶安2年からは永井氏が在城。明治7年に城跡の石垣石が鉄道建設の資材に用いられたこともあり、遺構はほぼ残っていない。*高槻市
|
| 茨木城(E・・・移築城門あり) 戦国 平城 |
[茨木藩] 茨木城の起こりははっきりしない。室町幕府の御番衆の茨木氏の居城であったようである。1571年に信長に背いた荒木村重は本城を奪い、中川清秀に預け、この地方を守らせた。豊臣氏の直轄の時期を経て、関ヶ原以後は片桐且元が入ったが、大坂落城後退去。元和の一国一城令により破却廃城。 現在遺構はほとんどなく、茨木神社とその北方の茨木小学校辺りといわれる。大和小泉慈光院表門が大手門、茨木神社東門が搦手門と伝えられる他、妙見寺山門も茨木城の城門と伝えられる。  正月休みを利用して行ってみたのだが、まず茨木神社は初詣の人でいっぱい。恐ろしい人ごみの中を歩いていくと、屋台の間に門が。裏側にこっそりと「茨木城搦手門」という説明札がある。ほんとにそのすぐ横でお好み焼きとかを売ってるものだからゆっくり見るわけにはいかなかったが、なかなか面白い経験だったように思う。ただ、文化遺跡のすぐ横で火を使うのは少しどうかと思うのだが。そして茨木小学校、これは何か同窓会のようなものをしていたために校門が開いていて入ることができた。校内に「城跡の森」というのがあり、小さな林の中に碑が立っている。また、その校門のすぐ横には大和郡山市に移築されているという大手門櫓が復元されている。これも教育の一環なのだろうか。(H12.1.3) 正月休みを利用して行ってみたのだが、まず茨木神社は初詣の人でいっぱい。恐ろしい人ごみの中を歩いていくと、屋台の間に門が。裏側にこっそりと「茨木城搦手門」という説明札がある。ほんとにそのすぐ横でお好み焼きとかを売ってるものだからゆっくり見るわけにはいかなかったが、なかなか面白い経験だったように思う。ただ、文化遺跡のすぐ横で火を使うのは少しどうかと思うのだが。そして茨木小学校、これは何か同窓会のようなものをしていたために校門が開いていて入ることができた。校内に「城跡の森」というのがあり、小さな林の中に碑が立っている。また、その校門のすぐ横には大和郡山市に移築されているという大手門櫓が復元されている。これも教育の一環なのだろうか。(H12.1.3) |
| 尼崎城(E) 近世 平城 |
[尼崎藩] 幕命により戸田氏鉄が四重の天守と三櫓を連結した連立式天守を建造。 |
| 三宅城(D) 戦国 平城 |
応仁の乱に際して細川晴元側に属した三宅氏の居城。初めは晴元側に属した三宅氏であったが、戦況が混乱してくるにしたがって晴元と長慶との間で主従関係を頻繁に変えた人物でもある。現在遺構は全く残ってはおらず、阪急電車(京都大阪線)沿線に「三宅城址」の碑があるのみである。 *三宅賢治氏のページ |
| 滝山城(E) 戦国 山城 |
*山ぽんのホームページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 交野城 | |
| 飯盛山城 戦国 山城 日本百名城:160 |
元畠山氏の居城であるが、三好長慶が入城、大改修を行った。その後織田軍に攻められ、廃城。 |
| 田原城 | |
| 若江城 | |
| 高屋城(E) 戦国 平山城(47m) |
築城時期などははっきりしないが、1450年前後に畠山氏が築城したと考えられている。1450年といえばまさに応任の乱が始まる時期である。世に応任の乱の一因として数えられるのが畠山氏の家督争いであることからも分かる通り、この城は特に抗争の中心地となった。戦国末期には三好長慶が攻略し、1575年には信長によって落城、以後は城として利用された様子はない。 城跡は築山古墳付近を本丸とした平山城で、現在は本丸・二の丸の北半分・三の丸の一部は山林として残り、土塁・堀・水掘等が見られる。大阪府教育委員会による発掘調査で中国式磁器や瀬戸系の陶器などが出土している。 |
| 千早城 上赤坂城 下赤坂城 (E) 南北朝 山城 日本百名城:55 |
元弘の乱(1331)において、笠置山城で戦っていた後醍醐天皇を迎えるべく楠木正成が急造したのが赤坂城であった。後醍醐天皇は赤坂城へ向かう途上で捕らえられたが、正成は護良親王を奉じて赤坂城に入った。北条軍は大軍でこの城を攻め、正成は親王らと共に金剛山中に逃れるが、翌年奪回。のちこの城を前衛基地とし、その上方に新たに築城。前衛基地は下赤坂城、本城は上赤坂城と呼ばれている。さらにその後詰めの城として千早城を築いた。現在、わずかに曲輪跡や空掘跡が残る。 千早城・・・千早神社という楠木親子を祭った神社が建っているところが城跡。ただ、神社まで行く途中に碑がぽつんと建っているだけで、他には何もない。階段が長くてつらいため、そう無理して行くものではないと思う。帰りに軽く数えてみたのだが、おそらく約600段くらいだと思う。苦労して行ってもなかなか報われないものだ。(H9.3.17) 千早城・・・千早神社という楠木親子を祭った神社が建っているところが城跡。ただ、神社まで行く途中に碑がぽつんと建っているだけで、他には何もない。階段が長くてつらいため、そう無理して行くものではないと思う。帰りに軽く数えてみたのだが、おそらく約600段くらいだと思う。苦労して行ってもなかなか報われないものだ。(H9.3.17) 上赤坂城・・・この城はどう行くのか少し迷ったが、西側の道から城に行く山道が出ている。ちょうど給食センターがある付近である。今度は階段ではなくひたすら山道。これがまた遠い。階段もつらいが、こちらもまた相当つらい。ただ間違いなくこの城がもっとも形態を良く残しているため、ゆっくりと在りし日を偲んで歩くといいと思う。ただこの日はもう夕日が沈みかけていたためにそうもできず、半小走りで何とか登り切った。本当にくたくたになった。無論残っているといっても石垣があるわけでもなく、ここが曲輪らしいというくらいしかわからない。それでもこの城が一番マシなのである。(H9.3.17) 上赤坂城・・・この城はどう行くのか少し迷ったが、西側の道から城に行く山道が出ている。ちょうど給食センターがある付近である。今度は階段ではなくひたすら山道。これがまた遠い。階段もつらいが、こちらもまた相当つらい。ただ間違いなくこの城がもっとも形態を良く残しているため、ゆっくりと在りし日を偲んで歩くといいと思う。ただこの日はもう夕日が沈みかけていたためにそうもできず、半小走りで何とか登り切った。本当にくたくたになった。無論残っているといっても石垣があるわけでもなく、ここが曲輪らしいというくらいしかわからない。それでもこの城が一番マシなのである。(H9.3.17) 下赤坂城・・・赤坂中学校の裏手に小さな丘があり、その上にぽつんと説明板と碑が立っているだけ。まったく遺構どころではなく、千早と上赤坂のおまけという感じであった。(H9.3.17) 下赤坂城・・・赤坂中学校の裏手に小さな丘があり、その上にぽつんと説明板と碑が立っているだけ。まったく遺構どころではなく、千早と上赤坂のおまけという感じであった。(H9.3.17) |
| 烏帽子形城 戦国 山城 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 岸和田城 近世 平城 日本百名城:161 |
 [岸和田藩] [岸和田藩]室町の昔から紀州街道の要衝として、または紀州の押えとして戦略的に重要な位置を占め、本格的な近世城郭が築かれてきた。1597年、小出氏の時代に、五層の天守閣が完成。その後松平康重、岡部宣勝らによって整備、改築が繰り返された。現在の天守閣は昭和29年に再建されたものであるが、往時のものとは全く無関係の模擬天守閣である。 *公式 *岸和田市
|
| 岸和田古城(E) 南北朝 平城 |
1334年、楠木正成が鎌倉幕府討伐の功により和泉国の守護に任ぜられた時に甥の和田高家を代官としてこの地を治めさせた。堺には本家の和田城があり、区別するため本家を「上の和田城」こちらを「岸の和田城」と呼ぶようになった。後にこれを受け継いだ信濃氏が現在の岸和田城を築城した。現在、『和田氏居城伝説地』の碑が立つのみである。 現在の岸和田城は南海本線岸和田駅の西側にあるが、ちょうど逆側で、東に少し行ったところにある。途中案内看板などは全くないのでわかりにくかったが、木が茂っているところに見当を付けて行ってみるとそれがビンゴだった。こんもりした丘で、中央部に「和田氏居城伝説地」の記念碑が立っている。“伝説”だけあって、遺構は全くない。丘を縄張りと見れば曲輪が残ってると言えなくもないが。(H8.11.13) 現在の岸和田城は南海本線岸和田駅の西側にあるが、ちょうど逆側で、東に少し行ったところにある。途中案内看板などは全くないのでわかりにくかったが、木が茂っているところに見当を付けて行ってみるとそれがビンゴだった。こんもりした丘で、中央部に「和田氏居城伝説地」の記念碑が立っている。“伝説”だけあって、遺構は全くない。丘を縄張りと見れば曲輪が残ってると言えなくもないが。(H8.11.13) |
| 大沢城(E) 室町 山城(322m) |
大沢権之介(後の根来佐太仁?)の築城と考えられている。大沢和泉守は永享年間に将軍義教によって美濃に移されたとの記録もあり、残った大沢氏が根来寺勢力に組み込まれたのではないかと言われている。かろうじて天守跡と井戸跡が残るのみ。 葛城山を岸和田側に少し下りたところにある大沢町というところにある。近くまで行って地元の人何人かに場所を聞いて歩くと知らないという人や違うことを教えてくれる人もいて登る前から相当マニアックな城であることを認識する。根福寺城とは違い、道はアスファルトで整備されていたが、歩くために作られたものではないらしく、ずいぶん疲れた。途中何度か道に迷いながらどんどん上がっていくと頂上にテレビのアンテナが立っているのが見えてくる。そこがどうも本丸跡らしい。(天守台かも)何の表示も無いため、さっぱりわからないが構造上そうとしか考えられない。その少し下には井戸の跡と思われるものも確かに存在した。(埋まっていたが)ただ、どこにもそれが大沢城だと示すものは存在せず、石垣の類も全く残ってはいない。その相当な疲労感に見合うインパクトはないため、この城は山登りが好きな人以外は行くべきではないであろう。(H9.1.10) 葛城山を岸和田側に少し下りたところにある大沢町というところにある。近くまで行って地元の人何人かに場所を聞いて歩くと知らないという人や違うことを教えてくれる人もいて登る前から相当マニアックな城であることを認識する。根福寺城とは違い、道はアスファルトで整備されていたが、歩くために作られたものではないらしく、ずいぶん疲れた。途中何度か道に迷いながらどんどん上がっていくと頂上にテレビのアンテナが立っているのが見えてくる。そこがどうも本丸跡らしい。(天守台かも)何の表示も無いため、さっぱりわからないが構造上そうとしか考えられない。その少し下には井戸の跡と思われるものも確かに存在した。(埋まっていたが)ただ、どこにもそれが大沢城だと示すものは存在せず、石垣の類も全く残ってはいない。その相当な疲労感に見合うインパクトはないため、この城は山登りが好きな人以外は行くべきではないであろう。(H9.1.10) |
| 根福寺城(D) 戦国 山城(276m) |
天文四年、細川家の将松浦肥前守守によって野田山城として築城された。守は細川家没落の後三好方についたが、その子と見られる孫五郎が根来方について三好と敵対、野田山城は根来寺に注進され、根福寺城と改称された。中央鞍部には大門跡と見られる石積が左右二か所、その北側斜面には階段状に石垣を見る事が出来る。 貝塚市の山奥にあり、ものすごい獣道を歩いていった。5分ほど歩くと二の丸らしき平地に行き当たり、そこからはさらに険しい竹薮の道を登っていかなければならなかった。途中でかろうじて石垣かなという感じの岩肌を見ながら上に上がると三段に奇麗に整備された平面が表われた。この辺一帯に本丸などがあったのだろう。その壁にも確かに岩はあったのだがぼろぼろに風化していて実際石垣だったのかどうかは確認する術が無い状態だった。戦国時代に作られた城だからもう少し分かるのかと思っていたのだが、本丸跡に碑すら立てられておらず、少し残念だった。とはいえ、獣道を歩かねばならない事を除けば、割合曲輪もわかりやすく残っており、麓には説明の書かれた看板も立っているので、この手の城が好きな人間はなかなか楽しめるのではないだろうか。(H9.1.10) 貝塚市の山奥にあり、ものすごい獣道を歩いていった。5分ほど歩くと二の丸らしき平地に行き当たり、そこからはさらに険しい竹薮の道を登っていかなければならなかった。途中でかろうじて石垣かなという感じの岩肌を見ながら上に上がると三段に奇麗に整備された平面が表われた。この辺一帯に本丸などがあったのだろう。その壁にも確かに岩はあったのだがぼろぼろに風化していて実際石垣だったのかどうかは確認する術が無い状態だった。戦国時代に作られた城だからもう少し分かるのかと思っていたのだが、本丸跡に碑すら立てられておらず、少し残念だった。とはいえ、獣道を歩かねばならない事を除けば、割合曲輪もわかりやすく残っており、麓には説明の書かれた看板も立っているので、この手の城が好きな人間はなかなか楽しめるのではないだろうか。(H9.1.10) |
| 土丸城(D) 南北朝 山城 |
もともと足利尊氏が高師泰に命じて豪族日根野盛治をして警護させた城だったが、その後南朝軍に攻め取られ、楠木氏や橋本氏などによって整備・拡張が行われ、南朝側の重要な拠点となった。その時に雨山に城域を拡大したと言われ、この時から土丸城は雨山城の三の丸もしくは支城として機能していくことになった。14世紀後半には山名氏清の猛攻によりついに陥落、その後将軍義満に討たれた氏清の息子の義理は跡を継いで警護したが、大内義弘の大軍を前にあえなく陥落してしまった。戦国時代には畠山氏内乱の舞台となり、江戸時代初期まで重要な戦略的拠点として機能していたと考えられる。 遺構としては本丸跡が残るだけであるが、曲輪上が奇麗に整備されており、遠くから見てもよくわかるし、その場にいても曲輪の形などを確認しやすいのでファンにはたまらないだろう。また、雨山ハイキングコースとつながっているため、なかなか良いハイキングコースにもなり、特におすすめの城。ただ、雨山から土丸に抜ける道の表示が無いので注意が必要。雨山城の井戸跡から奥に進むと土丸城に抜ける事が出来る。 |
| 雨山城(D) 南北朝 山城(341m) |
南朝の拠点として橋本正信によって築かれる。和泉地方と粉河地方とを結ぶ拠点として戦略的に重要な地位を占めていたと考えられる。今では説明の看板と千畳敷・井戸・月見亭・馬場跡などがわずかに往時を偲ばせる。現在雨山ハイキングコースとして整備されている。 熊取町にたまたま行って、たまたま見つけた雨山城に登ってみる。実際こんなに近くに城跡があるとは思ってなかったので非常に驚いた。「すぐやろう」という軽い気持ちで登ったのだが、なかなか険しい。結構しんどい目をして登ったのだが、城跡には何もない。解説の看板があるだけだった。でも眺めはすごく奇麗で、関西空港などが一望できた。その他には千畳敷・井戸・月見亭・馬場跡があった。どれもハイキングコースの一部に組み込まれていてゆっくり過ごすにはもってこいである。井戸は水がそこまであって、それだけ重要な城であったことをうかがわせる。この時は知らなかったのだがこの井戸の奥の小道を進むと隣の土丸城に抜けることができる。(H8.10.13) 熊取町にたまたま行って、たまたま見つけた雨山城に登ってみる。実際こんなに近くに城跡があるとは思ってなかったので非常に驚いた。「すぐやろう」という軽い気持ちで登ったのだが、なかなか険しい。結構しんどい目をして登ったのだが、城跡には何もない。解説の看板があるだけだった。でも眺めはすごく奇麗で、関西空港などが一望できた。その他には千畳敷・井戸・月見亭・馬場跡があった。どれもハイキングコースの一部に組み込まれていてゆっくり過ごすにはもってこいである。井戸は水がそこまであって、それだけ重要な城であったことをうかがわせる。この時は知らなかったのだがこの井戸の奥の小道を進むと隣の土丸城に抜けることができる。(H8.10.13) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 柳生陣屋(D) 戦国 山城(320m) |
柳生宗矩が構築後、柳生十兵衛が増改築。柳生一族が将軍家の剣術指南役として十三代居住。 |
| 多聞山城(E) 戦国 山城 |
松永久秀の居城で、日本で初めて塁上に長屋造りの多聞櫓を設け、近世城郭はこの城から始まったとも言われる。1573年に信玄と組んで信長に反抗しようとし、降伏して以来破却された。石垣は大和郡山城に使用され、建物は二条城に移されたといわれている。遺構としてはほとんど何もなく、現在若草中学校がその跡地である。わずかに本丸と見られる曲輪跡が校舎横に確認できる。
(写真15KB) |
| 平城京 | 言わずとしれた「なんと立派な」平城京である。日本で初めての大規模な中国式総構え都市型城郭といえよう。 奈良市全体が平城京であるのだが、遺構として平城宮がある。思っていたよりもずいぶん広く、ほぼ全面に芝生が敷き詰められていて素晴らしい公園になっている。文部省があったと思われるところに、建物と門が復元されており、(pm4:00まで入場無料)他にも礎石跡や植木を柱に見立てた建物跡などがあり、見ていて飽きない。とにかくスケールがでかいので懐古にはもってこいである。単なる公園としても、散策コースとしても、もちろん遺跡としても、どんな人にも楽しめるものになっているのではなかろうか。(H9.8.24) 奈良市全体が平城京であるのだが、遺構として平城宮がある。思っていたよりもずいぶん広く、ほぼ全面に芝生が敷き詰められていて素晴らしい公園になっている。文部省があったと思われるところに、建物と門が復元されており、(pm4:00まで入場無料)他にも礎石跡や植木を柱に見立てた建物跡などがあり、見ていて飽きない。とにかくスケールがでかいので懐古にはもってこいである。単なる公園としても、散策コースとしても、もちろん遺跡としても、どんな人にも楽しめるものになっているのではなかろうか。(H9.8.24) |
| 大和郡山城 近世 平城 日本百名城:165 |
 [郡山藩] [郡山藩]この城は郡山衆の居館から始まり、郡山衆が筒井氏の傘下に入ってから筒井氏が居城筒井城の北を守る支城として整備を始めた。三好家配下の松永久秀が信貴山城に入ってからは、筒井城を二度にわたって追われるなど、苦難の日々が続くが、信長に臣従するという幸運も手伝ってその猛攻を何とか凌ぎ、久秀が信貴山城で憤死を遂げて後、郡山城を本城にすべく改修を始める。順慶の死後、その子定次が伊賀上野に転封されて後、紀伊・大和・和泉百万石の太守に任ぜられた秀長が移り、拡張を繰り返した。その後水野・本多・柳沢と続き、柳沢吉里を藩祖とする郡山藩が誕生することになる。 今日残る石垣には転用石が多く用いられており、五輪塔の石(写真19KB)やさかさ地蔵(写真19KB)などが有名である。秀長の節約家ぶりがよくわかる遺構である。さかさ地蔵の前には供養のための小屋が建っている。 *柳沢文庫のページ  HPを見てメールをくれた田中さんが結構近くに住んでいるというので、一緒に城巡りをすることになった。その第一弾。想像していたよりも相当規模の大きな城だった。そして何と言っても印象に残ったのは多くの転用石を用いた天守台。転用石があるという話は聞いていたので五輪塔の石はすぐに見つけられたのだが、帰りに入り口付近の役所で他にも「さかさ地蔵」といって地蔵さんを石垣に使っているところがあることを知ってまた天守台まで戻り、それを確認しに行った。一見すると見逃してしまいそうなボロボロの建物の奥に地蔵さんがならべられてあり、その奥の石垣に足をこちら側に向けて下を向いた格好のお地蔵さんがあった。そこまでして石を調達したことを思うと、感慨深いものがあった。(H9.1.25) HPを見てメールをくれた田中さんが結構近くに住んでいるというので、一緒に城巡りをすることになった。その第一弾。想像していたよりも相当規模の大きな城だった。そして何と言っても印象に残ったのは多くの転用石を用いた天守台。転用石があるという話は聞いていたので五輪塔の石はすぐに見つけられたのだが、帰りに入り口付近の役所で他にも「さかさ地蔵」といって地蔵さんを石垣に使っているところがあることを知ってまた天守台まで戻り、それを確認しに行った。一見すると見逃してしまいそうなボロボロの建物の奥に地蔵さんがならべられてあり、その奥の石垣に足をこちら側に向けて下を向いた格好のお地蔵さんがあった。そこまでして石を調達したことを思うと、感慨深いものがあった。(H9.1.25) |
| 筒井城 戦国 平城 |
筒井順永が築城し、筒井氏が6代居城。順慶が大和郡山城に移って、廃城。 |
| 小泉陣屋 近世 平城 |
[小泉藩] |
| 高安城(E) 室町 山城(488m) |
信貴山のすぐ隣の高安山に築かれた朝鮮式山城。白村江の戦いに敗れた後、国防の必要性からこの地に築かれたものである。この城は信貴山を内郭とし、信貴山城は高安山を出城とした。そのため、信貴山城の拡張によって変形した部分が大きく、規模の特定も容易ではない。しかし昭和53年に倉庫跡の礎石が発見され、話題になった。 |
| 信貴山城(D) 戦国 山城(433m) |
木沢長政によって築城されるが敗戦時に焼け落ちてしまう。その後この城を再興したのが松永久秀で、ここを中心に大和攻略を推進する。周知の通り1577年には信長に反抗して自滅した。 城址は現在朝護孫子寺(日本で初めて毘沙門天が現れたと言われる)頂上の空鉢堂の部分が本丸であった。そのすぐ横の二の丸部分には記念碑が建てられている。(右写真参照)城は現在の寺のあるところとは逆部分に広がっていて、ハイキングコースになっている。下に降りると数々の曲輪やわずかの石垣を確認することができる。(写真21KB)  大阪方面に帰る途中で信貴山に寄ることにした。途中で雪が積もり出してちょっと焦ったが、とりあえずのどか村に到着、ここには出城があったという話。じゃあ本城はどれだ?ということで、信貴生駒スカイラインに乗ってみることにする。ところがチェーンがないと入れないとのこと。しかたないので朝護孫子寺(信貴山寺)に寄っていくことに。するとなんとそのお寺の頂上が城の本丸だったというではないか。ということで無事お城見物ができましたとさ。印象としてはこれも相当広い城。寺とは逆側に城跡があるのだがそちら側に降りていくと所々に林の中に曲輪跡が見え、少しだけだが石垣もあった。まだ雪が相当残っていて、滑りそうでちょっと恐かった。(H9.1.25) 大阪方面に帰る途中で信貴山に寄ることにした。途中で雪が積もり出してちょっと焦ったが、とりあえずのどか村に到着、ここには出城があったという話。じゃあ本城はどれだ?ということで、信貴生駒スカイラインに乗ってみることにする。ところがチェーンがないと入れないとのこと。しかたないので朝護孫子寺(信貴山寺)に寄っていくことに。するとなんとそのお寺の頂上が城の本丸だったというではないか。ということで無事お城見物ができましたとさ。印象としてはこれも相当広い城。寺とは逆側に城跡があるのだがそちら側に降りていくと所々に林の中に曲輪跡が見え、少しだけだが石垣もあった。まだ雪が相当残っていて、滑りそうでちょっと恐かった。(H9.1.25) |
| 立野城 戦国 山城 |
|
| 二上山城 戦国 山城 |
|
| 宇陀松山城 戦国 山城(473m) 続日本百名城:166 14世紀半ば頃に宇陀三将の秋山氏により築城。8年間城主をつとめた多賀秀種の時に、大規模な改修が行われたと推定されている。福島高晴が城主の時に「松山城」と改名されたが、高晴が大坂夏の陣で豊臣方と通じていた疑いで改易となったため、1615年に城は破壊された。 *奈良県歴史文化資源データベース |
|
| 高取城(C) 近世 山城(584m) 日本百名城:61 |
[高取藩] 当城は南北朝時代に築城されたが、当時は越智氏の支城に過ぎなかった。ところがその後天険の要害として重視され始め、信長の一国一城主義によって筒井順慶はこの城を破却するが、後に復活させて詰めの城としている。1640年には植村家政が入部し、以後14代に渡って城を守った。現在国の指定史跡となっている。  高校の時の友達と俺が卒業する前に一回会おうということで、車でどこかに行こうということになって吉野方面に向かう途中で立ち寄った城。確か大学の一回の頃に壷坂寺は来たことがあったのだが、その奥にこんな立派な城があるとは考えもしなかった。高取町に入る時、「日本一の山城の町にようこそ」というようなことが書かれてあったが、まったく日本一という表現がぴったりくる城である。大手門のあたりから歩いて登っていくのだが、山の中に入ると普通の山道かと思いきや、その中に忽然と現れる整然とした石垣の山。まったくうっそうとした林の中にほんとにきれいな石垣があるのだから驚かずにはいられない。そしてそのまま門の跡とか櫓台とかを抜けると少し開けた二の丸跡にでて、ここからは随分整備された公園風になる。本丸内の鉛櫓の台には日本でも唯一の遺構という胴木というものがあったらしいがどうしても見つけることができなかった。ただ、全体としては近世山城の形態が良く分かり、地形を利用して作られた美しい石垣は見る者を圧倒し、魅了すること請け合いである。かなりおすすめの城。(H9.3.17) 高校の時の友達と俺が卒業する前に一回会おうということで、車でどこかに行こうということになって吉野方面に向かう途中で立ち寄った城。確か大学の一回の頃に壷坂寺は来たことがあったのだが、その奥にこんな立派な城があるとは考えもしなかった。高取町に入る時、「日本一の山城の町にようこそ」というようなことが書かれてあったが、まったく日本一という表現がぴったりくる城である。大手門のあたりから歩いて登っていくのだが、山の中に入ると普通の山道かと思いきや、その中に忽然と現れる整然とした石垣の山。まったくうっそうとした林の中にほんとにきれいな石垣があるのだから驚かずにはいられない。そしてそのまま門の跡とか櫓台とかを抜けると少し開けた二の丸跡にでて、ここからは随分整備された公園風になる。本丸内の鉛櫓の台には日本でも唯一の遺構という胴木というものがあったらしいがどうしても見つけることができなかった。ただ、全体としては近世山城の形態が良く分かり、地形を利用して作られた美しい石垣は見る者を圧倒し、魅了すること請け合いである。かなりおすすめの城。(H9.3.17) |
| 吉野城(E) 室町 山城 |
護良親王が、赤坂落城後に山岳寺院城郭を築城したが、元弘三年に鎌倉幕府軍の攻撃で落城。さらにその後、笠置落ちした後醍醐天皇が吉野に入り、金輪寺を本拠とし、今度は室町幕府軍の高師直の攻撃を受け、金輪寺・蔵王堂が焼亡。 これは城と考えるかどうかの議論もあるが、南北朝時代の南朝の本拠地であり、その天然の要害は城と考えていいと思う。実際に吉野の中心的存在である蔵王堂の前には大塔宮護良親王が1333年に鎌倉幕府軍に攻められた時に陣を敷いたと言われる場所が残っている。また、中心部分の周りには石垣が作られ、立派なものが残っていた。ただ吉野といえば桜である。またそうした時期にも来てみたいものである。(H9.3.17) これは城と考えるかどうかの議論もあるが、南北朝時代の南朝の本拠地であり、その天然の要害は城と考えていいと思う。実際に吉野の中心的存在である蔵王堂の前には大塔宮護良親王が1333年に鎌倉幕府軍に攻められた時に陣を敷いたと言われる場所が残っている。また、中心部分の周りには石垣が作られ、立派なものが残っていた。ただ吉野といえば桜である。またそうした時期にも来てみたいものである。(H9.3.17) |
| 二見城(E) 近世 平城 |
[五條藩] 営業の帰りに地図を見ていると城跡があるというので立ち寄る。ところが、どうしても見つからず、歩いている人に尋ねてみるともうすでに遺構はないとのこと。城跡は、すべて宗教法人のお寺となってしまっており、在りし日を偲ぶこともできない。(H10.3.4) 営業の帰りに地図を見ていると城跡があるというので立ち寄る。ところが、どうしても見つからず、歩いている人に尋ねてみるともうすでに遺構はないとのこと。城跡は、すべて宗教法人のお寺となってしまっており、在りし日を偲ぶこともできない。(H10.3.4) |
お城トップページ |
トピックス |
データベースの歩き方 |
読み替え |
既訪城郭一覧 |
掲示板
蝦夷地 |
東山道 |
北陸道 |
東海道 |
畿内 |
山陰道 |
山陽道 |
南海道 |
西海道 |
琉球