

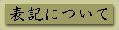
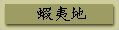
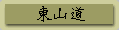
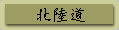
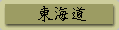
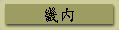
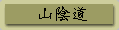
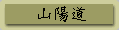
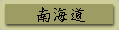
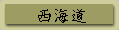
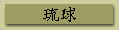
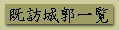

    | |
|---|---|
|
| |
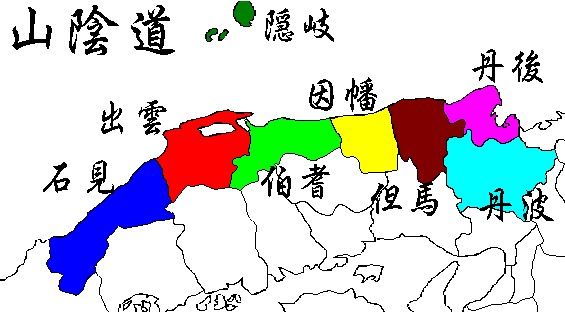
| |
  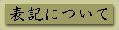 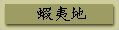 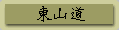 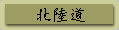 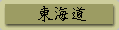 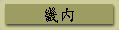 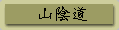 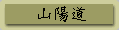 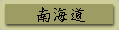 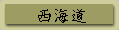 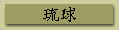 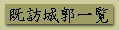 
|
| ||||||
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 篠山城(C) 近世 平山城 |
 [篠山藩] [篠山藩]関ヶ原の合戦後、豊臣方の封じ込めと分断を目的に計画された。縄張りを行ったのは藤堂高虎で、今治・津・駿府城に酷似している。また、西国20家が助役を命ぜられた天下普請による築城であった。三の丸内に輪郭状に二の丸・本丸が形成されており、東側には天守曲輪があるが家康の命で大天守は上げられなかった。しかし三方の隅に二重小天守が上げられていた。本丸殿舎大書院が現存していたが残念なことに昭和19年に焼失している。 *兵庫県のページ *篠山市 *攻城団  城崎温泉に友達3人で旅行した帰りに時間があったので寄る。駅から近いのかと思いきや、バスでずいぶんと行かねばならなかったが、藤堂高虎の縄張りらしく安心して見ることができる。遺構としては石垣しか残っていないが、中は広く、素晴らしい城だった。(H8.3.19) 城崎温泉に友達3人で旅行した帰りに時間があったので寄る。駅から近いのかと思いきや、バスでずいぶんと行かねばならなかったが、藤堂高虎の縄張りらしく安心して見ることができる。遺構としては石垣しか残っていないが、中は広く、素晴らしい城だった。(H8.3.19) |
| 福知山城 |  [福知山藩] [福知山藩]明智光秀が横山城を改修して城代を入れた。朽木氏の居城。 *福知山市  休みの日に、特急(スーパーくろしお、特急城崎号)を乗り継いで家から約4時間かけて見に行った。まず電車から見て、外観に感嘆。福知山の駅から歩いて約十分、だんだん近づいてくる外観にやはり感嘆。ところが坂道を登り始めて?城内に入ってみて?これは城ではない。まず、曲輪が全く無い。石段はごく一部だけであとはらせん状の坂道。こんな城すぐに攻め落とされてしまう。また、内部はお粗末な展示と無機質な事務所といった感じ。うーん、外観見るだけでいいな、この城。(H11.2.14) 休みの日に、特急(スーパーくろしお、特急城崎号)を乗り継いで家から約4時間かけて見に行った。まず電車から見て、外観に感嘆。福知山の駅から歩いて約十分、だんだん近づいてくる外観にやはり感嘆。ところが坂道を登り始めて?城内に入ってみて?これは城ではない。まず、曲輪が全く無い。石段はごく一部だけであとはらせん状の坂道。こんな城すぐに攻め落とされてしまう。また、内部はお粗末な展示と無機質な事務所といった感じ。うーん、外観見るだけでいいな、この城。(H11.2.14) |
| 亀山城(C) 近世 平城 |
[亀山藩] 室町時代、内藤氏が八木城の支城として砦を築いたのが始まり。明智光秀が丹波統治の拠点として基礎を作った。本能寺の変の際にはこの城から出陣している。豊臣秀勝、小早川秀秋を経て、徳川家康は譜代大名である岡部長盛を入封させ、天下普請を西国大名に命じ、藤堂高虎が縄張りを行い、修築させた。 *大本教 *亀岡市観光協会  京都学園大学で久宝留理子のライブがあるというのでその最寄り駅だった亀岡駅近くにあった城跡に足を伸ばす。波多野氏を攻めた後に明智光秀が築城した城らしい。明治以降荒れ地となっていたこの地を本拠としたのが大本教教団で、弾圧により天守台が破壊されたりもしたが、同教団の手によって石垣が復元されている。城跡は現在も同教団の聖地であり、現に行った時も結婚式のような儀式をしていた。本丸跡に教団の建物が建っていてそれだけの城跡である。わざわざ見に行くには値しないと思われる。(H8.11.3) 京都学園大学で久宝留理子のライブがあるというのでその最寄り駅だった亀岡駅近くにあった城跡に足を伸ばす。波多野氏を攻めた後に明智光秀が築城した城らしい。明治以降荒れ地となっていたこの地を本拠としたのが大本教教団で、弾圧により天守台が破壊されたりもしたが、同教団の手によって石垣が復元されている。城跡は現在も同教団の聖地であり、現に行った時も結婚式のような儀式をしていた。本丸跡に教団の建物が建っていてそれだけの城跡である。わざわざ見に行くには値しないと思われる。(H8.11.3) |
| 周山城(C) 近世 山城 |
丹波平定を織田信長に命じられた明智光秀が1579年に築いた総石垣の山城。本丸を中心に東西南北に曲輪が造成された。城が実在したのは光秀の晩年3年間で、山崎の戦いに敗れた明智勢の郎党によって破壊された。 |
| 柏原藩陣屋(A) | [柏原藩] 信長の弟信包が初代藩主。その後信雄の子孫が明治まで10代2万石の藩を守った。小藩ではあるが、尚徳門が現存し、陣屋全体も史跡指定を受けている。 *柏原市 |
| 綾部城(E) 戦国 平山城 |
[綾部藩] 波多野氏の重臣江田行範の居城。九鬼隆季が入封。  陣屋跡が小学校になっていて、その門が小学校の校門になっていると聞いて、わくわくしながら行ってみると、そこは城跡ではすでになかった。なんと大本教という宗教法人の所有するところとなり、お寺が建てられていた。結局城跡らしきものは全くなく、完全な無駄足。(H11.2.14) 陣屋跡が小学校になっていて、その門が小学校の校門になっていると聞いて、わくわくしながら行ってみると、そこは城跡ではすでになかった。なんと大本教という宗教法人の所有するところとなり、お寺が建てられていた。結局城跡らしきものは全くなく、完全な無駄足。(H11.2.14) |
| 園部城 近世 平山城 |
 [園部藩] [園部藩]元和五年から七年にかけて小出吉親が築城し、居城とした。  福知山、綾部に続いて見に行った。園部の駅から延々約20分歩いたところに園部高校がある。なんとその高校の正門が櫓門であり、二層の巽櫓が並存している。中には入れないが、こんな高校に通いたい。今更ながら。で、その奥を見ると、なんと天守閣がある。??いやこれは天守閣ではない。まず、櫓より位置が低く、また正面がガラス張りになっている。???近づいてみると、そこは園部公園の一角で、国際交流センターの建物なのだそうだ。歴史的には公園は詰の丸であり、その面影は無いものの、よく整備されたいい公園であった。(H11.2.14) 福知山、綾部に続いて見に行った。園部の駅から延々約20分歩いたところに園部高校がある。なんとその高校の正門が櫓門であり、二層の巽櫓が並存している。中には入れないが、こんな高校に通いたい。今更ながら。で、その奥を見ると、なんと天守閣がある。??いやこれは天守閣ではない。まず、櫓より位置が低く、また正面がガラス張りになっている。???近づいてみると、そこは園部公園の一角で、国際交流センターの建物なのだそうだ。歴史的には公園は詰の丸であり、その面影は無いものの、よく整備されたいい公園であった。(H11.2.14) |
| 八上城 戦国 山城(459m) |
[八上藩] 戦国大名波多野氏の居城。 *山ぽんのホームページ |
| 黒井城(D) 戦国 山城 |
波多野氏の重臣赤井直正の居城。和睦を進めていた明智光秀軍にあくまで屈せず、2度の戦いで大勝し、光秀は信長の叱責をかっている。3度目の攻撃でついに落城し、のちに亀山藩、柏原藩、武田越前之守に三分され、明治に至る。 *山ぽんのホームページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 舞鶴城 近世 平城 |
[田辺藩] 細川藤孝による築城。関が原では西軍が包囲し、勅命により開城。牧野氏が9代200年在城。 |
| 宮津城(B) 近世 平城 |
[宮津藩] |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 出石城 戦国 山城(341m)(近世・平山城) |
 [出石藩]
[出石藩]*兵庫県のページ *兵庫県のページ2  城之崎温泉に行く行き道で、昼食休憩に立ち寄った出石で昼飯を食わずに見に行く。これがまた寒くて特に城は雪だらけだった。景観としてはすばらしかったが、どこにも入れず、それだけではなく説明板すらなかった。でもま、雪の城跡を見れる機会はそう無いだろうし、よかったのではないだろうか。(H11.1.30) 城之崎温泉に行く行き道で、昼食休憩に立ち寄った出石で昼飯を食わずに見に行く。これがまた寒くて特に城は雪だらけだった。景観としてはすばらしかったが、どこにも入れず、それだけではなく説明板すらなかった。でもま、雪の城跡を見れる機会はそう無いだろうし、よかったのではないだろうか。(H11.1.30)*山ぽんのホームページ |
| 竹田城 戦国 山城(353m) |
 [竹田藩] [竹田藩]1443年に但馬守護職山名宗全が13年の歳月をかけて築城したといわれる山陰随一の山城。秀吉の但馬征伐の時に落城、赤松広英を最後に廃城となったが、穴太積みの見事な石垣と鳥が翼を広げたような縄張りが当時の様子を忍ばせている。その保存状態の良さが評価され、映画「天と地と」では上杉謙信の居城春日山城がこの地に再現され、ロケが行われたことで有名となった。 *兵庫県のページ *和田山中学校のページ  ハチ北スキー場にスキーに行った帰り、道路から立派な城が見えたので矢も盾もたまらんくなってふらふらと立ち寄った城。スキーで疲れ切った友達3人は俺の犠牲に・・・(^^;;; 無論僕も痛いふくらはぎを引きずりながら登ったわけだが、この城がまたすごいかっこいい。「天と地と」の映画で春日山城のロケが行われたこともあってか整備が進んでいて360度全方向にその勇壮な姿を見せている。その天守台から見た景色と縄張りは言葉に表せないほど。山城ファンならずとも一度は見ておく価値のある城である。(H9.3.5) ハチ北スキー場にスキーに行った帰り、道路から立派な城が見えたので矢も盾もたまらんくなってふらふらと立ち寄った城。スキーで疲れ切った友達3人は俺の犠牲に・・・(^^;;; 無論僕も痛いふくらはぎを引きずりながら登ったわけだが、この城がまたすごいかっこいい。「天と地と」の映画で春日山城のロケが行われたこともあってか整備が進んでいて360度全方向にその勇壮な姿を見せている。その天守台から見た景色と縄張りは言葉に表せないほど。山城ファンならずとも一度は見ておく価値のある城である。(H9.3.5) |
| 波賀城 戦国 山城 |
 石垣の構造から天正年間以前の成立と考えられる。二層の天守閣が平成2年に復元された。(写真とも池内さんのメールより) |
| 八木城 | [別所吉治領] |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 鳥取城 近世 山城(364m) 日本百名城:63 |
 [鳥取藩] [鳥取藩]守護山名氏が天神山城の出城を作ったのが始まり。家老の武田高信が城代となるが、天文17年反旗を翻し、本拠とする。山名豊国はこれを撃退し、その後ここを本拠とする。豊臣秀吉は12万の大群で兵糧攻めにし、落城させる。(鳥取城の渇殺)関が原以後は池田氏が12代在城。 *鳥取市  この城に行きたくて、飛行機で日帰り旅。結論としては、本当に素晴らしい城。山城と平城が一体化していて、平城部分の大量の石垣と縄張り、そして山城部分の険しさと山頂部分の曲輪群、どこを切り取っても第一級の城跡だと思う。 この城に行きたくて、飛行機で日帰り旅。結論としては、本当に素晴らしい城。山城と平城が一体化していて、平城部分の大量の石垣と縄張り、そして山城部分の険しさと山頂部分の曲輪群、どこを切り取っても第一級の城跡だと思う。まず、公営の駐車場にレンタカーを停め、2018年に復元されたという擬宝珠橋を渡り、2020年に復元されたという中ノ御門表門へ。明治の廃城令では陸軍の施設として認められて数年間廃城を免れたことから古写真等が残っているため、正確な復元ができるのだろう。お城の入口が復元されると一気にお城らしさが高まるし、ワクワクも高まった。ところが、中ノ御門表門を抜けると行き止まりになっていた。その奥の復元工事を進めているようだった。桝形全体を中ノ御門と言っているようで、これが2022年、その奥にある太鼓御門は2023年に復元予定だそうだ。ここまでの復元が終わると、大手登城路がよみがえることになる。最終的には二ノ丸三階櫓の復元までを計画しているらしい。最終形が完成したら、また是非再訪したいものである。 さて、行き止まりなので、迂回して仁風閣へ向かう。城跡の中に建つには違和感がある洋館だが、大正天皇が皇太子時代の宿泊所として建てられたらしい。明治時代に建てられた宮廷建築ということで、重要文化財に指定されているようだ。百名城スタンプを押して、一応見学。庭で先生や学生が楽器演奏やら踊りやらをやっていて、それを横目に見ながら見学を済ませた。 さて、ここからが本番である。中仕切り門を抜けて二ノ丸へ向かう。いきなりの大量の石垣。関東の城跡に行くことが多いので、これだけの石垣を見ると本当に圧倒される。途中、登り石垣、という見慣れない石垣に出会う。それ以外にもこの城、見慣れない石垣が多い。巻石垣もそうだが、作った人の趣味とかがあるのだろうか… 天球丸に行く前に、山上ノ丸への道を発見したので、山道へ。熊出現注意、とかの看板を見つつ、登っていく。結構登ったなぁと思ったら、「2合目」の看板。下からも山上ノ丸の石垣が見えるので、そこまで高くないと高を括っていたのだが、大きな誤りだった。数日前からの異常な暑さもあって、大量の汗と腰痛とも加わって、5合目まで来た時にはフラフラだった。と言ってここであきらめるわけにはいかない。力を振り絞って、残り半分を登り切った。直近だと要害山城に行った時も相当疲れたが、ここまでではなかったように思う。同じ山陰で言えば米子城や月山富田城も麓と山上に城を構えているが、この城の4分の1ない程度だろうか。そんな感覚だった。その山上ノ丸。本丸と二ノ丸があるのだが、これだけの山の上にこれでもかと石垣が積まれていて、圧巻。本丸の中に天守台があり、ここに天守が建っていたというのだから驚きである。天守台からは鳥取の町が一望でき、鳥取砂丘もきれいに見渡せた。少し休憩した後、下りへ。下りは登りほど体力はいらないのだが、滑り落ちたりしないよう、とにかく気を遣う。神経をすり減らしながら、何とか山下ノ丸まで到着したのだった。 あとは巻石垣を見ないとということで、天球丸に行き、天球丸下で巻石垣を発見。2012年に復元されたもののようだが、本当に珍しい。石垣の崩落を防ぐ目的で作られたものだが、やはり作った人のセンスが光っているように思う。先ほども書いたが、珍しい作りの石垣が多いように思う。何から何まで興味深い城跡である。 ということで、想定2時間コースと思っていたのだが、3時間コースになってしまった。ただ、この城はその価値が十分にある。この雰囲気を壊さないで、建物の復元等も進めてもらいたいと思う。あと、三の丸に建っている学校、さすがに違和感があるが、何とかならないものなのだろうか・・・。いずれにしても、城跡としては間違いなく最高ランクのお城である。(R4.7.2) |
| 鹿野城 戦国 山城 |
[鹿野藩] 志加奴氏歴代の居城。尼子氏によって落城。秀吉によって攻略された後、池田市の領有するところとなるも、一国一城令で破却。 |
| 天神山城(D) 戦国 丘城 |
二神山城に代わる因幡守護山名氏の拠点「因幡守護所」。山名豊国のとき鳥取に本拠を移し、廃城。 |
| 二上山城(C) 戦国 山城 |
山名氏の第一の因幡守護所。天神山城へ移転後、毛利氏の拠点となるが、秀吉の鳥取城攻略後、垣屋氏の預かりとなり、その後廃城。 |
| 若桜鬼ヶ城 戦国 山城 続日本百名城:168 |
 [若桜藩] [若桜藩]国人領主「矢部氏」累代の居城。尼子氏により落城、秀吉の攻略以後一国一城令で廃城。 *若桜町  鳥取城でクタクタになった後訪れた城跡。両足が機能不全に陥っていたため、下から登るのは断念し、車で山上まで上がらせてもらった。駐車場からなら10分ほど歩けばもう主郭に到着。一国一城令で廃城となった際に、石垣を崩されたと聞いていたので、もっとボロボロなのかと思っていたら、非常にしっかりした石垣が現れて驚いた。山頂にある古城らしく、苔やら何やらで歴史と風情は格別。その後、犬走りを歩いて進んでいくと、石垣がゴロゴロ落ちて(!)いる一角が。これはこれで歴史を感じられる。その奥には二ノ丸、そこには小屋があって続100名城スタンプがあり、そしてそこから本丸へ入れるようになっている。本丸から見る景色はこれまた素晴らしい。二つの街道を同時に見渡すことができる絶好のポイントで、どちらかから敵が攻めてきたら一目瞭然。確かに城を作るのにこんなに適した場所はなかったんだろう。 鳥取城でクタクタになった後訪れた城跡。両足が機能不全に陥っていたため、下から登るのは断念し、車で山上まで上がらせてもらった。駐車場からなら10分ほど歩けばもう主郭に到着。一国一城令で廃城となった際に、石垣を崩されたと聞いていたので、もっとボロボロなのかと思っていたら、非常にしっかりした石垣が現れて驚いた。山頂にある古城らしく、苔やら何やらで歴史と風情は格別。その後、犬走りを歩いて進んでいくと、石垣がゴロゴロ落ちて(!)いる一角が。これはこれで歴史を感じられる。その奥には二ノ丸、そこには小屋があって続100名城スタンプがあり、そしてそこから本丸へ入れるようになっている。本丸から見る景色はこれまた素晴らしい。二つの街道を同時に見渡すことができる絶好のポイントで、どちらかから敵が攻めてきたら一目瞭然。確かに城を作るのにこんなに適した場所はなかったんだろう。もう少し下に六角石垣という有名な石垣があったようなのだが、自らの足と相談し、今回は見に行くのをやめておくことにした。こちらも非常に素晴らしい城跡だった。(R4.7.2) |
| 桐山城 | [浦住藩] |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 米子城(C) 近世 平山城 続日本百名城:169 |
 [米子藩] [米子藩]出雲の京極氏に対する前線砦として、伯耆守護の山名教之の配下によって築かれたのが始まり。尼子氏に攻略されたが、吉川元春が支配下におさめ、三男元家が月山富田城に入ったとき、不便な山城のため、この城を本拠として新城を構築。関が原以後は池田氏の家老荒尾氏が入り、230年在城。 *「岡山のお城と町並み」 *「デジタル大工」のページ *「山陽・山陰のお城」のページ  あまり期待せずにふらりと寄ったのだが、ほんとに来てよかったというのが感想。大手には枡形の石垣がきれいに残り、そこからは少し山道が続くのだが、本丸に入る少し前くらいから大型の石垣が複数現れる。それだけでも充分満足なのだが、本丸に入ると眼下に中海が、さらには大山などが一望できる。かつてはここに2つの天守が建っていたというのだから、当時はどんな眺めだったことだろうか。想像するだけでも楽しくなってくる。 あまり期待せずにふらりと寄ったのだが、ほんとに来てよかったというのが感想。大手には枡形の石垣がきれいに残り、そこからは少し山道が続くのだが、本丸に入る少し前くらいから大型の石垣が複数現れる。それだけでも充分満足なのだが、本丸に入ると眼下に中海が、さらには大山などが一望できる。かつてはここに2つの天守が建っていたというのだから、当時はどんな眺めだったことだろうか。想像するだけでも楽しくなってくる。私は麓の車に嫁と娘を待たせていたのだが、天守台のところで、ちょうど我が家と同じくらいの家族構成の見物者と出会った。我が家と同様、旦那が城好きなのだろうか・・・。それにしてもこういうところには一般の観光客はなかなかこないんだなー。(H15.9.9)  テニスコートの横に車を停めて、山道を登る。途中で看板を見ると、テニスコートは二の丸、その向こうにある野球場が三の丸跡だという。確かにいい利用方法かもしれない。テニスコートの横には市内の長屋門が移築されているのだが、これがテニスコートの受付のようになっている。山道を登っている時にも、市民と思われる方と何度かすれ違ったのだが、犬を連れている人など、ちょっとした運動、散歩といった感じで城跡に来られている。全体的に城跡が市民生活に溶け込んでいる感じがあり、一体になって保存に取り組めればそれに越したことはないと思う。 テニスコートの横に車を停めて、山道を登る。途中で看板を見ると、テニスコートは二の丸、その向こうにある野球場が三の丸跡だという。確かにいい利用方法かもしれない。テニスコートの横には市内の長屋門が移築されているのだが、これがテニスコートの受付のようになっている。山道を登っている時にも、市民と思われる方と何度かすれ違ったのだが、犬を連れている人など、ちょっとした運動、散歩といった感じで城跡に来られている。全体的に城跡が市民生活に溶け込んでいる感じがあり、一体になって保存に取り組めればそれに越したことはないと思う。しかしこの山道、結構長い。二ノ丸と本丸が相当離れている。実質二ノ丸が本丸で、本丸は後詰の城という感じだろうか。右に行けば内膳丸、左に行けば本丸、という分かれ道を左に行くと、本丸の石垣がドーンと現れる。四重櫓台、鉄門跡、と続き、そして天守台のある本丸へ。海に張り出した半島の山頂に本丸があるので、とにかく眺望がすごい。まさに360度のパノラマが広がる。少し曇っていて大山は見えなかったが、それでもこの眺望がまさに「半端ない」。この広い天守台と、四重櫓台にも天守が二つも建っていたという。圧巻である。 本丸に入ったところで、続日本100名城のスタンプがあって押したのだが、そこで市の職員らしき人からアンケートの回答依頼があって、記入した。米子市に来た目的や今後の予定など。「これからどちらに行かれるんですか?」と聞かれ、「月山富田城に」と答えると、ポカーンとされていた。あまりそういう人はいないのだろうか・・・(R1.11.3) |
| 打吹山城 戦国 山城 |
|
| 羽衣石城(うえし) | [羽衣石藩] 南条氏の居城。尼子氏の猛攻により落城するが、以後毛利氏に属し、城に復帰。 |
| 黒坂城 | [黒坂藩] |
| 八橋城 | [矢橋藩] |
| 尾高城 |  城郭は鎌倉時代に築かれ、室町時代は山名氏の、戦国時代初期には尼子氏の、戦国時代後期には毛利氏の支配下に入った。江戸時代初期に米子城が築城されるにいたり、廃城となった。 城郭は鎌倉時代に築かれ、室町時代は山名氏の、戦国時代初期には尼子氏の、戦国時代後期には毛利氏の支配下に入った。江戸時代初期に米子城が築城されるにいたり、廃城となった。山中鹿之助が腹痛と偽って汲み取り口から脱出したエピソードは有名。  地図を見ていて、城跡マークを見つけて寄ってみた。着いてみてビックリしたのは、「尾高城の謎 夢の埋蔵金発掘探検トレジャーランド入口」という看板!(汗)なんだこりゃー!まぁそれはともかく、その横には建物の礎石跡や土塁空掘を見ることが出来た。小高い丘の上にあるのだとは思うが、すぐ横に学校があり、どうもあまり城跡という感じではなかった。しかし、トレジャーランドって???(H15.9.8) 地図を見ていて、城跡マークを見つけて寄ってみた。着いてみてビックリしたのは、「尾高城の謎 夢の埋蔵金発掘探検トレジャーランド入口」という看板!(汗)なんだこりゃー!まぁそれはともかく、その横には建物の礎石跡や土塁空掘を見ることが出来た。小高い丘の上にあるのだとは思うが、すぐ横に学校があり、どうもあまり城跡という感じではなかった。しかし、トレジャーランドって???(H15.9.8) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 松江城 近世 平山城 日本百名城:64 |
 [松江藩] [松江藩]〈天守〉 関ヶ原の合戦で徳川方に味方した堀尾吉晴は出雲一国を与えられ、戦国大名尼子氏の居城であった月山富田城に入城し、近世城郭に整備したが、麓を流れる富田川が度々氾濫し、城下町が水没するため、1607年当地に築城を開始、その四年後に完成した。本丸塁上には乾櫓・鉄砲櫓など六基が上がり、一段低い南側は二の丸として壮大な御殿と月見櫓・太鼓櫓など五基が上がった。さらに南側には三の丸として現在県舎となっている藩主邸を置き、北側には現在護国神社となっている上御殿が構えられた。しかし現在まで残る建築物は天守のみである。 *松江城公式ページ  非常に素晴らしい城だった。何もかもが素晴らしかったが、最もよかったのは周辺も含めた雰囲気。長い間、堀が水運として利用されていたということもあってかもしれないが、堀が非常によく残り、これを屋形船でめぐることができる。これに乗ってみると、周辺に武家屋敷をはじめ往時を偲べる雰囲気が多く残り、全体としての城を眺めることができる。こう言っては語弊があるのかもしれないが、町があまり発展しなかったからこそ、これだけの素晴らしい遺構を、これだけの規模で残せたのだろう。 非常に素晴らしい城だった。何もかもが素晴らしかったが、最もよかったのは周辺も含めた雰囲気。長い間、堀が水運として利用されていたということもあってかもしれないが、堀が非常によく残り、これを屋形船でめぐることができる。これに乗ってみると、周辺に武家屋敷をはじめ往時を偲べる雰囲気が多く残り、全体としての城を眺めることができる。こう言っては語弊があるのかもしれないが、町があまり発展しなかったからこそ、これだけの素晴らしい遺構を、これだけの規模で残せたのだろう。城内ももちろん素晴らしかった。二の丸には2001年4月に木で忠実に復元されたという南櫓・中櫓・太鼓櫓の三基の櫓と塀がある。さらに本丸に上がると、別名「千鳥城」の天守が聳え立つ。天守に入ると、この灼熱の日に「ヒンヤリ」とした感触。現存する城独特である。地下の倉庫にある井戸や、四層目にあるトイレ。当然あってしかるべきなのだが、こうしたものはなかなか見れない。 いくつか難癖をつけるとすると、天守の中で、隅々を見ることが出来ないこと。安全を考慮してのこととは思うが、中心部で柵が切られていて端の方には行けないようにしてあるのだ。破風の中の狭い空間が趣深くて非常に好きな私としては、そうしたところがいけないのは残念だった。それから、大手門から二の丸に上がる階段が当時の石垣ではなかった。これも障害者の方などが観光される時のことを考慮した結果だとは思うが、これから盛り上がっていく時だけに、残念ではあった。 余談だが、天守の一番上で、ゆっくりと余韻に浸っている時。2歳半の娘も思った以上に楽しんでいて、走り回っていた。靴を脱いで観光するというのが、どこかの家にお邪魔したような感じで楽しいのか、我が娘であるからか、この旅行で一番というくらい喜んでいた。はしゃぎすぎてかどうか分からないが、そこでいきなりキバリ出した。何とオムツにうんちをしたのだ。これを機に、後ろ髪を引かれながら天守を後にしたことは言うまでもない・・・(H15.9.8)  月山富田城に行った帰りに、100名城スタンプも押したかったので、再訪した。以前来た時にはまだ国宝指定されていなかったが、今回は「国宝」松江城である。観光客もすごい数で、駐車場も長蛇の列。近くのTimesに停めて、まずは近くをブラブラして、出雲そばを食べに行った。東京で食べるそばと違って、もちもち感と香りが強い感覚で、非常に美味しかった。 月山富田城に行った帰りに、100名城スタンプも押したかったので、再訪した。以前来た時にはまだ国宝指定されていなかったが、今回は「国宝」松江城である。観光客もすごい数で、駐車場も長蛇の列。近くのTimesに停めて、まずは近くをブラブラして、出雲そばを食べに行った。東京で食べるそばと違って、もちもち感と香りが強い感覚で、非常に美味しかった。さて、松江城である。敷地内に入ると、堀と高い石垣に復元された太鼓櫓・中櫓・南櫓とそれを繋ぐ塀が一体で素晴らしい雰囲気を醸し出している。少し歩くと、石垣に人が集まって写真を撮っている。どうもハート形をした石があって、それを撮っているらしい。もう少し歩くと、チケット売り場があり、その奥には天守が。米子城と月山富田城に行った後に来たからというのもあるかもしれないが、「もう天守?」という感想。天守=城という感覚の人にはちょうどいいのかもしれないが、やはり三の丸、二ノ丸とあって、その上で本丸があって、天守であってほしい感覚はある。その部分は若干物足りない感じはあるものの、それを補って余りあるこの天守。外観、内部、どれをとっても文句の付けどころがない。 前回来た時の感想に「中心部で柵が切られていて端の方には行けないようにしてある」とあるが、今回はそんなことはなかった。私が書いたからということでは絶対ないと思うが、そのように感じる人が多かったのだろうか。改善していただいていて、感動した。隅の方に入らせていただいて、まったりさせていただいた。 途中から、帰りの飛行機の時間が気になりだして、ゆっくり見れなくなってしまったが、とにかく日本が誇る名城の一つであることは間違いない。余談だが、松江における「国宝」推しがすごい。松江城の記載があるところ、すべてを「国宝松江城」と書き換えてある。バス停の名前表示まで「国宝」というシールを貼ってあって、そこまでする?という感じであった…。議会でそんな決議をしたのだろうか。気持ちは分かるけど。。。(R1.11.3) |
| 月山富田城(D) 戦国 山城(197m) 日本百名城:65 |
 築城は1150年台と推定されているが、はっきりしない。出雲の守護代から山陰地方の山陰・山陽十一州を手中に収めた尼子氏歴代が本城とし山陰・山陽制覇の拠点とした巨大な山城。毛利元就によって落城後は吉川氏等の毛利氏一族が支配、1608年に堀尾氏が出雲支配の中心地を松江に移し、廃城となった。 築城は1150年台と推定されているが、はっきりしない。出雲の守護代から山陰地方の山陰・山陽十一州を手中に収めた尼子氏歴代が本城とし山陰・山陽制覇の拠点とした巨大な山城。毛利元就によって落城後は吉川氏等の毛利氏一族が支配、1608年に堀尾氏が出雲支配の中心地を松江に移し、廃城となった。月山山頂部に本丸・二の丸・三の丸・西袖ヶ平と曲輪を置いて詰めの城とし、中腹部に山中御殿と呼ばれる広大な曲輪があって、他に花の壇、奥書院、太鼓壇、千畳平など数限りない曲輪があった。土塁・堀切・石垣など、多くの遺構が残り、尼子氏時代の土塁から吉川・堀尾氏時代に改修を加えた石垣まで、両方の時代の遺構を見ることができる。 *安来市観光協会  長い間行きたくて行きたくて・・・一念発起して朝一の飛行機で日帰りでやってきた。空港でレンタカーを借りて、米子城に寄り道したものの、島根の風景を楽しみながらドライブしていた。道から見える山々がきれいで、絵になるなぁと思っていていると、遠くに特徴的な山が一つ。「あれか?!」と思いながら近づくと、意に違わず、まさにそこが月山富田城だった。特に建物がなくても遠くから視認できる、さすがは名城である。 長い間行きたくて行きたくて・・・一念発起して朝一の飛行機で日帰りでやってきた。空港でレンタカーを借りて、米子城に寄り道したものの、島根の風景を楽しみながらドライブしていた。道から見える山々がきれいで、絵になるなぁと思っていていると、遠くに特徴的な山が一つ。「あれか?!」と思いながら近づくと、意に違わず、まさにそこが月山富田城だった。特に建物がなくても遠くから視認できる、さすがは名城である。安来市立歴史資料館で日本100名城スタンプを押して、周りを見てみると、本格的な登山の恰好をした人が多い。自分ももうそんなに若くもなし、軽い気持ちで来てしまったかと若干後悔。途中まで車で上がることもできると聞いて、少しでも負担を減らそうとそこまで車で上がることに。駐車場は花の壇横、大土塁の手前にあった。近くの階段を上がると、ところどころに石垣が残り、それを見ながら少し行くとそこは山中御殿。狭いところを石垣で固められた近世城郭と違って、スペースが広い。山中御殿も正直「だだっ広い」感じで、少人数では守りにくそうな感覚すら覚えた。というくらい、スケールが大きいということである。 そしてそこからが山登りである。七曲りと呼ばれるつづら折れの道で山頂部の曲輪に向かう。この道、完全に整備されていて、コンクリートの階段になっており、手すりも完璧に整っている。親子連れ、ご高齢の男女、など、多くの方とすれ違った。多くの人は挨拶を交わしてくれるなど、非常に和やかな雰囲気であった。ただ、私としては若干冷めてしまった。多くの人に来てもらうには整備が必要なのもよく分かる。そしてそれに成功しているのも分かる。でも・・・城跡感が半減してしまっている。これには賛否両論あろうが、私としては本当の山道を登りたかった。少し残念な気持ちがした。 とはいえ、厳しい山道には違いない。汗をかきかき、山頂部に。西袖ヶ平では飯梨川と市街地が一望でき、涼しい風が吹き抜け、最高の眺めである。そしてこの高さの山頂部に、三の丸、二ノ丸、本丸といずれもかなり広い面積の曲輪がある。いずれも独立していて、それぞれの曲輪に行くにも、直線的には行けないようになっている。いずれも本当に素晴らしい遺構であるのは間違いない。 帰り、行きには行けなかった花の壇に行った。掘立柱建物等の施設跡が残っており一部が復元・建設されている。2棟あるのだが、手前の建物に、土足厳禁と書かれているところに顔抜きパネルがあり、更にその奥に少し古いキッチンセットが置かれている。この城跡に建物はここだけで、大きさなどは発掘で見つかった礎石を元に作られているようなので間違いないのだと思われるが、何だか不可思議な感じではあった。さらに下に行こうか迷ったのだが、車まで戻るのが大変そうなので、そこで駐車場に引き返した。歴史資料館の隣には「広瀬絣センター」という道の駅があり、お土産を買うことができる。城関連のものも豊富で、見飽きることがない。いろんなものを購入し、城跡を後にした。 結論としては、「期待ほどではなかった」ということだろうか。ずっと行きたくてたまらなかったから、その思いが期待になって、期待が高すぎたというのはあるかもしれない。中世の城跡としては、大規模に、かつ良好に残っているし、戦国時代好きからすると尼子の本拠地というだけでワクワクする、素晴らしい城跡だと思う。それでもやはり城跡に来たからにはかつての雰囲気を味わいたい。この道を山中鹿之助が歩いたのかも、とかそういうことを感じたい。繰り返しになるが、整備の仕方については、どちらに正解があるわけではないと思う。私個人の感想である。(R1.11.3) |
| 白鹿城 戦国 山城(150m) |
|
| 三刀屋城 | *三刀屋町のページ |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 浜田城(C) 近世 平山城(70m) 続日本百名城:170 |
 [浜田藩] [浜田藩]1620年、伊勢松坂城主であった古田重治が5万5千国で転封となり、築いた城。 *浜田市のページ
|
| 津和野城 近世 山城(362m) 日本百名城:68 |
 [津和野藩] [津和野藩]鎌倉時代、元寇の後、1595年に吉見頼行が築城をはじめ、1324年に完成。その後、関ケ原の戦いで吉見家は毛利家について萩に移動、坂崎直盛が3万石で城主となる。千姫事件で所領を没収、その後は亀井家が明治まで在城した。
|
| 山吹城(B) 戦国 平山城 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 甲ノ尾城 戦国 丘城 |
隠岐清政が築城、宮田城から移る。以後隠岐氏の居城となる。 |
お城トップページ |
トピックス |
データベースの歩き方 |
読み替え |
既訪城郭一覧 |
掲示板
蝦夷地 |
東山道 |
北陸道 |
東海道 |
畿内 |
山陰道 |
山陽道 |
南海道 |
西海道 |
琉球