

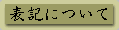
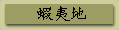
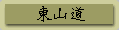
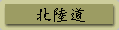
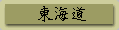
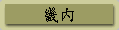
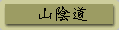
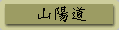
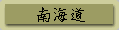
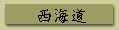
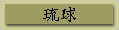
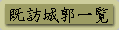

    | |
|---|---|
|
| |
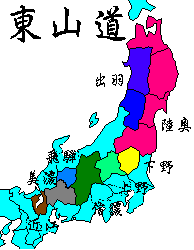 |
陸奥(青森・岩手・宮城・福島) 出羽(秋田・山形) 下野(栃木) 上野(群馬) 信濃(長野) 飛騨(岐阜北部) 美濃(岐阜南部) 近江(滋賀)
|
  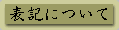 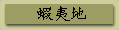 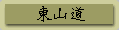 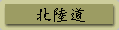 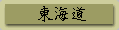 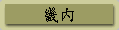 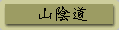 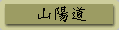 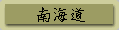 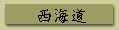 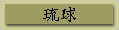 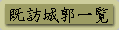 
|
| |||||||
| 城名 |
由来・遺構・エピソードな
|
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 秋田城(E) 古代 続日本百名城:107 |
 大和朝廷は多賀城に鎮守府を置き、蝦夷地経営の拠点としていた。その中で733年出羽柵をこの地に置き、前線基地とした。761年には秋田城と改称され、出羽国府を兼ねることになった。発掘調査により、1.1×1.3kmの外郭であった事が判明している。 大和朝廷は多賀城に鎮守府を置き、蝦夷地経営の拠点としていた。その中で733年出羽柵をこの地に置き、前線基地とした。761年には秋田城と改称され、出羽国府を兼ねることになった。発掘調査により、1.1×1.3kmの外郭であった事が判明している。 歴史資料館近くの駐車場に車を停め、まずはスタンプを押しがてら、歴史資料館を拝見する。古代の城は成り立ちや役割が中世以降の城とは異なるため、資料での解説は非常に助かる。城というと軍事的な意味合いを先に思い浮かべるが、ここは行政機関としての役割の方が強いことが良く分かる。知識を頭に入れたうえで、橋を渡って政庁へ。塀の一部と門があり、それを超えると広い道。やはりこれは一般的な城ではない。平城京や平安京に近く、政庁が御所で、朱雀門と羅生門を結ぶ朱雀大路が東大路ということだろう。出羽国における首都ということか。 歴史資料館近くの駐車場に車を停め、まずはスタンプを押しがてら、歴史資料館を拝見する。古代の城は成り立ちや役割が中世以降の城とは異なるため、資料での解説は非常に助かる。城というと軍事的な意味合いを先に思い浮かべるが、ここは行政機関としての役割の方が強いことが良く分かる。知識を頭に入れたうえで、橋を渡って政庁へ。塀の一部と門があり、それを超えると広い道。やはりこれは一般的な城ではない。平城京や平安京に近く、政庁が御所で、朱雀門と羅生門を結ぶ朱雀大路が東大路ということだろう。出羽国における首都ということか。しかし東門の外側にある水洗トイレは驚いた。奈良時代に水洗トイレがあったとは。当時、中国の東北部にあった渤海国との交易をしていたと言われており、渤海の商人に使ってもらっていたのだろうか。資料館には、水洗トイレで使っていたと思われる木の棒が展示されている。これでお尻を・・・?いろんな意味で想像を掻き立てられるというか。 総括すると、お城ファンの気持ちを高揚させる城ではないものの、日本史好きの人間の興味をそそるには十分と言える城だった。多賀城ほど広範囲ではなく、コンパクトに見ることができるのも良い点と言える。観光客はほぼ皆無だったが、資料館の受付にいた3人の女性、一日暇だろうなぁ・・・(R4.8.8) |
| 横手城 | 1550年ごろ、小野寺氏によって作られた城である。1868年戊辰戦争の際に落城。現在は昭和40年に展望台が建てられている。 |
| 上山城 | 最上氏の最南端の城塞 |
| 久保田城 近世 平城 日本百名城:9 |
 常陸にあった佐竹義宣は1602年に秋田減封となり、土崎湊城に入城。新しい居城としてこの地に築城を開始し、二年後には入城した。徳川政権への配慮から豪壮な建築はなく土壁づくりで櫓も多くは単層だった。しかし有事に備え、三重構えで惣構を伴う縄張りであった。御隅櫓・表門が復元されている他、濠、土塁が残っている。 常陸にあった佐竹義宣は1602年に秋田減封となり、土崎湊城に入城。新しい居城としてこの地に築城を開始し、二年後には入城した。徳川政権への配慮から豪壮な建築はなく土壁づくりで櫓も多くは単層だった。しかし有事に備え、三重構えで惣構を伴う縄張りであった。御隅櫓・表門が復元されている他、濠、土塁が残っている。 二ノ丸横のコインパーキングに車を停め、石段を上る。ただ、この石段、同じ長さ同じ高さの綺麗な石段で、昔からあるものかかなり疑問。土塁で作られた桝形的なものを超えると、「御物頭御番所」がある。唯一、現存している遺構ということで、秋田市から指定文化財指定を受けているらしい。中に入ることも許されていて、入ってみると真夏なのに少し過ごしやすい気温になるような気がする。木造建築ってすごいなぁと思う。中二階のような板張りもあり、非常に興味深い。 二ノ丸横のコインパーキングに車を停め、石段を上る。ただ、この石段、同じ長さ同じ高さの綺麗な石段で、昔からあるものかかなり疑問。土塁で作られた桝形的なものを超えると、「御物頭御番所」がある。唯一、現存している遺構ということで、秋田市から指定文化財指定を受けているらしい。中に入ることも許されていて、入ってみると真夏なのに少し過ごしやすい気温になるような気がする。木造建築ってすごいなぁと思う。中二階のような板張りもあり、非常に興味深い。そのすぐ横には表門。非常に立派な門で、25万石の居城に相応しいものということなのだろう。少し不思議だったのは、門の前に石段があること。石段を上った先に門がある。寺の山門的な雰囲気。そこを抜けると本丸なのだが、佐竹義尭の銅像がある以外、特に何があるわけでもない。奥に進むと、御隅櫓が再建されて建っているのだが、周りにある木が鬱蒼としていて、御隅櫓が全く見えない。近くまで来ないとそこに建物があることが分からない。シンボルとして再建したのだろうに、なんだか目的に沿っていないような気が。スタンプ押しがてら、中に入ったが、申し訳ないが、佐竹の変遷と言われても華やかさに欠け・・・城の模型は面白かった。 と、否定的な意見ばかり書いてきたが、秋田駅のすぐ近くにこれだけの規模の城跡があり、よく保存されているのは素晴らしいことだと思う。歴代の城主が全国的にネームバリューがある人がいないので、なかなかアピールが難しいのだろうと思う。市民の憩いの公園として、末永く地本の人に親しまれればいいのにと思う。 ちなみに、帰り、駐車場から出ようとして、200円を機械に入れたのに何も反応せず、警備会社に電話して来てもらった。葉っぱが入ったり、中に蜘蛛の巣が張って、そうなることが良くあるんだそうな…(R4.8.8) |
| 脇本城(C) 戦国 山城 続日本百名城:106 |
 由来は定かではないが、出土品の特徴から、15世紀にはすでに成立していたと思われる。日本海に突き出すようにそびえる標高100メートルの丘陵地に位置し、自然地形を巧みに利用した中世の土の城である。現在も150haにも及ぶ広範囲に曲輪・土塁・空堀、井戸跡を見ることができる。 由来は定かではないが、出土品の特徴から、15世紀にはすでに成立していたと思われる。日本海に突き出すようにそびえる標高100メートルの丘陵地に位置し、自然地形を巧みに利用した中世の土の城である。現在も150haにも及ぶ広範囲に曲輪・土塁・空堀、井戸跡を見ることができる。 道路脇の駐車場に車を停め、舗装された坂道を登る。車で上がれるかギリギリの幅で、すれ違えなさそうなので、下に車を置いて登ったのだが、途中までは車で行けたようだ。途中菅原神社を越えて歩いていくと案内所があり、そこでスタンプを押印、そのまま上に上がると、ほどなく遺構に辿り着いた。その日も草刈りをしている人が来ていたが、遺構部分は全体的に草を刈ってくれていて、それで遺構が非常にわかるようになっている。とにかく非常に広範囲に土塁と空堀があり、その間に多くの曲輪がある。ここまで広範囲に遺構が残っている城跡はほとんどないのではないだろうか。私が知る限りでは杉山城が近いように感じたが、規模は杉山城よりはるかに大きい。ただ、曲輪の分かれ方や構造的なものは杉山城の方がはるかにわかりやすい。 道路脇の駐車場に車を停め、舗装された坂道を登る。車で上がれるかギリギリの幅で、すれ違えなさそうなので、下に車を置いて登ったのだが、途中までは車で行けたようだ。途中菅原神社を越えて歩いていくと案内所があり、そこでスタンプを押印、そのまま上に上がると、ほどなく遺構に辿り着いた。その日も草刈りをしている人が来ていたが、遺構部分は全体的に草を刈ってくれていて、それで遺構が非常にわかるようになっている。とにかく非常に広範囲に土塁と空堀があり、その間に多くの曲輪がある。ここまで広範囲に遺構が残っている城跡はほとんどないのではないだろうか。私が知る限りでは杉山城が近いように感じたが、規模は杉山城よりはるかに大きい。ただ、曲輪の分かれ方や構造的なものは杉山城の方がはるかにわかりやすい。帰りは天下道と言われる道を辿って、菅原神社まで下りた。本当の古道という感じで、一部危険かと思われるところもあったが、雰囲気は抜群。地味ではあるが、非常に興味深い城であった。(R4.8.8) |
| 松山城(A) | 鶴岡藩の支藩として1779年に築かれた城である。非常に小さな藩だったのだが、立派な櫓門が残っている。酒田の豪商本間重利が1794年に寄進したもので、銅鯱が載る県下唯一の城郭建築遺構である。 |
| 鶴ヶ岡城(D) 近世 平城 |
古くは大宝寺城と呼ばれ、武藤氏の居城、のち最上氏の持城になった。近世になって酒井忠勝が入城し、1622年から改修工事を行い、部分的に石垣を伴う馬出虎口を配した城郭とした。今日、本丸一帯の塁濠が残り、外側には致道館が残る。 |
| 山形城 近世 平城 日本百名城:10 |
戦国大名最上義光の居城。近世城郭への改修は1592年から行われていたが、関が原の合戦で徳川方についた義光は更なる改修を許され、慶長末年までに13基の隅櫓と1基の太鼓櫓をあげ、二の丸に天守に代わる御三階櫓を上げた。最上氏は1613年に断絶、その後保科,松平,奥平,堀田,秋本氏らが入封。現在遺構としては二の丸の石垣・土塁・空掘が残る。 通り道だったので立ち寄ってみる。霞ヶ城公園が城址であるが、そこには野球場やら博物館やらがあるただの公園。???と思っていると、二の丸の奥に桝形が復元されていた。とはいえ、ただそれだけの城跡で、縄張りなんかはほどんど分からなかった。(H11.9.2) 通り道だったので立ち寄ってみる。霞ヶ城公園が城址であるが、そこには野球場やら博物館やらがあるただの公園。???と思っていると、二の丸の奥に桝形が復元されていた。とはいえ、ただそれだけの城跡で、縄張りなんかはほどんど分からなかった。(H11.9.2) |
| 米沢城(D) 近世 平城 |
 歴代伊達家の居城。政宗の時、領土拡大に伴い一時居城ではなくなり、秀吉の奥羽仕置きにより会津・米沢は蒲生氏郷領となり、その支城となる。その後上杉氏会津封入時には直江兼次が城主となり、関が原の合戦後は上杉景勝の本城となった。上杉氏は徳川家に対する配慮から拡張はしたものの石垣・天守無しで二基の御三階櫓を上げた簡素なものとした。 歴代伊達家の居城。政宗の時、領土拡大に伴い一時居城ではなくなり、秀吉の奥羽仕置きにより会津・米沢は蒲生氏郷領となり、その支城となる。その後上杉氏会津封入時には直江兼次が城主となり、関が原の合戦後は上杉景勝の本城となった。上杉氏は徳川家に対する配慮から拡張はしたものの石垣・天守無しで二基の御三階櫓を上げた簡素なものとした。現在本丸の土塁と水濠が残るくらいであり、城跡は上杉謙信と景勝を祭った上杉神社となっている。代々の城主がほぼ創始者と言えるこの二人を神格化していったために、結局は神社の形態になったということのようだ。 *米沢市のページ  旅行の序盤、仙台から裏磐梯に向かう途中、山形に入り、米沢越えをしたために立ち寄ることが出来た。とはいえ、ほんとに神社しかない。蓮の葉に埋まっている堀はあったものの、それ以外は遺構といえる物は見当たらず、ただ神社があるのみだった。(H11.9.2) 旅行の序盤、仙台から裏磐梯に向かう途中、山形に入り、米沢越えをしたために立ち寄ることが出来た。とはいえ、ほんとに神社しかない。蓮の葉に埋まっている堀はあったものの、それ以外は遺構といえる物は見当たらず、ただ神社があるのみだった。(H11.9.2) |
| 上山城 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 唐沢山城(C) 戦国 山城(230m) 続日本百名城:114 |
 平将門の天慶の乱を鎮めた藤原秀郷が築城したと言われるが、今日の遺構は佐野盛綱が戦国末期に築いたもの。その後支配権は北条・豊臣・徳川と移るが、城は佐野家が守り続けた。 平将門の天慶の乱を鎮めた藤原秀郷が築城したと言われるが、今日の遺構は佐野盛綱が戦国末期に築いたもの。その後支配権は北条・豊臣・徳川と移るが、城は佐野家が守り続けた。1602年江戸で明暦大火が起こった際、唐沢山城からいち早く見つけ、江戸に見舞いに駆けつけたところ「江戸を見下ろすところに居城するとは許さん」と廃城の沙汰が下り、まもなく佐野家は取り潰しとなったと言われる。 遺構としては石垣が本丸・二の丸・水の手・大手枡形等に残る。
|
| 足利氏館跡(C) 日本百名城:15 |
 源姓足利氏2代目義兼が1196年邸内に持仏堂を建て、鑁阿寺を創建。3代目義氏が堂塔伽藍を建立し足利一門の氏寺とした。周囲に土塁と堀をめぐらした寺域はほぼ正方形で、約4万平米、鎌倉時代の武家屋敷の面影を今に伝える。 源姓足利氏2代目義兼が1196年邸内に持仏堂を建て、鑁阿寺を創建。3代目義氏が堂塔伽藍を建立し足利一門の氏寺とした。周囲に土塁と堀をめぐらした寺域はほぼ正方形で、約4万平米、鎌倉時代の武家屋敷の面影を今に伝える。 ここを城跡と言えるかどうかは意見が分かれるところかもしれない。それでも寺の周りに土塁が巡らされ、その周りには水堀が囲んでいる。私の城郭観としては完全に城である。ただ、中はあくまで寺であり、城郭建築は当然何も無い。尊氏の地元だという興味を満たすだけであろう。ちなみに、すぐ近くには足利学校がある。日本最古の学校なのだそうだ。江戸期の建物が復元されており、中を見学することが出来るのだが、学校を見学しても正直そう面白いものでもなかった。(H16.10.2) ここを城跡と言えるかどうかは意見が分かれるところかもしれない。それでも寺の周りに土塁が巡らされ、その周りには水堀が囲んでいる。私の城郭観としては完全に城である。ただ、中はあくまで寺であり、城郭建築は当然何も無い。尊氏の地元だという興味を満たすだけであろう。ちなみに、すぐ近くには足利学校がある。日本最古の学校なのだそうだ。江戸期の建物が復元されており、中を見学することが出来るのだが、学校を見学しても正直そう面白いものでもなかった。(H16.10.2)
|
| 栃木城(D) 戦国 平城 |
 1394年皆川秀光が築城、その後本城の皆川城の支城となったが、小田原征伐で皆川城が廃城となったため、本領安堵された皆川広照が再築城した。広照は家康の6男忠輝の守役となるが、1609年の忠輝改易に連座させられ、城も廃城となった。 1394年皆川秀光が築城、その後本城の皆川城の支城となったが、小田原征伐で皆川城が廃城となったため、本領安堵された皆川広照が再築城した。広照は家康の6男忠輝の守役となるが、1609年の忠輝改易に連座させられ、城も廃城となった。 JR栃木駅から少し離れたところにある公園。一角に水堀の一部と土塁の一部が残っているだけであり、城というイメージは一切無い。水堀に泳ぐ鯉とこの季節に鳴いていたツクツクボウシが印象的だった。(H16.10.2) JR栃木駅から少し離れたところにある公園。一角に水堀の一部と土塁の一部が残っているだけであり、城というイメージは一切無い。水堀に泳ぐ鯉とこの季節に鳴いていたツクツクボウシが印象的だった。(H16.10.2) |
| 宇都宮城(E) 近世 平城 |
 藤原宗円が本拠としたのが最初といわれるが、室町時代にある程度城として機能し始め、宇都宮氏22代の居城となった。江戸と奥州を結ぶ要衝の立地ゆえに、とかく歴史上の登場は多い。小田原征伐後、豊臣秀吉が関東東北の大名配置を決めた「宇都宮仕置」はここでなされ、徳川家康が奥羽征伐に向かう振りをして関が原に方向転換をしたのもここである。家康死後は日光墓参に向かう宿泊地として重要性が増し、本多正純が入封、城の大改築が行われたという。最終的には1774年より戸田氏7代が支配して明治を迎えたが、戊辰戦争により建物はすべて焼失した。 藤原宗円が本拠としたのが最初といわれるが、室町時代にある程度城として機能し始め、宇都宮氏22代の居城となった。江戸と奥州を結ぶ要衝の立地ゆえに、とかく歴史上の登場は多い。小田原征伐後、豊臣秀吉が関東東北の大名配置を決めた「宇都宮仕置」はここでなされ、徳川家康が奥羽征伐に向かう振りをして関が原に方向転換をしたのもここである。家康死後は日光墓参に向かう宿泊地として重要性が増し、本多正純が入封、城の大改築が行われたという。最終的には1774年より戸田氏7代が支配して明治を迎えたが、戊辰戦争により建物はすべて焼失した。土塁や堀などの遺構が若干残されていたが、戦後の宅地化・都市化により、本丸の一部以外は破壊、その後『御本丸公園』として整備されるが、その際に残っていた遺構までも破壊して公園化を推し進めたため、現在はほとんど遺構と呼べるものは残っていない。なお、平成18年末を目処に土塁と空堀と櫓2基を復元工事中。 *「よみがえれ!宇都宮城」市民の会ホームページ *栃木の城+α *ザ・登城  JR宇都宮駅と東武宇都宮駅の中間地点に位置する。現在土塁と空堀と櫓2基を復元中ということだったが、土塁にはトンネルが掘られていて、復元をしようという意思はあまり感じられなかった。町の活性化の意味合いもあるのだろうからある程度は仕方ないとは思うが・・・。写真の手前にあるのは清明館という建物の前に放置されている二の丸跡地から工事中に出土した本多正純が城の改築に使用したと言われる石である。この状態であるからして・・・推して知るべしというところか。土塁の一部が残っているということだったが、そもそも公園に入ることが出来ない状態で、遠目にそれらしきものを視認したのみ。歴史的にも、宇都宮市は歴史的遺構を残そうという意識はあるのだろうか・・・。(H18.1.19) JR宇都宮駅と東武宇都宮駅の中間地点に位置する。現在土塁と空堀と櫓2基を復元中ということだったが、土塁にはトンネルが掘られていて、復元をしようという意思はあまり感じられなかった。町の活性化の意味合いもあるのだろうからある程度は仕方ないとは思うが・・・。写真の手前にあるのは清明館という建物の前に放置されている二の丸跡地から工事中に出土した本多正純が城の改築に使用したと言われる石である。この状態であるからして・・・推して知るべしというところか。土塁の一部が残っているということだったが、そもそも公園に入ることが出来ない状態で、遠目にそれらしきものを視認したのみ。歴史的にも、宇都宮市は歴史的遺構を残そうという意識はあるのだろうか・・・。(H18.1.19) |
| 烏山城(C・・・移築城門あり) 室町 山城(202m) |
 1418年那須資氏の次男沢村資重の築城で、以来那須氏八代の居城。那須資晴の時、小田原参陣に遅れたため秀吉の怒りを買い没落、江戸時代は譜代小大名の封地となった。 1418年那須資氏の次男沢村資重の築城で、以来那須氏八代の居城。那須資晴の時、小田原参陣に遅れたため秀吉の怒りを買い没落、江戸時代は譜代小大名の封地となった。遺構としては古本丸・本丸・二の丸・中城・北城・西城・若狭曲輪・太鼓曲輪等が保存され、二の丸吹貫門から常盤曲輪にかけて石垣がよく残る。野上には搦め手門が移築保存される。 *栃木の城+α  JR烏山駅から約30分程歩くとようやく入山口に到着、しばらく階段を上ると山頂に到着。更に行くと下りになり、また登る。再度下ってまた登るとようやく城跡らしきところに。どうも入口を間違えたらしい。まず車橋跡があり、吹貫門跡、正門跡、と続き、その向こうには古本丸・本丸・二の丸等の曲輪がよく残っている。特に吹貫門跡、正門跡、周辺にある石垣は若干ではあるものの、情緒が溢れ、素晴らしい。本丸の周りの曲輪は杉が鬱蒼と茂っているが、敷地が広く、また本丸周辺に残る空堀も規模が大きく、圧巻。思った以上に良い城跡であった。(H18.1.19) JR烏山駅から約30分程歩くとようやく入山口に到着、しばらく階段を上ると山頂に到着。更に行くと下りになり、また登る。再度下ってまた登るとようやく城跡らしきところに。どうも入口を間違えたらしい。まず車橋跡があり、吹貫門跡、正門跡、と続き、その向こうには古本丸・本丸・二の丸等の曲輪がよく残っている。特に吹貫門跡、正門跡、周辺にある石垣は若干ではあるものの、情緒が溢れ、素晴らしい。本丸の周りの曲輪は杉が鬱蒼と茂っているが、敷地が広く、また本丸周辺に残る空堀も規模が大きく、圧巻。思った以上に良い城跡であった。(H18.1.19) |
| 大田原城(D) | 1545年、大田原資清によって築かれ、以後何と廃藩置県まで16代326年間大田原氏の居城であり続けた。現在は龍城公園と呼ばれ、土塁等が残る。 |
| 小山城(D) 戦国 平城 |
 別名祇園城。築城は1146年、藤原秀郷の子孫太田政光が小山の地名を姓とし平城を築いた。1397年に政光直系の血が絶えたが、同族の結城氏が小山姓を継いだ。小田原征伐では、北条家と姻戚関係にあったため北条氏に加勢、1590年小山氏は滅亡、廃城。 別名祇園城。築城は1146年、藤原秀郷の子孫太田政光が小山の地名を姓とし平城を築いた。1397年に政光直系の血が絶えたが、同族の結城氏が小山姓を継いだ。小田原征伐では、北条家と姻戚関係にあったため北条氏に加勢、1590年小山氏は滅亡、廃城。現在は土塁と空堀が思川沿いに広範囲に残っている。  土塁と空堀だけではあるが、とにかく広大な公園がそのまま城跡である。思川の流れに沿って細長く城地があり、川の流れに垂直に何本も空堀が掘られている。その空堀によって曲輪が区切られている、というイメージ。思川を一方の堀として利用した形状など、充分楽しめるものだった。(H16.10.2) 土塁と空堀だけではあるが、とにかく広大な公園がそのまま城跡である。思川の流れに沿って細長く城地があり、川の流れに垂直に何本も空堀が掘られている。その空堀によって曲輪が区切られている、というイメージ。思川を一方の堀として利用した形状など、充分楽しめるものだった。(H16.10.2) |
| 伊王野城(C) |  那須七騎(七将)の1人、伊王野氏の居城。伊王野氏は代々那須氏に仕え、数々の合戦で手柄を立てたりと、最盛期には1万石を有する程までとなった。 那須七騎(七将)の1人、伊王野氏の居城。伊王野氏は代々那須氏に仕え、数々の合戦で手柄を立てたりと、最盛期には1万石を有する程までとなった。 那須に旅行に行ったついでに寄ってみた。全く期待していなかった割には郭や堀切が非常に明確に見ることができ、興味深かった。人が来ることはほとんどないと思われ、草が生え放題という状態で、蚊の大群が久しぶりの餌(汗)に群がってきた。(H20.8.27) 那須に旅行に行ったついでに寄ってみた。全く期待していなかった割には郭や堀切が非常に明確に見ることができ、興味深かった。人が来ることはほとんどないと思われ、草が生え放題という状態で、蚊の大群が久しぶりの餌(汗)に群がってきた。(H20.8.27) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 前橋(厩橋)城(D) 近世 平城 |
 15世紀末に長野氏が築城したが、要衝に位置し、戦略的に重要視されたことから戦国期は上杉・武田・北条の間で攻防が繰り返された。江戸時代には酒井氏が入り、西に利根川の絶壁を背にし、三層の天守を上げた近代城郭とした。ところが、利根川の激流が城を徐々に破壊し、修復が難しくなったため、時の城主松平朝矩が幕府に願い出て、一時廃城とし、川越藩の分領となった。(1767年) 15世紀末に長野氏が築城したが、要衝に位置し、戦略的に重要視されたことから戦国期は上杉・武田・北条の間で攻防が繰り返された。江戸時代には酒井氏が入り、西に利根川の絶壁を背にし、三層の天守を上げた近代城郭とした。ところが、利根川の激流が城を徐々に破壊し、修復が難しくなったため、時の城主松平朝矩が幕府に願い出て、一時廃城とし、川越藩の分領となった。(1767年)約百年の間、主を失った城下町は衰退したが、領民の再三の懇願により1863年、帰城が実現した。ところがその半年後、大政奉還となり廃城となってしまう。それでも廃藩置県ではここが県庁舎となり、今日の繁栄につながったと言われる。 現在、再築城跡は群馬県庁舎が聳え立っており、わずかな土塁と車橋御門石垣の一部が残るのみ。旧前橋城域はほとんどが利根川に沈んだものと考えられている。  予想に反して土塁が広範囲に残っていてビックリした。歴史的経緯から、城内に県庁舎が建っているのは仕方ないと思うし、それでこれだけの土塁が残っているのは素晴らしいと思う。県庁舎の裏に回ると、前橋城の歴史をつぶさに見てきたであろう利根川の激流が今も変わらずそこにあった。(H16.9.25) 予想に反して土塁が広範囲に残っていてビックリした。歴史的経緯から、城内に県庁舎が建っているのは仕方ないと思うし、それでこれだけの土塁が残っているのは素晴らしいと思う。県庁舎の裏に回ると、前橋城の歴史をつぶさに見てきたであろう利根川の激流が今も変わらずそこにあった。(H16.9.25) |
| 高崎城 近世 平城 |
 1590年、家康の関東移封に伴い、上州の要として箕輪城に入った井伊直政は1598年、小城であった和田城を大拡張、近世城郭とし、高崎城と改称してここに移った。三重の天守閣と四基の隅櫓が置かれ、特に天守閣は県下で唯一明治まで残っていたものである。その後1600年に井伊直政は近江佐和山に移封となるが諏訪・酒井・松平・安藤・間部・大河内氏などをが入った。現在、二重隅櫓と長屋門が移築保存されて残っている。 1590年、家康の関東移封に伴い、上州の要として箕輪城に入った井伊直政は1598年、小城であった和田城を大拡張、近世城郭とし、高崎城と改称してここに移った。三重の天守閣と四基の隅櫓が置かれ、特に天守閣は県下で唯一明治まで残っていたものである。その後1600年に井伊直政は近江佐和山に移封となるが諏訪・酒井・松平・安藤・間部・大河内氏などをが入った。現在、二重隅櫓と長屋門が移築保存されて残っている。 外堀と土塁がかなり広範囲に残っている。これに加え、場所は異なるようだが、乾櫓と東門がかなりの修復の手が加えられているとはいえ、現存している。本丸は市役所などの施設になってしまっていて、往時を偲ぶものは何も無いが、それでもこれだけの遺構は大規模な城域を想像するに充分である。公園としても整備され、居心地のいい空間となっていると思う。(H16.9.25) 外堀と土塁がかなり広範囲に残っている。これに加え、場所は異なるようだが、乾櫓と東門がかなりの修復の手が加えられているとはいえ、現存している。本丸は市役所などの施設になってしまっていて、往時を偲ぶものは何も無いが、それでもこれだけの遺構は大規模な城域を想像するに充分である。公園としても整備され、居心地のいい空間となっていると思う。(H16.9.25) |
| 箕輪城(C) 日本百名城:16 |
1500年頃、長野尚業によって築かれたと言われ、戦国時代にはあの長野業政の居城となった城。上州攻略を目指す武田信玄の軍勢に対し、西上州の武将をまとめて奮戦するも、72歳で業政が病没した後は、その団結も崩れ、1566年箕輪城も落城。その後武田・織田(滝川一益)、徳川(井伊直政)と支配が変わり、1598年直政が高崎に城を移したことで廃城となる。 *群馬県箕郷町 |
| 金山城(C) 戦国 山城(223m) 日本百名城:17 |
 1157年、新田義重が築城したと伝えられる。鎌倉幕府倒幕に活躍した新田義貞の居城である。新田氏滅亡の後、一旦は廃城となるが、戦国時代に由良氏のものとなり、全盛期を迎える。上杉武田の猛攻にも落城することの無い難攻不落の名城であったが、後北条氏方に無血開城、小田原征伐後、廃城となる。 1157年、新田義重が築城したと伝えられる。鎌倉幕府倒幕に活躍した新田義貞の居城である。新田氏滅亡の後、一旦は廃城となるが、戦国時代に由良氏のものとなり、全盛期を迎える。上杉武田の猛攻にも落城することの無い難攻不落の名城であったが、後北条氏方に無血開城、小田原征伐後、廃城となる。1996年から整備事業がスタートし、発掘調査結果に基づいた復元作業が行われている。2001年には第一期整備事業が完成。 *群馬県埋蔵文化財調査事業団  非常に驚いた。関東にここまで石を多用した城があるとは思わなかった。もちろん、現存している石垣はわずかなようで、かなり補完されているようだが、それでもこのような総石垣の山城が関東にあるとは・・・ただただ驚きである。 非常に驚いた。関東にここまで石を多用した城があるとは思わなかった。もちろん、現存している石垣はわずかなようで、かなり補完されているようだが、それでもこのような総石垣の山城が関東にあるとは・・・ただただ驚きである。それと同時に、かなりな違和感も覚えた。この城で最も石垣の多い場所である虎口の作り方である。真ん中に階段状の一本通路があり、両側に段段に曲輪を配置、さらにその周りには多くの石垣が複雑に組まれている。しかも、その石垣が繊細というか、細かい作りをしている。その上側に本丸・二の丸・三の丸があるのだが、実城と言われるその中心部には石垣が無い。どこでも見たことの無い作りである。 看板の解説を読んで、少し納得した。「朝鮮式山城と和式山城を融合させ」ているらしい。全国に現在残っている城跡はほとんどが江戸期のものであるため、それが普通と思っていた。江戸初期に藤堂隆虎や加藤清正などの築城の名手が手がけた城がモデルケースとなり、それが一般化したということなのだろう。非常に面白い。復元工事はまだ続くようでもある、完全形が完成した時にはまた是非とも見に行きたいものだ。(H16.10.2) |
| 岩櫃城(C) 戦国 山城(593m) 続日本百名城:117 |
 南北朝時代に築城されたこの城は、1563年真田幸隆によって武田領となって以降、沼田城と上田城を繋ぐ要衝として重要視された。また、甲斐の岩殿城、駿河の久能城と並び、武田領内の3名城と称された。真田昌幸が武田勝頼にこの城への撤退を進言したのは有名な話。一国一城令により廃城。 南北朝時代に築城されたこの城は、1563年真田幸隆によって武田領となって以降、沼田城と上田城を繋ぐ要衝として重要視された。また、甲斐の岩殿城、駿河の久能城と並び、武田領内の3名城と称された。真田昌幸が武田勝頼にこの城への撤退を進言したのは有名な話。一国一城令により廃城。 急峻な岩山にある城というイメージがあって、腰と膝を痛めて以降、登れるか不安に思って行きそびれていたが、一念発起して攻城。結果としては、3合目まで車で行けて、城跡は中腹にあるため、岩山という感覚もなく、身体的には問題なかった。ちょうど暖かくなりかけの時期だったので、若干の残雪があったが、それも登城に支障はなく、そんなことよりなにより、とにかく素晴らしい城だった。 急峻な岩山にある城というイメージがあって、腰と膝を痛めて以降、登れるか不安に思って行きそびれていたが、一念発起して攻城。結果としては、3合目まで車で行けて、城跡は中腹にあるため、岩山という感覚もなく、身体的には問題なかった。ちょうど暖かくなりかけの時期だったので、若干の残雪があったが、それも登城に支障はなく、そんなことよりなにより、とにかく素晴らしい城だった。駐車場から登山路入口に行き、少し上ると前面に土の壁が現れる。近づいてみると、左に上る道がある。そこを上ると、広大な曲輪が現れる。と、この展開、意図を感じないわけにはいかない。攻め手からすると、高い土壁は相当な威圧感だろうし、その上には広大な曲輪があるわけで、そこの兵が代わる代わる上から攻撃してきたとしたら・・・これだけ時間が経って、経年劣化も進んでいるはずなのに、それでもこれだけの威圧感が残っているのはすごいことだと思う。また、その広い曲輪は「中城」というらしいのだが、本当に広大で、もしかしたらここが城の中心部で、奥の本丸は後詰の城なのかと思うほど。そしてその奥には100メートルを超えると思われる竪堀を使った一直線の山道がある。竪堀を通らせる縄張りはあまり覚えがない。そこからは三の丸、二の丸、本丸と続く。 土の城というと関東圏には北条の城が多く、その印象が強いが、この城は全く違う。明らかに手段と目的が異なるように感じた。これが武田と北条の違いなのか、もしくは真田の独自の何かなのか、良く分からないが、そんなことを感じられる貴重な城だと思う。(R7.3.24) |
| 沼田城(C) 近世 崖端城 続日本百名城:116 |
 1544年沼田景泰の築城以来、上杉・武田・北条によって奪い合われるという戦略上重要な位置を占めた城である。1589年の秀吉の仲介により徳川家の人質となった真田信之はこの城に入り、その後1595年には本丸を総石垣とし、五重大天守と三重小天守を上げ、信吉の代にも拡張された。しかし1691年の真田騒動により大小天守は引き降ろされ、その後本多・黒田・土岐氏などが入城した。 1544年沼田景泰の築城以来、上杉・武田・北条によって奪い合われるという戦略上重要な位置を占めた城である。1589年の秀吉の仲介により徳川家の人質となった真田信之はこの城に入り、その後1595年には本丸を総石垣とし、五重大天守と三重小天守を上げ、信吉の代にも拡張された。しかし1691年の真田騒動により大小天守は引き降ろされ、その後本多・黒田・土岐氏などが入城した。 城跡は沼田公園として整備されており、想像以上に城跡としての遺構はなかった。天守台の跡と、その周辺に若干の石垣があったが、明治で廃城になった城とは違って、時間の経過により遺構が残っていないということか。城の全体像を想像することが難しく、そういう意味で少し残念な城だった。とはいえ、城跡公園の面積は非常に広く、よく整備されていて、地元の人には良い公園であろうと思う。(H30.9.14) 城跡は沼田公園として整備されており、想像以上に城跡としての遺構はなかった。天守台の跡と、その周辺に若干の石垣があったが、明治で廃城になった城とは違って、時間の経過により遺構が残っていないということか。城の全体像を想像することが難しく、そういう意味で少し残念な城だった。とはいえ、城跡公園の面積は非常に広く、よく整備されていて、地元の人には良い公園であろうと思う。(H30.9.14)  続日本百名城のスタンプを押すために再訪。何度行っても残念な城だった。前回は天守台の跡と書いてあるが、正確には西櫓台跡。櫓台の中にある桜の木が倒れそうになっていて、石垣が崩壊する危険性があるということで櫓台の周りは立入禁止になっている。また、下には桜の木を支える造作物が・・・問題を先延ばししているだけな気もするが・・・(R7.3.24) 続日本百名城のスタンプを押すために再訪。何度行っても残念な城だった。前回は天守台の跡と書いてあるが、正確には西櫓台跡。櫓台の中にある桜の木が倒れそうになっていて、石垣が崩壊する危険性があるということで櫓台の周りは立入禁止になっている。また、下には桜の木を支える造作物が・・・問題を先延ばししているだけな気もするが・・・(R7.3.24) |
| 名胡桃城(C) 戦国 山城 続日本百名城:115 |
 戦国時代に沼田氏の一族の名胡桃景冬が築城。1589年豊臣秀吉の仲介で北条氏に上野を与え、真田氏は名胡桃一帯を支配することで和解協定が成立。翌年、北条氏が沼田城から名胡桃城を攻撃したため、怒った秀吉は小田原北条氏を攻め滅ぼし、天下統一を成した。 戦国時代に沼田氏の一族の名胡桃景冬が築城。1589年豊臣秀吉の仲介で北条氏に上野を与え、真田氏は名胡桃一帯を支配することで和解協定が成立。翌年、北条氏が沼田城から名胡桃城を攻撃したため、怒った秀吉は小田原北条氏を攻め滅ぼし、天下統一を成した。 中世城郭でここまで保存状態が良く、且つ郭が明確に分かる城は初めてだと思う。感動したと言っていい。まず、般若郭の跡にある駐車場に車を停め、馬出、三郭、二郭、本郭、ささ郭とそれぞれの郭が明確に分かれて保存されており、順番に見学することができる。利根川の河岸段丘をうまく使った城で、利根川と段丘を天然の堀と防御壁として作られている。上の写真はささ郭から利根川、沼田市街地方面を見たものである。言葉ではなかなかうまく説明できないが、中世の城でここまで堀切と郭がきれいに保存されていることは、本当に珍しいし、素晴らしい。心から現地に行ってもらいたい城である。(H30.9.14) 中世城郭でここまで保存状態が良く、且つ郭が明確に分かる城は初めてだと思う。感動したと言っていい。まず、般若郭の跡にある駐車場に車を停め、馬出、三郭、二郭、本郭、ささ郭とそれぞれの郭が明確に分かれて保存されており、順番に見学することができる。利根川の河岸段丘をうまく使った城で、利根川と段丘を天然の堀と防御壁として作られている。上の写真はささ郭から利根川、沼田市街地方面を見たものである。言葉ではなかなかうまく説明できないが、中世の城でここまで堀切と郭がきれいに保存されていることは、本当に珍しいし、素晴らしい。心から現地に行ってもらいたい城である。(H30.9.14) 続日本百名城のスタンプを押すために再訪。何度行ってもいい城だった。元の地形を利用して、堀切を作って、曲輪を作る縄張りをして、というのが良く分かる。山奥でないのにここまで縄張りがわかる状態で残っているのは驚くべきことだと思う。やむを得ないのだと思うが、曲輪内をコンクリートで固めるのは何とかならないものか。本郭では歩きやすいようにパルプ材のようなものが敷かれており、こちらは非常に好感が持てた。できる限り、当時の雰囲気を感じられるようにしてもらいたいものである(R7.3.24) 続日本百名城のスタンプを押すために再訪。何度行ってもいい城だった。元の地形を利用して、堀切を作って、曲輪を作る縄張りをして、というのが良く分かる。山奥でないのにここまで縄張りがわかる状態で残っているのは驚くべきことだと思う。やむを得ないのだと思うが、曲輪内をコンクリートで固めるのは何とかならないものか。本郭では歩きやすいようにパルプ材のようなものが敷かれており、こちらは非常に好感が持てた。できる限り、当時の雰囲気を感じられるようにしてもらいたいものである(R7.3.24) |
| 中山城(C) 戦国 丘城 |
 1582年、真田の拠点である岩櫃城と沼田城の中間にある地点に北条氏が築城。本丸を三方から囲む形で二の丸を設置、さらに二の丸を囲むように三の丸が作られた。1590年、北条氏の滅亡とともに廃城。 1582年、真田の拠点である岩櫃城と沼田城の中間にある地点に北条氏が築城。本丸を三方から囲む形で二の丸を設置、さらに二の丸を囲むように三の丸が作られた。1590年、北条氏の滅亡とともに廃城。 国道脇の駐車場に車を止め、田んぼの間の道を進むと、山への入り口に着く。登っていくと、少し開けたところに着くが、もうそこが本丸跡らしい。これだけの城跡かぁ・・・と思って奥に行くと、そこには深い空堀があり、ビックリ。本丸と二の丸の間の堀なのだろう。専門的なことは良く分からないけど、確かに北条の城という感じ。(R7.3.24) 国道脇の駐車場に車を止め、田んぼの間の道を進むと、山への入り口に着く。登っていくと、少し開けたところに着くが、もうそこが本丸跡らしい。これだけの城跡かぁ・・・と思って奥に行くと、そこには深い空堀があり、ビックリ。本丸と二の丸の間の堀なのだろう。専門的なことは良く分からないけど、確かに北条の城という感じ。(R7.3.24) |
| 横尾八幡城(C) 戦国 山城 |
中之条盆地の東端、川の合流点付近にあって、自然の要害になっている。 車で走っていたら看板が出ていたので寄ってみたが、恐ろしく細い山道になって、対向車が来ないことをひたすら祈りながら、登っていくと、本丸跡横に。群生する篠竹を避けながら進むと、そこには看板も何もないが、本丸らしき曲輪が。こういう城跡もエモい。(R7.3.24) 車で走っていたら看板が出ていたので寄ってみたが、恐ろしく細い山道になって、対向車が来ないことをひたすら祈りながら、登っていくと、本丸跡横に。群生する篠竹を避けながら進むと、そこには看板も何もないが、本丸らしき曲輪が。こういう城跡もエモい。(R7.3.24) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 上田城 近世 平城 日本百名城:27 |
 真田昌幸が天正11年から3年の工事を経て松尾城から居を移した。真田氏はこの城で徳川勢を二度迎え撃ち、どちらも撃退している。元和8年信幸が松代に移封後、仙石忠政が入城し、近世城郭に整備された。 真田昌幸が天正11年から3年の工事を経て松尾城から居を移した。真田氏はこの城で徳川勢を二度迎え撃ち、どちらも撃退している。元和8年信幸が松代に移封後、仙石忠政が入城し、近世城郭に整備された。*上田市のページ *上田城の歴史  夏休みに北長野に旅行に来たので、帰りに立ち寄った。小さい頃に一度来たことがあるはずなのだが、おぼろげな記憶とは全く異なっていて驚いた。 夏休みに北長野に旅行に来たので、帰りに立ち寄った。小さい頃に一度来たことがあるはずなのだが、おぼろげな記憶とは全く異なっていて驚いた。城跡面積は非常に広くて、本丸と二の丸を散策できる。また石垣と土塁が混在している状態で、かつての状態に近いと思われ、見ていて飽きない。櫓は1つ現存、2つは移築されていたものを買い戻して再度復元されていて、その2櫓の間にあった東虎口櫓門が復元され、一体として中に入れるようになっている。何度も解体、復元、を繰り返しているせいか、櫓の中の階段が妙に新しかったり、どこまでが本当に在りし日の姿かが分かりにくいところはあったが、それでも歴史を感じさせる木の匂いや太い柱等、構造は非常に興味深かった。 上田観光の目玉となっていると思われるが、史実に忠実に復元を進めようとしている感覚が非常に共感できる。間違ってもかつて作られなかった天守を建てたりなどしないでほしい。(そうした城跡が日本にはたくさんあるから・・・)かつては櫓門2基、隅櫓7基が存在したわけで、復元を進めるのであれば、その状態に、ということになるのかもしれないが、私の感覚としては現状維持で十分ではないかと思う。天守がないことから派手さがなく、観光地として脚光を浴びることが少ないと思われるが、こうした城こそ、是非とも全体としての保存、一段の公園整備を進めてもらいたいものである(H22.8.25) |
| 小諸城(A) 近世 平山城 日本百名城:28 |
 〈大手門,三之門〉 〈大手門,三之門〉天正18年仙石秀久により石垣を用いた近世城郭に整備され、城下町経営が行われた。現存天守台は牛蒡組みの野面石垣で、三層天守があった。 *小諸市のページ *甲信越のお城  内部は非常に広く、一部は遊園地になっている。懐古園の額が掲げられてある門は三の門で、駅の向こう側に大手門が現存している。どちらも国指定重要文化財。しかし当時はそれを知らず三の門しか見てこなかった。非常に残念。もしこれから行かれる方は要チェック。奇麗な公園であるが、天守台跡には人の姿もまばら。よく保存される石垣などを十分に堪能したい城ではないだろうか。(H3.8.8) 内部は非常に広く、一部は遊園地になっている。懐古園の額が掲げられてある門は三の門で、駅の向こう側に大手門が現存している。どちらも国指定重要文化財。しかし当時はそれを知らず三の門しか見てこなかった。非常に残念。もしこれから行かれる方は要チェック。奇麗な公園であるが、天守台跡には人の姿もまばら。よく保存される石垣などを十分に堪能したい城ではないだろうか。(H3.8.8)
|
| 松本城 近世 平城 日本百名城:29 |
 《天守》 《天守》1582年信長の武田攻略により、前身深志城には小笠原貞慶が入城。1590年、小笠原氏古河移封に伴い、石川数正が入城、築城を開始。この康長の代に完成した。関ヶ原の合戦後、小笠原氏が再入城するが、ついで松平康長が入城。直正の代に月見櫓が整備され、1642年には水野忠清が入城。その頃城下町経営が本格的に整う。 *松本城公式ページ  さすがは天下の松本城というのが正直な感想。連結複合式の天守の勇壮さ・重厚な内部の作り等はもとより、全体的なバランス(天守閣はちょっと頭でっかちではあるが)、堀の広さなど一日中いてもいいくらいの印象だった。ただ、小学生の遠足やらおじいさんおばあさんのツアーか何かにちょうどぶつかってしまって、内部見学を静かにできなかったのだけは残念ではある。(H10.9.4) さすがは天下の松本城というのが正直な感想。連結複合式の天守の勇壮さ・重厚な内部の作り等はもとより、全体的なバランス(天守閣はちょっと頭でっかちではあるが)、堀の広さなど一日中いてもいいくらいの印象だった。ただ、小学生の遠足やらおじいさんおばあさんのツアーか何かにちょうどぶつかってしまって、内部見学を静かにできなかったのだけは残念ではある。(H10.9.4)
|
| 高島城 近世 水城 |
 天正18年に日野根高吉が入城、1598年までの工事で原型を作り、関ヶ原合戦後に諏訪頼水により完成を見た。以後諏訪氏の居城となる。諏訪湖と周りの河川が堀の役割をして、水中から城郭のみが浮き出した形となっており、「諏訪の浮城」と呼ばれ、その威容を誇った。今日、天守以下が復元されているが、明治5年までは柿葺きの屋根の天守が現存していた。
天正18年に日野根高吉が入城、1598年までの工事で原型を作り、関ヶ原合戦後に諏訪頼水により完成を見た。以後諏訪氏の居城となる。諏訪湖と周りの河川が堀の役割をして、水中から城郭のみが浮き出した形となっており、「諏訪の浮城」と呼ばれ、その威容を誇った。今日、天守以下が復元されているが、明治5年までは柿葺きの屋根の天守が現存していた。*諏訪市のページ  城壁が黒塗りでも白塗りでもなく、木そのもので茶色なのが印象深い。それに天守閣のバランスも何か丸みを帯びていて、少し奇妙な印象を受けた。外見はそれなりに興味深いものがあったのだが、内部はやはり復元の悲しさかコンクリート尽くめのつまらない資料展示のオンパレード、またかつての「諏訪の浮城」の面影はなく、汚れきった諏訪湖からは1キロほども内陸にあるだろうか。 城壁が黒塗りでも白塗りでもなく、木そのもので茶色なのが印象深い。それに天守閣のバランスも何か丸みを帯びていて、少し奇妙な印象を受けた。外見はそれなりに興味深いものがあったのだが、内部はやはり復元の悲しさかコンクリート尽くめのつまらない資料展示のオンパレード、またかつての「諏訪の浮城」の面影はなく、汚れきった諏訪湖からは1キロほども内陸にあるだろうか。指月庵・・・上諏訪駅から1キロほど歩いたところにある旧諏訪藩別邸と庭園。かつて諏訪氏が菩提寺である温泉寺に墓参する折に休息所として利用した。かつては借景を利用した雄大なものであったそうだが、今やその面影はなく、民家に囲まれたちっぽけな庭があるだけである。(H10.9.8)
|
| 高遠城(C) 近世 平山城 日本百名城:30 |
 1547年、武田信玄が伊那谷から三河へ進行する前線基地として築城された。武田流縄張りを物語るものとして勘介曲輪・笹曲輪・法幢院曲輪が今も残る。のち保科氏の時代に近世城郭として整備され、鳥居氏、内藤氏と続いた。 1547年、武田信玄が伊那谷から三河へ進行する前線基地として築城された。武田流縄張りを物語るものとして勘介曲輪・笹曲輪・法幢院曲輪が今も残る。のち保科氏の時代に近世城郭として整備され、鳥居氏、内藤氏と続いた。*伊那市
|
| 松代城(海津城)(C) 近世 平城 |
*さなだんご *真田宝物館  完全な公園になっていて、全然観光地ではない。公園の柵を石垣にしただけといった風であった。でもなかなか地元の人の生活に溶け込んでいる感じがよかった。そんなところで遊んで成長した子供は幸せだろう。(H3.8.7) 完全な公園になっていて、全然観光地ではない。公園の柵を石垣にしただけといった風であった。でもなかなか地元の人の生活に溶け込んでいる感じがよかった。そんなところで遊んで成長した子供は幸せだろう。(H3.8.7) |
| 大峰城 戦国 山城 |
川中島合戦の頃築城され、1558年からは武田川の支配するところとなる。現在は「チョウと自然の博物館」となっている。 |
| 飯田城(B) | 坂西氏の居城であったが、武田氏に降伏し、秋山信友らが入り、改修。武田氏滅亡後、毛利秀頼が入城した。現在本丸跡が長姫神社境内であり、桜丸門、脇坂門が現存している。 |
| 飯山城(C) | 戦国時代、高梨氏の中野城の支城となる。上杉方の川中島方面への前進基地として、補修が重ねられた。本田氏の居城。 |
| 龍岡城(C) 続日本百名城:129 |
 函館とともに日本に二つしかない星形稜堡を持つ洋式城郭。信州佐久と三河国奥殿に領地を持つ大給松平氏が幕末激動の情勢に応じて、1864年に着工、1867年に完成。しかし5年後の1872年に廃藩置県により城は取り壊しになった。現在、濠と石垣、お台所が残る。 函館とともに日本に二つしかない星形稜堡を持つ洋式城郭。信州佐久と三河国奥殿に領地を持つ大給松平氏が幕末激動の情勢に応じて、1864年に着工、1867年に完成。しかし5年後の1872年に廃藩置県により城は取り壊しになった。現在、濠と石垣、お台所が残る。*佐久市
|
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 高山城(D) 近世 平山城 |
高山外記が築城、その後金森長近が新城を築いた。金森氏が減転封された後、幕府直轄となり、飛騨支配の中枢とした。現在、山頂に石垣、堀などが残るほか、陣屋は復元整備、保存されている。 |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 郡上八幡城 近世 平山城 |
 *郡上八幡城
*郡上八幡城*岐阜の旅ガイド  山奥にある城だが、天守のすぐ近くまで車で行くことが出来、天守の上から見る景色は最高である。その時には知らなかったのだが、もともと天守はなかったらしく、天守閣は模擬であるが、天守台自体はもともとあったものであり、復興された櫓などと共にしっくりと馴染んでいる。なかなか行きにくい城であるが、一度訪れる価値のある城である。(H5.8.3) 山奥にある城だが、天守のすぐ近くまで車で行くことが出来、天守の上から見る景色は最高である。その時には知らなかったのだが、もともと天守はなかったらしく、天守閣は模擬であるが、天守台自体はもともとあったものであり、復興された櫓などと共にしっくりと馴染んでいる。なかなか行きにくい城であるが、一度訪れる価値のある城である。(H5.8.3) |
| 岩村城(C) 近世 山城(721m) 日本百名城:38 |
 高取・備中松山と並ぶ日本三大山城の一つ。海抜721メートルは全国の山城で最高地にある。築城は遠山景朝が築城、織田信忠が攻略し、川尻氏に続き、森蘭丸の居城となる。現在本丸・東曲輪・二の丸・八幡曲輪・出丸など、各曲輪の石塁が完存。 高取・備中松山と並ぶ日本三大山城の一つ。海抜721メートルは全国の山城で最高地にある。築城は遠山景朝が築城、織田信忠が攻略し、川尻氏に続き、森蘭丸の居城となる。現在本丸・東曲輪・二の丸・八幡曲輪・出丸など、各曲輪の石塁が完存。*城下町ホットいわむら
|
| 大垣城 近世 平城 |
 *大垣市文化事業団
*大垣市文化事業団*大垣市  復元されているのは本丸だけなのだが、本丸全体を復元しているのがよい。遺構として残っているのは移築されたという門と石垣(大洪水の跡がある)くらいなものなのだが、周りを囲む塀や櫓等もちゃんと復元されているのである。ただ、天守閣内部は古ぼけた事務所と同レベルであり、屋上はただの部屋である。展示物はそれなりのものではあったが、保存状態はそれほどいいとも思えなかった。中よりも外観を楽しむべき城といえるだろう。(H9.8.31) 復元されているのは本丸だけなのだが、本丸全体を復元しているのがよい。遺構として残っているのは移築されたという門と石垣(大洪水の跡がある)くらいなものなのだが、周りを囲む塀や櫓等もちゃんと復元されているのである。ただ、天守閣内部は古ぼけた事務所と同レベルであり、屋上はただの部屋である。展示物はそれなりのものではあったが、保存状態はそれほどいいとも思えなかった。中よりも外観を楽しむべき城といえるだろう。(H9.8.31) |
| 岐阜城 戦国 山城 日本百名城:39 |
 *岐阜市
*岐阜市*ぎふ金華山ロープウェー  この城は要注意の城である。金華山という山の上にあるのだが、麓からロープウェイがある。「これは助かる。山を登る苦労がなくなる。」とばかりにそれに乗り込む。山頂についても城はどこにもない。「え?城は?」隣の山を見るとそこに天守閣の姿が。そこから歩いていくことも出来たらしいが、家族と共に行ったため一人行くことも出来ず、断念。何とかしてもう一度行かねばならない城の一つである。(H5.8.2) この城は要注意の城である。金華山という山の上にあるのだが、麓からロープウェイがある。「これは助かる。山を登る苦労がなくなる。」とばかりにそれに乗り込む。山頂についても城はどこにもない。「え?城は?」隣の山を見るとそこに天守閣の姿が。そこから歩いていくことも出来たらしいが、家族と共に行ったため一人行くことも出来ず、断念。何とかしてもう一度行かねばならない城の一つである。(H5.8.2) 上記の願いをついに叶える。しかしロープウェイを降りたら城まではものの5分ほどであった。あの時どうして行かなかったのか・・・ただ、実際に行ってみると全くの観光地になってしまっていてちょっと幻滅したのも確かである。ロープウェイを降りると軽い階段と山道を登って行くのだが、途中で見える岐阜城はなかなか渋く、期待させる。ところが行った時は石垣か何かの工事中という事もあってか、近くに行くとすごい貧弱な城に見えてしまった。なぜか入城は無料だったのだが、中は古びたコンクリートの匂いが立ち込め、展示物も見るべき物は少ない。また屋上の手すりの上につけられている柵は安全のためとはいえ外観まで損ねてしまっており、全く納得できない。(H9.8.31) 上記の願いをついに叶える。しかしロープウェイを降りたら城まではものの5分ほどであった。あの時どうして行かなかったのか・・・ただ、実際に行ってみると全くの観光地になってしまっていてちょっと幻滅したのも確かである。ロープウェイを降りると軽い階段と山道を登って行くのだが、途中で見える岐阜城はなかなか渋く、期待させる。ところが行った時は石垣か何かの工事中という事もあってか、近くに行くとすごい貧弱な城に見えてしまった。なぜか入城は無料だったのだが、中は古びたコンクリートの匂いが立ち込め、展示物も見るべき物は少ない。また屋上の手すりの上につけられている柵は安全のためとはいえ外観まで損ねてしまっており、全く納得できない。(H9.8.31) |
| 苗木城(C) |  遠山景村が築城後、森長可によって攻略、川尻直次が城代となったが、関が原後遠山氏が復帰。現在天守台、千畳敷跡等が残る。 遠山景村が築城後、森長可によって攻略、川尻直次が城代となったが、関が原後遠山氏が復帰。現在天守台、千畳敷跡等が残る。*中津川市のページ
|
| 菩提山城(B) | あの竹中半兵衛の城。半兵衛の父「重元」は1558年、この城を奪って居城としたもの。半兵衛重治の子、重門は関が原で東軍に属し、本領安堵、城を廃して麓に館を建てた。以後、竹中氏は五千石の旗本として、明治維新まで続く。 現在は学校や役場の敷地となるが、櫓門と石垣が残る。 |
| 墨俣城(E) 戦国 平城 |
*大垣市 *日本の城(中部地方) |
| 城名 |
由来・遺構・エピソードなど |
| 彦根城 近世 水城 日本百名城:50 |
 《天守、附櫓及び多聞櫓》 《天守、附櫓及び多聞櫓》〈天秤櫓,太鼓門及び続櫓,二の丸佐和口多聞櫓,西の丸三重櫓及び続櫓,馬屋〉 琵琶湖に臨む寄せ集めの名城。1600年、井伊直政が佐和山城主となるが、実戦的すぎるために西の磯山に築城されたのがこの城。石垣は安土・長浜・大津・佐和山各城から運び込まれ、天守は大津城の天守、天秤櫓は長浜から、太鼓門は佐和山から西の丸の三重櫓は小谷の天守、山崎曲輪の三重櫓は長浜の天守、佐和山口多聞櫓は佐和山の天守を移築したものである。 *公式 *滋賀県観光情報 *彦根市  どっしりとした天守が印象深く、100メートルほどの山の上にあるが、それを苦に感じさせない趣があった。自然が多く、一日ゆっくりと過ごすにもいいかもしれない。(H5.8.2) どっしりとした天守が印象深く、100メートルほどの山の上にあるが、それを苦に感じさせない趣があった。自然が多く、一日ゆっくりと過ごすにもいいかもしれない。(H5.8.2) 梅見を兼ねて、再度ゆっくりと城見物にやってくる。ところがあいにくの雨、かつ梅はまだツボミ状態で、決して良い環境とは言えなかったが、それでもこのお城は相当すばらしかった。やはりお城と言えば曲輪ありき、そして現存天守ありき、天守だけではなく櫓、門などありき、とすべてのお城ファンを納得させるだけのものを持っていると言える。表門から入って本丸の曲輪に入るにはいったん別の曲輪に入らねばならず、そこから木の橋を渡って初めて本丸に入れるといった戦闘を考えた曲輪のつくり方。天守閣の中の木の良い匂いと感触、歴史を感じさせる建築技法などなど。またそれだけではなく、長浜や小谷、佐和山から持ってきたと言う数々の建物など、本当に見所がありすぎて困ってしまった。 梅見を兼ねて、再度ゆっくりと城見物にやってくる。ところがあいにくの雨、かつ梅はまだツボミ状態で、決して良い環境とは言えなかったが、それでもこのお城は相当すばらしかった。やはりお城と言えば曲輪ありき、そして現存天守ありき、天守だけではなく櫓、門などありき、とすべてのお城ファンを納得させるだけのものを持っていると言える。表門から入って本丸の曲輪に入るにはいったん別の曲輪に入らねばならず、そこから木の橋を渡って初めて本丸に入れるといった戦闘を考えた曲輪のつくり方。天守閣の中の木の良い匂いと感触、歴史を感じさせる建築技法などなど。またそれだけではなく、長浜や小谷、佐和山から持ってきたと言う数々の建物など、本当に見所がありすぎて困ってしまった。特に思ったのは、この城にしても松山城にしても、天守が現存しているところと言うのは天守閣自身は不細工であることが多い。それは本物である証拠で、徳川幕府の規制であるとか、時間的に差し迫った事情があるとか、そういった本物の歴史を伝えてくれている歴史の証人なのだと痛感した。観光用に模擬天守を建てる際、勢いカッコイイ天守を作りたくなる気持ちは良くわかるが、やはり歴史を正確に後世に伝えるためにも、是非とも正確な復元をお願いしたいものだ。(H11.3.7)  (H27.8.15) (H27.8.15) 何度目の訪問だろうか。電車で来たが、駅を出ると正面に天守が見える。城を中心に街づくりがなされたことがわかる。姫路もそうだが、そういう城は街全体が城というか、そういう雰囲気が漂っていて心地よい。 何度目の訪問だろうか。電車で来たが、駅を出ると正面に天守が見える。城を中心に街づくりがなされたことがわかる。姫路もそうだが、そういう城は街全体が城というか、そういう雰囲気が漂っていて心地よい。 城につくと、広大な水堀の先に佐和口多門櫓が出迎えてくれ、桝形虎口を抜けた先に馬屋がある。全国にここにしか現存していないという馬屋の遺構であり、今回は是非見学しようと思っていたのだ。外から見るだけかと思っていたら、きちんと中に入れるようになっている。21頭をつなぐことができるようになっており、馬の排泄物処理のために下に穴が開いていたり、非常に興味深い。藩主の馬などがつながれていたらしく、仕切りもゆったりしている。修理したてなのかかなりきれいで、私としてはもう少し傷んでいてくれた方がいいと感じたが、それでも本物である重みは揺るぎない。非常に興味深い遺構だった。 城につくと、広大な水堀の先に佐和口多門櫓が出迎えてくれ、桝形虎口を抜けた先に馬屋がある。全国にここにしか現存していないという馬屋の遺構であり、今回は是非見学しようと思っていたのだ。外から見るだけかと思っていたら、きちんと中に入れるようになっている。21頭をつなぐことができるようになっており、馬の排泄物処理のために下に穴が開いていたり、非常に興味深い。藩主の馬などがつながれていたらしく、仕切りもゆったりしている。修理したてなのかかなりきれいで、私としてはもう少し傷んでいてくれた方がいいと感じたが、それでも本物である重みは揺るぎない。非常に興味深い遺構だった。表門で入城券を購入し、山道を登ると天秤櫓が見えてくる。天秤櫓にかかる橋の下を通って、ぐるっと回ってその橋を渡って太鼓丸に入るこの一連の流れ。元々一連の尾根だったところを切り取って、本丸を独立させ、鐘の丸を馬出し的に使っているようにも見えるこの構造。彦根城の導入部分だが、クライマックスと言っても過言ではない。姫路や松山も元々の山の構造を生かした作りになっているが、彦根は山そのものを城にした感じが最も強い気がする。井伊家の居城らしく、城全体から武骨な雰囲気が感じられて、本当に心地よい。また、天秤櫓には入れるようになっていて、中から外をのぞくと、各通路から来る敵をこの櫓だけですべて狙うことができるようになっていることが見て取れる。本当によく考えられた縄張りである。 太鼓門を抜けると本丸、天守が見えてくる。この天守、前から思っていたのだが、破風が多すぎる。大津城から移築されてきたものであり、改変を加えて今の姿になっているらしいから、いろいろやむを得なかったのかもしれないが、この城の縄張りとか全体から醸し出される雰囲気と天守のゴテゴテしたきらびやかな感じがどうもミスマッチな気がしてしまう。いろんな事情があってそうなったのだろうし、それが歴史の真実なのだからそれに勝ることはないのだが、いろいろと思索できるというのも名城たるゆえんなのだろう。 天守に入る。附櫓が入口になっており、石垣の切れ目から入城、重厚な鉄扉を抜けて階段を登ると、天守内部に入ることができる。天守内部は戦を想定したシンプルな構造になっている。当たり前だが階段はどれも急勾配で、それも心地よい。階段には滑り止めと転落防止と思うが、金具のようなものが敷かれているのだが、この急勾配だと、このレベルはやむを得ないかと思う。そして、破風部分に入る小さな入口がそこかしこにあって、さすがに入ることは許されていないが、見ることはできる。中には隠し狭間があって、そこから攻撃できるようになっているそうだ。破風が多いのはそういう意図もあったのだろうか。それと、大型の破風部分に当たる部屋には入れなくなっていて、「耐震構造上危ないから入場できません」という記載が。すべてが本物ならではである。 駅に向かって歩いていると、店頭に「彦根城を世界遺産に」という記載を見つけた。確かに世界遺産に推薦したくなる日本屈指の城跡である。私的には、松山と高知を国宝にするのが先な気もするが・・・。(R5.12.1) |
| 安土城(C) 戦国 山城(199m) 日本百名城:51 |
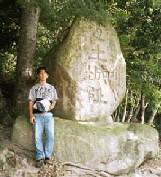 言わずと知れた織田信長による幻の名城。工事に要した6年間を含めても7年間に達しない短命の城。本能寺の変後明智秀満が入城し、これを攻めた織田信雄が焼き払ったと言われる。地上六階地階を含め、七重の天守だったと言われる。城郭史上、天守閣を作った最初期の城の一つである。現在残る石垣は昭和40年代前半に修復されたもの。 言わずと知れた織田信長による幻の名城。工事に要した6年間を含めても7年間に達しない短命の城。本能寺の変後明智秀満が入城し、これを攻めた織田信雄が焼き払ったと言われる。地上六階地階を含め、七重の天守だったと言われる。城郭史上、天守閣を作った最初期の城の一つである。現在残る石垣は昭和40年代前半に修復されたもの。*公式 *滋賀県観光情報  内定式に向かう途中にゆっくりと城めぐりをする第一の城。石垣だけだが、これでも相当修復をしたらしい。小高い山の上にあるため、琵琶湖を臨む眺めが非常に奇麗。建物としては信長が京都から移築してきたという三重の塔が残る。室町時代からあるわけで、時代を感じさせるとても良いものだった。なぜか知らんがカップルが多いのが気になった。ちなみに、後で知ったことだが、奇しくも同じ日に滋賀県教育委員会が安土城から金の鯱片や瓦片が見つかったと発表していたことが翌日の日本経済新聞に載っていた。安土城で見つかるのは初めてで、城郭としては最古の例だという。(H8.9.28) 内定式に向かう途中にゆっくりと城めぐりをする第一の城。石垣だけだが、これでも相当修復をしたらしい。小高い山の上にあるため、琵琶湖を臨む眺めが非常に奇麗。建物としては信長が京都から移築してきたという三重の塔が残る。室町時代からあるわけで、時代を感じさせるとても良いものだった。なぜか知らんがカップルが多いのが気になった。ちなみに、後で知ったことだが、奇しくも同じ日に滋賀県教育委員会が安土城から金の鯱片や瓦片が見つかったと発表していたことが翌日の日本経済新聞に載っていた。安土城で見つかるのは初めてで、城郭としては最古の例だという。(H8.9.28) |
| 小谷城(C) 戦国 山城(299m) 日本百名城:49 |
*京都新聞のページ *内橋さんのページ  小谷山という結構高い山の上にあるが、車で相当高いところまで登れる。そこからは歩くことになるが、20分ほどで本丸跡まで着いた。この時は家族を車で待たせて登ったため、多くを見ることは出来なかった。山城ファンの人には納得できる城ではないかと思う。もう一度ゆっくりと行ってみたい城である。この城と前後して姉川古戦場と賎ヶ岳古戦場にも行った。姉川は、川沿いに「姉川古戦場跡」の看板があるだけ。賎ヶ岳の方はリフトで登って10分あまり山を登れば古戦場を一望できる山頂に行くことが出来る。そこから見える琵琶湖と余呉湖は非常に奇麗だった。(H8.7.30) 小谷山という結構高い山の上にあるが、車で相当高いところまで登れる。そこからは歩くことになるが、20分ほどで本丸跡まで着いた。この時は家族を車で待たせて登ったため、多くを見ることは出来なかった。山城ファンの人には納得できる城ではないかと思う。もう一度ゆっくりと行ってみたい城である。この城と前後して姉川古戦場と賎ヶ岳古戦場にも行った。姉川は、川沿いに「姉川古戦場跡」の看板があるだけ。賎ヶ岳の方はリフトで登って10分あまり山を登れば古戦場を一望できる山頂に行くことが出来る。そこから見える琵琶湖と余呉湖は非常に奇麗だった。(H8.7.30) |
| 観音寺城(D) 戦国 山城(433m) 日本百名城:52 |
*京都新聞のページ 安土城に行った時にもらった簡単な周辺マップを見て、近くにこの城がある事を知り、山城ファンとしては行っとかなくては・・・ということで行くことにした。ところがこれがものすごい山で、ヘトヘトになってしまった。でもそれなりに石垣が残っていて、馬洗い場か井戸かというものもあり、山城ファンにはこたえられないもの。そのすぐ下には西国第32番霊場「観音正寺」があり、そこからの眺めはまた最高。でも山登りが相当好きな方にしか勧められない。(H8.9.28) 安土城に行った時にもらった簡単な周辺マップを見て、近くにこの城がある事を知り、山城ファンとしては行っとかなくては・・・ということで行くことにした。ところがこれがものすごい山で、ヘトヘトになってしまった。でもそれなりに石垣が残っていて、馬洗い場か井戸かというものもあり、山城ファンにはこたえられないもの。そのすぐ下には西国第32番霊場「観音正寺」があり、そこからの眺めはまた最高。でも山登りが相当好きな方にしか勧められない。(H8.9.28) |
| 大津城(E) 近世 水城 |
坂本城落城後、浅野長政が遺構を移して築いた。京極高次が在城の時、関ヶ原で大阪方の猛攻により落城。 |
| 長浜城 時代:戦国 形態:水城 |
*お城めぐりFANのページ *日本の城(中部地方)へ *滋賀県のページ *京都新聞のページ  家族旅行で近くの旅館に泊まったので立ち寄る。復元したてといった天守閣がおもちゃのようだが、城自体は整った奇麗なものだった。ここも例によって天守閣内部の展示物はよいものとは言えず、頂上からの眺めも工事現場などが多く必ずしも良くはなかった。(H8.7.29) 家族旅行で近くの旅館に泊まったので立ち寄る。復元したてといった天守閣がおもちゃのようだが、城自体は整った奇麗なものだった。ここも例によって天守閣内部の展示物はよいものとは言えず、頂上からの眺めも工事現場などが多く必ずしも良くはなかった。(H8.7.29) |
| 坂本城(D) 戦国 水城 |
明智光秀の居城。本能寺の変後、明智秀光により焼失 琵琶湖畔に城跡の碑があるが、ほんとに何も無い。坂本公園とかいう公園があって、みんな釣りをしていた。。。(H10.11.1) 琵琶湖畔に城跡の碑があるが、ほんとに何も無い。坂本公園とかいう公園があって、みんな釣りをしていた。。。(H10.11.1) |
| 大溝城(D) 近世 山城 |
*お城めぐりFANのページ |
| 近江八幡城(D) 近世 山城 |
 六角氏の家臣伊庭氏の居城。その後、豊臣秀次、京極高次等により増改築の後、廃城。 六角氏の家臣伊庭氏の居城。その後、豊臣秀次、京極高次等により増改築の後、廃城。 家族旅行の途中で立ち寄る。ロープウエーがあって、それで八幡山に上ることができる。上では琵琶湖を一望でき、非常に清々しい。一部石垣が残っていて、城らしいところもあるが、基本的に「琵琶湖の展望台」という感じであった。(H27.8.15) 家族旅行の途中で立ち寄る。ロープウエーがあって、それで八幡山に上ることができる。上では琵琶湖を一望でき、非常に清々しい。一部石垣が残っていて、城らしいところもあるが、基本的に「琵琶湖の展望台」という感じであった。(H27.8.15) |
| 膳所城(B) | 〈膳所神社表門,鞭崎神社表門,篠津神社表門〉 家康の天下普請により、大津城の隣地に新城を構築、戸田一西が入城。その後本田氏の居城となる。 *京都新聞のページ  近江大橋の西側の入り口のすぐ近くに膳所城跡公園がある。天守台や石垣が残り、門が復元されている。湖に水没している石垣がまだまだあるように感じられた。(H10.11.1) 近江大橋の西側の入り口のすぐ近くに膳所城跡公園がある。天守台や石垣が残り、門が復元されている。湖に水没している石垣がまだまだあるように感じられた。(H10.11.1) |
| 佐和山城(E) | 「治部少に過ぎたるもの、嶋左近に佐和山の城」石田三成の居城としてあまりにも有名な城。 |
| 水口城(みなくち)(D) 近世 平城 |
[水口藩] 中村一氏が築城、増田長盛、長束正家らが城主になったが、将軍の宿所として「御茶屋」と呼ばれた平城となり、幕府直轄の番城として城代が置かれた。その後加藤明友が入り、水口藩が成立した。> |
| 鎌刃城(D) 戦国 山城(380m) |
15世紀後半に築城された地元領主の居城。この城は信長に攻め落とされたが、信長が破城攻撃をした跡が見つかったことで注目された。「破城」とは石垣で築かれた城がその機能をなさなくなる様、石垣を破壊すること。石垣が築かれるようになるのは近世から(安土城以降)というのが通説となっていたが、信長が破城を行ったということは石垣を構えていたということ。鎌刃城は1974年に廃城になったとされており、安土城築城(1576〜79年)以前に石垣が存在したことになる。(H11年9月8日の新聞より) |
| 鯰江城(E) 戦国 丘城 |
 営業の帰りにちらりと寄る。といっても何もなく、看板が道路沿いにひっそりと立つだけ。(H10.8.11) 営業の帰りにちらりと寄る。といっても何もなく、看板が道路沿いにひっそりと立つだけ。(H10.8.11) |
お城トップページ |
トピックス |
データベースの歩き方 |
読み替え |
既訪城郭一覧 |
掲示板
蝦夷地 |
東山道 |
北陸道 |
東海道 |
畿内 |
山陰道 |
山陽道 |
南海道 |
西海道 |
琉球